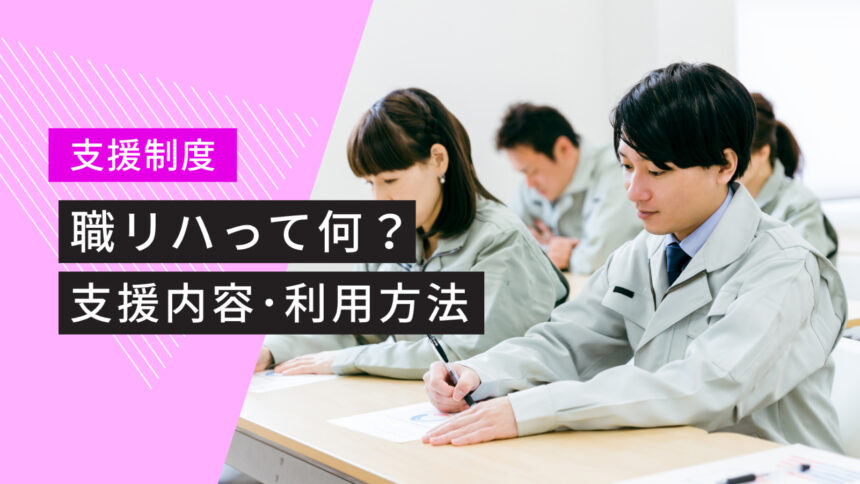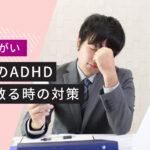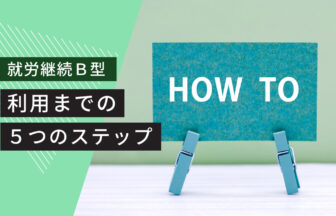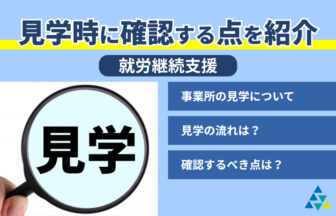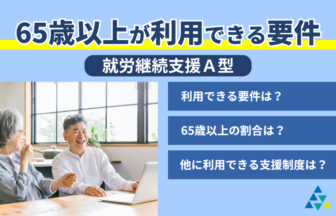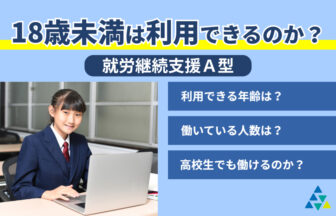障がいのある方にとって、いきなり社会に出て働き始めるのはとても勇気がいりますよね。
「自分の体調とうまく付き合いながら働きたい…」
そう考えている方は職業リハビリテーション(通称:職リハ)を利用してみてはいかがでしょうか?
職業リハビリテーションでは、社会に出て働く前にスキルを身につけるための支援や就職活動のサポートが受けられます。
- 職業リハビリテーションとは何か
- 各施設で受けられる支援内容
について解説していきます。
職業リハビリテーション(通称:職リハ)とは?

職業リハビリテーションとは、通称「職リハ」とも呼ばれており、障がいのある方が社会に出るために必要なスキルを身につけられるようサポートする制度です。
国際労働機関による1983年の職業リハビリテーション及び雇用(障害者)条約(第159号)第1条2では、
職業リハビリテーションの目的が、障害者が適当な職業に就き、これを継続し及びその職業において向上することを可能にし、それにより障害者の社会における統合又は再統合の促進を図ることにあると認める。引用:1983年の職業リハビリテーション及び雇用(障害者)条約(第159号)第1条2|国際労働機関
としています。
また、障害者の雇用の促進等に関する法律の第二条七項では、職業リハビリテーションの定義を
障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。引用:障害者の雇用の促進等に関する法律第二条七|e-GOV法令検索
としています。
障がいのある方に対し、専門の機関が連帯し、職業指導、職業訓練、職業紹介などの支援を行います。
職リハ(職業リハビリテーション)は誰が利用できるの?
サポートを受ける施設によって対象者は異なりますが、職業リハビリテーションを受けられる方は下記の通りです。
- 身体障害者
- 重度身体障害者
- 知的障害者
- 重度知的障害者
- 発達障害を含む精神障害者
- その他心身の機能障害者(障害者手帳を持っていない方含む)
職業リハビリテーションを行う施設によっては、利用対象が定められている場合があるため、自分の障がい・病気に合わせた施設を選ぶ必要があります。
職業リハビリテーションではどんな支援が受けられる?

職業リハビリテーションでは主に「職業相談・職業評価」「職業訓練」「職業紹介」の3つの支援を受けることができます。
職業相談・職業評価
職業リハビリテーションを利用する前に、各機関が的確に支援をするため、計画表を作成する際に必要な評価を行います。
基礎学力、健康状態、本人からの要望などを確認後、その施設への入所が適切か判断します。
- 地域障害者職業センター
- ハローワーク
- 障害者就業・生活支援センター
- 就労移行支援事業所
- など
職業訓練
職業評価をもとに、自分の特性に合った訓練を行います。
一般的には自分の体調を管理する方法を習得することから始まります。その後、徐々に仕事をする上で必要になるスキルを習得するための訓練に移行していきます。
具体的にはビジネスマナーやパソコンスキルなどの実務的な訓練から、電子機器などのメカトロ系、建築系などの専門的な訓練を行うこともあります。
受けられる訓練のコースについては、後の[3-5]の項目で詳しくご紹介します。
- 国立職業リハビリテーションセンター
- 就労移行支援事業所
- 職業能力開発校
- など
職業紹介
職業訓練を行い自分の特性を理解し、働く上で必要なスキルも身につけることが出来たら、自分に合った仕事を紹介してもらえるようになります。仕事探しの相談だけでなく、面接練習や企業へ提出する必要書類の添削などもしてもらえます。
採用試験や面接を受けた後、どのような配慮が必要か、配慮に対応できるかなどを確認するために、「職場実習」や「トライアル雇用」を行う場合もあります。
トライアル雇用に関しては、下記の記事で解説しています。
他にも、ジョブコーチ支援という制度があります。
ジョブコーチ支援制度とは、障害者職業センターに在籍しているジョブコーチが、障がいのある方が安定して働き続けられるよう就職活動を支援したり、職場に同行して会社側へ働きやすい環境を作るよう交渉したりしてもらえる制度です。
このように、就職後も引き続き支援を受けることができます。
- ハローワーク
ハローワークは地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所とも連携しているので、各事業所でも求人情報を探したり、書類の添削をしてもらったりすることができます。
ただし、企業との職業紹介を行っているのはハローワークのため、求人に応募する際はハローワークを通す必要があります。
職業リハビリテーションに関わる施設について

ここまで支援内容について紹介してきましたが、施設によって受けられる支援は異なります。
この項目では、各施設の利用方法や利用料金などをお伝えしていきます。
公共職業安定所(ハローワーク)
公共職業安定所では、求職者登録完了後に専門の職員や職業相談員が一人ひとりの障がいやその特性に合わせた職業相談や紹介、職場定着指導支援などを行っています。職業訓練の相談も可能です。
相談員から仕事を紹介してもらうことはもちろん、設置されている検索機を使用して自分で求人を探すこともできます。応募書類の添削や面接の相談も可能です。職業紹介から就職後の支援までを一貫で利用できるのが利点でしょう。
利用方法
総合窓口に出向き、求職者登録後に利用可能となります。事前予約は不要です。
ハローワークでは一般と障がい者向けの相談窓口が別になっていますが、分からなければ総合窓口に行けば案内してもらえます。ハローワークの規模によっては障害者専門窓口が設置されていない場合もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
下記のサイト内に全国の障害者関連窓口一覧が記載されています。
障害者に関する窓口|厚生労働省
基本的には持ち物は不要ですが、初めて利用する障害者手帳や主治医の診断書を持っている場合は持参しておくと良いでしょう。
求職者登録の際に自分の特性や障がいの話をしておくと情報が記録されるため、その後の職業相談がスムーズに利用できるようになります。
利用料金
ハローワークは公共の職業紹介機関のため、無料で利用できます。
ハローワークの利用については、下記の記事でも解説しています。
地域障がい者職業センター
地域障害者職業センターでは、職業評価、職業指導、職業準備訓練、ジョブコーチ支援など専門的な職業リハビリテーションを受けられます。
全国の都道府県に設置されており、公共職業安定所(ハローワーク)や企業、医療・福祉施設などと連携し、一人ひとりのニーズに沿った支援を行っています。
利用期間は基本的に3か月です。
利用方法
最寄りの地域障害者職業センターへ事前に連絡し、相談する日時を予約します。直接出向いたり、説明会への参加が難しい場合は電話で具体的な希望を伝えることもできます。
申し込みの際は、障害者手帳や主治医の診断書があれば持っていきましょう。また、面談で障がいの状況や職歴、生活歴、支援してほしいことなどを聞かれるため、事前に準備しておくと良いでしょう。
個別相談や利用説明会後も利用したい場合、職業相談・職業評価を受け、計画に基づいた職業リハビリテーション支援を受けることになります。
利用料金
相談や職業リハビリテーションは無料で利用できます。職業リハビリテーションの過程で作業を行う場合がありますが、工賃や交通費等の支給はありません。
地域障害者職業センターについては、下記の記事でも解説しています。
障がい者就業・生活支援センター(なかぽつ)
障害者就業・生活支援センターでは、就労面と生活面での支援を地域の関係機関と連携して行っています。就労面では、職業準備訓練や職場実習の斡旋、就職後のアフターフォローをしてもらえます。
生活面では、安定して仕事を続けられるよう、生活支援担当者から自己管理や健康維持に対するアドバイスを受けられます。
利用方法
基本的には電話で面談予約を取ります。
面談では障がいの特性やこれまでの職務経歴などのヒアリングが行われ、具体的な支援内容について話し合います。継続して利用する場合はセンターへの登録を行います。
来所が困難な場合は、担当者が自宅へ出向いてもらえる場合もあるので最寄りのセンターへ相談してみましょう。
利用料金
障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)は無料で利用できます。
障害者就業・生活支援センターについては、下記の記事でも解説しています。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所では、職業相談から職業訓練、職業紹介まで、職リハとして受けられるサービスを一貫して提供しています。一人ひとり個別の支援計画が作成され、職業訓練や就職活動の支援の他、就職後も職場定着サポートを受けることができます。
利用方法
利用申し込み手続きはお住まいの市区町村にある窓口で行いましょう。事業所の見学・体験から比較・検討を行い、利用先を決めたら、各市区町村にある障がい福祉課などの福祉を担当する部署に障害福祉サービス受給者証を申請します。
その後、事業所と利用契約を結び、就労移行支援の利用が可能になります。
利用料金
多くの方が無料で利用していますが、前年度の世帯収入に応じて自己負担が発生する場合があります。
事業所の例
例として、発達障がいのある方に特化した「atGpジョブトレ 発達障害コース」や、IT・Web分野を専門としている「NeuroDive」などがあります。事業所ごとに特色が違うため、利用を考える場合は各所に一度見学し、自分にあった場所を選びましょう。
就労移行支援事業所については、下記の記事でも解説しています。
国立職業リハビリテーションセンター
先の項目で軽く触れた国立職業リハビリテーションセンターは、埼玉県所沢市に設置されている国の機関で、職業リハビリテーションで受けられる支援を一括で行っています。同等の職業リハビリテーション施設として、岡山県に吉備高原職業リハビリテーションセンターもあります(令和6年11月時点)。
利用対象は高等学校卒業者、もしくはそれと同等以上の学力を有する方で、週5日通所し、1日6時間程度の職業訓練を1年間継続して受講できる方となっています。
個別の訓練カリキュラムをもとに、一人ひとりに合わせた訓練や職場実習を行う他、専任の看護師による健康相談・指導も受けられます。
利用方法
国立職業リハビリテーションセンターは年間10回の入所機会を設けられており、ハローワークから手続きができます。
まずは、居住地を管轄するハローワークへ行き、職業訓練の利用について相談しましょう。
身体障害や難病、高次脳機能障害のある方は宿舎を利用することができます。宿舎の利用は利用申請と同時にお住まいの市区町村への利用相談が必要です。
宿舎の利用を希望する場合、隣接されている国立障害者リハビリテーションセンターの施設を利用することになります。手続きに2~3か月程度時間がかかるため、利用を希望する場合は国立障害者リハビリテーションセンター総合相談課へ連絡する必要があります。
その後、ハローワークへ入所申請書類を提出します。職業評価(入所選考)を受け、入所の許可が下り次第、ハローワークで入所手続きを行います。
訓練の種類はさまざまで、2024年現在、11科・17コースが設けられています。
内容は下記の通りです。
| 訓練系 | 訓練科 | 訓練コース |
|---|---|---|
| メカトロ系 | 機械製図科 | 機械CADコース |
| 電子機器科 | 電子技術・CADコース | |
| テクニカルオペレーション科 | FAシステムコース | |
| 組立・検査コース | ||
| 建築系 | 建築設計科 | 建築CADコース |
| 情報系 | OAシステム科 | ソフトウエア開発コース |
| システム活用コース | ||
| 視覚障害者情報アクセスコース | ||
| DTP・Web技術科 | DTPコース | |
| Webコース | ||
| ビジネス系 | 経理事務科 | 会計ビジネスコース |
| OA事務科 | OAビジネスコース | |
| オフィスワーク科 | オフィスワークコース | |
| 物流系 | 物流・資材管理科 | 物流・資材管理コース |
| 職域開発系 | アシスタントワーク科 | オフィスアシスタントコース |
| 販売・物流ワークコース | ||
| サービスワークコース |
| 訓練系 | 訓練科 | 訓練コース |
|---|---|---|
| メカトロ系 | 機械製図科 | 機械CADコース |
| 電子機器科 | 電子技術・CADコース | |
| テクニカルオペレーション科 | FAシステムコース | |
| 組立・検査コース | ||
| 建築系 | 建築設計科 | 建築CADコース |
| 情報系 | OAシステム科 | ソフトウエア開発コース |
| システム活用コース | ||
| 視覚障害者情報アクセスコース | ||
| DTP・Web技術科 | DTPコース | |
| Webコース | ||
| ビジネス系 | 経理事務科 | 会計ビジネスコース |
| OA事務科 | OAビジネスコース | |
| オフィスワーク科 | オフィスワークコース | |
| 物流系 | 物流・資材管理科 | 物流・資材管理コース |
| 職域開発系 | アシスタントワーク科 | オフィスアシスタントコース |
| 販売・物流ワークコース | ||
| サービスワークコース |
利用料金
受講料は無料で、実習用の器工具や教材は貸してもらえます。ただし、訓練を受ける科によっては参考書や作業服などが必要になるため、年間5,000~20,000円程度の自己負担があります。
障がい者職業能力開発校
障害者職業能力開発校では仕事をする上で必要な知識や技術を習得するための職業訓練が受けられます。
図面の読み方や機械の操作方法を学ぶコースや、Word・Excelなどの事務作業を一通り学ぶコースなど、各校によって設置されているコースはさまざまです。
利用対象は18歳以上、もしくは中学卒業以上です。年齢や障がい種別によって受けられるコースは異なります。利用できる期間は1年間としているところが多いです。コースによっては、1~3か月、6か月、2年間の場合もあります。
地域のハローワークとつながっているため、ハローワークやその他の支援期間からのサポートを受けることができます。訓練期間中に就職が決まる方もいます。就労定着支援として、就職後に職場であった困り事を相談をすることも可能です。
また、障害者職業能力開発校の他、障がい者向けの訓練コースを設置している一般の職業能力開発校や、企業や法人などが実施している委託訓練もあります。
利用方法
ハローワークで入校の申し込みを受け付けています。
「入校申込書」もしくは「入校願書」という応募書類をハローワークへ提出し、審査を通過すれば利用開始となります。
申し込みの際は、下記の書類を持参しましょう。
- 入校申込書
- 診断書
- 障害者手帳の写し
- 調査書
(中学・高校・特別支援学校を新しく卒業してから応募する方は、必要になる可能性があります)
利用料金
入校料、授業料は無料です。その他、教科書代や資格試験代は実費負担となります。
また、障害者職業能力開発校は職業訓練のため、一定の条件に該当する場合に限り、各種手当が支給されます。
障害者職業能力開発校については下記の記事でも解説しています。
先に述べた国立職業リハビリテーションセンターや委託訓練等を含め、全国の障害者職業能力開発校を下記から探すことができます。
2.ハロートレーニング(障害者訓練)の概要|ハロートレーニング(障害者訓練)|厚生労働省
まとめ|職業リハビリテーション(通称:職リハ)とは
- 職業リハビリテーションとは、障がいのある方が社会に出るために、必要なスキルを身につけるサポートを受けられる制度。
- 支援を受ける施設によって幅は異なるが、基本的に障がいのある方が利用対象。障害者手帳が無くても利用できる場合がある。
- 受けられる支援としては、職業相談・職業評価や職業訓練、職業紹介がある。
- 職業リハビリテーションに関わる施設としては、ハローワークや地域障害者職業センター、就労移行支援事業所、職業能力開発校などがあり、それぞれ受けられる支援が異なるため、必要に応じて選択する。
職業リハビリテーションでは基本的に無料で一人ひとりに合ったサポートを受けることができます。
各施設で受けられる支援は多岐に渡りますし、自分に合う方法で綿密なサポートを受けられたら安心ですね。
障がいの状態や体調をもとに、どのような職業リハビリテーションを進めていくか、医師や家族と相談しながら決めていくと良いでしょう。