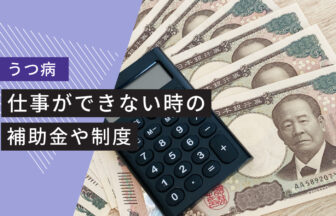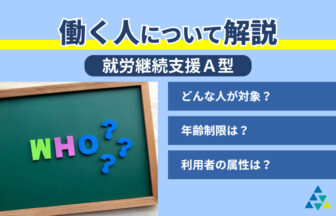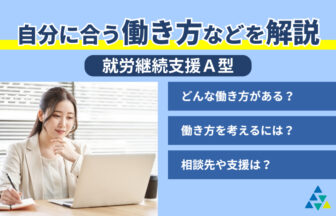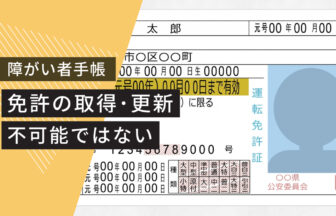「どのように就職活動を進めていいかわからない…」
「自分に合っている仕事はどんな仕事?」
「今のスキルでできることはなにがある?」
などの悩みや疑問はありませんか?
障がいがあると、長く続けられる仕事を自分一人で探すのはなかなか大変ですよね。仕事探しは「能力」や「適性」を考えて判断していくことが重要です。
地域障がい者職業センターでは、障がいがある方に対して、就業に関して専門的なサポートを行っています。
- 地域障がい者職業センターの役割
- 支援を受ける条件
- ハローワークやなかぽつ(障がい者就業・生活支援センター)との違い
について解説します。
地域障がい者職業センターの役割

地域障がい者職業センターの活動は次の5つです。
- 障がい者の就職に向けた職業リハビリテーション
- 職場へ定着して働けるようサポートするジョブコーチ支援
- メンタルの不調を整え、職場へ復帰するためのリワーク支援
- 障がい者雇用を行う企業に対する助言・支援
- 地域の関係機関に対する助言・援助
上記の中から、障がいがある当事者に直接関係のある3つを説明します。
職業リハビリテーション
まず、職業リハビリテーションの流れを説明します。
1.適性検査と面談を基に、「職業リハビリテーション計画」を作成
まずはじめにこれまでの職歴や障がいについて職員と話し合い、適性検査を受けます。
この過程は「職業相談」「職業評価」と呼ばれることがありますが、就職の可否や適性を判断するものではありません。就職活動の進め方や長く働き続けるための計画を立てるためのものです。
適性検査は時間をかけてじっくり行われます。働くうえで自分の適性を知ることはとても大切です。障がいがあると、得意なことと苦手なことの差が大きく開いている場合があります。苦手な作業をメインに行う仕事に就くと、ストレスが積み重なり短期間で辞めてしまうことも少なくありません。
自分の強みや弱みを分析すると、どんな仕事が合っていて続けられそうか想像することができますよね。負荷が少なく自分に適した仕事を選ぶと、仕事を長く継続できて生活の安定につながります。
適性検査の結果を見ながら希望の職種などについて職員と話し合い、今後どういった支援が必要かを明確にします。そして「職業リハビリテーション計画」の形で職業訓練の計画が作成されます。
2.計画に沿って職業訓練や講習に取り組む
「職業リハビリテーション」は、いわゆる”職業訓練”のイメージとは少し違うかもしれません。PCでの入力作業や簡単な事務作業、そのほかピッキングや部品の組み立て作業などを行います。
地域障害者職業センターでの職業訓練はスキルアップして就職することを目指しているのではなく、今持っているスキルと能力を活かし就職することを目的としています。作業を行いながら、ミスを繰り返さないための対処法を考えたり、休憩の取り方を学んだりして今の自分にプラスできる技術を習得していきます。
個人の作業のほかに、グループワークもあります。講習を受けるメンバーで、職場でのコミュニケーションを想定した模擬練習などを行い、ルールやマナーを学びます。
職場での声のかけ方や、上司への質問のまとめかたなど、円滑なコミュニケーションがとれるように練習します。相手の様子を見ながらコミュニケーションをとり、コツをつかんでいきましょう。
ストレスへの対処法を考えるトレーニングなど、職場定着に関するスキル向上のための講座も行っています。イライラや落ち込みの感情を溜め込まないようにすることはとても大切です。日々、自分をメンテナンスするイメージで取り組んでみてください。
3.履歴書作成と面接練習、就職活動
リハビリテーションの終盤では、履歴書の作成や面接練習を行い、アドバイスをもらいます。
履歴書に書く文章では、内容にねじれがないようにしましょう。
面接の練習も受けられます。緊張して思うように話せないこともあると思いますが、何度も練習を繰り返して落ち着いて臨めるようにしましょう。面接はマナーだけでなく、おどおどしない態度も大切です。
地域障害者職業センターでは直接就職先の紹介は行っていませんが、ハローワークと連携しているため、求人情報の相談など、ハローワークで行っている支援も受けることができます。
また、ハローワークでは「障害者就職面接会」が定期的に開催されているため、そこへ応募することもできます。面接会の頻度は1年に1~3回程度ですが、多くの企業から求人が来るため、チェックしてみると良いでしょう。
上記の一連の流れが「職業リハビリテーション」です。
ハローワークでの職業紹介など、次の段階に着実に移行するために、職業訓練や講習の一環として、職業準備支援を行う場合もあります。施設内での作業体験や、社会生活技能訓練などを通じて、基本的な労働習慣を身に付け、作業遂行力の向上の支援、コミュニケーション能力・対人対応力の向上などを支援する目的です。
職業準備支援の期間は個別に設定されるため、人によって期間が異なります。また、利用にかかる費用は無料ですが、工賃・交通費などの支給はありません。
職場適応援助者(ジョブコーチ)支援
地域障害者職業センターでは、障がいのある方が就職の際、職場にうまく適応できるよう、専門のジョブコーチを職場へ派遣し、問題の改善に向けて支援を行う、職場適応援助者(ジョブコーチ)支援も行っています。
実際の職場にジョブコーチが訪問し、作業場や対人関係等の不安や課題について、直接支援を行います。課題や適応状況に合わせた支援期間や訪問頻度、支援内容を提案、支援計画を作成してもらえます。
仕事の内容だけでなく、同僚や上司とのトラブルなど、仕事を続けるうえで困ったことがあれば相談しましょう。
障がいがある当事者だけでなく、企業に対しても合理的配慮・関わり方のポイントなど雇用管理の助言や、指導の仕方などの直接的、専門的支援を行います。一人では解決が難しいトラブルに対しても職場との間に入ってもらえるので、一人で抱え込まず、積極的に相談していきましょう。
雇用前、雇用と同時、雇用後のどの段階でも利用できます。利用料金は無料です。
ジョブコーチ支援を受けられる期間は人によって異なりますが、標準的には2~3か月程度です。支援期間終了後も頻度は下がりますが定期的に訪問し、フォローアップを行います。
リワーク支援
うつ病など、何らかの精神疾患が原因でメンタルの不調で休職している方のために、リハビリテーションを通して職場復帰を目指す「リワーク支援」というプログラムもあります。
リワーク支援では
- 生活リズムの立て直し
- 業務遂行のための集中力、持続力、判断力等の回復
- 対人場面での不安の軽減やコミュニケーションスキルの向上
- 再発予防のためのセルフケア講習
- 職場で想定されるストレスの把握、対処方法の習得
などを行います。
支援内容や期間は人によって異なります。主治医や企業と連携しながらプログラムを作成していきます。
精神的につらい状態になると、一旦立ち止まり休む必要が出てきます。無理なく職場復帰できるよう、ゆっくりと心と体を整えましょう。
休職中の企業に対しては、支援の経過報告や職場復帰受入れの準備、復職後の職務設定の仕方など、病気に関する留意事項についてアドバイスを行います。企業側への配慮を求めることが可能です。
対象者は民間企業等の雇用保険適用事業所に雇用されている休職中の方です。休職中の方に対する復職プログラムのため、離職予定、既に離職された方は利用できません。地域障害者職業センターでは、再就職のための支援も行っているため、そちらを利用しましょう。
支援にあたり、本人だけでなく、主治医、事業所の同意が必要です。
利用料金は無料ですが、交通費、昼食費は自己負担となります。
地域障がい者職業センターの支援の条件について

地域障害者職業センターは、障害者手帳を持っていなくても利用できます。
自分で障がいがあるかもしれないと思う場合は一度相談してみましょう。
支援の対象になる方
地域障害者職業センターは、障がいがある方、難病がある方、障がいがあると認められる方が利用対象です。
障害者手帳の所有は必須条件ではありません。診断書がある方、障害者手帳申請中の方、障がいの疑いがある方など、相談したい場合は問い合わせてみましょう。
また、障がい者の雇用や就業に関する助言・支援を行っているため、障害者雇用を行う企業や就労支援関連機関も対象となります。
利用するには?
地域障害者職業センターは全国47都道府県に設置されており、北海道、東京都、愛知県、大阪府、福岡県には支所も設置されています。
地域障害者職業センターを利用したいと思ったら、最寄りのセンターへ電話で問い合わせてみましょう。
相談は予約制となっているため、相談内容を伝え面談日の日時を決めます。面談での相談のほか、センターによっては業務内容を紹介する「利用説明会」を行っている場合もあります。予約制の場合が多いため、事前に確認してから参加してみるのも良いでしょう。
地域障害者職業センター|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
地域障害者職業センターの利用について|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
地域障がい者職業センターとハローワークの違い

障害者職業センターは「職業リハビリテーション」を行っていますが、ハローワークはどんな役割をしているのでしょうか?
ハローワークでは障がいがある方に対し、地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)と連携し、就業のサポートを行っています。
ハローワークには「障害者相談窓口(障害者関連窓口)」が設置されています。ここでは障がいや障がい者の就労について専門知識がある職員に就職相談をすることが可能です。就職活動は一人ではわからないことも多いので、積極的に利用・質問すると良いでしょう。
職業紹介だけでなく、履歴書など、応募書類の書き方支援や、模擬面接なども受けられるなど、障がいの特性に合わせた支援を行います。
さまざまな支援機関と連携しているため、すぐに求職活動ができない場合でも、連携している地域障害者職業センターでの職業訓練を行うことを提案されたり、障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)の紹介から生活支援を受けたりなど、就職に向けての取り組みを始めることができます。
ハローワークの利用方法については、下記の記事で解説しています。
地域障がい者職業センターと障がい者就業・生活支援センター(なかぽつ)の違い

「なかぽつ」こと、「障害者就業・生活支援センター」の役割も見てみましょう。
なかぽつは、障がいがある方の就業面と生活面における包括的な支援や相談を受けています。
就業面に関する支援として下記のようなことを行っています。
- 就職に向けた準備支援
- 特性・能力に合った職務の選定
- 就職活動支援
- 職場定着支援
生活面に関する支援として下記のようなことを行っています。
- 生活習慣形成、健康管理、金銭管理等、日常生活の自己管理に関する助言
- 住居、年金、余暇活動等、地域生活・生活設計に関する助言
そのほか、障がい者を雇用する企業へ、雇用における助言や相談も行っています。企業に向けて助言を行っているところは地域障害者職業センターと同じですね。
なかぽつは相談者から相談を受け、地域障害者職業センターやハローワークを紹介する、橋渡し役的役割を行っています。
障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)については、下記の記事で解説しています。
それぞれの機関がつながって一体となり、障がい者の就業を支えていることがわかります。
国立の職業リハビリテーションセンター

国立の職業リハビリテーションセンターは、「中央広域障害者職業センター」と「中央障害者職業能力開発校」の二つの側面を持つ機関です。
「国立」がついている職業リハビリテーションセンターは令和6年現在、埼玉県の国立職業リハビリテーションセンターと岡山県の国立吉備高原職業リハビリテーションセンターの2か所のみです。地域障害者職業センターと同様、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しています。
年間複数回の入所を行っており、個人に合わせて個別の訓練カリキュラムを作成、実施しています。
センターへ週5日通所し、1日6~8時間程度の職業訓練をコース終了期間(場所・訓練コースによって異なる)まで継続して受講できることが応募要件の一つとなっています。宿舎も設置されているため、居住地から遠くても安心して利用できます。
入所選考があるため、応募したら必ず入所できるとは限りませんが、入所後は一定の期間、職業訓練に集中して取り組むことができます。
定期的にオープンキャンパスとして、訓練の見学や体験、入所に関する相談ができる機会が設けられているので、興味があれば参加してみるのも良いでしょう。
詳細は、各センターのサイトをご確認ください。
まとめ|地域障がい者職業センターとは
- 地域障害者職業センターでは、職業リハビリテーションやジョブコーチ支援、リワーク支援などを行っている。
- 「職業リハビリテーション」は適性検査・計画作成⇒職業訓練・講習⇒履歴書作成・面接練習、就職活動の流れで行われる。
- 「ジョブコーチ支援」では、職員が職場へ訪問し仕事を続けるうえで困りごとを相談できる。
- リハビリテーションを通して職場復帰を目指す、「リワーク支援」というプログラムもある。
- 障害者雇用を行う企業や地域の関係機関に対して、助言・支援も行う。
- ハローワークや障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)とも連携を行っている。
地域障害者職業センターは、障がいがある方に「職業リハビリテーション」を提供したり、休職ののち復職を希望している方へ「リワーク支援」を行ったり、と地域の就業を支えている機関です。
専門家のアドバイスをもらい、自分にできる仕事、やりがいを感じられる仕事を探してみませんか?
自分を見つめなおして気持ちを整え、就職に向けて踏み出してみましょう。
ちなみに、地域障害者職業センター以外にも、「ミラトレ」のような就労移行支援事業所もおすすめです。利用することで、生活習慣の改善、コミュニケーション訓練、職業スキル習得など、障がいを抱えている人に必要なサポートを受けることができます。
障害者手帳がなくても、医師の診断書や自治体の判断などがあれば利用可能です。見学や体験は無料で行えるので、気になる方はぜひ一度、確認してみましょう。