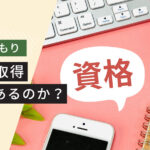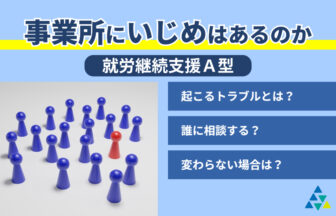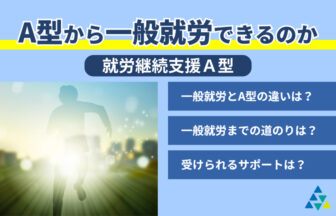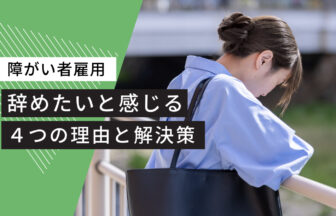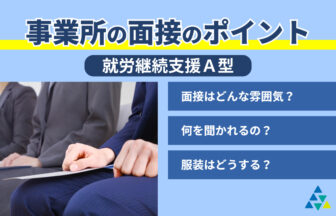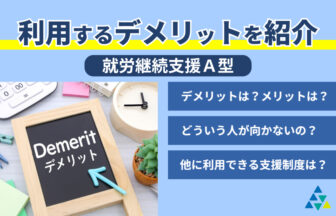「いきなり長時間働くのは不安があるから、短時間から働きたい…」
などの不安や悩みはありませんか?新しい仕事探しはどうしても不安でいっぱいになりますよね。誰しも、最初の一歩を踏み出すには相当な勇気がいることでしょう。
仕事に対して不安がある障がい者の方に向けた制度として、「障害者トライアル雇用制度」があるのはご存じでしょうか。
- 「障害者トライアル雇用」「障害者短時間トライアル雇用」とは何か
- 制度を利用する際のメリット・デメリット
- 応募方法
- 就労移行支援や就労継続支援との違い
について解説します。
利用方法やメリット、デメリットなどを知ることで新しい就職先へと繋げていきましょう。
障がい者トライアル雇用制度とは

障害者トライアル雇用制度は障がい者それぞれの仕事に対する適性を見極めながら、新たな就職への道筋を作ることを目的として作られた制度です。
仕事に対して不安のある方や働いた経験がない方でも、必ず面接を受けて、採用されればトライアル雇用として職場に入り、実際の仕事を体験することができます。実際に働きながら業務内容や職場環境を確認し、働き続けることができるかを判断します。
就職を希望する障がい者は原則3か月、精神障害・発達障害の場合は最長12か月まで、トライアル雇用として働くことが可能です。
契約期間終了後、本人と会社の双方が雇用継続を希望する場合、そのまま続けて働くことができます。ただし、それぞれの企業によって定められている年齢などの条件・規定は満たす必要があります。
試しに働いてみたものの、残念ながら仕事内容が合わないと感じた場合やこれ以上就労継続が困難と判断された場合は、その時点で契約終了とすることもできます。ちなみに、この制度を利用した8割以上の方は正式雇用へ移行しています。
障がい者トライアル雇用制度を利用できる人は?
障害者トライアル雇用制度を利用できる方は、「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に定められた障がい者に該当する、
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者障害者の雇用の促進等に関する法律|e-GOV法令検索
です。
障がいの原因や種類は問われません。障がいにより仕事をする上で制限や困難のある方が対象となります。
障害者トライアル雇用を利用するには、「継続雇用されることを希望するしており、障害者トライアル雇用制度を理解したうえで、障害者トライアル雇用によって雇われることも希望している」ことに加えて、下記のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望していること
- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返していること
- 紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えていること
- 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
障がい者短時間トライアル雇用とは?
週20時間以上の勤務が難しい方に対し、週10~20時間で短時間の試行的雇用から開始し、職場への適応状況や体調などに応じて、トライアル雇用期間中に20時間以上の就労を目指す制度「障害者短時間トライアル」もあります。
対象となるのは、継続雇用されることを希望しており、障害者短時間トライアル雇用制度について理解したうえで、障害者短時間トライアル雇用によって雇われることも希望している精神障害または発達障害のある方が対象です。
テレワークによる勤務を行う場合は?
障害特性によって通勤困難な方や在宅勤務を希望する方などが能力を発揮する方法として、テレワークがあります。
しかし、企業ごとに異なるテレワークの環境に適応できるか見定めるには3か月という機関では足りない場合があります。そのため、原則3か月のトライアル雇用期間を最長6か月まで延長できます。
「テレワークによる勤務」とは、対象労働者の1週間の所定労働時間の2分の1以上、情報通信技術を活用して勤務していることをいいます。ただし、在宅またはサテライトオフィスでの勤務に限られています。
助成金の支給額変更、期間延長分の助成金支給はないので注意が必要です。
一般トライアル雇用については、下記の記事で解説しています。
障がい者トライアル雇用を利用するメリットとデメリットは?

障害者トライアル雇用後もおよそ8割の方が継続雇用されています。
| 継続雇用率 | |
| 令和2年 | 81.4% |
| 令和3年 | 80.4% |
| 令和4年 | 80.3% |
トライアル後の就職率が8割以上と非常に魅力的な「障害者トライアル雇用制度」ですが、メリットばかりではありません。詳しく見ていきましょう。
利用者側のメリット・デメリット
まずは利用者側、働く側のメリットを見ていきましょう。
メリット
- 応募すればそのまま面接へと進むため、一般的な就職よりも就労へのハードルが低い
- 一緒に働く上司や同僚を事前に知ることで、人に対する不安を軽減できる
- 実際の仕事での適性を本採用前に確かめられるので、仕事への不安を軽減できる
- 賃金を受け取りながら職場でのスキルを習得できる
デメリット
- トライアル雇用期間終了後、確実に採用されるとは限らない
- 複数の企業へ同時に応募することはできない
- 不採用の場合は新たな求人を再び探すことになる
障害者トライアル雇用を利用するメリットとして、応募すれば書類選考なしで面接へと進むため、就労に向けてのハードルが低いことが挙げられます。
仕事内容や職場環境、人間関係などを確かめてから就職できるので、安定して長く働き続けられる傾向があります。また、「初めての業務が上手くできるか?」「人間関係はうまくいくか?」などの不安の解消にも役立ちます。
賃金を受け取りながら職場でのスキルを習得できる点もメリットと言えます。
ただし、トライアル雇用制度を利用したからと言って、確実に採用されるとは限りません。また、複数の企業で障害者トライアル雇用を利用することはできませんし、不採用となった場合、新たな求人を探すことになります。
会社側のメリット・デメリット
次に会社側、雇用する側のメリットを見ていきましょう。
メリット
- 会社が求める仕事への適性を本採用前に確認できる
- トライアル雇用の時点で働きやすい労働環境を準備し、実際の仕事を通して試すことができる
- 実際の職場における本人の状況を周りが具体的に把握することができる
- 助成金が支給されるため、コスト面の不安を軽減できる
- トライアル雇用修了後も雇用を継続する場合、条件に該当すれば、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース※)、障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)などを申請可能
※:高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる場合
デメリット
- 仕事に慣れるまでに時間がかかるケースも多く、採用判断が難しい
- 助成金を受給するまでの手続きに労力が必要
- 求人数以上の障害者トライアル雇用の実施はできない
障害者トライアル雇用は、利用者だけでなく、企業側にもメリットがあります。「雇用経験がないため、漠然とした不安がある」「配置する部署が障がい者との関わりが初めて」など、障害者雇用に対して不安がある企業も少なくありません。障害者トライアル雇用を行うことで、働く能力を確認でき、雇用する不安を軽減することができます。
実際の職場での本人の状況を周りが把握して、合理的配慮、働きやすい労働環境の準備も可能です。
また、一定の条件を満たせば助成金が支給されるため、採用のコストを減らせることもメリットと言えます。
デメリットとしては、仕事に慣れるまでに時間がかかるケースが多く、即戦力とは限らない可能性があることです。だからと言って求人数以上の実施はできないため、求人数を定めずに障害者トライアル雇用を実施することはできません。
また、助成金受給の手続きが少々煩雑なため、労力がかかる点もデメリットでしょう。
障がい者トライアル雇用制度助成金とは?
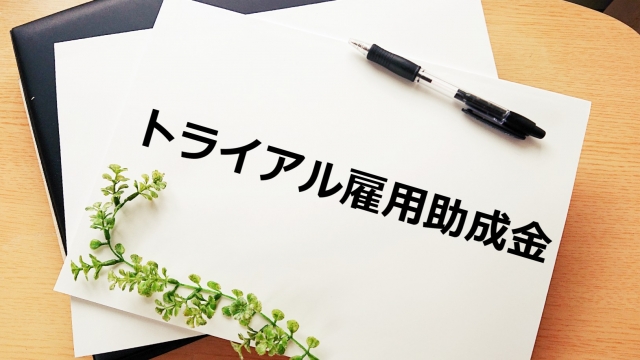
「障害者トライアル雇用制度助成金」とは、障害者雇用の促進と継続的な雇用の促進を目的として、障がいのある方を雇用する会社に対して助成金が支払われる制度です。
- 重度身体障害者、重度知的障害者の場合は1人につき月額4万円(最長3か月)
- 精神障害者の場合は月額8万円(最初の3か月)+月額4万円(残りの3か月)
のように、特に精神障害者に対して手厚い助成がされています。
「障害者短時間トライアル雇用」の場合も、同様に月額最大4万円(最長12か月間)が雇用者に支給されます。
障がい者トライアル雇用への応募方法
- ハローワークへ電話や対面で相談
- 求人を紹介してもらい、ハローワークから企業へトライアル雇用を申し込む
- 面接が行われる
- トライアル雇用開始
障害者トライアル雇用への応募は主にハローワークで行います。
まずはお住まいの地域のハローワークへ電話で相談したり、実際に訪問して話を聞いてみましょう。
ハローワークでは障害特性に合わせた働き方のアドバイスを専門家から聞くことができますし、求職登録をすれば、トライアル雇用制度を導入している企業へ応募もできます。
また、ハローワーク以外にも、障がいのある方に対して就職支援を行っている「地域障害者職業センター」および「就労移行支援事業所」で「障害者トライアル雇用」の申し込みができます。その場合、職業センターや事業者がハローワークを通して応募を行うことになります。そのため、ハローワークへの求職者登録は必須です。
トライアル雇用制度では、書類選考ではなく面接採用が原則とされており、面接後に採用が決まれば雇用契約を結び、トライアル雇用がスタートする流れとなっています。
障がい者トライアル雇用と就労移行支援・就労継続支援の違い
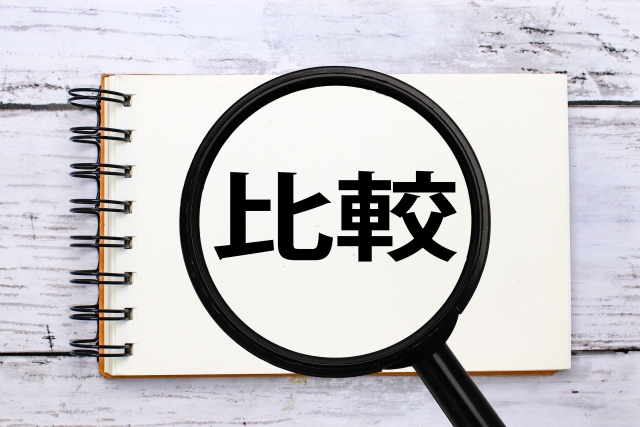
障がい者の就労を支援する制度としては、障害者トライアル雇用制度の他にも「就労移行支援」と「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」があります。
就労移行支援
就労移行支援とは、一般企業への就職を目指している方が求職活動前に、ビジネスマナーやコミュニケーションなど足りない知識やスキルを身につけたいときに受けることができる支援です。雇用契約はなく、生産活動は行わないので基本的に工賃も発生しませんが、職業訓練に近いサービスを受けることができるシステムです。
例として、個人の不安に配慮した少人数制のプログラムに強みを持つ「ココルポート」や、発達障がいに特化した「atGPジョブトレ 発達障害者コース」のようなものがあります。
就労移行支援そのものについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
就労継続支援
一般就労する体力がまだない、とても不安があるという方には、一般就労が困難な方向けの制度である「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」がオススメです。
- 就労継続支援A型事業所
雇用契約を結び、最低賃金(時給)が保障された就労機会を提供。
事業所によって多様性があるが、さまざまな分野での単純作業や専門性のある業務を行う。 - 就労継続支援B型事業所
雇用契約を結ばず、工賃払いでの生産活動の場を主に提供。
事業所によって多様だが、さまざまな分野の単純作業が中心。
就労移行支援や就労継続支援は、主に一般企業への就職を希望する障がいおよび難病のある65歳未満の方が支援を受けることができます。
いきなり3か月以上の障害者トライアル雇用に挑戦することに不安のある方は、「就労移行支援」と「就労継続支援」という段階的な選択肢もあることを頭の隅に置いておきましょう。
自分に合った適切な支援を受けるために、今の自分自身に「何ができて、何ができないのか」を把握しておくことは大切です。しかし、1人では判断が難しい場合、制度を利用する際、相談窓口の担当者に自身の現状を伝えてみるのも一つの方法です。
まとめ|障がい者トライアル雇用とは
- 「障害者トライアル雇用」は、原則3か月間、精神障害や発達障害の場合は最長12か月間、会社で試しに働くことができる制度。
- 週20時間以上の勤務が難しい場合、短時間(週10~20時間程度)から働ける「障害者短時間トライアル雇用」もある。
- 設定された期間を終了後、そのまま継続雇用への移行も可能で、トライアル雇用制度を利用した8割以上の方が、正式に雇用されている。
- 障がい者向けの就労支援として、トライアル雇用の他、就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)がある。
利用者、企業側ともにメリットが多くある「障害者トライアル雇用制度」を利用して、是非とも自分に適した新しい仕事を見つけましょう。