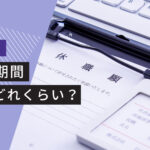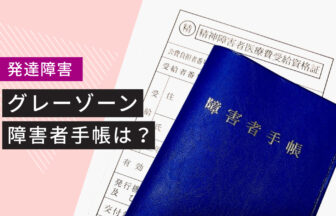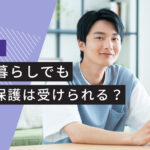「ギャンブルが頭から離れられず、浪費がやめられない…」
あなたには、このような悩みはありませんか?
パチンコをはじめとするギャンブルに手を出して依存症になってしまうのは、発達障がいの特性が原因かもれません。
- 発達障がいと依存症の関係
- ADHDとギャンブル依存症の関係
- ギャンブル依存症の対策
- ギャンブル依存症で困った時の相談先
を紹介していきます。ギャンブル依存症になってしまう原因を確認し、一緒に対策を考えていきましょう。
発達障がいと依存症の関係
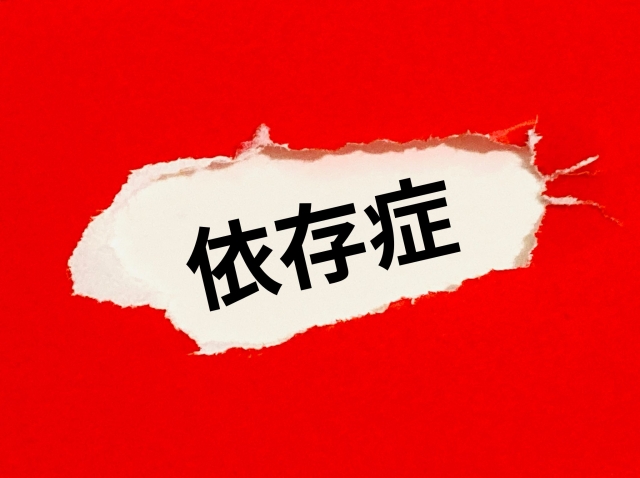
発達障がいのある方が依存症になりやすいとされる理由には、2つの要因があります。1つ目はストレスの発散、そして2つ目は脳の報酬系機能の低下です。
1.ストレスの発散
発達障がいの方は社会の中でさまざまな生きづらさを抱えやすく、ストレスを溜めこみやすいです。その結果、ストレス発散のために、ギャンブル・アルコール・スマートフォン・ゲーム・薬物などを利用するようになり、依存していってしまうことがあります。
2.脳の報酬系機能の低下
「報酬系」を調べると、下記の内容が出てきます。
欲求が満たされたときや満たされるとわかったとき、あるいは報酬2を期待して行動しているときに活性化し、快感をもたらす神経系。脳内報酬系。※報酬2:脳科学において、人に特定の行動を促す、快感をもたらす刺激。また、その原因となるもの。引用:報酬系|デジタル大辞泉|コトバンク
つまり、報酬系機能とは、快感や満足感を得られる行動を繰り返そうとする脳の仕組みのことです。
報酬系機能が低下していると、日常生活や社会生活の中で脳が快感や満足感を得られなくなるため、より強い刺激を受けられる行為に熱中しやすくなります。発達障がいの方は、後述するドーパミン不足との関係で報酬系機能が低下しやすい傾向があるため、依存症になりやすい傾向にあります。
上記のように、発達障がいと依存症の関係は、生きづらさから来るストレスの発散と、脳の報酬系機能の低下という2つの要因によってもたらされています。
中でも脳の報酬系機能の低下は、ADHD(注意欠如・多動症)の方に多くみられる特性です。この項目では、ADHDの方が依存症になりやすい理由を解説していきます。
ADHDが依存症になりやすい2つの要因
依存症研究を行っている依存症対策全国センターは、ADHDの方が依存症と重複しやすいことを指摘しています。実際に、海外のデータではADHDの方の15.2%が物質関連障がい※・依存症を併発していると発表されています。
※物質関連障がい
物質関連症は、アルコール、カフェイン、タバコ、違法薬物(例:覚醒剤、コカイン、大麻)などの物質が、過剰使用や依存によって以下のような影響を及ぼす状態を指します。
- 身体的依存:物質を摂取しないと禁断症状が現れる。
- 精神的依存:物質に対する強い渇望があり、摂取をやめられない。
- 社会的機能の低下:仕事、学校、家庭など日常生活における役割が果たせなくなる。
また、2020年に公開された『成人の発達障がいに合併する精神及び身体症状・疾患に関する研究』での調査によると、ADHDの成人が合併する疾患の5.0%が依存症の診断を受けたことがある、という結果が出ています。この調査での回答者は若年層に偏っているため、実際に依存症を併発している方の割合はもう少し高い可能性があります。
では、なぜADHDの方は依存症になりやすいのでしょうか?
これには、前述した「報酬系機能の低下」とADHDの特性である「衝動性」の2つの要因が関わっています。
次の項目で解説していきます。
ドーパミンの不足による報酬系機能の低下
先述した報酬系機能は、ドーパミンという神経伝達物質と密接に関わりがあります。
ドーパミンは、分泌することで脳内の報酬系機能が活性化し、快感を与えたり意欲や集中力を高めたりする効果があります。ドーパミンが不足してしまうと報酬系機能が低下し、抑うつ気分になりやすく、やる気が起きない、気分が落ち込むなどの状態になります。
しかし、ADHDの場合、脳機能の異常により元々ドーパミン分泌量が少なかったり、うまく調整できなかったりすることが多いため、慢性的な意欲や集中力の低下が起こります。そのため、ドーパミン不足による報酬系機能を補うために刺激を求めて、ギャンブルやアルコール、タバコ、スマートフォン、ゲームなどに依存していくのです。
衝動性
ADHDの代表的な特性として
- 不注意傾向
集中力が途切れやすく、注意散漫で忘れっぽい。
物事に集中できない、忘れっぽい、計画を立てることが苦手など。 - 多動性
落ち着きがない、感情や欲求が変化しやすい。
じっとしているのが苦手、手遊びや貧乏ゆすりが止められないなど。 - 衝動性
思いついたことや、外部からの刺激に対して、衝動的に反応・行動してしまう。
我慢ができない、余計な一言を口に出してしまう、衝動買いなど。
の3つがあります。
「衝動性」の特性は、欲望のコントロールが難しく、長期的に我慢して得られる報酬よりすぐに得られる報酬を優先してしまうという影響を与えます。
そのため、ハイリスクでありながらもハイリターンに期待できるギャンブルや、すぐに快楽を得られるアルコール、タバコ、ゲームなどへの依存につながっていくのです。
ギャンブル依存症とは?定義・診断基準について
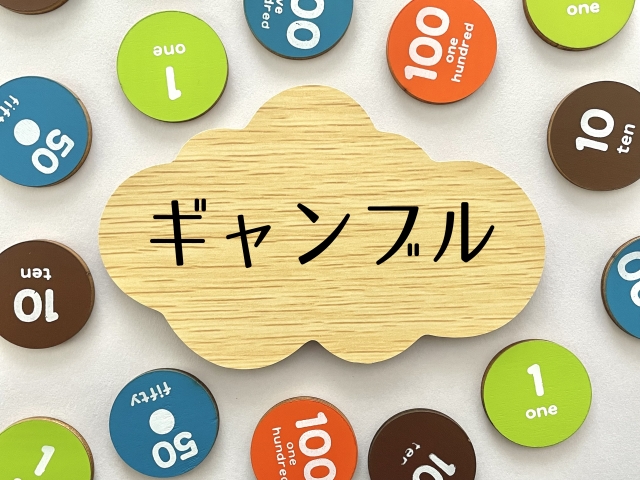
ここまで、発達障がいと依存症の関係に注目して、ADHDの方が依存症になりやすいことを解説してきました。
では、「ギャンブル依存症」とは、一体どのような依存症なのでしょうか?
この項目では、改めてギャンブル依存症の定義について確認していきましょう。
ギャンブル依存症の定義とは?
「依存症」について、厚生労働省では
特定の何かに心を奪われ、「やめたくても、やめられない」状態になることです。
人が「依存」する対象は様々ですが、代表的なものに、アルコール・薬物・ギャンブル等があります。
このような特定の物質や行為・過程に対して、やめたくても、やめられないほどほどにできない状態をいわゆる依存症といいます。
引用:依存症についてもっと知りたい方へ|厚生労働省
と定義しています。
つまり、「ギャンブル依存症」は、「ギャンブルの行為や過程に心を奪われ、やめたくてもやめられない状態になること」です。
より具体的に説明すると、ギャンブルによって普段の生活や社会活動に支障が出る精神疾患で、自分に不利益、有害な結果を生じていて、やめたいと考えることはできても、コントロールできずに、ギャンブルを続けたいという衝動が抑えられない状態のことを指します。
ギャンブル依存症の診断基準
ギャンブル依存症は米国の診断基準(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5)で下記のように定められています。
(1) 興奮を得たいがために、掛け金の額を増やし賭博をする欲求。
(2) 賭博をするのを中断したり、または中止したりすると落ち着かなくなる。またはいらだつ。
(3) 賭博をするのを制限する、減らす、または中止したりするなどの努力を繰り返し成功しなかったことがある。
(4) しばしば賭博に心を奪われている(例: 過去の賭博体験を再体験すること、ハンディをつけること、または次の賭けの計画を立てること、賭博をするための金銭を得る方法を考えること、を絶えず考えている)。
(5) 苦痛の気分(例: 無気力、罪悪感、不安、抑うつ)のときに、賭博をすることが多い。
(6) 賭博で金をすった後、別の日にそれを取り戻しに帰ってくることが多い(失った金を“深追いする”)。
(7) 賭博へののめり込みを隠すために、嘘をつく。
(8) 賭博のために、重要な人間関係、仕事、教育、または職業上の機会を危険にさらし、または失ったことがある。
(9) 賭博によって引き起こされた絶望的な経済状態を免れるために、他人に金を出してくれるよう頼む。引用:DSM-5 によるギャンブル障害の診断基準|第1章 ギャンブル依存症とは?|
『ギャンブル依存症サバイバル』|中外医学社
上記の9項目のうち、過去12か月間に4項目以上に当てはまると依存症の可能性が疑われます。
ギャンブル依存症の方の考え方|どんな結末を招くのか?
ギャンブル依存症の方は、先述した診断基準に加えて、
- 負けが続いても最終的には勝てると確信している
- 負けた時のことはよく覚えていないのに、勝った時のことはよく覚えている
- 迷信的な行動で運をコントロールできると信じる
など、ギャンブルに対して偏った考えを持っていることが多くあります。
あなたがこのような感覚に陥っていたり、周囲にこのような考えを持っている方がいたりする場合、ギャンブル依存症の可能性はさらに高まるでしょう。
ギャンブルに対する考え方が偏ると、生活にもさまざまな支障が出てしまいます。
最も大きな影響としては、経済的問題です。ギャンブル依存症になると、借金をしてでもギャンブルをしてしまうため、貯金を使い果たし、さらに多重債務を抱えて破産することがあります。家族や友人がいる場合、その関係が悪化することも考えられるでしょう。
また、そこから連鎖してお金を盗む、詐欺行為を行う、などといった犯罪行為に手を染めてしまう可能性もあります。
これらは一部ですが、ギャンブル依存症になってしまうと、このように生活が破綻して深刻な事態に至る場合があります。
ギャンブルにはADHDの方が依存しやすい要素が多い
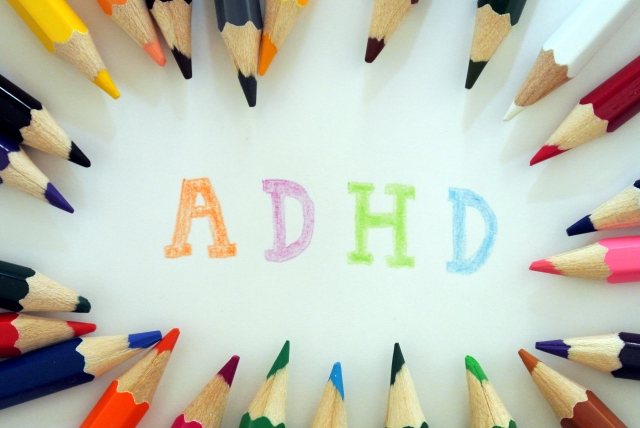
先にも紹介した依存症対策全国センターの研究では、海外のデータに基づきギャンブル依存症患者のうち約15%がADHDであったことを示しています。
これは、ギャンブルがドーパミンの分泌と衝動性を強く刺激してしまうためです。
この項目では、ギャンブルがなぜこの2つの原因を刺激しやすいのか、ギャンブル特有の性質に注目して解説していきます。
1.お金を儲けることでドーパミンが強く分泌される
ドーパミンは、やる気や集中力を高めるだけでなく、快楽に関わる物質でもあります。ギャンブルは成功すれば実際にお金を儲けることができるので、1度でも「ギャンブルで勝った」という成功体験があるとドーパミンが大量に分泌され、快楽を感じるようになります。この経験は、「また儲かるかもしれない」という期待感を生み出して、ギャンブルが習慣化するきっかけにつながります。
さらに、ギャンブルが習慣化すればするほど、ドーパミンが分泌される量や頻度も増え、快楽や喜びを感じやすくなります。しかし、この習慣を長期的に続けると耐性ができてしまい、次第に通常のギャンブルでは快感を得られなくなっていきます。負けが続いた場合にストレスが蓄積してしまうこともあるでしょう。
その結果、「常にギャンブルをしていないと落ち着かない」という依存症状態に陥り、「過去の負けを取り返したい」「もっとハイリスク・ハイリターンなギャンブルがしたい」と考えて、より大きな賭けに手を出しやすくなってしまいます。
2.すぐに報酬を得ることができる
ギャンブルには、勝ち負けがすぐに分かりやすく、勝った場合は即座に報酬が得られるという性質があります。先述した通り、ADHDの衝動性はすぐに得られる報酬を優先する傾向がある特性です。ギャンブルには衝動性を刺激する要素が多く含まれていることが分かります。
私たちの脳はスリルを感じるとドーパミンの分泌量が増加して興奮状態に入る構造になっているため、ドーパミンの分泌量に異常が見られやすいADHDの方は、ギャンブル特有の「結果がどうなるか分からない」というスリルによってさらに衝動性が高まりやすいのです。
また、パチンコなどの遊技機は音や光などの過剰な演出による刺激でドーパミンを分泌させる仕組みとなっており、依存しやすい傾向があります。
上記のような理由から、ADHDの方はギャンブル依存症になりやすいといえます。
自分でできる、ギャンブル依存症の改善方法3選

自分がギャンブル依存症ではないかと思ったら、どうすれば良いのでしょうか?
最適なのは病院受診やカウンセラーへの相談ですが、病院に抵抗がある方や、受診・相談までに時間がかかる方もいらっしゃるでしょう。
この項目では、自分でできる3つの改善方法を紹介します。順に見ていきましょう。
人とコミュニケーションをとる
人とコミュニケーションをとったり、触れ合ったりすることで、脳内のドーパミンが分泌されます。特に自分の話をしている時に、ドーパミンは多く分泌されることがわかっていますので、まずは自分のことを話すことができる相手を見つけ、コミュニケーションをとるようにしましょう。
新しい趣味や活動を見つける
ギャンブル以外に打ち込める新しい趣味や活動を見つけることは、ギャンブルへの依存や欲求を減らすことにつながります。ギャンブルについて意識的に考えない時間をつくるために、集中できることや趣味を見つけましょう。
金銭管理を徹底する・他の人にお願いする
金銭管理の意識を高めることは、ギャンブル依存症の改善に効果的です。不要な銀行口座やクレジットカードを解約して、収入と支出をしっかり把握するように努めましょう。
また、家族や信頼できる方にお金を管理してもらうことで、ギャンブルをするお金がない状況を作りだすこともできます。ギャンブルと物理的に距離を置くことができれば、依存できない状況を作れます。
上記の3つの対策によって、ギャンブル依存症を治していきましょう。
困ったときの相談先・専門機関

依存症から自力で回復するのは非常に難しいことです。そのため、専門機関への相談や適切な治療を受けることが、最も効果的な改善方法と言えるでしょう。
この項目では、ギャンブル依存症の方が相談できる専門機関について、順に見ていきましょう。
医療機関
医療機関、特に依存症対策に力を入れている医師がいる心療内科・精神科を受診すると良いでしょう。「認知行動療法」という考え方や行動に働きかける手助けをする治療や、投薬による治療を受けることができます。
回復には時間がかかりますが、あきらめずに続けていくことが大切です。
精神保健福祉センター
精神保健福祉センターとは、精神保健の向上および精神障害者の福祉の増進を図るために、国が各都道府県および政令指定都市に設けている施設です。ここでは、ギャンブル依存症などの依存症対策について、予防から社会復帰まで対応しています。相談が主な業務となっていますが、一部のセンターでは、精神科デイケアを受けることもできます。
下記のリンクから、全国の精神保健福祉センターを探すことができます。
全国の精神保健福祉センター|厚生労働省
精神科デイケアではどんなことをするのか気になる方は、下記の記事を参考にしてみてください。
ギャンブラーズ・アノニマス(GA)
ギャンブラーズ・アノニマス(GA)とは、ギャンブル依存症当事者の自助グループです。
ここでは、依存症に悩む方や回復を目指す方が話し合うことで、互いの「ギャンブルをしない」という意思を支えあって回復を目指しています。GAは全国にグループがあり、定期的にミーティングを開いており、こちらに参加することもできます。
あくまで自助グループであり、登録や参加費などはありません。「ギャンブルを辞めたい」とお悩みの方は参加してみてはいかがでしょうか。
Gamblers Anonymous Japan Information Center(GA日本インフォメーションセンター)
発達障がい者支援センター
依存症になっている原因が発達障がいであることがわかっているのであれば、発達障がい者支援センターを頼ることもできます。
ここでは、発達障がい者とその家族が豊かな地域生活を送れるように、関係機関と連携し、地域における総合的な支援ネットワークを構築しながら、発達障がい者とその家族、関係機関の職員からのさまざまな相談に応じ、指導と助言を行っています。
発達障がい者支援センターについては、下記の記事で詳しく解説しています。
依存症に関しての相談ができる窓口は全国にあります。
全国にある依存症専門の相談窓口は下記のリンクから探すことができます。
全国の相談窓口・医療機関を探す|依存症対策全国センター
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、主に一般就労を目指す障がい者の支援を目的とした支援機関ですが、その一環として生活支援も行っています。
お金の使い方からアドバイスをもらうことができるので、ギャンブル依存症で困っているADHDの方が生活を立て直すきっかけを作るのに最適です。
障がい者手帳が無くても、医師の診断書さえあれば利用できます。以下はおすすめの就労移行支援事業所です。無料見学も受け付けているので、気になる方はチェックしてみてください。
ココルポート
ココルポートは、温かく包み込むような支援スタイルが特徴の就労移行支援事業所です。ADHDの方も安心して通えるよう、一人ひとりの心境に配慮した、無理のないペースでのプログラムを提供しています。
基本的なPCスキルからグループワークまで、多様な活動を通じて「できること」を増やしながらギャンブル依存症を改善していくことができます。相談しやすい環境が魅力です。
atGpジョブトレ 発達障害コース
atGpジョブトレ 発達障害コースは、発達障がいのある方に特化した就労移行支援事業所です。発達障がい者に対するサポート実績が豊富で、ギャンブル依存症のADHDの方にも効果的なサポートを提供しています。
専任のスタッフが、こまめな個別面談を通じてあなたの問題の対処法について一緒に考えてくれます。もちろん就労についてのサポートも手厚いので、利用できれば社会復帰もスムーズです。
ギャンブル依存症でも障がい者手帳や障がい年金はもらえるのか?
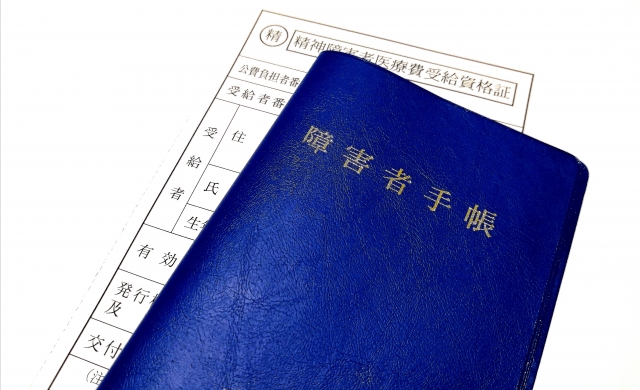
結論だけでいえば、ギャンブル依存症のみの診断では、障がい者手帳や障がい年金をもらうことはできません。ギャンブル依存症は医療機関での治療が必要な精神障がいですが、国のガイドラインでは、精神障がいのうち依存症などの一部の精神疾患は、対象外とされています。
しかし、ADHDなどの発達障がいが原因で依存症を併発している場合、発達障がいの程度によっては精神障がい者保健福祉手帳を取得できる場合もあります。お住まいの自治体の福祉相談窓口や、かかりつけ医に確認してみると良いでしょう。
発達障がいと精神障がい者保健福祉手帳の取得については、下記の記事で詳しく解説しています。
周囲にギャンブル依存症で困っている方がいたら

依存症は本人だけでなく、家族や周囲も巻き込んで、生活にさまざまな影響を及ぼしてしまう場合もあります。
周囲の方は、「自分の関わり方が悪かった」と思わず、依存症に対する正しい知識を得ることから始めましょう。そして、先述した医療機関や相談機関へ、早めに相談することが大切です。また自助クループは、当事者向けの物だけでなく、「家族会」もありますので、そちらの利用を検討してみても良いでしょう。
依存症の本人も治療を拒否しているように見えても、実は「治療や相談をうけてみようかな」という気持ちを持っている場合があります。本人がギャンブル依存症を自覚していたり悩みを抱えたりしている場合は、治療の提案を受け入れてもらいやすいでしょう。本人が関心を示したら「一緒に行ってみる?」など、声をかけてみることが大切です。
下記の記事は発達障害の診察を勧める場合のケースですが、今回のテーマとの共通点もあるので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
まとめ|ADHD(注意欠如・多動症)とギャンブル依存の原因・対策
- 発達障がいの方は、生きづらさから来るストレスの発散や、報酬系機能(ドーパミン)の低下により、依存症になりやすい傾向がある。特にADHDの方は、もともとドーパミンの分泌量が少なく、衝動性の特性により目の前の快楽に手を出しやすいため、依存症になりやすい。
- 特にギャンブルは、即時にお金という報酬が手に入るので、ドーパミンの分泌と衝動性が刺激されやすく、依存症になりやすい。
- ギャンブル依存症になると、貯金を使い果たしたり、借金をしてしまったりして、生活が苦しくなる。また、それが原因で人間関係の悪化や犯罪に手を染めてしまうこともある。
- ギャンブル依存症を治すには、専門機関を頼ることが必要。自分でできる対策としては、他の人とコミュニケーションをとる、他に打ち込めるものをつくる、お金を他人に管理してもらうことなどが挙げられる。
- ギャンブル依存症で困ったときに相談できる機関としては、心療内科などの医療機関、精神保健福祉センター、ギャンブラーズ・アノニマス(GA)などがある。
- ギャンブル依存症では障がい者手帳や障がい年金はもらえないが、ADHDなどの発達障がいに起因する依存症の場合、取得できる場合がある。
- 周囲にギャンブル依存症で困っている人がいたら、本人が悩んでいる時に、早めの受診を勧めると良い。ただし、決して相手の依存症を見逃してしまった自分を責めることはしない。
いかがだったでしょうか?自分がギャンブル依存症かもしれないと感じたら、臆することなく、周りの方や専門機関を頼りましょう。
依存症の回復には時間がかかるとされており、長期間、ゆっくりと歩んでいくことになります。また、一時的に依存を止めることができても、ささいなことがきっかけで再燃してしまうこともあります。しかし、それであきらめずに再度治療をすることが大切です。
依存症対策については、厚生労働省のサイトにもまとめられています。
依存症対策|厚生労働省
この記事がギャンブル依存症に悩む発達障がい(ADHD)の方の参考となれば幸いです。