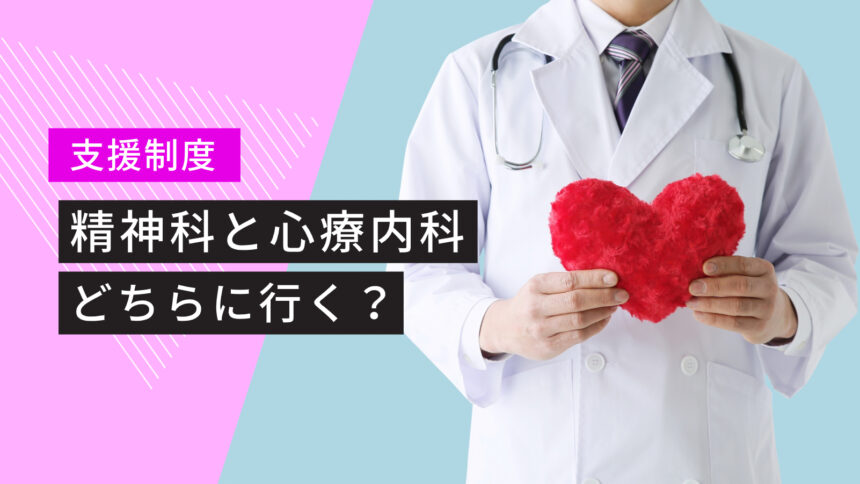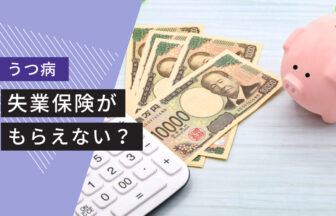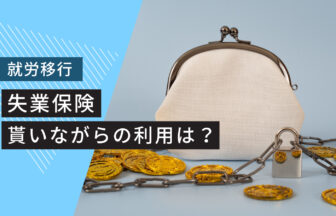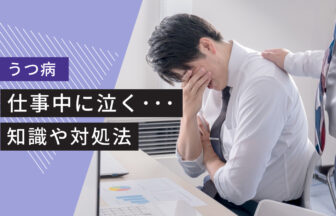「精神科と心療内科どっちに行けばいいの?」
この記事を読んでいるあなたにも、こうした疑問はありませんか?
精神に不調をきたして治療を受けたいと思った時、多くの方は「精神科」や「心療内科」を思い浮かべるのではないでしょうか。
しかし、この2つの違いがよくわからない方も多いでしょう。
日常生活で馴染みがないと、どちらを受診すれば良いか分からないですよね。
- 精神科、心療内科、メンタルクリニックの違い
- 受診すべき科の判断ポイント
- 精神科と心療内科の初診の流れ
について解説します。
あなたの不安が少しでも軽くなれば幸いです。
精神科・心療内科・メンタルクリニックの違い

精神科と心療内科は、「こころ」に関係する不調を治療する場所です。
ただし、厳密には下記のような違いがあります。
| 診療科目 | 精神科 | 心療内科 |
|---|---|---|
| 違い | 「こころの不調そのもの」を治療する | 「心理的ストレスが原因の体の不調」を治療する |
さらに、これらと混同されがちな言葉として、「メンタルクリニック」が挙げられます。
こちらは、精神科や心療内科がある診療所のことを指します。
精神科、心療内科、メンタルクリニックの詳しい特徴について確認していきましょう。
精神科とは?
精神科とは、「こころの病気」を専門に治療を行う施設です。具体的には「うつ病」や「依存症」など、こころの不調そのものに対する治療を行います。
精神科の検査や治療法は、施設によっても異なりますが、下記のものが一般的です。
- 身体検査
- 血液検査
- 薬物療法
- 心理療法(カウンセリング)
- 生活指導
心療内科とは?
心療内科は、「心理的ストレスが原因で体にあらわれる症状」を治療する施設です。具体的には、心理的ストレスによって起きる「腹痛」や「過呼吸」などがこれに該当します。
※心理的ストレスとは、仕事のプレッシャーや職場の人間関係などからくるストレスのことです。
心療内科の検査や治療法は、下記のように精神科と共通するものが多いです。
- 身体検査
- 血液検査
- 薬物療法
- 心理療法(カウンセリング)
- 生活指導
メンタルクリニックとは?
メンタルクリニックは、精神科や心療内科がある診療所(※)のことです。
精神科や心療内科を受診したいときは、病院やメンタルクリニックに通うことになるでしょう。
受信する科目の判断ポイント

では、精神科と心療内科はそれぞれどのような人が受診すべきなのでしょうか。
下の表に、科目を判断する大まかなポイントをまとめました。
| 受診する科 | 判断ポイント | 具体例 |
|---|---|---|
| 精神科 | こころの症状がはっきりしている |
|
| 心療内科 | 心理的ストレスが原因で体の不調が続く |
|
詳しく説明していきます。
精神科を受診すべき人
こころの症状がはっきりしている場合は、精神科を受診してみてください。
- 【精神科を受診すべき人の主な症状】
- やる気が出ない
- 気分が落ち込む
- 何をしても楽しくない
- 不意に涙が出てくる
- 会社に行けない
- 仕事に集中できない
- 仕事でミスが多い
- 起きるのが辛い(仕事の日)
- 気分に波がある
精神科を受診する方は、このような症状が多いです。
症状や検査結果をもとに、医師があなたの「こころの状態」を判断してくれます。
心療内科を受診すべき人
心理的ストレスが原因で体の不調が続くときは、心療内科を受診してみてください。
- 【心療内科を受診すべき人の主な症状】
- 会社に行く前に腹痛が起きる
- 車や電車に乗ると過呼吸になる(通勤のとき)
- 原因不明の頭痛、吐き気が続く
- 寝ても体の疲れが取れない
- 耳鳴りが続く
- 音や光に敏感になった
- 冷や汗が止まらない
心療内科を受診する方は、このような症状が多いです。
腹痛や吐き気などの体調不良は、心理的ストレスが原因となる場合があります。原因が分からない体調不良が続くときも、心療内科を受診してみると良いでしょう。
どちらを受診するべきか迷った時の対処法
どちらを受診すべきか決められないときは、精神科と心療内科が併設されている病院やメンタルクリニックを選ぶと良いでしょう。
そうすることで、窓口の方が適切な科目に案内してくれます。
- <手順>
- 1.ネットで精神科と心療内科が併設されている病院を探す
- 2.電話で予約するときに「どちらの科を予約すればいいかわからない」と伝える
Webサイトにある「お問い合わせ」から確認しても良いでしょう。
受診に抵抗がある時の対処法
精神科や心療内科の受診に抵抗があるなら、まずは相談窓口を活用してみるのも良いでしょう。
その一つとして、「こころの耳相談」をオススメします。株式会社法研に委託運営されている「こころの耳相談」は、メンタルヘルスの不調に困っている方を対象とした相談窓口です。
人間関係や仕事の悩みに対応し、あなたの「こころ」の健康をサポートしてくれます。
「こころの耳相談」には、下記の方法で相談が可能です。
- 電話(フリーダイヤル 料金無料)
- SNS(LINE)
- メール
守秘義務があるため、ここで話したあなたの情報が他の方に伝わることはありません。安心して利用してくださいね。
早期診断・早期治療が重要
メンタルの不調をどうにかしたいけど、受診するべきか悩むこともあるでしょう。
あなたが少しでも「こころの不調」を感じているのなら、勇気を出して受診してみてください。早期診断や早期治療できれば回復も早くなるでしょう。
厚生労働省の情報サイトにも、次のような記載があります。
近年、心の病気についてもできるだけ早くその症状に気づき、正しい対処や治療が速やかになされれば、回復も早く軽症で済む可能性があることがわかってきました。精神疾患の早期発見・治療の重要性|健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~|厚生労働省
筆者は、精神疾患で精神科に通院しています。メンタルの不調を感じてから2週間ほどで精神科を受診しました。早期診断したおかげもあり、今は服薬と通院をしながら働くことができています。
そのため、迷ったら精神科や心療内科を受診することをオススメします。
精神科と心療内科の初診の流れ

受診するにあたって不安が大きい方は、診断の流れを事前にイメージしておくと良いでしょう。
精神科や心療内科の初診の流れは、おおよそ下記の通りです。
- 予約
- 受付
- 診察
- 会計
詳しく確認していきましょう。
精神科や心療内科の診察は、基本的に予約制です。基本は電話予約ですが、Webサイトから予約できる場合もあります。
注意しなければならないのは、病院によって予約から診察まで時間がかかる点です。電話をしてから1か月ほど待たなければならないケースもあるため、こころの不調を悪化させないために、なるべく早く予約すると安心ですね。
- 【初診のときの持ち物】
- 健康保険証
- お薬手帳
初診の際は、健康保険証を忘れないようにしましょう。
一般的な病院やクリニックは、精神科、心療内科いずれも3割負担で診察してもらえます。
また、お薬手帳は診断するときの判断材料になります。出された薬の記録にも使用するので、持っていくようにしましょう。持っていない場合はその日からの記録にはなりますが、薬局で発行してもらうこともできます。
初診は、問診票の記入が求められます。問診票には下記のような項目を記入します。
- 住所
- 氏名
- 生年月日
- 電話番号
- お困りの症状
- 症状の経緯
- 飲酒、喫煙歴
- 病歴
症状や経緯など、気持ち的に書きにくい場合は無理に書く必要はありません。あなたが記入できるものだけで大丈夫ですよ。
※Web予約の場合は、予約のときにサイト内で記入を求められる場合があります。
問診票の記入は15分程度かかります。そのため、診察開始30分前には病院やクリニックに到着しておくと安心です。
診察前に、こころや体の不調の原因を見つけるため、次のような検査を行います。
- 尿検査
- 血液検査
- 体温
- 体重測定
※検査は診察後に行うこともあります。
<診察>
診察は「問診」が中心です。医師から質問され、質問に回答する流れです。次のような質問をされることが多いため、受診前に回答を考えておくと良いでしょう。
- 【聞かれやすい質問】
- どんな点で生活に困っているのか?
- いつから困っているのか?
- 原因として思い当たること
- 仕事の内容
- 家族関係、交友関係、仕事の人間関係
- 睡眠の状態(寝れない、寝すぎるなど)
- 食欲について
- 性欲について
なお、プライベートな内容なので、全てのことに答える必要はありません。あなたが言える範囲で大丈夫です。
スマホやメモ帳に症状を記録しておくのも良いですね。先生の前でうまく話せないときは、メモを見ながら説明しましょう。何がつらいのか説明できないときも、その旨を先生に伝えると良いですよ。
<診断>
問診や検査の結果を踏まえて、医師があなたの状態を診断します。
また、医師から今後の治療方針(薬の有無や種類)が伝えられます。
診察が終わったら会計です。
<診察料金の目安>
| 初診 | 2,500~4,000円 |
|---|---|
| 再診 | 1,500円前後 |
初診は検査や診断書、薬の費用が追加されることがあるため、費用にばらつきがあります。
精神科や心療内科の診察は、基本的に保険診療のため自己負担額は3割です。料金が心配な場合は、事前に電話やWebサイトで確認しておくと安心ですね。
精神科と心療内科のQ&A

ここからは、精神と心療内科に関する、よくある疑問と回答をまとめています。
受診の際の参考にしてください。
病院とクリニック(診療所)の違いは?
病院とクリニック(診療所)の大きな違いは、ベッドの数です。
病院は、入院できる患者のベッドの数が20床以上です。一方でクリニック(診療所)は、入院できる患者のベッドの数が無床または19床以下の医療機関を指します。
クリニックは夕方まで診療可能であったり、土日の診療に対応していたりと、通院しやすいメリットがあります。どちらに通うか迷ったときは、あなたが通いやすい方を選ぶと良いでしょう。
オンラインで診察してもらえる?
オンライン診察が可能な精神科や心療内科もあります。インターネットで「精神科 オンライン診療」「心療内科 オンライン診療」と調べてみてください。
オンライン診察は、スマホやパソコンのビデオ通話を使って診察します。自宅で診察してもらえるので、安心して受診できますよ。
予約なしで診察してもらえる?
精神科や心療内科は、基本的に予約制です。
初診の場合は1か月以上、予約が取れないことがあります。医師不足やこころの不調を感じる方の増加が原因です。そのため、こころの不調を感じたら早めに予約を取るようにしましょう。
まとめ|「精神科」と「心療内科」の違いと選び方
- 精神科は「こころの不調そのもの」、心療内科は「精神的ストレスが原因の体の不調」を治療する施設。
- メンタルクリニックは精神科や心療内科のある診療所のことを指し、夕方まで診療可能であったり土日の診療に対応していたりと、通院しやすいメリットがある。
- 精神科を受診すべき人は「やる気が出ない」「気分が落ち込む」など、こころの症状がはっきりしている人。
- 心療内科を受診すべき人は「会社に行く前に腹痛が起きる」「車や電車に乗ると過呼吸になる(通勤のとき)」など、心理的ストレスで体の不調が続く人。
- どちらを受診すべきか決められないときは、精神科と心療内科が併設されている病院やメンタルクリニックを選ぶと良い。また、早期診断・早期治療ができれば回復も早くなる。
精神科と心療内科を受診するときは、上記の判断ポイントを押さえておくと良いでしょう。
先述したように、心の病気は早期診断・早期治療が重要です。あなたが少しでも精神の不調を感じているなら、まずは気楽に受診してみましょう。
また、精神科等には「精神科デイケア」というサービスも存在するため、生きづらさや精神的不調等を抱えている場合にはリハビリを兼ねた通院をすることもできます。
下記の記事で詳しく解説しておりますので、あわせて読むことをオススメします。
加えて、精神科デイケアと併用できる「就労移行支援」は、「ココルポート」のような就労移行支援事業所で提供されています。
利用することで生活面のサポートから職業訓練、就職活動の支援、就職後の定着支援まで、一貫したサポートを受けられるため、療養しながら社会復帰を目指している方にとっては非常にオススメできる選択肢です。
障害者手帳がなくても、医師の診断書や自治体の判断などがあれば利用可能です。所得状況によっては費用の負担もありません。気になる方はぜひ一度、確認してみましょう。