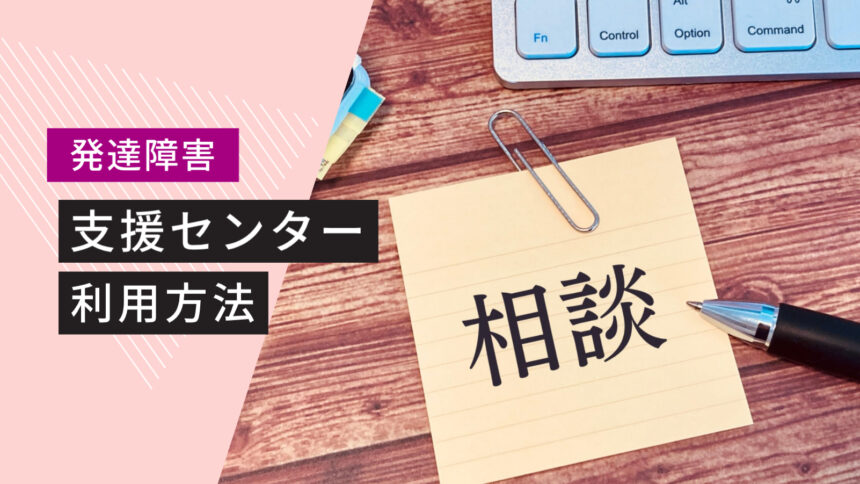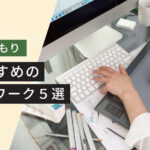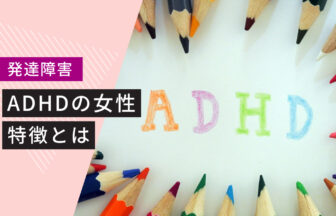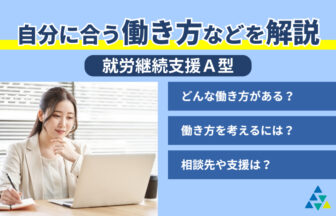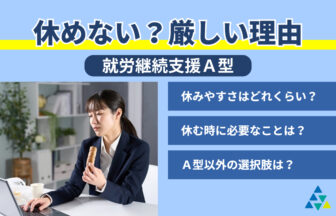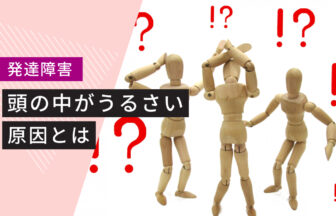あなたは、「発達障害者支援センター」という施設をご存知でしょうか。
近年、発達障害でお悩みの方は増加傾向にあると言われています。中でも、大人になってから初めて発達障害を疑い始める、いわゆる“大人の発達障害”の場合、「困りごとを誰に相談したらいいのか分からない」と悩んでいる方も多いでしょう。
発達障害者支援センターは、そうした方々が気軽に相談できる窓口の一つです。発達障害の診断を受けている方のみならず、その可能性がある方は誰でも相談可能です。
「支援センターではどんな支援が受けられる?利用方法は?」
この記事では、こうした疑問をお持ちの“大人の発達障害”の方に向けて、発達障害者支援センターの特徴についてお伝えしていきます。
- 発達障害者支援センターとは
- 発達障害者支援センターの支援内容
- 発達障害者支援センターの利用方法
- 発達障害者支援センターで診断できるのか
以上について解説します。
発達障害者支援センターとは?

発達障害者支援センターは「発達障害者支援法 第三条」にもとづき、発達障害への総合的な支援を行う地域拠点として平成16年12月に発足しました。
下記に挙げるような発達障害の方(およびその傾向のある方)と、その家族、発達障害に関わる関係機関の職員などを対象としています。
- ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)
- ADHD(注意欠陥多動性障害)
- LD(学習障害)/SLD(限局性学習症) など
2023年3月現在で98拠点あり、全国47都道府県すべてに設置されています。自治体自らの運営、または都道府県知事などが指定した特定非営利活動法人、社会福祉法人等によって運営されています。
各センターの事業内容は地域性による違いもあるため、詳しい事業内容に関しては、下記のリンクより、それぞれの対象地域の発達障害者支援センターへ直接問い合わせるとよいでしょう。
発達障害者支援センター・一覧|国立障害者リハビリテーションセンター
事業内容
それぞれの施設にもよりますが、常駐する専門の職員以外にも下記のような専門家が配置されており、その専門に沿った適切なサポートを受けることができます。
発達障害者支援センターでは、発達障害者とその家族が安心して地域生活を送れるように保健や福祉、労働などの関係機関とも密接に連携しており、その地域における包括的な支援ネットワークを構築しています。
これらの幅広いサポート体制により、発達障害者とその家族に対するさまざまな対応が可能となります。
受付窓口
受付窓口は各都道府県や政令指定都市の自治体となっており、居住する地域の事業所での対応が基本となります。一つの自治体に複数のセンターがある場合は、事業所を選ぶことも可能です。
自治体から委託された事業所が窓口となる場合もありますが、いずれの事業所においても相談はすべて無料での対応となります。
発達障害者支援センターの支援内容

発達障害者支援センターでは、それぞれの発達障害での困りごとに合わせて、大きく分けて「相談」「発達」「就労」の3つの支援をおこなっています。これらは、年齢問わず発達障害のある方や、その家族、関係機関の職員などを対象としています。
また相談者への支援だけでなく、発達障害に関する「普及啓発活動」や関係機関の職員などを対象とした「研修」も実施しています。
これらの活動によって周囲の方々に対しても、より発達障害への理解を深めてもらい、それぞれが適切なサポートを受けられる環境づくりを目指しています。
相談支援
発達障害者本人とその家族、関係機関等からの日常生活や仕事におけるさまざまな相談に対応しています。
また、必要に応じて医療機関や、障害者就業・生活支援センター、企業、市区町村、などとの連携したサポートも行っています。
発達支援
発達障害者とその家族、関係機関の発達支援に関する相談に対応し、家庭における療育方法のアドバイスをします。また、必要に応じて発達検査などの実施や、それぞれの特性に応じた具体的な支援方法についての計画作成や助言を行います。
それをもとに関係機関や医療機関などとの連携および調整を図ります。
就労支援
就労希望の発達障害者に対して、就労に関する相談に応じるとともに、公共職業安定所(ハローワーク)、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどの労働関係機関と連携して情報提供を行います。
また必要に応じて、発達障害者支援センターから就労先を訪問し、作業内容や職場環境のチェックなどのアフターフォローなども行います。
下記の記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひあわせてお読みください。
普及啓発・研修
発達障害者支援センターでは、より多くの方に発達障害を理解してもらう普及啓発のために、さまざまな研修や講演会への講師派遣などを行っています。また、発達障害を支援する関係機関や、行政の職員などを対象にした研修や講演会も開催しています。
下記のリンクに公的機関が主催、共催、助成している、発達障害に関する研修会やイベントなどの情報が掲載されているので参考にしてください。
イベント・研修会情報一覧|国立障害者リハビリテーションセンター
発達障害者支援センター利用の流れ

発達障害者支援センターには、本人だけでなくその家族も相談可能です。発達障害に関わることであれば、どなたでも無料で相談を受けられます。
ここでは、発達障害者支援センターの利用の流れについてご紹介します。
直接来所する以外にも、電話やメールなどで対応が可能な場合もあるので事業所に確認すると良いでしょう。
その相談内容をもとに、具体的に必要な支援を話し合って決めていきます。
それぞれの必要に応じて、障害者支援の各種施設や医療機関、企業、学校などと連携の上で適切なサポートを受けることになります。
発達障害者支援センターで診断が受けられるの?

発達障害者支援センターでは、発達障害の「診断」は行っていません。発達障害者支援センターの目的は、あくまでも発達障害のある方とその家族を「支援」することです。
そのため、ふさわしい病院をセンターから紹介してもらい、診断は基本的に各自で受けることになります。
発達障害者支援センターでは、それぞれのライフステージにふさわしい、相談・発達・就職などの支援を受けることができます。また、その時点で医師による診断が必要とされる場合は専門医を紹介してもらうことも可能です。
多くの自治体のサイトに発達障害に関わる医療機関の一覧が掲載されていますので、一度ご自分で確認してみると良いでしょう。
また、国が提供するポータルサイトからも発達障害に特化した詳しい情報を調べることができます。活用してみてはいかがでしょうか。
全国自治体マップ検索|J-LIS 地方公共団体情報システム機構
発達障害ナビポータル
また、発達障害の診断については、下記の記事でも詳しく解説しております。
まとめ
- 発達障害者支援センターは、発達障害の方(およびその傾向のある方)と、その家族が無料で相談できる機関。全ての都道府県に設置されている。
- 地域の各機関とも連携しており、専門家による幅広いサポートを受けることができる。それぞれの困りごとに合わせて、主に「相談」「発達」「就労」の3つの支援を行う。
- 利用する際は、最寄りの窓口に電話で事前予約をする。その後、担当スタッフとの面談を通して支援計画を作成し、サポートが開始される。
- 発達障害者支援センターでは、発達障害の「診断」はできない。基本的にセンターから病院を紹介してもらい、診断は各自で受けることになる。
いかがでしたか?
本記事では、発達障害の方やその傾向がある方の悩み事を相談できる機関、「発達障害者支援センター」について紹介いたしました。
発達障害で「つらい」と感じたら、一人で抱え込まずにまずは相談してみましょう。自身の特性と上手く付き合い、生きづらさを少しでも緩和していくきっかけになるはずです。
ちなみに、発達障害者支援センター以外にも、「atGPジョブトレ 発達障害者コース」のような就労移行支援事業所も相談先としておすすめです。
就労支援の一環として生活支援も行っており、発達障害者に対するサポート実績が豊富なので、あなたのお悩みにも具体的なアドバイスやサポートをしてもらえます。
障害者手帳がなくても、医師の診断書や自治体の判断などがあれば利用可能です。気になる方はぜひ一度、確認してみましょう。