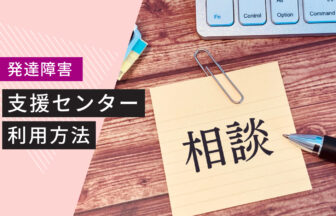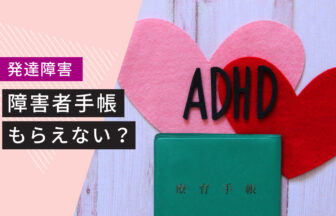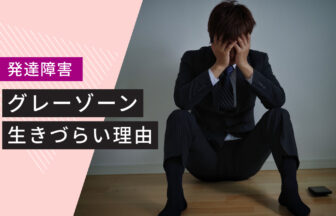同じ職場で働いている同僚の言動に、発達障害を疑っている方もいるのではないでしょうか?
ただ、本人に自覚は無く病院を受診している感じも無いとなると、発達障害の話題を出してもいいものなのか迷ったり、接し方が分からなかったりするなど様々な悩みが出てくると思います。
「自覚がない人にどうやって伝えればいい?」
「病院を受診してもらいたいけど、勧め方が分からない…」
などの疑問を抱えている方に向けて、
- 発達障害の人が職場で取りやすい言動や特徴
- 発達障害の自覚がない人に対しての接し方
- 発達障害の話題を出す時の注意点
- 病院の受診を勧める方法
以上を解説していきます。
この記事が、少しでも役に立てば幸いです。
発達障害の人が職場で取りやすい言動や特徴

発達障害は、脳機能の偏りによって様々な特性が起こるとされていますが、未だに詳しい原因は分かっていません。発達障害には主に、ADHD(注意欠如・多動症)、ASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)などの種類があります。
以下では、職場で起こりうる具体的な症例を紹介していきます。ただし、個人差が大きく当てはまらない場合もあるので、参考程度にしていただけると幸いです。
ADHD(注意欠如・多動症) の人の場合
ADHD(注意欠如・多動症)の人の場合、以下のような言動や特徴があります。
ADHDは、
の特性が目立ちます。
その影響により、注意散漫になったり同じ内容のミスを繰り返したりしてしまいます。その人に合った対策や工夫などをしないと、双方にとって強いストレスの要因になってしまうので、注意が必要です。
ASD(自閉スペクトラム症)の人の場合
ASD(自閉スペクトラム症)の人の場合、以下のような言動や特徴があります。
ASDは、自閉症やアスペルガー症候群、広汎性発達障害などの総称です。特に、他者とのコミュニケーションを取ることが苦手な傾向があり、社会人になってから複雑な人間関係に悩まされる人も多いようです。
ASDの特性を知っておくと、少しずつでも円滑なコミュニケーションを取れるようになるかもしれません。
LD(学習障害)の人の場合
LD(学習障害)の人の場合、以下のような言動や特徴があります。
LDは、知的能力には問題がないものの、読む・書く・計算する能力に困難が生じる発達障害です。主に3つのタイプがあります。
学習障害(限局性学習症、LD)は、読み書き能力や計算力などの算数機能に関する、特異的な発達障害のひとつです。学習障害には、読字の障害を伴うタイプ、書字表出の障害を伴うタイプ、算数の障害を伴うタイプの3つがあります。
引用:e-ヘルスネット│厚生労働省
LDによる症状は個人差が大きく、ほとんどの場合、上記の特徴に全て当てはまるわけではありません。ADHDやASDと併発している場合もあるので、特性として知っておくと工夫や対応がしやすくなるでしょう。
発達障害の方の具体的な特徴については、以下の記事でも詳しく解説しております。
発達障害の自覚がない同僚への接し方

上記のように、発達障害の特性には、さまざまな種類があると分かりました。
こうした方々が職場にいる場合、周囲の適切なサポートや配慮が求められます。ですが、その影響により、周りの人がカバーして仕事量が増えている、あるいは精神的に疲れてしまっているなど、負担が大きくなっている可能性があります。
では、発達障害の自覚がない人に対して、どのように接していけば双方の負担が減らせるのでしょうか?
ここでは、主に4つの対策を紹介していきます。
- 客観的に得意・苦手なことを分析する
- 周囲で対応の仕方を決めておく
- 具体的な指示を意識する
- 「普通の人は~」などの言葉を使わない
順に見ていきましょう。
客観的に得意・苦手なことを分析する
発達障害の人は特性により、得意なこと・苦手なことがきっぱり分かれている人が、多い傾向にあります。「ここの部署の人が少ないから」などの理由で業務を任せている場合は、まず客観的にその人の得意なこと・苦手なことを分析することが有効です。
また、何気ない会話の中で本人から、特に何に対して苦手意識をもっているのかなどを聞くと、本人にとっても周りの人にとっても仕事がしやすくなるでしょう。発達障害の話題を出さなくても聞ける内容なので、実践するハードルも比較的低くなります。
周囲で対応の仕方を決めておく
ミスが起こってから対応するとなると、業務の量が増えたり、普段の仕事が滞ってしまったりする可能性が大きくなります。それを防ぐため、あらかじめ周囲で対応の仕方を決めておくことをオススメします。
具体的には、ダブルチェックをしたり声掛けを強化したり、ミスが続く理由をその人だけの原因にせず、体制に目を向けることが大切です。
その際の注意点として、一人の社員に負担をかけすぎないことが重要になります。しっかりと職場内全体で問題を共有し、対策を立てましょう。
具体的な指示を意識する
日常的に曖昧な表現で業務の指示をしている場合は、一度見直して、具体的な指示を意識してみましょう。例えば、「早めに書類提出してね」「この資料いい感じに直しておいて」など、自分の頭の中ではゴールがある状態なのに、それを相手に伝えていないような表現です。
発達障害の特性により、急な変更や曖昧な表現を受け取ることが苦手な人の場合、共通認識の齟齬から、仕事のミスや業務に支障が出てしまいます。
具体的な内容の指示を意識することは、仕事をする上で全ての人にプラスに働きます。なかなか意思疎通が取れずに悩んでいる場合、まずは自身の言葉の使い方を見つめ直してみましょう。
「普通の人は~」などの言葉を使わない
同じようなミスを連続でされるなどして、特に余裕のない状態の時、「普通の人は~」や「これぐらいどうしてできないの?」など、その人のプライドや心を傷付けるような言葉を投げかけることは、絶対に止めましょう。
特に、診断を受けていない発達障害の特性がある人は、生き辛さを抱えて生活している人も多いです。
「周りの人に迷惑をかけてしまって申し訳ない…」
などと、自分でもミスをしてしまう理由が分からず、迷惑をかけている罪悪感を抱いている場合があります。そこに追い打ちをかけるような言葉を言ってしまうと、その人との関係性はおろか、職場環境も悪くなってしまいます。
また、発達障害の人は二次障害と言って、日常的なストレスから、うつ病などの精神疾患になってしまう人が多いとされています。相手に言葉をかけるときは、十二分に考えてから発言しましょう。
そもそもにはなりますが、発達障害関係なく、他人同士を比べることは無意味です。感情的になる前に、「どうしてそうなるのか」の理解を進めていく作業がとても大事になります。
また、以下の記事では発達障害の方の話し方の特徴や、改善方法等について詳しく解説しております。
自覚がない同僚に発達障害の話題を出す時の注意点

業務に支障が出ていたり、人間関係で改善してほしいと思う部分があったりして、「そろそろ本人に発達障害の話題を切り出したいな……」と考えている方もいらっしゃると思います。
ここでは、本人に発達障害の話題に出す時の注意点を、4つ紹介していきます。
- 発達障害をよく知らないまま話題に出さない
- 本人との関係性を考慮する
- サポートをしていく旨も同時に伝える
- 業務に支障が出ていない範囲であれば、無理に話題を出さなくてもいい
順に見ていきましょう。
発達障害をよく知らないまま話題に出さない
身近に発達障害の人がいなかったり接する機会がなかったりすると、なかなか特性について知ることは難しいですよね。ですが、発達障害の特性を全く知らない状態では、無意識に言った言葉などで傷付けてしまうリスクがあります。発達障害について完全に理解することは難しくても、分かろうと努力することはできます。
それを怠って、「発達障害って、結局やる気の問題でしょ?」「やろうと思えばできるんでしょ?」などの間違った情報を言うことがないように、発達障害の特性を知識としてきちんと知っておきましょう。
また、特性は個人差がとても大きいです。「ADHDはこういう特性があるから、○○さんもそうなんだ」と決めつけず、しっかりその人自体と向き合うことが大切になります。
本人との関係性を考慮する
発達障害の話題を出す上で、本人との関係性や信頼関係はとても重要になってきます。なぜなら、上司やあまり親しくない人から伝えられると「責められている」「辞めさせたいんだ……」とマイナスな方向に思考が働いてしまうかもしれないからです。
普段から関わりがある人が同席するだけでも、話し合いの場の緊張感が和らぎ、本人の心情的にも少し楽になるかもしれません。
サポートをしていく旨も同時に伝える
発達障害の話題を出す時に、同時にサポートをしていく旨も伝えることが大事です。
上記の内容とも重なりますが、「この話題を出すのは、自分を辞めさせるためじゃないんだ」と本人に理解してもらうことで、安心感をもって話を聞いてもらいやすくなります。
また、誰かに気にかけてもらっていると実感することは、精神的に救われる要素でもあります。発達障害の特性は、仕事の面だけではなく生活を送る上でも密接に関わってくるので、ひとつの大きな支えになるかもしれません。
業務に支障が出ていない範囲であれば、無理に話題を出さなくてもいい
そもそもにはなってしまいますが、業務に支障が出ていない範囲であれば、発達障害の話題を無理に出す必要はありません。というのも、人にはそれぞれの性格があり、専門家でない私たちが「この人は発達障害なんじゃないか?」と思うことは、実は危険を孕んでいると、念頭に置いておく必要があるからです。
ネット上で簡単に情報を得られる環境では、他者の特徴を病気や障がいに当てはめて考えることに慣れてしまいがちです。ですが本来、発達障害は特性の個人差が大きく、専門家の人でさえ診断が難しいとされています。
もちろん、傍から見ていて本当に本人や周りの人が困っている場合は、発達障害の話題を出すことが、改善の一歩になるでしょう。
ただし、業務などに支障が出ない程度で、なんとなく当てはまるかな?というレベルの場合、もちろん本人との関係性にもよりますが、無理に話題を出さないことも選択肢のひとつです。
発達障害の自覚がない同僚に病院の受診を勧める方法

ここでは、発達障害の自覚がない人に対して病院の受診を勧める方法を、主に3つ紹介していきます。
当然、人それぞれ受け取り方は異なるので、その人の状況に合った方法が一番です。あくまで一例として、少しでも参考になれば幸いです。
順に見ていきましょう。
業務が比較的落ち着いているタイミングで切り出す
精神的に追い込まれているタイミングだと、誰しも冷静に話を聞くことが難しくなってしまいます。
特に、繁忙期などで慌ただしい時期だと、双方ともに余裕がない状態になるので、良い方向に話を進めることが、難しくなってしまう可能性もあります。仕事が比較的落ち着いているタイミングを見計らって、病院の受診を勧めてみましょう。
客観的事実を理解してもらう
本人が業務の中で難しいと感じていること、その影響で周りの人がどういう業務が増えているかなどを、具体的に知ってもらうことが大切になってきます。
ここで重要なのは、「事実と感情を分ける」ということです。特に苦手な作業、時間がかかる業務などの”事実”と、だから「仕事ができない」「みんな困っている」などの”感情”を切り離して伝えることを意識しましょう。
上記したように、「病院の受診を勧めることは、あなたを責めているわけではない。サポートをしたい」という思いを伝えることが、最重要事項になります。事実とマイナスな感情をイコールで伝えてしまうと、その思いがうまく伝わらなくなってしまうので、注意が必要です。
発達障害者支援センターの利用を勧める
発達障害の診断は、主に精神科や心療内科で行われています。また、近年では発達障害専門外来なども設立されており、大人になって初めて病院を受診し、発達障害を自覚する人も増えているようです。
しかし、現在では精神疾患にかかる人が増加していて、病院自体の予約がなかなか取れない、または数か月待ちになっていることが問題になっています。そんな時は、発達障害者支援センターを勧めることも視野に入れておくといいでしょう。
発達障害者支援センターとは、発達障がい者の支援を総合的に行っている専門的な機関です。福祉や医療などの機関と連携し、様々な相談や支援を行っています。各都道府県に設置されていますが、自治体によって支援内容は変わってくるので、まずはお近くの機関を探してみましょう。
発達障害者支援センター・一覧 | 国立障害者リハビリテーションセンター
まとめ
- 発達障害には、ADHD(注意欠如・多動症)、ASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)などがある。また、特性は個人差が大きい
- 発達障害の自覚がない人に対しては、客観的に得意・苦手なことを分析したり、あらかじめ周囲での対応を決めておいたりすることで、周りの人の負担が減る可能性がある。また、自分自身の接し方に意識を向けると、職場全体が仕事をしやすくなる場合もある。
- 発達障害の話題を出す時は、発達障害の特性をしっかりと理解しておくことや、本人との関係性を考慮すること、同時にサポートをする旨を伝えることが重要。話題に出す必要性をよく考えることも大切。
- 病院の受診を勧めるのは忙しくない時がオススメ。精神的に落ち着いた状態で、現状難しいことなどを伝える。その時に、事実と感情を分けることが大切。また、発達障害者支援センターに相談することも視野に入れておくと良い。
この記事では、発達障害の人が職場で取りやすい言動や特徴、発達障害の自覚がない同僚への接し方、発達障害の話題を出す時の注意点や、病院の受診を勧める方法などを紹介してきました。
発達障害は、適切な治療やカウンセリングによって、生活を送りやすくできる可能性があります。非常にデリケートな問題ですが、本人や周りの人のためにも、勇気と思いやりをもって話題に出すことが大事になります。
また「病院の受診を勧めるのは、あなたを責めているわけではなくサポートをしたいからだ」という思いも、全面的に伝えていきましょう。
伝えられた側の受け取り方は、その人の性格によっても大きく変わってきます。ストレートに伝えた方がいいのか、クッションを挟みながら丁寧に伝える方がいいのかなど、普段からのコミュニケーションを大切にすることが、双方にとっていい方向へ向かう重要な要素となるでしょう。