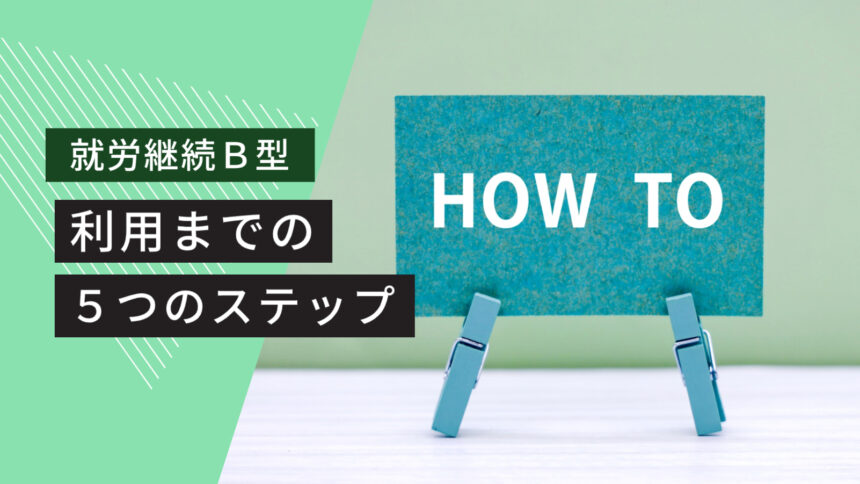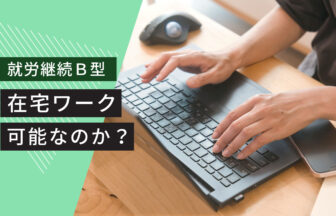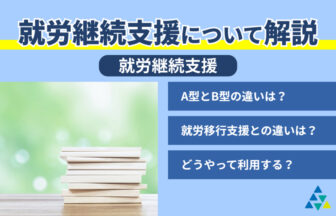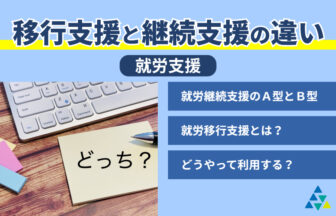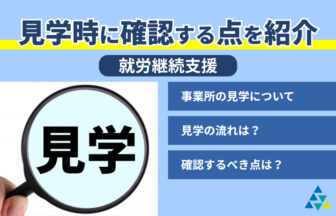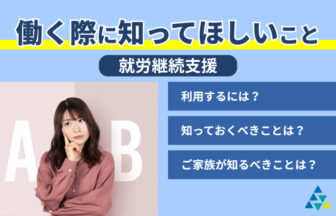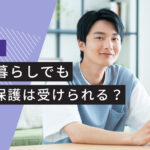障がいや病気によって一般企業で働くことが難しい場合、就労継続支援B型を利用するという選択肢があります。ですが、
「利用手続きを1人でこなせる自信がない…」
このような疑問や不安を抱えてしまい、働くための一歩をなかなか踏み出せない方もいらっしゃいますよね。
そこで、初めて就労継続支援B型の利用を検討しているあなたのために、
- 就労継続支援B型の利用までの流れ
について解説していきます。
この記事が、あなたの疑問や不安を解消するための一助となれば幸いです。
就労継続支援B型・利用手続きの5ステップ

就労継続支援B型の利用手続きは以下の5つのステップに分けられます。
- 主治医に就労継続支援B型を利用したいことを伝える
- 利用したい事業所を探す
- 「障害福祉サービス受給者証」を申請する
- サービス等利用計画案を作成して提出する
- 就労継続支援B型仕業所と手続きをして利用開始
注)「障害福祉サービス受給者証」とは、就労継続支援B型を利用するための許可証のようなものです。
「5つもステップがあるなんて大変そう…」と感じた方も安心してくださいね。就労継続支援B型の利用手続きは、「主治医や病院のスタッフ」「B型事業所のスタッフ」「市役所の職員」などのサポートを受けながら進めていきます。あなたが1人で行わなければいけない手続きはほとんどありません。
以下では、この5つのステップについて詳しく解説していきます。
【ステップ1】主治医に就労継続支援B型を利用したいことを伝える
まずは定期通院をしている病院の主治医に、「B型事業所を利用したいです」という旨を相談して許可をもらいましょう。この時に「どのようなB型事業所を選べばいいか?」について、主治医からアドバイスをもらうことも大切です。
障害者手帳を持っている場合であれば他に作成を依頼する書類などはありません。主治医からの許可をもらうだけで「ステップ1」は終了です。
就労継続支援B型を利用するにあたり障害者手帳は必須ではありませんが、この場合は主治医の「意見書」や「診断書」が必要になるため、以下の記事をご参考にしてください。また、障害者手帳を取得すると様々な料金割引や福祉サービスを受けられるため、特別な理由がない場合は障害者手帳の申請を行うことをオススメします。
【ステップ2】利用したい事業所を探す・事業所選びのポイントも紹介

就労継続支援B型の利用手続きの中で、「事業所探し」は最も大切なステップです。まずはお住いのエリアにどのようなB型事業所があるのかをチェックしましょう。B型事業所の情報はWEBサイトで検索する以外にも、「市役所の障害福祉窓口」や「ハローワーク」に相談することで集めることができます。
B型事業所を探す際に注目したいポイントは以下の通りです。
- 事業所が扱う作業内容の中にあなたが「やりたい作業」「できる作業」はあるか?
- 事業所の雰囲気はあなたにとって居心地がよさそうか?
- 負担なく通所できるか?(交通機関のアクセスや送迎サービスの有無に注目しましょう)
- あなたの障がいや病気は事業所の支援対象であるか?(特に身体障がいの方はバリアフリーに対応した事業所でなければ大きな負担となる可能性があります)
- 貰える工賃の金額はどれくらいか?
上記のポイントを意識しながら、気になる事業所が見つかったらメールや電話で見学・体験を申し込みましょう。「事業所の雰囲気」「作業があなたに合っているか?」など、実際に見学・体験をしなければわかりにくい部分を確認することが大切です。
納得できるB型事業所に出会えたら「ステップ2」は終了です。
B型事業所をWEBで検索する場合は、以下のサイトを利用するのがオススメです。
全国の就労継続支援B型事業所を探す|LITALICO仕事ナビ
障害福祉サービス事業所検索|WAM NET
「パソコン作業」「ITの仕事」を扱うB型事業所をお探しの方は、以下の「就労継続navi」をご活用ください。
【ステップ3】「障害福祉サービス受給者証」を申請する
お住いの自治体の市役所にある障害福祉窓口へ行き、「障害福祉サービス受給者証」を申請しましょう。
以下の書類や持ち物を用意しておくとスムーズに申請できます。
- 障害者手帳(なければ主治医の意見書や診断書など)
- 本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
- 自立支援医療の受給者証(利用している方のみ)
- お薬手帳
- 印鑑
また、障害福祉サービス受給者証の申請の時は、職員との面談が実施されて以下のようなことについて質問されます。
これらの質問について事前に整理しておくと、あなたの考えをスムーズに伝えられるでしょう。
書類を提出して面談を終えたら「ステップ3」は終了です。障害福祉サービス受給者の発行には2週間~1月程度の時間が必要となります。
【ステップ4】サービス等利用計画案を作成して提出する

障害福祉サービス受給者証の申請の後に、もう1つ必要な手続きが「サービス等利用計画案」の作成です。
サービス等利用計画案とは、あなた自身がB型事業所の利用を通して、
などを明確にして、より質の高いサービスを実現するために作成されます。サービス等利用計画案は、相談支援専門員と協力して作成します。
相談支援専門員とは、障がいや病気を抱える人が自立した日常生活・社会生活を送るために、全般的な相談支援を行う人のことです。相談支援専門員を自力で見つけるのは大変な作業になるため、「利用する予定のB型事業所」や「市役所の障害福祉窓口」、「地域包括支援センター」などから紹介してもらうのがオススメです。
サービス等利用計画案が作成できたら「ステップ4」は終了です。その後の書類の提出などは全て相談支援専門員が行ってくれます。
【ステップ5】B型事業所と契約をして利用開始
障害福祉サービス受給者証が発行されたら、B型事業所と契約を結んで利用開始となります。
まとめ
- 就労継続支援B型を利用する場合、「主治医への相談」→「利用したいB型事業所を選ぶ」→「障害福祉サービス受給者証の申請をする」→「サービス等利用計画案を作成する」→「B型事業所と契約を結んで利用開始」という5つのステップがある
- 初めて就労継続支援B型を利用する場合は利用手続きに戸惑うこともあるが、ステップごとにサポートしてくれる人がいる
- 障害者手帳がなくても就労継続支援B型は利用できるが、障害者手帳を取得するメリットは申請する手間以上に大きい
- B型事業所を選ぶ場合は、「作業内容」「事業所の雰囲気」「貰える工賃の額」などに注目して納得できる事業所を探すことが大切
今回の記事では、「就労継続支援B型の利用の流れ」について解説しました。
まずは自分のペースで社会復帰をして、その中で少しずつ「障がいや病気との付き合い方」「働くためのトレーニング」を積み重ねていきたいと考えている方に、就労継続支援B型は最良の選択肢となるでしょう。
あなたの新しい一歩に幸多からんこと祈りつつ、この記事の最後とさせていただきます。
就労継続支援については、以下の記事でも詳しく解説しております。