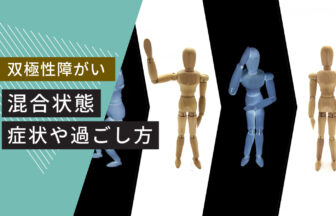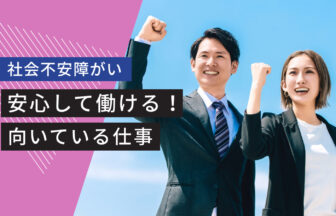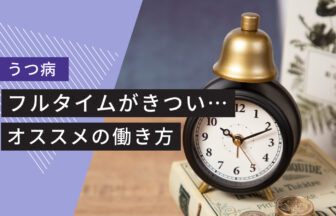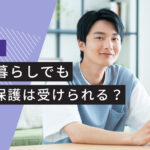あなたはうつ病の影響で仕事を休みがちになり、
「周りに迷惑ばかりかけて申し訳ない…」
など、自分を責めて苦しい気持ちになっていませんか?
休みたくて休んでいるわけではないのに、繰り返し襲ってくる罪悪感は本当につらいですよね。
- うつ病だと「迷惑をかけている」と感じやすい理由
- 上手に休むことが仕事復帰への近道になる理由
- 罪悪感を和らげる4つのヒント
- 少しでも肩の力を抜くための5つの工夫
- 頼れる相談先と利用できるサポート
について解説していきます。
少しでも心を軽くして、あなたらしい働き方を見つけるため、一歩を踏み出すために、一緒に考えていきましょう。
うつ病だと「迷惑かも」と罪悪感を感じやすい理由

その強い罪悪感は、うつ病特有の症状や、もともとの性格傾向などが関係している可能性があります。
この項目ではその理由について、少し見ていきましょう。
うつ病による思考のクセ
うつ病になると、気分だけでなく考え方にも偏り(認知の歪み)が生じやすくなります。
- 「自分は役に立たない」という自己否定感
- 「完璧にやらなければ」という完璧主義
- 「全て自分のせいだ」という過剰な責任感
などが強まるため、罪悪感につながることがあります。
責任感によるもの
元から責任感が強く真面目な方ほどうつ病になりやすく、「休む=責任を果たせない、期待を裏切る」と感じやすいのです。
以前のように働けない自分を受け入れられず、強く責めてしまうことがあり、罪悪感を抱きやすい傾向があります。
周りの目が気になって不安になる
うつ病は普通の病気のように、目に見える形で症状が表れるものではありません。そのため「怠けていると思われていないか」「嫌われているのではないか」など、他者からの評価を過剰に気にしてしまうことも、罪悪感の要因です。
職場の理解不足による実際のプレッシャーが、さらに罪悪感を強める場合もあります。
上手に休むことが「迷惑」を減らすことにもつながる

「休んだら迷惑がかかる」と思いがちですが、うつ病と付き合いながら働く上では、「上手に休む」ことが、長期的に見て職場への迷惑を減らし、安定した復帰への近道になるという考え方もあります。そもそも、無理して出勤した場合、ミスの増加や集中できないことで、かえって周りの負担が増えたり、回復の遅れにつながったりする場合もあります。
うつ病は再発しやすい病気です。焦らず十分な休息をとることは、再発を防ぎ、長く安定して働くための土台作りになります。仮にうつ病でなかったとしても、働いている以上、気が付かないうちに迷惑をかけている場合もあります。
「休みがちだから休まないようにしないと」と考えるよりも、上手な休み方を見つけることで安定して働き続けていきましょう。
「自分を責めない」ための一歩|罪悪感を和らげる4つのヒント
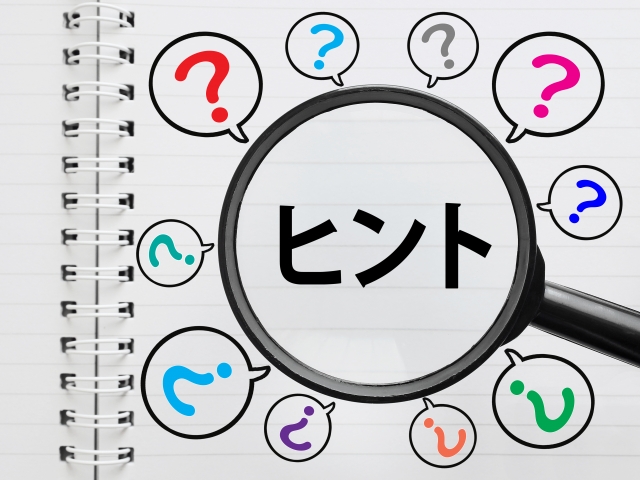
すぐに気持ちを切り替えるのは難しいかもしれませんが、考え方を少しずつ柔軟にすることで、心の負担を軽くすることは可能です。
この項目では、罪悪感を和らげるためのヒントを4つご紹介します。
「休む=回復に必要な時間」と考える
休むことは、回復のために必要な時間だと考えてみましょう。
うつ病は気力や根性などで乗り切れるものではなく、心身が休息を求めているサインです。無理して働き続けると、かえって回復が遅れる可能性もあります。周りの負担を考えると割り切れない気持ちも分かりますが、適切な休息は、長期的に安定して働くための「準備期間」です。
長く働くための合理的な判断だと捉えてみましょう。
「今の自分にできること」に目を向ける
「以前のように完璧に」という考えを手放し、今の自分にできる範囲の小さな一歩に目を向けましょう。うつ病のときは、体力や集中力が低下していることがほとんどです。
「今日はここまでできた」「少し進んだ」など、小さな「できたこと」を見つけてみましょう。「今日も一日、何とか過ごせた」それだけでも十分です。
目標のハードルを下げ、スモールステップで取り組んでみましょう。
自分のペースを大切にする
周りの同僚や元気だった頃の自分と比べるのをやめましょう。
回復の道のりは人それぞれです。比較は焦りや劣等感を生み、回復を妨げることがあります。
調子の波が激しく予定が立てられなくとも、計画通りに進まなくて当たり前、と割り切ることも大切です。「最低限これだけは」という低い目標を設定し、他は体調次第で調整する柔軟な姿勢で進めてみませんか?
「人は人、自分は自分」と割り切り、今の自分の体調と心に正直に向き合い、無理のないペースで進むことを最優先で考えましょう。
ネガティブ思考に気づいたら「一旦距離を置く」意識を持つ
「自分はダメだ」といったネガティブ思考になり始めたら、「これはうつ病の影響かも」と客観的に気づき、意識的にその思考から「一旦距離を置く」練習をしてみましょう。
思考を無理に止めようとする必要はありません。「あ、また考えてるな」と気づくだけでも大きな一歩です。余裕があれば、深呼吸や軽い気分転換を試してみると良いでしょう。
少しでも肩の力を抜いて働くために|具体的な5つの工夫

考え方が少し変わってきたら、次は働く場面での具体的な工夫を試してみましょう。
この項目では5つ紹介します。「これなら少し試せるかも」と思えるものから、無理なく取り入れてみてはいかがでしょうか。
業務量・内容を正直に伝えてみる
今の状態に合わせて業務の調整が可能か、上司や人事に相談してみましょう。
「相談することは迷惑になるのでは?」と感じるかもしれませんが、現状を伝えることが解決の糸口になることもあります。
具体的に
- どの業務が負担か
- どの程度ならできそうか
などを整理して伝えてみましょう。情報が整理されていれば、相手も理解しやすくなります。
すぐに希望通りにならなくても落ち込む必要はありません。伝えること自体に意味があります。
タスクを細かく分けてみる
大きな仕事は小さなステップに分解してみましょう。
例:「資料作成」
- 「情報収集」
- 「構成案作成」
- 「1ページ書く」など
小さな目標(「今日は構成案のメモ書きだけ」など)を設定し、完了したらチェックするなど、視覚的に進捗を確認すると達成感を得やすくなります。
スモールステップで進めていきましょう。
計画的な休息を意識してみる
症状に波があることを前提に、疲れを感じる前に意識的に休息を取るようにしましょう。
こまめな休憩を取ることで消耗を防ぎ、安定して働くことにつながります。
- 「〇分作業したら〇分休む」
- 昼休みはしっかり休む
- 有給休暇を計画的に取る
など、自分に合った方法でやってみましょう。
休息を取ることにも罪悪感があるのであれば、「休むことも仕事のうち」と捉えてみてください。
「手伝っていただけたら助かります」と伝えてみる
可能であれば、小さなことから周囲に助けを求める練習を始めてみましょう。1人で無理をし続ける方が、結果的に負担をかける可能性もあります。頼れる雰囲気でなければ難しいかもしれませんが、もし頼れそうな状況なら、コピーや簡単な確認など、負担の少ないことから「申し訳ないのですが…」と丁寧にお願いしてみましょう。
丁寧にお願いし、助けてもらえたときに感謝を伝えることで、相手も少し気分が良くなり、その後も協力を受けやすくなるでしょう。
同僚にはすべて話す必要はありません。「体調不良で治療中であり、日によって体調に波があるためご迷惑をおかけするかもしれませんが、ご理解いただけますと幸いです。」のように、状況と協力のお願いを簡潔に、誠実に伝えましょう。
伝える相手やタイミングを慎重に選んで伝えてみましょう。
少しでも楽な環境・時間帯を探してみる
自分が比較的集中しやすい、ストレスを感じにくい環境や時間帯を把握し、調整できないか相談してみましょう。
- 静かな席への移動
- パーテーション設置
- ノイズキャンセリングイヤホンの使用許可
- フレックスや時短勤務、在宅勤務の検討
など、希望を伝えてみることが大切です。
自分だけで解決しようとせず、上司などに相談することで、思わぬ方向からの解決が可能な場合もあります。
困ったら頼れる相談先や支援制度

ここまでの内容を試してみても、うまくいかないということもあるかもしれません。
そのようなときは1人で抱え込まず、頼れる相談先や支援制度の活用を検討してみましょう。
主治医
定期的に精神科・心療内科に通院している場合、主治医であれば相談しやすいでしょう。
病気や治療について最も良く理解しており、治療と仕事の両立について相談できる相手です。
診断書や意見書の作成だけでなく、休職・復職の相談も可能です。また、必要に応じて福祉や公的支援につなげてもらうことも可能です。
会社の上司・人事・産業医
会社の中で誰に相談すべきか迷ったら、まず人事や産業医を頼ってみましょう。
職場環境の調整や社内制度(休職、時短勤務など)について、困りごとを相談できます。
仕事の量や内容について、どこまで話していいのかわからない場合は、上司へ守秘義務について確認すると安心です。流れで上司に相談するのも良いでしょう。
場合や状況によっては休職を勧められる場合もあります。休職に対して不安はあるでしょうが、無理を続けて離脱する方がより迷惑が大きくかかるかもしれません。
休職はキャリアの中断ではなく「準備期間」と捉え、回復を最優先しましょう。
困りごとを相談できる機関
仕事上での困りごとを社内の方には言いづらい、ということもあるでしょう。うつ病に限らず、第三者に困りごとを相談できる支援機関もあります。
機関によって担当している内容は異なりますが、必要に応じて適切な機関や福祉制度を紹介してもらうことも可能です。
こころの耳
困りごとはあるけどどこに相談したらいいかわからない、という場合には、「こころの耳相談」の利用がオススメです。専門的な知識が必要な相談はできませんが、困りごとに応じて適切な相談先を案内してもらうことができます。
対面で相談するのは緊張する、という方でも電話やメール、SNSでの相談が可能です。
また、困りごとに応じた各種相談窓口も記載されているので、参考にしてみると良いでしょう。
精神保健福祉センター
うつ病であれば、こころの病気なども扱う精神保健福祉センターへの相談も可能です。
全国に設置されており、行きやすい範囲の施設へ行ってみましょう。専門の相談員や保険師の方に無料で相談することができます。
基本的に対面か電話での相談が主となりますが、こころの健康に関する困りごとの相談やアドバイスなどを受けられます。また、精神科デイケアを行っている場合もあるため、休職中に利用してみるのも良いでしょう。
地域障がい者職業センター
地域障がい者職業センターでは、障がいのある方に対する専門的な職業リハビリテーションなど、専門性の高い支援を行っています。
全国47都道府県に設置されており、障がいのある方や障がい者雇用に関わる方であれば無料で利用できます。障がい者手帳が無くとも利用できる場合もあるので、問い合わせてみましょう。
休職から職場復帰に向けたリワーク支援や、職場への適応を手助けしてもらえるジョブコーチ支援が利用できる場合もあります。
リワーク支援やジョブコーチ支援の利用には、本人と事業主双方の同意が必要です。休職して回復に努めた後、復職に向けて動き出すときにも活用できます。
地域障害者職業センター|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
公的な支援制度
仕事を休みがちだと働いた分の給与が減るため、経済的な不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。公的な支援制度は、経済的な不安を和らげるために活用できます。
- 傷病手当金
療養期間中、本来の報酬額の3分の2を受け取ることができます。 - 自立支援医療(精神通院医療)
医療費の自己負担を1割軽減できます。
その他、障がい者手帳の取得や障害年金、生活困窮者自立支援制度なども状況によっては利用できる場合があります。
ただし、公的な支援制度は実際に受給できるようになるまで時間がかかることが多いため、余裕がなくなる前に利用したいところです。休職する際は、会社や主治医だけでなく、自治体の障害福祉を担当する窓口や、病院のソーシャルワーカーにも相談してみましょう。
家族や友人など、信頼できる人
家族や友人など、信頼できる方は心の支えとなる存在です。
ただし、相手によっては心配をかけてしまう、うつ病について理解されない可能性もある、といった難しさもあるため、過度な期待はせず、気持ちを整理する場として頼ってみましょう。
うつ病で仕事を休みがちなあなたへ

周りから取り残されるようで焦りを感じることもあるでしょう。これは自然な感情ですが、回復の妨げになる場合もあります。今は自分の回復を最優先に考えましょう。
SNSから距離を置く、無理をしない、など意識を自分のケアに向けることが必要です。無理に意欲を出そうとせず、自分を責めないように。仕事を休めない状況であれば、「席に座っているだけで十分」と考え、可能ならメールチェックなど、負担の少ない業務から試してみましょう。
回復すれば、自分のペースで進められるようになるでしょう。
まとめ:うつ病で仕事を休みがちなとき、罪悪感から抜け出す方法
- うつ病の症状によっては「迷惑をかけているかも」と感じやすい。うつ病による思考のクセや、責任感、周囲の目が気になることで不安になる、などが理由。
- 上手に休むことが「迷惑」を減らすことにつながる。休まないようにしないと、と思うより、回復できる上手な休み方を見つけることが大切。
- 「休むこと=回復に必要」と捉える、「今の自分にできること」に目を向ける、自分のペースを大切にする、ネガティブ思考していると気づいたら「一旦距離を置く」意識を持つ、など考え方を柔軟にして、罪悪感を和らげよう。
- 肩の力を抜いて働ける工夫をしてみよう。具体的には、業務量・内容を正直に伝えて調整してもらう、タスクを細かく分ける、計画的に休息を取るよう意識してみる、相手の様子を見て「手伝ってもらえたら助かります」と伝えてみる、少しでも楽な環境・時間帯を探す、などして負担を軽減することで休みがちな状態の改善を目指す。
- 自分だけで抜け出そうとするのではなく、信頼できる相談先や支援機関・制度を利用してみることも方法の1つ。主治医や会社の上司・人事・産業医、家族や友人の他にも、精神保健福祉センターなどの機関や公的な支援制度も利用できる。1つが上手くいかなくても、相談できる先を複数知っておくことで安心できる。
仕事を休みがちだからといって、焦る必要はありません。
もし休職することになったとしても、それも回復に向けた一歩です。まずは自分の心と身体を労わりながら、無理なく「自分らしい働き方」を見つけるための一歩を踏み出していきましょう。
いざ休職しても、どうしていいかわからない場合には、下記の記事が参考になるでしょう。
この記事が、少しでもあなたの心の負担を軽くし、明日へ踏み出すための支えとなることを、心から願っています。