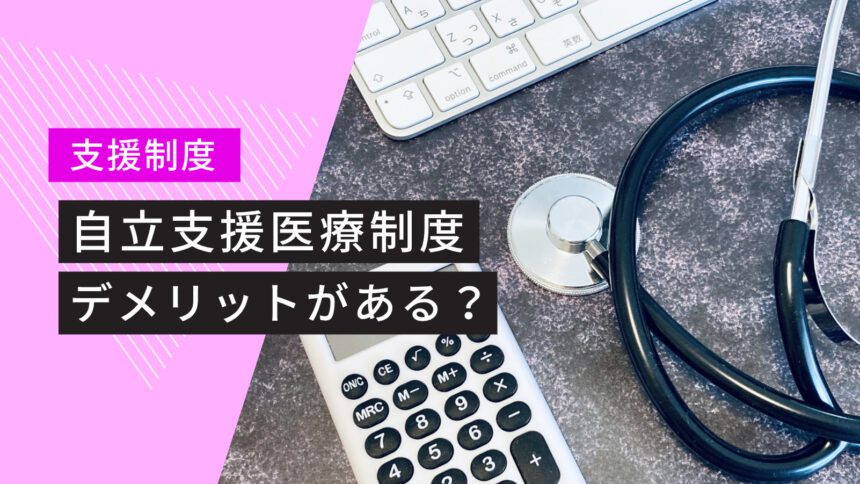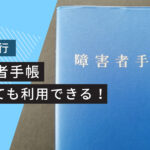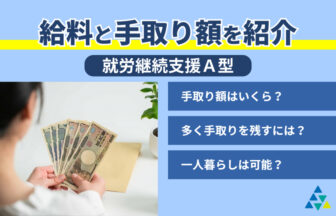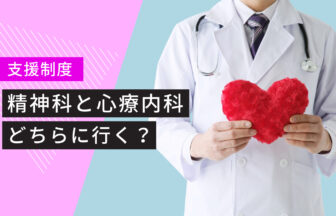うつ病や統合失調症などの精神疾患の治療には継続した通院が必要になります。そこで、医療費の負担を減らすためにオススメされているのが「自立支援医療制度」です。
ですが、この記事にたどり着いたあなたは、
「自立支援医療制度を利用したら何かデメリットがありそうで不安……」
このような疑問や不安を抱えており、制度の利用に踏み切れずにいませんか?
- 自立支援医療制度とはどんな制度?
- 自立支援医療制度を利用してもデメリットはないの?
- 自立支援医療制度の申請方法
について解説していきます。
実は、筆者も精神疾患を抱えており、自立支援医療制度を使いながら通院しています。この記事を通して自立支援医療制度について正しく理解して、あなたの治療にお役立ていただければ幸いです。
自立支援医療制度とは?

自立支援医療制度とは、うつ病や発達障害などの様々な精神疾患を抱えている人を対象に、医療費の負担額を軽減して通院治療を支援するための制度です。
通常では、健康保険が適用される医療の自己負担割合は3割となりますが、自立支援医療制度を利用することで自己負担割合を1割まで軽減させることができます。
また、自立支援医療制度には世帯の所得状況に合わせて自己負担の上限月額が設定されており、上限月額を超える部分の医療費の支払いが免除される仕組みとなっています。
2024年時点での自己負担の上限月額は以下の表の通りです。
家族全員の住民税の合計が235,000円以上自立医療支援制度の対象外
| 世帯所得状況 | 自己負担の上限月額 |
|---|---|
| 住民税非課税世帯+本人の収入80万円以下 | 2500円 |
| 住民税非課税世帯+本人の収入80万円以上 | 5000円 |
| 家族全員の住民税の合計が235,000円未満 | 医療保険の自己負担限度額まで |
自立支援医療制度の「1割負担+自己負担の上限月額」は、
- 外来での診察費用と処方された薬の代金
- デイケアや訪問看護の利用料金
に適用されます。
一方で、
- 診断書の発行料金
- 入院時の医療費
- 健康保険が適用されない治療(病院外でのカウンセリングなど)
- 精神疾患とは関係のない病気や障がいの医療費
これらには、自立支援医療制度が適用されないため注意が必要です。
自立支援医療制度を利用する2つのメリット

先述の通り、自立支援医療制度は精神疾患の治療にかかる経済的な負担をサポートするものです。特に、経済的に苦しい状況に置かれている方は手厚い支援を受けられるため、あなたが精神疾患の診断を受けた場合は積極的に活用したい制度となります。
以下では、自立支援医療制度を利用するメリットを詳しく見ていきましょう。
経済的に困窮していても治療を諦めずに済む
精神疾患の診断を受けた時、仕事を休職したり離職したりという選択をする人もいらっしゃいますよね。
しかし、精神疾患の多くは症状が長期化しやすく、治療のためには継続的な通院が必要になります。そのため、収入が減少している中で精神疾患の治療を行わなければならないという、厳しい状況に置かれている人が多いのです。
また、経済的な困窮に加えて、
「いつまで通院しなければいけないの?治療の見通しが全く分からない…」
このような不安が積み重なることで、通院治療を途中で辞めてしまうケースもあります。
自立支援医療制度とは、まさにこのような不安を抱えている人を支援するための制度です。医療費の負担を気にすることなく最適な治療を受けられるという点に、自立支援医療制度を利用する最大のメリットがあるのです。
障害者手帳がなくても障害福祉サービスを利用できる
自立支援医療制度の利用を申請すると、「自立支援医療受給者証」が発行されます。
この受給者証を所持していることで、障害者手帳がなくても、
- 障がい者の就労や就職活動をサポートする「就労支援サービス」
- 障がい者の買い物や家事などをサポートする「生活支援サービス」
- 障がい者の日中の活動や居場所づくりをサポートする「地域活動支援センター」
などの障害福祉サービスを利用できるようになります。
障害者手帳は初めて病院を受診した日(初診日)から半年が経過していなければ申請できません。一方で、自立支援医療制度は主治医が「治療のために継続的な通院が必要」と判断したらすぐに申請ができます。
そのため、通院治療の開始と同時に障害福祉サービスの利用を希望する場合、自立支援医療制度を利用することで大きなメリットがあるのです。
就労支援サービスについては、以下の記事でも詳しく解説しております。
自立支援医療制度にデメリットはない!よくある4つの誤解

自立支援医療制度を利用する上でデメリットが発生することはありません。
ですが、ネットでは、
「自立支援医療 就職 不利」
「自立支援医療 ローン 組めない」
「自立支援医療 生命保険 加入できない」
このようなキーワードで検索する人が多くいらっしゃるようです。
このような誤解が生まれる背景には、「精神疾患を抱えていることで発生する制限」が「自立支援医療制度を利用することで発生するデメリット」に変換されてしまっている事情があるように思えます。
以下では、自立支援医療制度に対するよくある4つの誤解を解消していきましょう。
自立支援医療制度を利用していることは会社にばれる?
あなたが自己申告をしない限り、自立支援医療制度を利用していることが会社にばれることはありません。
自立支援医療制度の申請手続きに会社が関わることはありませんし、この制度を利用しているという情報が会社に通知されることもないのです。もっとも、自立支援医療制度の利用が会社に伝わったとしても問題が発生することはありませんが、自分に精神疾患があることを他人に知られたくない方もいらっしゃいますよね。
自立支援医療制度を利用していることは「健康保険組合」「市町村の役所」「医療機関」の3つの機関で共有されます。しかし、あなたのあらゆる医療情報はプライバシーに関わるため、個人情報保護法2条3項に定められている通り、扱いに細心の注意が必要な情報(要配慮個人情報)となっています。
つまり、「自立支援医療制を利用していること」を含めた医療情報が、現在働いている会社や将来就職する会社へ本人の同意を得ずに提供される心配はないのです。
自立支援医療制度を利用すると就職で不利になるの?
自立支援医療制度を利用しても就職で不利になることはありません。
会社が精神疾患を抱えている人の採用を検討する時、最も重視されるのは「今のあなたは問題なく働ける状態なのか?」という点です。。精神疾患を抱えている筆者自身も、自立支援医療制度を利用しながら就職活動をしていた経験がありますが、面接の時にこの制度の利用について聞かれたことは一度もありませんでした。
精神疾患を抱えている人の就職活動には、
- 一般企業への就職を目指す
- 障害者手帳を取得して障害者雇用枠での就職を目指す
- 就労支援サービスを利用して段階的に社会復帰を目指す
などの様々な方法がありますが、あなた自身の体調が安定していなければ選べる選択肢も限られてしまいます。そのため、まずは自立支援医療制度を利用しながら精神疾患の治療を進めて、「問題なく働ける状態」を目指していきましょう。
自立支援医療制度を利用してもローンは組めるの?
自立支援医療制度を利用していてもローンを組むことは可能です。
ローンを組む際には、申請者の「収入」「資産」「返済能力」が主な審査項目となります。そのため、自立支援医療制度を利用していることが、ローンの審査に直接影響を与えることはありません。
「自立支援医療制度を利用するとローンが組めない」という誤解は、「精神疾患を抱えている人はローンを組みにくい」という事情と混同されてしまった結果に生まれたものでしょう。
働きながらローンを返済する場合、最も大切となる資本は体ですよね。そのため、住宅ローンや事業資金ローンなどの健康状態の告知を求められることが多いローンでは、精神疾患を抱えていると審査が通りにくくなるのです。
つまり、あなたが将来的にローンを組むことを検討している場合、まずは自立支援医療制度を積極的に利用して精神疾患の治療に専念することが大切です。
自立支援医療制度を利用しても生命保険に加入できるの?
自立支援医療制度を利用していても生命保険に加入することは可能です。しかし、精神疾患を抱えている人の場合、先述している「ローンが組めない」というケースと同様に「生命保険に加入できない」という事態に直面しやすくなります。
生命保険を契約する際、ほとんどの場合に「持病がないか?」などの健康状態の告知が求められます。その時に、うつ病や統合失調症などの精神疾患を抱えている人は「入院リスクが高い」と判断されやすく、加入を断られたり保険料金が高くなったりする可能性があるのです。
また、生命保険の種類によって加入の条件は異なりますが、
- 精神疾患が完治して5年以上経過している場合
- 過去に精神疾患と診断されていても、現在は健康であることを医師が証明できる場合
- 精神疾患の症状が軽度であり、医師が経過観察中と判断した場合
このような場合では、問題なく通常の生命保険に加入できるとされています。
自立支援医療制度の利用が生命保険の加入に影響することはないため、生命保険の加入条件を確認すると同時に精神疾患の治療を進めることが大切です。
自立支援医療制度の申請方法
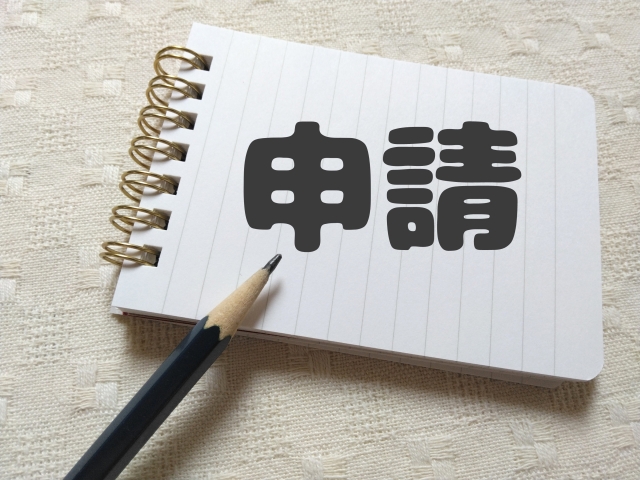
自立支援医療制度の申請は、必要な書類を準備して自治体の担当窓口に提出するだけで完了します。しかし、初めて手続きを行う人の場合、「役所関係の手続きは複雑そう…」と不安を抱えてしまうこともありますよね。
そのような方でも安心してください。
以下では、自立支援医療制度の申請方法について詳しく解説してきます。
また、自立支援医療制度は「指定自立支援医療機関」の対象になっている病院と薬局でなければ利用できません。稀ではありますが、小規模なクリニックなどでは自立支援医療制度を利用できないことがあるため、事前に通院予定の病院と薬局が指定自立支援医療機関であるかを確認しておきましょう。
申請に必要な書類を用意して窓口に提出する
自立支援医療制度の申請に必要な書類は以下の通りです。
- 医師の診断書
- 申請書(支給認定申請書)
- 世帯の所得が確認できる書類
- 健康保険証
- マイナンバーが記載されているもの
また、自治体によっては必要な書類が一部異なる場合があるため、申請の前に市役所で確認することが大切です。
医師の診断書
主治医に自立支援医療制度を利用したい旨を伝えて、診断書を作成を依頼しましょう。診断書の制作費用は病院ごとに異なりますが、3000円~5000円程度であることが一般的です。また、診断書の有効期間は医師が内容を記載した日から3カ月間であるため、この期間内に申請手続きを行う必要があります。
申請書(支給認定申請書)
申請書は市役所の申請窓口で貰えるほか、お住いの自治体のホームページから印刷することも可能です。申請書の記入の仕方が分からないという場合は、窓口で職員の指示を受けながら申請書を作成することができます。この場合は印鑑を持って行きましょう。
世帯の所得が確認できる書類
市役所の担当窓口で「所得課税証明書」を発行しましょう。また、障害年金などの非課税の金銭給付を受けている場合は、「年金振込通知書」などの受給金額を証明できる書類を持参すると申請がスムーズになります。
健康保険証
健康保険証の写しではなく原本を持参しましょう。
マイナンバーが記載されているもの
申請にあたりマイナンバーの記入を求められる場合があります。自分のマイナンバーを覚えている人は問題ありませんが、マイナンバーカード(所持していなければマイナンバーが印字されている住民票など)を用意しておくと安心です。
これらの書類を用意して市役所の担当窓口に提出すれば申請は完了します。
書類提出後の流れ
提出した書類に不備がなければ審査が行われます。審査には通常1~2カ月程度の時間がかかり、その結果は郵送で通知されます。無事に審査が承認されると、通知の中に「自立支援医療受給者証」が同封されており、それ以降は病院や薬局で受給者証を提示すると医療費の減額を適用されます。
また、申請日から受給者証が届いた日までの間に医療費が発生した場合、その費用の払い戻しを受けることが可能です。
例えば、7月1日に自立支援医療制度の申請を行い、9月1日に受給者証が届いた場合では、7月1日~9月1日までの間に3割負担で支払った医療費を自立支援医療制度が適用された状態で再計算して、その差額を返金してもらうことができます。
自立支援医療制度の3つの注意点

以下では、自立支援医療制度を利用する場合の3つの注意点を紹介します。デメリットではありませんが、初めて自立支援医療制度を利用する人が勘違いしやすいポイントがあるため、しっかりと注意点を把握しておきましょう。
指定した病院と薬局でなければ減額は適用されない
自立支援医療制度を申請する際に、指定自立支援医療機関の中から利用する病院と薬局を1件ずつ指定することが求められます。医療費の減額は、申請時に指定した病院と薬局でしか適用されない点に注意が必要です。
また、医療費は3割負担となりますが、指定した病院以外で治療を受けることに制限は発生しません。市役所での手続きが必要になりますが、後から指定した病院や薬局を変更することも可能です。
精神疾患の治療と関係のない薬には減額が適用されない
精神科・心療内科では、精神疾患の治療のための薬以外にも、風邪薬や下痢止めなどの処方を受ける場合があります。しかし、このような精神疾患の治療と関係のない薬については、自立支援医療制度の対象外となり減額されないため注意が必要です。
1年ごとに更新が必要
自立支援医療制度の受給者証の有効期限は1年となっているため、継続して制度を利用する場合は更新手続きを行う必要があります。更新手続きは期限が切れる3カ月前から行うことができますが、更新にも1~2カ月程度の時間がかかるため、事前に主治医に相談しておくことが大切です。
また、受給者証の更新手続きには、2年に1度診断書の提出が求められます。この時の診断書の作成にも費用が発生するため注意が必要です。
まとめ
- 自立支援医療制度とは、通精3割負担となる精神疾患の通院治療費を1割負担に軽減できる制度であり、経済的に厳しい状況の人ほど手厚い支援を受けられる
- 自立支援医療制度を利用すると「就職で不利になる」「ローンが組めない」「生命保険に加入できない」というのは誤解であり、この制度を利用するデメリットはない
- 自立支援医療制度の申請は必要な書類を用意して市役所の窓口に提出するだけで完了するが、自治体によって手続き方法が異なる場合があるため事前に確認することが大切
- 申請の際に指定した病院と薬局でしか医療費の減額は受けられず、精神疾患と関係のない薬の処方などについても制度の適用外となる点は特に注意が必要
自立支援医療制度の申請の通過率について公開されているデータはありません。しかし、筆者が主治医や市役所に確認した時には、「収入が多くて申請要件から外れているケースや治療する精神疾患が制度の対象外であるケース以外で、申請が拒否されたケースは聞いたことがない」という回答を頂いています。
自立支援医療制度とは、精神疾患を抱えている多くの人が利用できる制度です。申請や更新には手間がかかりますが利用してもデメリットは発生しないため、この制度を積極的に活用して精神疾患の治療を進めていきましょう。
なお、自立支援医療制度とあわせて利用できる就労支援サービスとしては、「ミラトレ」のような事業所が行っている「就労移行支援」がおすすめです。症状を抱えた状態での働き方に不安を抱えている方も、各事業所が提供している模擬オフィスでの業務体験や企業実習を通じて、働くことのイメージを具体化できます。
障害者手帳がなくても、医師の診断書や自治体の判断などがあれば利用可能です。所得状況によっては費用もかかりません。気になる方はぜひ一度、確認してみましょう。