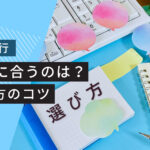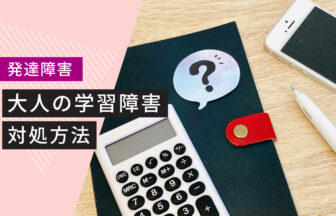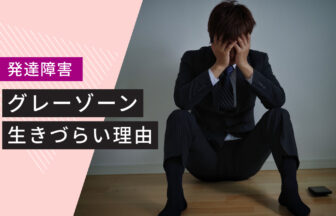公務員は、安定した職業として非常に人気があります。そのため、「自分でも公務員になれるのかな?」と気になる発達障害の方も多いと思います。
結論から言うと、発達障害の方も、障害者手帳を持っていれば障害者枠で公務員試験を受験し、公務員になることができます。
他にも、次のような疑問をお持ちではないですか?
「発達障害の人が公務員を目指すメリットは?」
そんなあなたに向けて、
- 障害者雇用での公務員はきついのか
- 発達障害者が公務員を目指すメリット
- 発達障害者が公務員を目指すための試験対策
以上を解説していきます。
本記事を通して、発達障害の方が公務員を目指すメリットや具体的な試験対策について知り、自分に合った仕事かどうか確認していきましょう。
障害者雇用の公務員はきついって本当?

発達障害を持っていても持っていなくても、公務員になるのはとても難しいです。さらに、障害者雇用となると、より難しくなるかもしれません。どんな理由があるのでしょうか。
ここでは主に、3つの理由を紹介していきます。
- 公務員試験に向けた勉強が必要
- 倍率がとても高い
- 配属先を自分で選ぶことができない
順に見ていきましょう。
公務員試験に向けた勉強が必要
公務員になるためには、選考試験を受ける必要があります。選考試験は自治体によって異なりますが、主に次の3つがあります。
- 書類選考
- 筆記試験
- 面接
一般枠と障害者枠の筆記問題の難しさは変わりません。そのため、きちんと勉強して臨まなければ、公務員試験を通過することは難しいでしょう。勉強に苦手意識がある方は、しっかりと対策をする必要があります。
試験対策として、公務員になるための専門学校や予備校に通うという選択肢もあります。
倍率がとても高い
公務員は安定している職業なのでとても人気が高く、倍率が非常に高いです。さらに、以前は公務員の障害者枠は身体障害者のみでしたが、今は精神障害者や知的障害者も対象になっています。その結果、障害者枠内の競争率も非常に高くなりました。
そのため、採用されるに至るまでにたくさんの努力と時間が必要になるでしょう。
配属先を自分で選ぶことができない
障害者枠で採用されても、公務員は配属される部署を選ぶことができません。希望する職場につけるとは限らず、事務職に配属されることが多いです。また、同じように異動先も選ぶことができません。
たとえ厳しい採用試験をクリアして公務員になったとしても、自分がやりたい業務ができない可能性がある点には留意が必要でしょう。
発達障害の方が公務員を目指すメリット

上記のように、発達障害のある方が公務員を目指すことは決して楽ではありません。しかし同時に、発達障害者が公務員になることには、多くのメリットも存在します。
ここでは主に、以下の3つを紹介していきます。
- 一般企業の障害者枠より給料が高い
- 安定して働ける
- 休日が多く、有給休暇制度がしっかりしている
順に確認していきましょう。
一般企業の障害者枠より給料が高い
公務員の障害者枠は、一般企業の障害者枠と比べて高い傾向があります。さらに、公務員は一般枠と障害者枠で給料に差がありません。
こうした給与面のメリットは、発達障害の方が公務員を目指す大きな理由となるでしょう。
安定して働ける
一般的に、公務員の最大のメリットとされるのが「安定していること」です。実際に、公務員の離職率は一般企業と比べても低いです。クビにされる心配もないため、安心して働くことができるでしょう。
また、公務員は社会的な信頼度も高く、金融機関や物件の審査などで有利になりやすいといったメリットもあります。
休日が多く有給休暇制度がしっかりしている
障がいを持っていても持っていなくても、体調管理に休日は必須です。特に、発達障害の方は通院などで休むこともあると思います。
公務員は休日が多く、有給休暇制度もしっかりとしています。そのため、「人より疲れやすい」など発達障害による特性があっても、仕事を長期間続けやすくなるでしょう。
障害者雇用で公務員に採用されると勝ち組?

障害者枠で公務員に雇用されると「勝ち組」だと言われることもあるようです。障害者雇用で公務員になると「勝ち組」と言われるのは、以下のような理由があるからかもしれません。
- 仕事内容が事務や雑用が多い
- よほどのミスをしない限り解雇されない
- 1~5年で異動するため、人間関係をあまり気にしなくていい
- 昇給やボーナスがある
障害者枠での公務員の仕事は、主に簡単な雑用や事務、データ入力などです。他にも、役所などではペーパーワーク、臨時職員ではシュレッダーなどの業務をすることもあります。
ただし、一般枠と同じような業務を期待されることもあり、必ず簡単な業務になるとは限りません。
また、発達障害には個人差があるので、得意・苦手な分野は人それぞれです。発達障害の特性は、仕事に対して良い方向にも悪い方向にも影響するため、公務員の仕事の内容が自身に合うかどうか、よく考えることが大切になります。
支援機関などであらかじめ自分の特性を理解することで、どのように進めていくのかも、分かりやすくなるかもしれません。
発達障害の方が公務員を目指すための試験対策
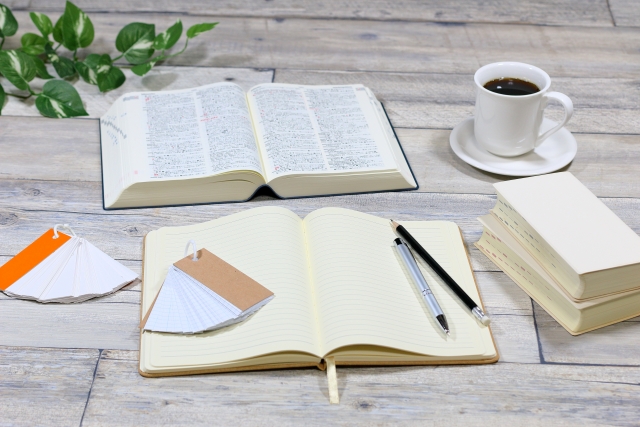
公務員になるためには、公務員試験に合格しないといけません。それは障害者枠でも同じです。まずは、試験がどんな内容なのかを知りましょう。試験は、「書類選考」「筆記(教養・作文)」「面接」の3つから構成されます。
書類選考は一般企業と同じ程度なので、特別に準備する必要はありませんが、筆記試験は一般企業の障害者枠で行われることは少なく、対策が必須になります。ただし、一般雇用の場合のように年単位で準備をするものではありません。
筆記試験の問題は教養と作文です。教養では、過去問の中で事務職のものを覚えておくと良いでしょう。本屋での問題集や、ウェブで公開されているものがあります。専門学校や予備校で学ぶのも良いですが、教養はいままでの学力が必要になってくるため、効果が小さい可能性があります。
分かりやすい問題で、しっかりと自分の考えを表現できるようにする練習が効果的です。
公務員試験の対策は、就労移行支援などで準備できる場合もあるので、うまく活用しましょう。例えば大阪市の就労移行支援事業所「With You」では公務員対策講座があります。
大阪の就労移行支援事業所WithYou | 公務員試験対策コース
また、先に民間企業に就職してから公務員を目指す方もいます。そうすることにより、実績や経験を生かすことができるため、試験で有利に働きます。
ただ、就職活動をしながらの長期での活動となるので、体力を消耗してしまう可能性もあります。ご自身のペースに合った対策が必要となるでしょう。
就労移行支援については、以下の記事でも詳しく解説しております。
まとめ
- 公務員試験には障害者枠がある。発達障害のある方も、障害者手帳を持っていれば障害者枠を利用して公務員を目指すことができる
- 公務員は人気があるため試験倍率が高く、対策としてきちんと勉強をする必要がある。配属先を選べない点からも、障がい者に公務員は「きつい」と言われることがある
- 一般企業の障害者雇用より給料が高い点、安定した職業で休日がしっかりとれる点など、発達障害の方が公務員を目指すことにはメリットも大きい
- 仕事内容に事務や雑用が多いこと、解雇されづらいことや昇給やボーナスがあることなどから、障害者雇用で公務員になれると「勝ち組」と言われることもある
- 公務員試験の対策としては、まず試験がどんな内容なのか情報収集をして、過去問などに取り組むことが重要。専門学校や予備校、就労移行支援を利用するという選択肢もある
発達障害を持っていても障害者枠を利用し、公務員になることは可能です。ただし、とても倍率が高く、筆記試験では問題の難易度に差はないため簡単ではありません。
解説してきたように、合格できれば多くのメリットがあるので、挑戦する価値はあります。ただし、必ずなれるとは限らないので、一般企業の障害者枠を利用して就職することも考えておいた方が良いでしょう。
この記事が参考になりましたら幸いです。