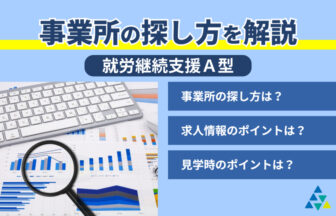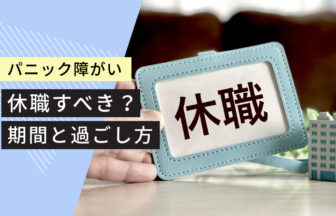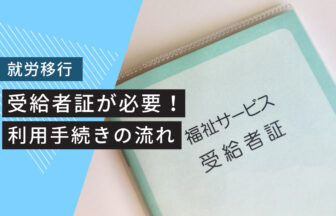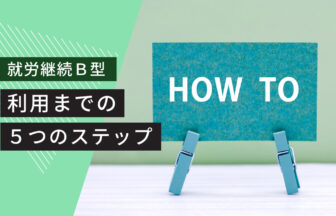「リワークには、どのようなメリット・デメリットがあるの?」
などの疑問がある方もいらっしゃるでしょう。
うつ病で休職していたけれど、体調が回復してきたのでそろそろ復職したいと考えている方には、リワーク支援を利用するという選択肢もあります。
- リワーク支援とはどのようなものか?
- うつ病の方がリワーク支援を利用するメリット
- リワーク支援を利用するデメリット
- リワーク支援の種類を選ぶ際のポイント
について、解説していきます。
リワーク支援を受けるかどうか、受けるとしたらどのような形態が自分に合っているかを考える際の参考になれば幸いです。
リワーク支援とは?

リワークは「return to work」の略語で、職場復帰を意味します。うつ病や適応障害などの精神的な不調で休職している方の復職を目的とした支援プログラムです。退職している方は利用できないため、職業準備支援などの別の支援プログラムを受けることになります。
リワーク支援のプログラムとして下記のようなものがあります。
- 精神疾患を再発させないための心理支援
- 復職に向けて体を慣らしていく訓練
- 生活リズムを安定させるための定期的な通所
- コミュニケーションスキルの向上のためのSST(ソーシャル・スキル・トレーニング)
- 復職後のイメージをつかむキャリアプランの作成
など
これらのプログラムを通して復職のための準備を行い、スムーズな職場復帰につなげていきます。また、リワークで身につけたスキルを復職後も長く働き続けるために活用することも、リワークの目的の1つです。
職場復帰を目指す、という言葉こそ簡単ですが、正式に職場復帰を行う前に準備期間を設けても、本人が復帰を焦ってしまうなど、復職へのハードルは高いのが現状です。リワークについての理解を深め、スムーズな復職、再休職の予防のために、慎重なリハビリが必要です。
リワークは実施する施設によって大きく3種類に分けられます。
- 医療リワーク(医療機関の場合)
- 職リハリワーク(地域障害者職業センターの場合)
- 職場リワーク(職場で実施する場合)
この項目では、リワーク支援を実施している施設の特徴を解説します。
医療リワーク|医療機関で受ける
病院などの医療機関で行われるリワークが「医療リワーク」です。医師や看護師、臨床心理士などの専門家による、医学的リハビリテーションとして実施される復職支援特化のプログラムが受けられます。
復職に向けた訓練だけでなく、作業療法や認知行動療法のような治療も受けることができます。
医療リワークの利用には料金が必要です。健康保険が利用できますが、3割負担の場合、1回あたり2,000~3,000円程度の費用がかかるケースが多いようです。ただし、自立支援医療制度を利用している場合は1割程度の負担額でプログラムを受けることができます。
利用する期間は、数週間程度の短期から年単位がかかる長期のものまでありますが、平均的には3~6か月程度としている施設が多いです。
医療リワークを利用するには主治医の許可が必要になります。しかし、すべての医療機関で医療リワークを実施しているわけではないため、近隣で医療リワークを行っている機関を紹介される場合もあります。
医療リワークを受けたい場合は、まず主治医に相談してみましょう。
職リハリワーク|地域障害者職業センターで受ける
地域障害者職業センターで行われるリワーク支援が「職リハリワーク」です。
地域障害者職業センターは、障がいがある方に対して専門的な職業リハビリテーションサービスを提供する機関です。基本的に各都道府県に設置されています。職リハリワークは、地域障害者職業センターのサポートに含まれるリワーク支援です。
医療機関のような治療ではなく、職場復帰に向けた本人と雇用主への支援を目的としています。職業カウンセラーが間に入り、休職者本人と雇用主、主治医と相談しながら、支援プランに基づいて職業リハビリテーションを実施します。
職リハリワークの利用に料金はかかりません。ただし、交通費や昼食代は自己負担となります。利用期間は体験等を含め14週間(約3か月)程度を標準としています。
職リハリワークを利用したい場合は、各センターの利用説明会に参加しましょう。なお、職リハリワークは雇用保険適用事業所で働く方が対象のプログラムであるため、公務員の方は利用することができません。
地域障害者職業センターについては、下記の記事で解説しています。
職場リワーク|職場・企業で受ける
休職者が所属している企業でもリワーク支援を行う場合があり、職場で行われるリワーク支援を「職場リワーク」と呼ぶ場合があります。こちらは「職場復帰支援プログラム」とも呼ばれており、求職者がスムーズに復職できるように行われます。
主治医から職場復帰可能の判断を受けてから、企業の人事部や産業医などの産業保健スタッフと連携し、実際の職場で復職に向けたプログラムを受けることができます。
プログラム内容は、企業ごとに異なります。内部に医療機関や専門部署がある企業や役所では、職場復帰訓練制度や、EAP(従業員支援プログラム)サービスを利用する場合もあるようです。
基本的に企業内で行われるので、復職に対する不安を減らすために「試し出勤(慣らし勤務)」を行うこともできます。
利用料金は、本人が所属している企業で行われるので、企業負担で受けられます。期間は1~2か月程度になることが多いようです。ただし、職場リワークは法的に義務付けられているものではないため、実施していない企業や整備がされていない企業もあります。
職場リワークを利用したい場合は、主治医に復職が可能か相談した後、人事担当者や総務担当者に確認してみましょう。
リワーク支援を利用するメリット

リワーク支援を利用すると、主に5つのメリットがあります。
- 復職への負担を軽減でき、無理なく職場に復帰できる
- 精神疾患の再発を防止し、再び休職することを防げる
- 生活リズムを安定させることができる
- ストレスへの対処方法を身につけられる
- 職場でのコミュニケーションスキルを向上できる
この項目では、上記のメリットについて解説していきます。
復職への負担を軽減でき、無理なく職場に復帰できる
長期の休職後では体力が落ちていたり、生活リズムが乱れていたりする場合があります。この状態で復職をすることは、体への負担が大きいため、再び体調を崩すことにつながる可能性があります。症状が安定していない状態では、勤務に対しての不安も強くなるでしょう。
リワークでは、実際の労働を想定したオフィスワークや軽作業のプログラムが実施されます。プログラムを通して、復職に向けて徐々に体を慣らし、以前のスキルを取り戻していくことを目的としています。
また、リワークのスタッフは利用者の様子や状態を客観的な視点で確認しています。
復職して問題がないか、スタッフと相談しながら決めることで、十分に回復してからの復職が可能になります。
精神疾患の再発防止、再休職を防ぐ
リワーク支援には、復職してからも長く働き続けるという目的もあります。
特にうつ病は、病気の性質上、再発しやすい病気です。リワーク支援を受けることで病気の特性を知り、病気とうまく付き合う方法を見つけることができます。また、ストレスへの対処法を身につけることで過度なストレスを避け、再休職を防ぐことができるでしょう。
実際にリワーク支援を受けた方と受けなかった方では、リワーク支援を利用した方が就労継続率が高いというデータもあります。少し古いデータですが、「リワークプログラム利用者の復職後1年間の就労継続性に関する大規模調査」では、リワーク利用者の復職後1年間後の就労継続率は約80%程度だと推定されています。
リワーク支援で行っている、復職後も働き続けるための準備は、精神疾患の再発と再休職を防止する効果があると言えるでしょう。
生活リズムの安定につながる
休職によって生活リズムが乱れてしまう方もいらっしゃるでしょう。リワークでは週3~5日程度、日中の同じ時間帯に通うことになるので、生活リズムの安定化を促すことができます。
多くの場合、リワーク支援は週1~2回の利用から始まり、徐々に利用する頻度を上げていきます。最終的には復職後の勤務時間に近いリズムを作り、スムーズに復職につなげていくことを目指します。
通所の日程やプログラム内容は施設によって変わってくるので、事前に日程を確認して自分に合う施設を選ぶのが大事です。
生活リズムが乱れた状態で復職するのはかなり大変ですが、リワーク支援を利用することで生活リズムを整えてから復職ができます。
ストレスマネジメントの方法を身につけられる
リワークでは認知行動療法などの心理プログラムが用意されている場合があります。これらのプログラムを通して、ストレスコーピングの方法を身につけることができます。
ストレスコーピングとは、ストレスに対して適切な対処を行うスキルです。このスキルによって、復職後に過度なストレスを受けた場合でも、うつ病の再発を防止し、再び休職する事態を回避できるようになるでしょう。
リワークでは実務に近い環境で実践的に訓練が行えるので、ストレスへの対処法を効果的に学ぶことができます。
ストレスコーピングについては、下記の記事で解説しています。
職場でのコミュニケーションスキルの向上を目指せる
職場での人間関係の問題によって体調を崩し、休職することになった方もいらっしゃるでしょう。リワークのプログラムでは実際の職場を想定したコミュニケーションのトレーニングも実施されています。
コミュニケーションスキルの向上を目的として、「SST(ソーシャル・スキル・トレーニング)」を取り入れている施設もあります。SSTは、人間関係や社会生活における対人関係を円滑にするスキルを身につけるためのプログラムです。社会生活技能訓練と呼ばれることもあります。
グループワークなどを通して実践的に対人スキルの向上に取り組むことができます。
プログラムで身につけたコミュニケーションスキルは、職場での人間関係を円滑にし、再休職の可能性を減少させてくれるでしょう。
SST(ソーシャル・スキル・トレーニング)については、下記の記事で解説しています。
リワーク支援を利用するデメリット

リワークを利用するデメリットとしては、大きく2つあります。
- 職場復帰まである程度時間がかかる
- 費用がかかる場合がある
この項目では、それぞれのデメリットについて解説していきます。
職場復帰まで、ある程度時間がかかる
リワーク支援を開始してから復職するまで、3~6か月程度かかる場合が多いです。
支援を受けている期間中は、金銭面が心配になることもあるかもしれません。また、会社の休職期間の規定により、十分な期間利用できない場合もあります。
うつ病を発症した後は、時間をかけてリハビリを受けて、十分に回復したことを確認してからの復職が望ましいです。
しかし、職場復帰まであまり時間がかけられないときは、リワーク支援が中途半端に終わったなど、準備が不十分なまま復職することになる点は大きなデメリットとなるでしょう。焦って復職をしてまた体調を崩すことがないように、体調をしっかりと見極めて復職のタイミングを決めるのが大切です。
リワーク支援を利用する過程で費用がかかる場合がある
リワークの利用料金は施設や利用形態ごとに異なりますが、医療リワークの場合、利用料金として医療費を支払う必要があります。自立支援医療制度を利用すれば自己負担額を1割に軽減できますが、収入が限られている状況では少額でも厳しいものです。
また、職リハリワークや職場リワークのような利用料金は無料の場合でも、交通費や昼食代は自己負担による実費が必要となる場合が多いです。利用にかかる料金は、施設や利用形態などで異なってくるので、事前に調べておき、自分に合った施設を見つけましょう。
自立支援医療制度については、下記の記事で解説しています。
リワーク支援を選ぶポイント4選

リワーク支援を選ぶ際のポイントを4つご紹介します。
リワーク支援を実際に受けた方の中には、効果を実感できなかった、という方もいらっしゃるでしょう。しかし、リワーク支援を受けずに復職した方は再休職される方が多いと言われています。リワークの効果を得るためにも、リワーク支援の目的をしっかり把握して、自分に合った支援を検討しましょう。
交通アクセス
交通アクセスの良し悪しは、リワーク選びの大切なポイントです。
リワークへの通所は最初は週1~2回の通所から始まり、最終的には週3~5回通うことになります。
リワーク施設が遠くて通所に時間がかかる、ラッシュ時が非常に混雑するなど、交通アクセスが悪いと体力面、経済面での負担が大きくなってしまいます。一方で、施設が自宅から近すぎるとあまり訓練にならないという面もあります。
通所に負担がかかるために通えなくなっては意味が無いので、無理なく通える立地の施設を選びましょう。施設を見学する際は、交通の良し悪しも確かめておきましょう。
また、実際の通所時間に移動してみて、混雑具合を確認するのも良いでしょう。
施設の雰囲気
実際に見学をして、施設の雰囲気を確認することも大事です。施設に入ったときに、整理整頓ができているか、人数分のスペースは十分にとれているか、ほこりっぽくはないかなど、不快感・違和感がないか確かめましょう。
見学対応をしたスタッフの印象も大事です。施設内の雰囲気はスタッフによってつくられる部分が大きく、あまり良い印象がなければ別の施設も見学して、比較してみることも検討しましょう。
また、余裕があれば他の利用者の様子を見てみると良いでしょう。
プログラムの内容によっては他の利用者の方と交流することもあります。他の利用者となじめそうか確認しておくのも良いでしょう。
プログラムの内容
多くのリワーク支援で共通しているのは、復職の基本となる生活リズムの改善を目的としている点です。しかし、それ以外だと、施設ごとにさまざまなプログラムが用意されています。
医療リワークでは認知行動療法などが取り入れられており、症状からの回復や、再発の予防など治療の側面が大きいプログラムが組まれています。
職リハや職場でのリワークでは、職場での業務を想定した動きが求められる訓練が行われることが多いです。
事前に施設の訓練内容などを調査して、自分のニーズに合った施設を選びましょう。
アフターフォローの有無
復職後も定期的にフォローアップをするプログラムがあるかどうかも、リワーク支援施設を選ぶ際のポイントになります。フォローアッププログラムは、再休職のリスクを抑える目的で行われています。復職した後の仕事や生活での問題や悩みを解消して、職場定着を目指します。
フォローアッププログラムの実施については施設ごとに異なるので、リワーク支援を受ける前に確認しておきましょう。
リワーク支援利用の流れ

リワーク支援を利用したい場合、何から始めればいいでしょうか。
この項目では、リワーク支援利用開始までの簡単な流れを紹介します。
復職に向けてリワーク支援を利用したいと思ったときは、まず、相談をしましょう。通院している病院、勤務(休職)している会社、事業所の3つに相談すると良いでしょう。
- 通院している病院の主治医、またはケースワーカーに相談
- 勤務している会社の人事担当者や、産業医・保健師に相談
- 利用を検討している、リワーク支援を利用したい事業所へ直接問い合わせる
先述したように、リワーク支援の細かな内容は場所によって異なります。見学・体験が可能な所もあるので、自分に合うリワーク支援を探すことができます。ただ、定員が設定されている場合もあるので、利用したい場合は直接連絡し、受け入れ可能か確認する必要があります。
利用先が決まったら、手続きが必要な書類等の確認を行います。
利用には診断書が必要となる場合がほとんどのため、主治医に依頼をします。
会社とリワーク先が連携をとって復職に向けた計画を立てる場合もあるので、会社の担当者とも協力して進めることになります。
本人、主治医、会社、リワーク先の意向を踏まえて、復職に向けた計画を作成します。
計画に合意が取れてから、利用開始となります。
利用開始から復職までの流れは人それぞれ異なり、数か月で復職できる場合もあれば、数年かけて復職を目指す場合もあります。焦らず、着実に進めましょう。
※リワーク支援の種類などによっては、流れが変わる場合があります。詳しくは、利用を検討しているリワーク先へご確認ください。
まとめ|うつ病からリワーク支援を受ける場合のメリット・デメリット
- リワーク支援は休職している方が復職に向けた訓練を行う支援プログラム。退職している場合は職業準備支援など、別の支援を利用することになる。
- リワーク支援を利用するメリットは「再休職を防ぐ」「生活リズムを整えられる」「職場で必要なコミュニケーションスキルの向上」など。
- リワーク支援を利用するデメリットは「職場復帰まで3~6か月程度かかる」「施設によっては利用料金がかかる」などがある。
- リワーク施設を選ぶ時のポイントは「通所に負担にならない程度の交通アクセスの方法があるか」「施設の雰囲気は良いか」「プログラム内容が自分に合っているか」などに注目すると良い。
職場復帰に向けてリワークを利用したい場合は、メリット・デメリットを考慮して自分に合った施設を選ぶことが大切です。
復職後も長く働くためにも、リワークプログラムの目的を把握して利用を検討しましょう。
なお、より負担の少ない職場への転職も視野に入れている場合は、エージェントサービスのご利用も考えておくとよいでしょう。
障害者手帳をお持ちである場合は「dodaチャレンジ」のような、障がい者向けの求人を提供しているエージェントも利用できます。あなたに合った求人を提供してくれるだけでなく、うつ病についてどのように応募書類に書くか、面接のときどう返答すべきかなどもアドバイスしてくれるのでおすすめです。
無料相談を受け付けているので、気になったら気軽に試してみてください。