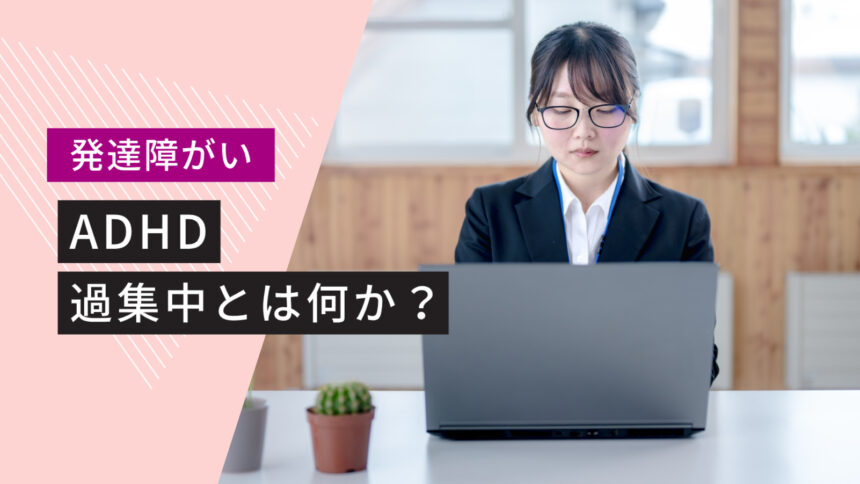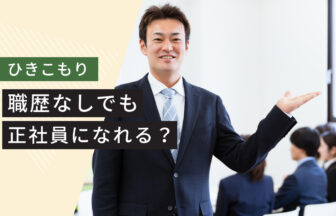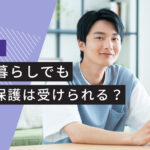「集中できる事とできない事の差が激しく、仕事の質にムラが多い…」
などの悩みを抱えてはいませんか?
このような状態は「過集中」と呼ばれることがあります。
過集中とは、その名の通り「物事に過剰に集中してしまう」という状態のことです。過集中はADHDの方に現れやすい特性と言われており、特定の場面において高い集中力を発揮できる一方で、自力で集中力をコントロールできずにトラブルが起きてしまうこともあります。
- 過集中とは何か?ADHDの人は過集中になりやすい?
- 過集中によるメリットとデメリット
- 過集中対策に有効な「ポモドーロ・テクニック」とは?
について解説していきます。
ADHDの方の過集中という特性は、上手く対策できると大きな強みになることもあります。この記事を、過集中に悩むあなたの一助としていただけたら幸いです。
ADHDの過集中とは?
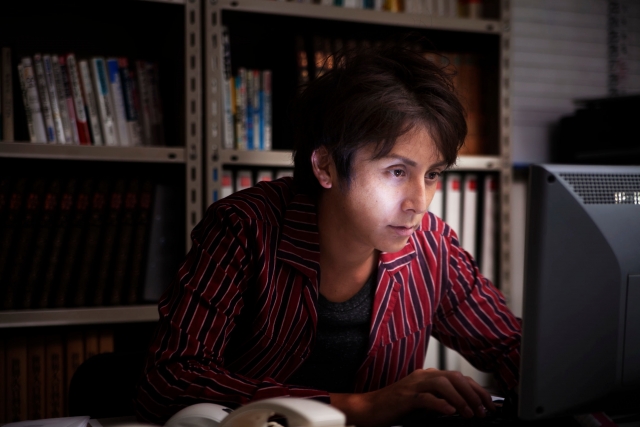
ADHDとは「注意欠如・多動症」とも呼ばれており、「不注意」「多動性(落ち着きがない)」「衝動性」という3つの特性が現れやすい発達障害の1つです。これらの特性から、一般的に知られているADHDの性質として「集中力が低く注意散漫」「じっとしていることが苦手」などがあります。
一方でADHDの方には、特定の物事や作業に極めて高い集中力を発揮する「過集中」の性質が現れやすいことでも知られています。
過集中の状態に入ると、下記のような特徴が見られやすくなります。
- 時間が経過する感覚が極端に鈍くなる
- 自己の感覚が薄れることで空腹や疲労などを感じなくなる
- 周囲の話し声、物音、出来事などの刺激が遮断される
- 1つの物事や作業にのみ集中して、他のことを完全に忘れてしまう
- 過集中の状態の間は高いパフォーマンスを発揮できる
ADHDの方が過集中になりやすい原因として、脳内でのドーパミンの分泌が影響していると考えられています。次の項目では、その原因について詳しく見ていきましょう。
ADHD特有のドーパミン分泌による影響
ドーパミンとは、分泌されることでやる気や意欲を引き起こしたり、集中力や注意力を向上させたりする効果がある神経伝達物質の1つです。ドーパミンが適切に分泌されていれば、日常的な作業であっても一定の集中力や注意力を維持できるほか、やりがいを感じられる仕事をする時に高いモチベーションを維持させることができます。
しかし、ADHDの方は脳機能の発達の偏りによって、
- 通常時の脳内ではドーパミンが不足しやすい
- ドーパミンの分泌量を上手く調節できない
という2つの特徴を持っていることが分かっています。
この影響により、ADHDの方は興味がない作業や単調な仕事を行う時にドーパミンが不足しやすく、集中力が持続しない原因となります。一方で、得意な作業ややりがいを感じる仕事を行う時にドーパミンが過剰に分泌されやすく、過集中に陥ることが多いです。
ADHDの方はドーパミンが適度に分泌されないために集中力をコントロールすることが苦手であり、集中力のオンとオフが両極端になりやすいことがわかります。
過集中によるメリット3選

過集中の状態は、極めて高い集中力の発揮と共に自分の能力を最大限に活用できるタイミングであるため、「ゾーン(フロー状態)」に近い概念であると言われています。
次の項目では、過集中によって得られるメリットを紹介していきます。
仕事の生産性や質が向上する
過集中の状態に入ると最も顕著に現れるメリットが、仕事の生産性や質の向上です。
通常であれば私たちの集中力は時間と共に低下していくため、90分~120分程度が集中力を維持させる限界と言われています。一方、ADHDの方の過集中は1つの仕事に没頭することで、数時間~1日中ほかのことを完全に忘れて極めて高い集中力を維持させることができます。
そのため、過集中の状態には、
- 仕事の効率化により、生産性の向上する
- 細部の見落としがなくなることにより、仕事の正確性の向上する
- 高い洞察力やこだわりを発揮することにより、新しいアイデアの発見に繋がる
上記のようなメリットがあるのです。
過集中はマルチタスクやスケジュール管理が求められる環境には向かない反面、シングルタスクにおいて特に有利に働く状態と言えるでしょう。
学習能力が向上する
過集中の状態になると、周囲の物音や他の情報・考え事などを切り離して学習内容にのみ深く集中できるため、高度な理解力の発揮と長期的な記憶の定着に期待できます。また、通常の学習では見逃しがちな細かな知識や情報にも注意を向けられるため、周辺知識を自然に身に付けられることでより専門的な知識の習得に役立つのです。
過集中時の学習はADHDの方にとって1つの成功体験となり、学習に対するモチベーションが高まるというメリットもあります。
過集中は、特に強い興味や関心を持っているテーマの学習において発揮されやすい傾向があります。
そのため、ADHDの方は、
- プログラマーやエンジニアなどの技術職
- 問題の発見と解決能力が求められる研究職
- 自身のこだわりや創造性を生かせる作家やデザイナーなどのクリエイター職
などの仕事に高い適性を持つことが多く、実際にこれらの仕事に従事している方にADHDの特性が見られることも多いです。
過集中の状態にはリラックス効果がある
先述の通り、過集中の状態に入る際には脳内でドーパミンの分泌量が増加します。このドーパミンの増加はモチベーションや集中力の向上だけでなく、報酬感覚を引き出す効果があることで知られています。
報酬感覚とは、
- 特定の物事、作業、経験などから快感を得ることができる
- 作業を終えた時に大きな達成感や報酬を得られるという期待を抱く
という状態を指します。
そのため、報酬感覚が得られる仕事では、それ自体を脳が「快感や報酬」であると捉えるようになり、「働くことが楽しい」という状態を生み出します。過集中による没入感とそこから得られる報酬感覚はリラックスやストレス軽減の効果をもたらすため、過集中は心身の健康に繋がるというメリットもあります。
過集中によるデメリット3選

集中力をコントロールすることが苦手なADHDの方は、何の前触れもなく急に過集中状態に陥ってしまうことがあります。そのため、意図せず過集中に陥ることでさまざまな困りごとを発生させてしまうことがあるのです。
次の項目では、過集中のデメリットについて見ていきましょう。
他の仕事や予定を完全に忘れてしまう
ADHDの方は生まれ持った脳機能の特性により、
- 短期的な記憶が苦手であり、予定や約束をど忘れしやすい
- 目についた作業から衝動的に取り掛かってしまい、作業の優先順位を見失いやすい
- 複数の仕事に集中したり注意を向けたりが苦手であり、マルチタスクができない
など、日常的にこのような困りごとに直面しやすい傾向があります。
過集中の状態では、時間間隔が鈍くなり周囲からの情報や刺激も遮断されてしまうため、ADHDの方が抱えている「予定管理の苦手さ」「マルチタスクの苦手さ」などの困りごとを際立たせてしまうことがあるのです。
そのため、過集中には、
「過集中の影響で予定通りに仕事を進行させることができなかった」
などの事態に直面しやすくなるデメリットがあります。
過集中から抜け出したら虚脱状態になりやすい
過集中に入ると、脳は通常の状態よりも高いパフォーマンスで活動するため、エネルギーの消費量も増加します。一方で、過集中の間は自分自身の疲労や空腹を感じにくくなるため、適度な休憩・食事・睡眠などを取らずに活動を続けてしまいます。
その結果、過集中から抜け出した瞬間に急激に疲労感が押し寄せてきて、虚脱状態に陥ることが多いのです。
虚脱状態になると、
- 身体と精神の疲労による強い無気力感がある
- 頭がぼんやりして、思考力や判断力が低下している状態が続く
- イライラや気分の落ち込みを感じやすく、感情が不安定になる
このような状態になることがあります。
過集中と虚脱状態を繰り返してしまうと、仕事の質や効率に大きなムラを生み出すことに繋がります。また、慢性的な睡眠不足や体調不良を引き起こし、燃え尽き症候群などを引き起こすリスクが高まります。
さまざまな依存症になりやすい
ADHDの方は慢性的にドーパミンが不足しやすいため、先述している報酬感覚を得られる活動に対して過敏に反応してより強い快楽を感じやすくなります。そのため、ADHDの方は過集中の状態に突入できる活動に対して依存しやすくなるのです。
実際に、ADHDの方は定型発達の方と比較して、アルコール・ギャンブル・ゲームなどの依存症になるリスクが3倍程度高いという研究結果があります。また、「仕事」「運動」「勉強」などのポジティブな活動が依存の対象となることもありえます。
例えば、仕事に対する依存はワーカホリックを発症して、常に仕事をしていないと落ち着かない状態になります。プライベートの時間にも仕事のことを考えてしまい、余暇時間や家族・友人関係を犠牲にしてまで働こうとする場合があります。
過集中によるポジティブな活動に対する依存は一時的にプラスの効果をもたらすこともありますが、生活習慣の乱れや健康への悪影響などを発生させるデメリットがあります。
ADHDの方の過集中対策に効果的!「ポモドーロ・テクニック」

ポモドーロ・テクニックとは、1980年代にイタリアで考案された時間管理法です。実践することで高い集中力を維持できるため仕事や勉強の質の向上や効率化を見込めるほか、ADHDの方の過集中対策にも効果的です。
一般的に、過集中の対策には、
- タイマーやアラームを利用して時間管理を行う
- 休憩時間を決めて置き、毎日の習慣とする
- 休憩時間には体を動かしたり適度な食事や水分補給を行ったりする
などの方法が挙げられています。
そのため、これらをまとめて実践できるポモドーロ・テクニックは、過集中対策に特に有効な方法となるのです。次の項目で、ポモドーロ・テクニックの実践方法を詳しく見ていきましょう。
ポモドーロ・テクニックの実践方法
ポモドーロ・テクニックには、25分間という単位に作業を細分化するため進捗状況の確認や予定の管理を行いやすくなる効果もあります。ポモドーロ・テクニックを活用することで、過集中の状態をコントロールしながら、日常的に高い集中力を発揮できる習慣を身に付けられるのです。
まとめ|ADHDによる過集中のメリット・デメリットと対策
- 過集中とは、特定の物事や作業に対して極めて高い集中力を発揮できる状態である。
- 脳内で多くのドーパミンが分泌された時に過集中になりやすい特徴があるため、生まれつきの特性によりドーパミンの分泌が不安定であるADHDの方は過集中になりやすい。
- 過集中には、「仕事の質や生産性が向上する」「学習能力が向上する」「リラックス効果を得られる」などのメリットがある。
- 過集中には、「他の仕事や予定を忘れやすい」「過集中から抜け出したら反動で虚脱状態になりやすい」「依存症になるリスクが高まる」などのデメリットがある。
- 過集中の対策には、25分という短い時間に作業を小分けしてタイマーで時間管理を行う「ポモドーロ・テクニック」の実践が効果的。
今回の記事では、ADHDの方に見られやすい過集中のメリット・デメリットやその対策について解説しました。
ADHDの方にとって過集中を完全に制御することは難しいと言われていますが、「ポモドーロ・テクニック」のような対策方法を実践することで困りごとを改善していくことが可能です。
ご自身の特性と向き合って困りごとを解消していきましょう。
ご自身での工夫に加え、過集中という特性を仕事でより良く活かし、安定した就労を目指すなら「atGPジョブトレ」も良い選択肢です。発達障害専門の就労移行支援で、ADHDの特性に応じた時間管理や集中力のコントロール術を学ぶトレーニングを提供しています。
まずは詳細を確認し、相談を検討してみてはいかがでしょうか。
この他にも、ADHDによる仕事のミスでお困りでしたら、こちらの記事で具体的な対策を解説しています。