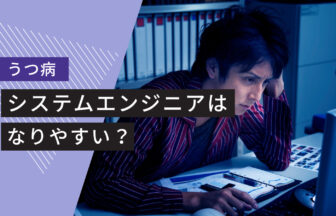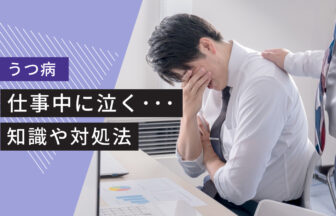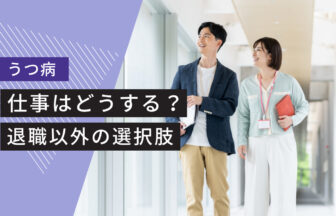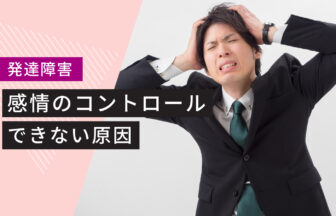「上手く笑えず、冷たい・愛想がない人という印象を持たれやすい…」
この記事にたどり着いたあなたは、このような悩みを抱えていませんか?
昨今では、社会人になってから「集団生活に上手く適応できない」「周りと何かズレている気がする」などの漠然とした生きづらさに気付いたことをきっかけに、病院を受診して診断される大人の発達障がいを抱える方が増加しています。
発達障がいは見た目からでは判断できない障がいですが、表情や感情表現に影響を与える場合があることでも知られています。
- なぜ、発達障がいだと表情が乏しくなるのか?
- 表情が乏しいことで発生するデメリットについて
- どうしても自然な表情を作れない時の3つの対処法
について解説していきます。
発達障がいで無表情・笑えないことに悩んでいるあなたの一助となれば幸いです。
なぜ発達障がいだと表情が乏しくなるのか?

発達障がいはいくつかの種類に分けられていますが、その中でも無表情・笑わないという特性は「ASD(自閉スペクトラム症)」「ADHD(注意欠如・多動症)」の2つの発達障がいで表れる傾向があります。
この項目では、ASDとADHDの2つを取り上げて、発達障がいの方の表情が乏しくなる原因について解説していきます。
ASD(自閉スペクトラム症)の方が無表情・笑わない原因
ASDとは、「対人関係やコミュニケーションの困難さ」「特定の物事に対する強いこだわりや興味を持つ」という特性が表れやすい発達障がいです。以前は「自閉症」「アスペルガー症候群」などと呼ばれていましたが、現在は「ASD(自閉スペクトラム症)」という診断名にまとめられています。
ASDは人によって軽度から重度まで特性の程度に大きな差があり、さまざまな性質が表れる障がいですが、無表情・笑わないことが多い傾向はある程度共通しています。
次の項目では、ASDの方がなぜ無表情・笑わないのか、その原因について見ていきましょう。
自分の感情を認識したり自覚したりすることが難しい
ASDの方には、自分が抱えている感情を自覚したり理解したりすることに困難を抱えている場合があります。そのため、内面にある喜怒哀楽を言語化したり表情に出したりすることが難しく、実際の感情と表情や態度の間にギャップが生じやすいのです。
このような状態は「アレキシサイミア(失感情症)」とも呼ばれています。「失感情症」と訳されますが、感情が無いというわけではなく、自分の感情に気づきづらく、感情の言語化が難しい状態です。感情をうまく表現できないためにストレスを蓄積しやすく、身体症状が表れることもあります。
ASDの方が全員アレキシサイミアというわけではありませんが、ASDの方はアレキシサイミアの特性を持ちやすく、
- 「面白いのに笑えない」「悲しいのに泣けない」などの場面が多い
- 「なぜ笑っているのか?」「なぜ泣いているのか?」などの感情を理解できない
- 「〇〇についてどう思う?」などの質問に対して「普通」「分からない」と答えてしまう
- 自分の感情に気づかないため、他者に対する感情にも気づきづらく、他者に対する共感も苦手
などの状況に直面することが多くなります。
一方で、ASDの方に感情の変化自体がないわけではないため、自分の感情を適切に伝えられないことにストレスを抱えたり孤立感を覚えたりすることがあります。
非言語コミュニケーションが苦手
ASDの代表的な特性として、非言語コミュニケーションの苦手さがあります。これにより、ASDの方は相手の表情や視線から感情を察することが難しいと同時に、自分の感情を表情や視線を用いて伝えることも難しいことが多いです。
通常であれば、非言語コミュニケーションのスキルは幼少期から身近な人の表情を観察したり行動を真似したりすることで、成長と共に無意識的に身につくものです。
一方で、ASDの方は幼少期から、
- 相手の顔を見ることが苦手で、表情や視線を観察する経験が不足しやすい
- 表情や視線がコミュニケーションで重要な役割を持つことを理解しにくい
- 他者への関心が薄く、誰かと一緒に行動したり真似したりする経験が不足しやすい
などの特徴が表れやすく、非言語コミュニケーションのスキルの発達が遅れやすいことが分かっています。
その結果、ASDの方は大人になってから周囲の人と比較して無表情・笑わないという特性が目立ちやすく、それが「社会的スキルの不足」として大きな悩みに繋がるのです。
ADHD(注意欠如・多動症)の方が無表情・笑わない原因
ADHDとは、「注意欠如・多動症」と呼ばれている通り、「不注意」「衝動的な行動」「多動性」という3つの特性が表れやすい発達障害です。
ADHDの代表的な困りごととして「ケアレスミスを繰り返す」「落ち着きがない」などが挙げられますが、「感情のコントロールが苦手」「マルチタスクが苦手」などの特性から無表情・笑わないという性質がある方も珍しくありません。
次の項目では、ADHDの方が無表情・笑わない原因について解説していきます。
感情をコントロールしようと意識しすぎる
ADHDは未解明な部分が多い障がいですが、「感情のコントロール」や「行動の制御」などの機能を持つ脳の前頭葉の異常によって発生する障がいだと考えられています。そのため、ADHDの方は些細な出来事でも喜怒哀楽の感情が急激に湧き上がることがあります。
その結果、
- 強すぎる感情をどのように処理して表現すればいいのかわからない
- 自分と周囲の人の感情の違いから、理解されないと感じて感情表現を避ける
- 感情をコントロールすることへの疲れやストレスが蓄積してしまう
などの状況に直面して、表情が乏しくなりやすいのです。
また、「感情的になりすぎて人間関係のトラブルを起こしてしまった」などの経験を持つADHDの方は、過去の失敗から学習して意識的に感情表現を抑え込むことが習慣化します。つまり、自分の感情を過度に意識してコントロールをしようとすることが、無表情・笑わないという特性に結びつくのです。
会話中に意識的に表情を作ることが難しい
ADHDの代表的な特性として、集中力をコントロールしたり複数の物事に注意を向けたりすることへの苦手さがあり、マルチタスクにおいて困難が発生しやすい傾向があります。これにより、ADHDの方は会話に集中している時ほど自分の表情に注意を向けることが難しくなったり、表情を作るべきタイミングを見失ったりしやすいのです。
そのため、ADHDの方は、下記のような特徴が見られることがあります。
- 会話の内容や場面の空気を把握しながら表情を作ることができない
- 話題の切り替わりに応じて適切に表情を変化させることができない
- 会話中に、相手の話に合わせて相槌を打ったり頷いたりできない
- 表情の作ることを意識しすぎて、会話の内容を聞き逃してしまう
会話にはADHDの方が苦手とするマルチタスクの要素が含まれているため、「会話の内容や場面・状況を把握しながら、意識的に表情を作ること」が難しく、無表情・笑わないという特性が表れやすいのです。
感情表現だけでなく、人との適切な距離感がわからない、という方は下記の記事がオススメです。
表情が乏しいとどうなる?3つの大きなデメリット
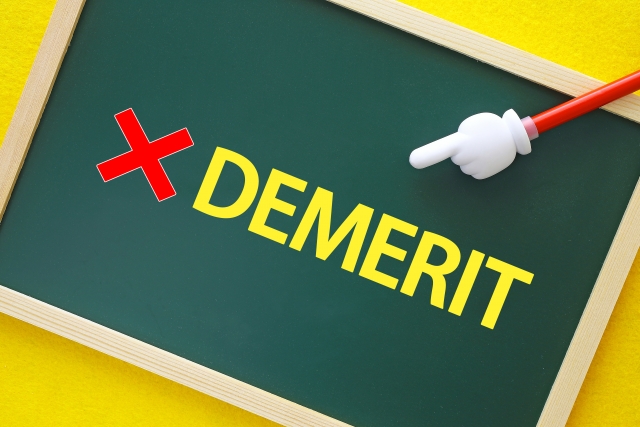
テレビCMや広告、街頭ポスターなどにさまざまな表情を浮かべた人物が映し出されている通り、表情にはコミュニケーションを円滑にして相手に感情や話の意図を伝える効果があります。
対人関係が重視される社会生活の中では、「相手との信頼関係の構築」において、表情は重要な役割を持っているでしょう。
もっとも、無表情・笑わない原因には発達障がいの特性以外にも、その人の性格や考え方などのさまざまな要因が影響しているため、表情が乏しいのは悪いことではありません。ですが、表情が乏しいことを悩みとして抱えている方にとって、無表情・笑えないとどのようなデメリットが発生するのかを理解するのは大切なことです。
この項目では、無表情・笑わないデメリットについて解説していきます。
相手に誤解されやすい
私たち人間は他者の表情から共感や関心を受け取ることが多いため、無表情・笑わない人は周囲から「冷たい人」「愛想が悪い人」と誤解されやすくなります。特に、初対面の相手に対して表情が与える影響は大きく、笑顔や柔らかい表情を作れなければ「距離を置きたい人」「話しにくそうな人」といったネガティブな印象を与えてしまうのです。
また、会話中に適切な表情を作れなければ、
- 「自分の話に無関心なのかな?」という印象を相手に与えてしまう
- 「不機嫌なのかな?」「嫌いな話題なのかな?」と相手に必要以上の気遣いをさせてしまう
- あなたの話す内容が「つまらない」「熱意が足りない」と思われてしまう
などの誤解を生んでしまう可能性があります。
その結果、「周囲から孤立してしまう」「仕事で適切な評価を受けられない」などの問題が発生しやすくなるのです。
感情労働に苦手意識を抱えやすい
感情労働とは、接客・顧客対応やクレーム対応などが伴う職種全般を指す言葉です。対人コミュニケーションが発生する業種のほとんどは感情労働に該当するとされています。ビジネスにおいては「対応の丁寧さ」が重要な評価基準とされることが多く、機械やAI技術では代替が難しい感情労働は非常に価値が高い仕事です。
ですが、無表情・笑わない人は「信頼・熱意・誠意」などが相手に伝わりづらいため、感情労働に対して苦手意識を抱えやすくなります。
実際に、感情労働において表情が乏しいことで発生したトラブルとして、
- クレーム対応時に誠意が伝わらず、相手を余計に怒らせてしまった
- 信頼や熱意が伝わらず、新規顧客を獲得できずに業績が伸び悩んでしまった
- 顧客の満足度が低下して、リピーターを獲得できずに業績が悪化してしまった
などの事例が挙げられています。
このように、無表情・笑わない人は感情労働に苦手意識を抱えやすく、「対人関係のすれ違い」「思うように仕事の成果が出ない」などの悩みからストレスを抱えやすくなるのです。
さまざまな感情を抱え込みやすくなる
感情や思考などの心の状態を顔や身振りに表す「表情」には、感情を発散させる効果があります。笑ったり泣いたりすることにはリラックス効果があるほか、怒りを感じた時に眉をひそめたり溜息をついたりすると気持ちを落ち着かせることができるのです。
しかし、無表情・笑わない人は表情を使った感情の発散が難しくなります。また、表情が乏しければその人の感情や状況に周囲が気付けないだけでなく、その人自身も自分の感情や状況を自覚しにくくなります。
そのため、無表情・笑わない人は、
- 表情がもたらすリラックス効果を得にくくなる
- あらゆる感情を我慢の限界まで抱え込んでしまう
- 悩みや辛さを周囲に言い出せず、助けを求められない
などの問題に直面しやすくなります。
日常的に感情を発散できていなければメンタルヘルスに異常が起こりやすく、ある日突然に限界を迎えた感情があふれ出して、情緒が不安定な状態になることもあるのです。
発達障がいで表情を作れない時の対処法

あなた自身が無表情・笑わない性質を自覚できていても、それが発達障がいの特性によるものであれば意識的に表情を作るのは難しいかもしれません。周囲の指摘やあなたの自覚・意識だけでは簡単に改善できない点に、発達障害が「障がい」とされている理由があるからです。
一方で、発達障がいであっても小さな工夫やトレーニングの積み重ねによって、少しずつ自然な表情を作れるようになっていきます。
この項目では、表情の乏しさを改善するために効果的な対処法を見ていきましょう。
小さなリアクションを意識しよう
コミュニケーションを行う時に無表情であっても、下記のような小さなリアクションを返すことができれば、相手に興味・関心を示したり自分の感情を伝えたりすることが可能です。
- 「はい」「そうですね」などの短い言葉で相槌を打つ
- 軽くうなずく動作を取り入れる
- 会話の中で数秒間だけ相手の目を見つめるタイミングを作る
など
また、無表情であっても口角を少し上げるだけで親しみやすい印象を与えられます。時折、鏡の前で口角を上げる練習をして会話中に実践するだけでも、コミュニケーションを円滑に進められるようになるでしょう。
小さなリアクションの積み重ねは表情筋のトレーニングや感情表現の練習になるため、少しずつ自然な表情を作るための土台が形成されていきます。表情の乏しさを改善するためには、無理に表情を作ろうとするのではなく、あなたのペースで小さなリアクションを意識することが大切です。
感情を言葉で表現する「アサーティブ」コミュニケーションを意識しよう
アサーティブとは、相手の気持ちや立場に配慮しながら自分の感情や意見を率直に伝えるコミュニケーションスキルのことです。アサーティブでは感情を言葉で表現することが大切とされており、これは発達障害の方の表情の乏しさを補う有効な方法の1つでもあります。
もっとも、最初はアサーティブを複雑に考えるのではなく、下記のようなシンプルな言葉で感情を表現できると良いでしょう。
- 「そうですよね」「その気持ち、よくわかります」などの共感を示す言葉
- 「面白そうですね」「ワクワクします」などの楽しさを伝える言葉
- 「大丈夫でしょうか?」「心配です」などの不安を伝える言葉
- 「納得できません」「困ります」などの不満を伝える言葉
など
感情を言葉で表現する習慣が身に付いていくと、自分が抱えている感情を正しく自覚できるようになっていきます。自分の感情を理解して言葉で相手と共有することは、自然な表情を引き出すきっかけにもなるのです。
医療機関や就労支援機関などで「SST」を受ける
「SST」とは「ソーシャルスキルトレーニング」の略称であり、社会的スキルを身につけて人間関係やコミュニケーションの困難を改善するために実施される訓練のことです。
大人の発達障がいの方に向けたSSTは「精神科・心療内科」などの医療機関で受けられるほか、「地域若者サポートステーション」や「障害者就労・生活支援センター」、「就労移行支援事業所」などの就労支援機関で実施されている場合があります。
SSTでは、先述したアサーティブの実践訓練のほか、下記のような訓練が実施されています。
- 決められたテーマに対して意見を出し合うディスカッション
- 複数人で工作や料理などを行う共同行動
- 生活や仕事などの特定の場面を想定し、どのように対処するかを考えるロールプレイ
など
そのため、SSTを受けることで表情の乏しさの改善が見込めるほか、発達障がいの特性に起因する対人関係やコミュニケーションの困難さについても軽減できる可能性があります。
特に、「就労移行支援事業所」は「atGPジョブトレ 発達障害コース」のように発達障がいに特化した事業所もあり、よりあなたの抱える悩みにアプローチしたトレーニングを受けることができるのでおすすめです。
大人のSST(ソーシャルスキルトレーニング)については、下記の記事でも解説しています。
まとめ|発達障がいの方の表情が乏しい理由と対処
- 無表情・笑わないという特性は、「ASD(自閉スペクトラム症)」「ADHD(注意欠如・多動症)」の2つの発達障がいに表れる傾向がある。
- ASDの方は、「自分感情を自覚することが難しい」「非言語コミュニケーションの苦手さ」などの特性から、表情が乏しくなりやすい。
- ADHDの方は、「意識的に感情をコントロールしようとしすぎる」「会話の内容や場面に合わせて意識的に表情を作ることが難しい」などの特性から、表情が乏しくなりやすい。
- 表情が乏しい人は、「相手に誤解されやすい」「感情労働に苦手意識を抱えやすい」「さまざまな感情を限界まで溜め込んでしまう」などの問題に直面しやすくなる。
- コミュニケーションの中で、相槌を打ったり軽くうなずいたりなどの小さなリアクションを返すことができれば、表情の乏しさを補うと同時に自然な表情を作るための訓練にもなる。
- 自分の感情を言語化する「アサーティブ」の実践や、「SST(ソーシャルスキルトレーニング)」によって、表情の乏しさを改善させることが可能。
今回の記事では、発達障がいの方が無表情・笑わない原因を中心に、表情が乏しいことで発生する問題やその対処法について紹介しました。
発達障がいの方にとって、自身が抱えている感情の処理や表情の作り方に課題を抱えてしまうケースは珍しくありません。無表情・笑わないことは決して悪いことではありませんが、表情が対人関係やコミュニケーションに与える効果を理解して、無理のない範囲で対処法を実践することも大切です。
あなたがあなたらしい表情を見せられる日が来ることを祈っています。