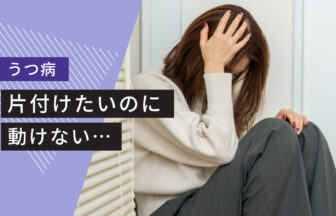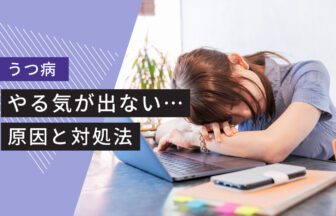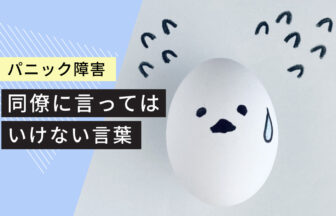「異性に距離が近いと言われて、嫌な顔をされてしまった」
などの経験はありませんか?
大人の発達障がいの方の中には、人との適切な距離感がわからずに困っている方がいらっしゃいますよね。
ここでいう距離感とは、物理的な距離と心理的な距離の両方を指しますが、人に不快感を与えない距離感は曖昧で理解しにくいため、戸惑ってしまいますよね。
人との距離感に苦労しているあなたに向けて
- 人との距離感がわかりにくい2つの発達障害
- 人との距離感がわからないと起こり得るトラブル
- 大人の発達障がいでも人との適切な距離感をつかむ方法
について解説します。
人が不快に思わない距離感を学び、良好な人間関係を築くための参考にしていただければ幸いです。
人との距離感がわかりにくい2つの発達障がい

職場やプライベートで関わる人との適切な距離感がわからないのは、発達障がいが原因の可能性があります。
人との適切な距離感がわかりにくい発達障がいとしては、
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 注意欠如・多動症(ADHD)
こちらの2つが挙げられます。
発達障がいを持っている方は、人間関係や対人コミュニケーションを苦手とする傾向があります。この傾向が、人との適切な距離感をわからなくさせてしまう状態に繋がっているかもしれません。
そのため、相手を不快にさせてしまうことが多かったり仕事に支障が出たりしている場合には、発達障がいの可能性が高くなるでしょう。
次の項目では、「ASD」や「ADHD」だと、なぜ人との距離感がわかりにくくなるのか、詳しく解説していきます。
自閉スペクトラム症(ASD)
ASDの方は、
- 表情やジェスチャー、声のトーンから相手の気持ちを理解することが苦手
- 冗談や曖昧表現を理解するのが苦手
- 相手の様子を伺わずに一方的に話し続けてしまう
などの性質が表れやすいです。
その結果、
- 相手の嫌がっている表情や社交辞令がわからずに近づいてしまう
- 「自分のことをわかってくれる」と感じた人には出会ったばかりでも馴れ馴れしく接してしまう
などが起こりやすくなります。
ASDの方に見られやすい「共感能力が低さ」が、人との適切な距離感をわかりにくくしていると考えられます。
注意欠如・多動症(ADHD)
ADHDの特性の1つに「衝動性」があります。衝動性とは、思いついたことや外部の刺激に対して衝動的に行動、反応してしまう特性です。
ADHDの方は衝動性が原因で、
- 思いついた言葉をすぐに口に出してしまい相手を傷つけてしまう
- 適切な段階を踏まずにプライベートな質問をしてしまう
- 会話のタイミングを掴むことや空気を読んで発言することが苦手
などの性質が表れやすいです。
その結果、ADHDの方は興味のある相手に衝動的に話しかけてしまい、一方的にコミュニケーションを取ってしまうことがあります。
初対面の相手なのにも関わらず、プライベートについての質問をしてしまうことから、いきなり距離感を詰めすぎて相手を困らせたり馴れ馴れしい印象を持たれたりすることに繋がるのです。
人との距離感がわからないと起こりうるトラブル

コミュニケーションにおいて人と適切な距離感がわからないと、相手を不快に思わせてしまったり、トラブルの原因になったりしますよね。
具体的には、
- 社外の方に対して馴れ馴れしい言葉遣いをしてしまい、相手を怒らせてしまう
- 信頼関係を築いていないのにも関わらずボディータッチをしてしまい、相手に不快な思いをさせてしまう
- 悪気なく相手のコンプレックスを指摘してトラブルに発展してしまう
などがあります。
人との距離感を間違えると会社に迷惑がかかるだけではなく、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどの犯罪につながることもあります。
相手に誤解を与えてトラブルに発展しないためにも、対処法をしっかりと確認しましょう。
大人の発達障がいでも人と適切な距離感をつかむ方法6選

ここでは大人の発達障がいの方でも人と適切な距離感をつかむための方法をご紹介します。
- 対人距離は1.2m〜3.5mを基準にする
- 敬語を使う
- プライベートな話題を質問しない
- 相手の外見についての話をしない
- 専門家や相談窓口に相談する
- 就労移行支援事業所「atGPジョブトレ 発達障害コース」を利用する
順番に見ていきましょう。
対人距離は1.2m~3.5mを基準にする
対人距離とは、他人が接近してきた時に不快と感じてしまう空間のことで、パーソナルエリア、パーソナルスペースとも呼ばれています。 対人距離は人間関係や場面によって変化しますが、多くの方は相手との物理的な距離感を保ちながらコミュニケーションを取っています。
具体的な距離感は、アメリカの文化人類学者エドワード・ホールの研究である「対人距離の分類」を参考にしてみてください。
| 対人距離の分類 | |
|---|---|
| 密接距離:0~45cm |
|
| 個体距離:45cm~1.2m |
|
| 社会距離:1.2m~3.5m |
|
| 公衆距離:3.5m以上 |
|
この表から分かるように、職場の方や関係が深くない方と会話をする場合は、1.2m〜3.5mの範囲を基準にすると良いです。
一定の距離感を保つことで、相手は安心した状態であなたと会話することができるでしょう。
ただ、業務の中では
- 名刺交換をする
- お茶を出す
- 上司や同僚に相談する
など、相手との距離が近くなる場合もあるでしょう。
その際は、「失礼いたします」や「今、お時間はよろしいでしょうか?」など、相手に一言伝えると良いですね。
急に相手に近づくと、相手を驚かせてしまったり不快に思わせてしまったりする原因になります。一言だけでも前置きを挟むことで相手は話す準備ができ、あなたと安心してコミュニケーションが取れるでしょう。
敬語を使う
職場の方や関係が深くない方との会話は、敬語で話しましょう。敬語は相手に敬意を示す言葉である一方、相手と心理的な距離を取るために使われる言葉でもあります。
上司や社外の方にはもちろんのこと、同僚や関係が深くない方との会話も敬語を基本にすると良いですね。
敬語を使うことで、馴れ馴れしい言葉遣いが原因で相手を怒らせてしまうことは減るでしょう。
プライベートな質問をしない
相手とトラブルにならないために、初対面の方と話すときはプライベートな質問をしないことも大切です。
具体的には、
- 休みの過ごし方や趣味などの行動について
- 家族のことや恋人の有無
などのプライベートな話題は、人間関係を深めるために必要なときもありますが、人によっては個人的な話をしたくない方もいらっしゃいます。
相手と親しくなるまでは、プライベートな話題は相手に質問された時に返答する程度が丁度良いでしょう。
相手の外見についての話をしない
相手とトラブルにならないためにも、
- 相手の髪型や顔などの容姿
- 相手の服装
など、外見について話題は避けるのが無難です。
自分の外見に何らかの悩みを抱えている方は8割を超えていることが分かっているため、多くの方にとって外見の話題はセンシティブなテーマです。
相手を褒めるつもりで言った言葉でも、相手がコンプレックスに感じている場合は相手を傷つけたり、不快に思わせたりしてしまいます。
専門家や相談窓口に相談する
あなたが人との適切な距離感がわからずに困っていたり、仕事に支障が出たりしているならば、専門家や相談窓口に相談することも大切です。
専門家や相談窓口に相談することで、あなたが抱えている生きづらさが軽減される可能性があります。
具体的には、
- 「精神科」や「心療内科」の医師
- 障がい者就業・生活支援センター、発達障害者支援センター
などの専門家や相談窓口に相談してみてください。
発達障がいの特性についての相談
発達障害の特性については、「精神科」や「心療内科」の医師に相談してみましょう。発達障がいの検査や診断を通して、医師があなたの特性・性質を判断してもらえます。
あなたに適した治療を受けることで今の状態が改善されたり、ストレスが軽減されたりするでしょう。
発達障がいについての相談窓口
障がい者就業・生活支援センターや発達障害者支援センターは、発達障がいのある方を総合的に支援してくれる専門機関です。
日常生活や仕事、人間関係などの困りごとの相談に応じています。
専門機関で適切なサポートを受けることで、生きづらさを軽減できるでしょう。
障がい者就業・生活支援センターについては、下記に詳しい情報があります。
発達障害者支援センターについては、下記の記事で紹介しています。
就労移行支援を利用する
就労移行支援は、障がいを抱えた方が就職を目指し、社会参加への準備を整えるための公的サポートです。生活習慣の改善、コミュニケーション訓練、職業スキル習得など、個々の課題に合わせた支援を特徴としています。
障害者手帳がないと利用できないと思われがちですが、なくても精神科医の診断書等があれば利用可能です。以下でおすすめをご紹介しますので、気になる方は確認してみましょう。
ミラトレ
ミラトレは、実際の企業が求めるスキルや人物像を意識した実践的な訓練に強みがある就労移行支援事業所です。発達障害で人との距離感がわからないという方も、模擬職場やインターンシップを通じて少しずつその感覚を養うことができます。
ビジネスマナーや専門スキルを習得し、就職活動を有利に進めるためのサポートが充実しており、多くの卒業生が希望の職場で活躍しています。
NeuroDive
NeuroDiveは、IT・Web分野に特化したカリキュラムで、専門スキルを身につけたい方に最適の就労移行支援事業所です。人との距離感がわからないという方でも比較的負担感の少ない仕事である、プログラミングやデザインなどの技術を基礎から学べます。
発達障害で、特定の分野への高い集中力を持つ方に向いている事業所です。スタッフも専門知識を持つ方が多く在籍しています。
atGPジョブトレ 発達障害コース
atGPジョブトレ 発達障害者コースは、発達障害のある方に特化した就労移行支援事業所です。
疑似職場においてビジネスコミュニケーションに注力したトレーニングを行っており、仕事における人との適切な距離感を学ぶことができます。
発達障がいを専門としており、ノウハウが豊富な点が魅力的です。
まとめ|発達障がいと人との距離感の取り方
- 人との適切な距離感がわからないことが原因で仕事に支障が出たり、相手を不快にさせてしまったりする場合は、発達障がいの可能性がある。
- 自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)の「人間関係」や「対人コミュニケーション」の苦手さが、人との適切な距離感がわからないという特性を助長させている可能性がある。
- 人との適切な距離感がつかめないと会社や異性との間でトラブルが起きることもあるため、対処法を学ぶことが大切。
- 人との適切な距離感をつかむためには、対人距離は1.2m〜3.5mを基準にする、敬語を使う、プライベートな質問をしない、相手の外見についての話をしない、専門家に相談する、などの方法が効果的。
人との適切な距離感はわかりにくいかもしれませんが、対処法を実践して職場やプライベートで良好な人間関係を築いていきましょう。
この記事が、あなたの生きづらさを減らすための一助になれば幸いです。![]()