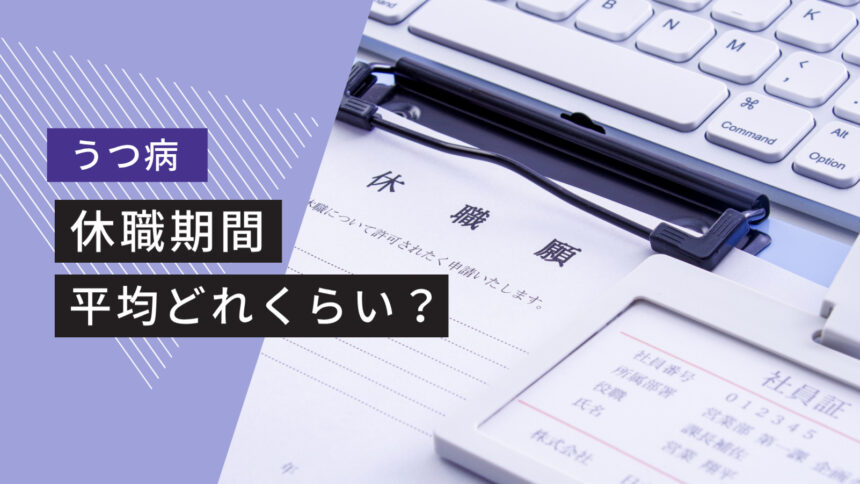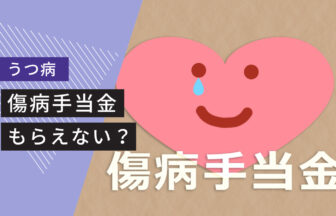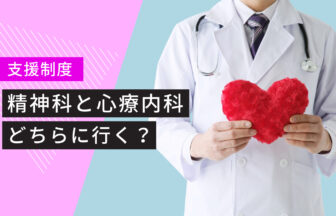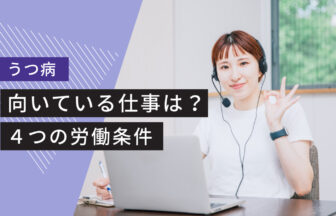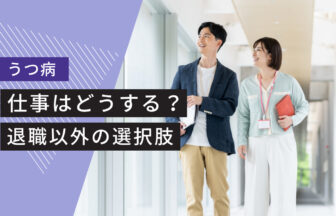この記事にたどり着いたあなたは、
「休職している間の給料やボーナスってあるのかな…」
「休職中はどう過ごせばいいのかな…」
という疑問を抱えてモヤモヤしていませんか?
うつ病の治療には休息期間が必要です。仕事をしている方は、治療のために休職を選ぶことも多いかと思います。しかし、いざ休むと決めても不安がなくなるわけではありません。
不安はうつ病の治療を妨げることがあります。できれば解消しておきたいですよね。
- うつ病による休職の平均期間や、休職期間を決める要素
- 休職中の給料や手当、過ごし方など
- 休職するときに利用できる支援制度
について解説します。
回復のお役に立てれば幸いです。
うつ病の休職期間は平均どのくらい?

うつ病の休職期間は平均だとどのくらいなのでしょうか?
厚生労働省が発表したデータを元に、実際の平均的な期間について見ていきます。
うつ病の平均的な休職期間
うつ病の休職期間の平均は、休職した回数によって異なります。
厚生労働省の調査で出た結果は下記の通りです。
| 1回目 | 107日(約3.5か月) |
|---|---|
| 2回目 | 157日(約5か月) |
平均病休日数について」
| 1回目 | 107日(約3.5か月) |
|---|---|
| 2回目 | 157日(約5か月) |
詳細は後述しますが、休職期間は会社ごとに上限が決まっているため、会社によっては平均より休職できない可能性があります。念のため必ずあなたの会社の就業規則を確認してください。
また、個人の症状や治療の進行状況によって休職期間は異なります。あくまで目安として参考にしてください。
2回目の休職が長くなる理由とは?
うつ病による休職は、1回目の休職より、2回目の再休職のほうが長くなる傾向にあります。
その理由は下記のように考えられます。
- 1回目の休職では治療が不十分で、復職後にうつ病が再発する
- 復職後、職場環境やストレスの原因が改善されず、同じ原因でうつ病が悪化する など
このような理由により、1回目より休職期間が長くなることがあります。
また、復職後に再休職する確率は1年以内で28%、5年以内で約47%となっており、うつ病による休職は非常に再休職率が高いといえます。
うつ病の休職期間を決める2つの要素とは?

うつ病の休職期間は会社が判断します。
会社によって基準は異なりますが、休職期間を判断する要素は下記の2つです。
- 就業規則の規定
- 診断書に記載されている療養期間
順番に見ていきましょう。
就業規則の規定
就業規則とは、労働者の賃金、労働時間などの労働条件や、職場内の規律について一律に定めた規則です。
多くの会社は、職期間や条件など、休職に関する規定をあらかじめ就業規則に定めています。また、休職制度の最長期間の上限を設ける企業も存在します。
障がい者職業総合センターが行った調査によると、休職期間の上限として、6か月以上~2年以下の範囲が多い結果でした。企業によってばらつきはあるものの、傷病手当金の最長支給期間である1年6か月を意識して定めているところが多いようです。
診断書に記載されている療養期間
診断書とは、主治医が医師法に基づいて発行する公的な証明書で、病名や症状、必要に応じて治療期間などが記載されています。
うつ病の診断は専門医にしかできません。そのため多くの会社では、うつ病であることの証明や、病状の把握、病院での治療を促すために、休職する上で診断書の提出を必要としています。
なかでも会社側は症状の程度から「復帰までにどれくらいかかるのか」を重要視しているので、主治医から診断書をもらうときは、うつ病の療養期間(休職期間)も記載してもらうようにしましょう。
うつ病の方の復職は、軽症の場合は1か月程度で済むこともありますが、症状が重い場合は1年以上かかることもあります。会社の就業規則であらかじめ休職期間が定められている場合でも、主治医の診断書に基づく休職期間が優先されることがあります。また、企業の人事部や労務担当者と相談して、適切な休職期間を決めることもあります。
うつ病で休職するための3つのステップ
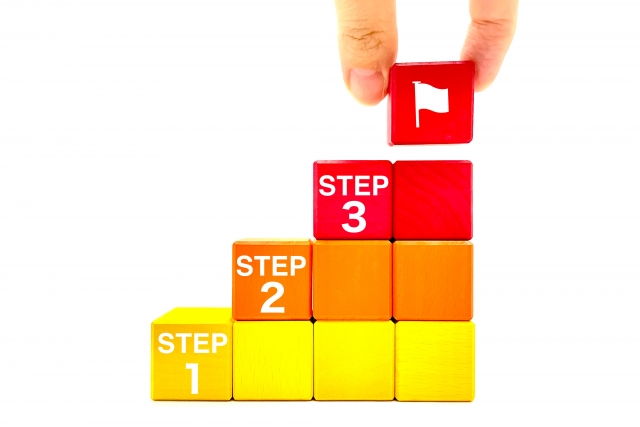
いざうつ病で休職するとなると、手続きの仕方に不安がある方もいらっしゃるでしょう。
この項目では、大きく3つに分けて休職への入り方を解説していきます。
- 就業規則を確認する
- 医師の診断を受ける
- 会社で求職の手続きを行う
➀ 就業規則を確認する
前述した通り、うつ病で休職する場合、就業規則の確認はとても重要です。
労働基準法により、常時10人以上の労働者を雇用する企業(事業場)は就業規則の作成と周知徹底の義務があります。
労働基準法施行規則|e-GOV 法令検索
そのため、労働者(従業員)は雇用形態にかかわらず、下記の形で就業規則を閲覧することができます。
- 事業場の見やすい場所に掲示、または備え付けられたもの
- 交付された書面
- 常時確認できるよう共有されたデジタルデータ
就業規則に休職制度の規定があるか、休職期間の上限はどのくらいかを確認し、条件や必要なものを最初に確認しましょう。
➁ 医師の診断を受ける
繰り返しになりますが、うつ病で休職するには、精神科や心療内科などの専門の医療機関を受診して、医師から診断書を発行してもらう必要があります。
受診時にスムーズに話せるか不安な方は、
- 事前に話す内容をメモに書き出す
- 家族に付き添って受診する
などを試してみると良いでしょう。
「直接病院に行くことに抵抗がある」「どの病院に行けばいいかわからない」という方は、
- 勤務先の産業医
- お住まいの地域の精神保健福祉センター、または保健所
上記へ相談しておきましょう。状態や困りごとに応じた適切な支援が受けられます。
自身の症状や仕事の状況、ストレスの要因に関わることなど、しっかりと主治医と話し合い、正確な診断書を書いてもらうようにしましょう。
下記の記事では、精神科と心療内科の違いを解説しています。どの病院に行くか迷った時の参考になるでしょう。
➂ 会社で求職の手続きを行う
医療機関でうつ病の診断書を受け取ったら、診断書とともに会社や上司へ相談しましょう。このとき、会社によっては、体調を考慮して電話やメールなどで休職の申請ができることがあります。
また、通常は上司の了解を得た後に人事担当者と休職の手続きを進めますが、もしうつ病の原因が上司にある場合は、直接人事担当者とやり取りさせてもらえる場合もあります。
休職する上で必要な手続きは会社によって異なりますが、主に3つの取り決めがあります。
- 休職願の提出
- 休職中の会社との連絡手段
- 社会保険料の徴収について
順番に解説していきます。
休職願の提出
休職願(休職届)は、休職する際に会社に提出する重要な書類です。一般的には下記の内容を記載します。
- 休職期間
- 休職理由
- 休職中の連絡先
勤めている会社から休職願の用紙を受け取り、必要事項を記入して提出しましょう。休職が正式に決定したら、多くの場合、会社から休職通知書が発行されます。
休職期間中の会社との連絡手段
休職期間中の会社との連絡手段を確認しましょう。就業規則に明記されていることが多いですが、一般的にはメールによる連絡が多く、週に1回程度の頻度で行われます。
これらの連絡は、
- 休職者の状況を会社が確認するため
- 社会的孤立を防ぐため
- 復職をしやすくするため
に行われます。
会社によっては、家族が代理で連絡することも可能です。
社会保険料の徴収について
休職期間中であっても被保険者であるため、社会保険料の支払いは必要です。休職と給与については次の項目で詳しく説明しますが、多くの場合は傷病手当金を主な収入として生活していきます。そのため、通常は給与から控除されている社会保険料の支払い方法を事前に決める必要があります。
休職中の社会保険料を支払う方法として、主に下記の方法があります。
- 会社から送られてくる保険料の請求書に従い、指定された口座に振り込む
- 会社が一旦傷病手当金を受け取り、そこから保険料を控除した上で従業員に支給する
- 会社が保険料を一時的に立て替え、復職後に従業員が会社に支払う
会社の就業規則に保険料の徴収方法が明記されている場合は、それに従いながら手続きを進めましょう。
休職中に給与はもらえる?

休職するうえで経済的な不安が強い方もいるかもしれません。
この項目では、
- 休職中の給与
- 傷病手当金
を順番に紹介していきます。
休職中の給与について
休職期間中の給与については、会社からの給与は支払われないことが主流です。これは、労働基準法や民法に基づく「ノーワーク・ノーペイの原則※」によるもので、労働者が労務を提供しない場合、会社には賃金を支払う義務がないからです。
休職期間中に貰うことができるのは、主に傷病手当金による給付となっております。
また、賞与(ボーナス)についても、休職中の支給を行わない会社が約7割を占めており、通常通りの賞与が支給されることはあまり期待できません。
民法には下記の規定があります。
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。民法第624条|e-GOV法令検索
「労働者が使用者と約束した労働の内容を提供しなければ、報酬をもらう権利が発生しない」という意味です。
つまり、「労働をしなければ、給与の支払いがない」ということ。
これを「ノーワーク・ノーペイの原則」と呼びます。
傷病手当金を利用する
傷病手当金とは、社会保険や被保険者が病気やケガで休養する際に、一定の要件を満たした場合に受け取れる給付金で、多くの場合、休職期間中は傷病手当金を受け取りながら生活することになります。
支給額は直近12か月の平均収入の3分の2(約67%)で、支給開始日から通算で1年6か月間受け取ることができます。
全国健康保険協会のホームページに記載されている支給条件は下記の4つです。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金の詳細は、全国健康保険協会のホームページで詳細を確認することができます。
加入している健康保険によっては書類の書式が異なるので、詳細は会社や健康保険の組織に確認しましょう。
【休職期間中の過ごし方】3つの期間に分けて解説

ここまで休職に入る前のことについて解説してきましたが、いざ休職に入り生活がガラッと変わると、何もすることがなく不安を感じてしまうかもしれません。
この項目では、休職期間中の過ごし方について、
- 急性期
- 回復期
- 再発予防期(復職準備期)
に分けて解説していきます。
急性期
急性期に入ったばかりはうつ病の症状が強く、
- 眠れない
- 考え事が止まらない
- 何もやる気が出ない
などの精神症状が出やすいとされています。
仕事をしていないことに罪の意識を感じ、自分を責めたり、早く回復するよう焦ったりするかもしれません。しかし、急性期は休養期とも呼ばれており、落ち着いて心と体を休ませることが大切です。
眠りたいときに眠り、1日中横になってダラダラするのも良いでしょう。無理に外に出たり仕事のことを考えたりする必要はないので、服薬を続けながらのんびりと休息をとりましょう。
この時期は特に、家族や職場からの理解とサポートが欠かせません。自身が十分な休養をとれるよう、家族には日常生活のサポートをお願いしましょう。
注意点として、うつ病の症状が強いときは判断力が鈍ることがあるため、大きな決断は少し待ったほうがいいかもしれません。
例えば、大金を使ったり、退職を決めたりすることは、その時は真剣に考えているつもりでも、後悔する可能性があります。
回復期
休養や服薬によりうつ症状が回復してくると、自然に活動する気力が湧いてきます。大切なのは、焦りや責任感で行動しないことです。
気持ちが軽くなり始めたら、
「少しだけ散歩してみる」
といったことに、少しずつ挑戦してみましょう。
すぐに体力や集中力が戻るわけではないので、「今日はここまで出来た」と自分を褒めながら無理のないペースで生活リズムを整えていきましょう。
再発予防期
回復期を終えて体力や気持ちの回復が進んだら、復職への準備を徐々に始めていきます。このとき、症状が治まっても、医師の指示に従いながら服薬を続けましょう。急に服薬を止めると強い離脱作用や症状の再発を招く可能性があります。
復職については、主治医・会社の両方と相談しながら進めていきます。
障害者職業総合センターの「職場復帰支援の実態等に関する調査研究」によると、「休職制度を設けている」と回答した会社のうち、約97%の会社が「復職判断には条件がある」と回答しています。
具体的には、
- 復職の意思がある
- 生活リズムが整っており、1人で安全に通勤ができる
- 所定労働時間の就労が継続して可能
- 主治医から復職可という診断書が出ている
などが挙げられました。
また、多くの会社では、復職直後には短時間勤務や定期的な面談を行うなど、段階的に復職を目指す企業も多いようです。
うつ病で休職する方が利用できる支援制度3選
うつ病の方が利用できる制度には、休職中の給与の項目で紹介した「傷病手当金」以外にも、下記のような支援制度があります。
- 自立支援医療制度
- 障がい年金(障害厚生年金)
- 精神障がい者保健福祉手帳
順番に解説していきます。
自立支援医療制度
自立支援医療制度は、精神科への通院が継続的に必要な方に対し、治療にかかる費用が軽減される制度です。
通常、医療保険適用による医療費の自己負担額は3割ですが、自立支援医療制度を利用すると自己負担額は1割に軽減されます。また、市民税が非課税の場合、世帯収入に応じて1か月あたりの自己負担額に上限が設定されるため、経済的に苦しいほど助かる制度と言えるでしょう。
市町村の障害福祉課や保健福祉課で手続きを行い、申請が認められると「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。
自立支援医療制度については下記の記事でさらに詳しく解説しています。
障がい年金(障がい厚生年金)
障がい年金には大きく分けて2種類あり、国民年金に加入している場合は「障がい基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障がい厚生年金」に申請ができます。
今回のようにうつ病で休職する場合は、会社員として社会保険料を支払っているため、障がい厚生年金が主な対象となります。
障がい厚生年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障がいの程度によって受け取れる年金額が変わります。
詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
障害厚生年金の年金額|障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
障がいの程度は、
- 1級:常時介護が必要
- 2級:随時介護が必要
- 3級:労働制限
のような目安があります。
うつ病で休職する場合、3級の労働制限に該当する可能性があります。障がい年金は申請から支給開始まで4~5か月程度かかるため、休職期間も考慮しつつ、主治医と相談して受給できるか確認してみると良いでしょう。
精神障がい者保健福祉手帳
精神障がい者保健福祉手帳は障害者手帳の1つです。
市町村の担当窓口に必要な書類を提出して申請し、精神障がいの状態を総合的に判断した上で、1級から3級までの等級に分けて交付されます。
さまざまな制度やサービスの利用の利用を目的としており、
- 所得税、住民税、相続税の控除
- 公共料金等の割引
- 福祉手当や通所交通費の助成
- 障がい者雇用枠での応募
などのサービスが受けられます。
注意点として、申請には初診日から6か月以上経過している必要があります。
これは、精神障がいの症状は時間の経過とともに変化することが多いため、6か月の経過観察期間を設けることで、症状が持続的な状態であることを確認するためです。
まとめ|うつ病の休職期間と判断基準
- うつ病の平均的な休職期間は、1回目が107日(約3.5か月)で、2回目が157日(約5か月)。休職期間を決める要素は「会社の就業規則」「主治医の診断書」の2つが大きい。
- うつ病の休職期間は、勤めている会社の就業規則と診断書に記載された療養期間から、会社が判断する。
- うつ病で休職するには、まず就業規則の休職制度を確認し、医師の診断を受けた上で、会社で手続きを行う。
- 休職中、会社から給与を支払われるケースは少ないので、主に傷病手当金を利用して生活する。
- 休職期間中の過ごし方は、うつ病の症状が強い時期は落ち着いてゆっくり休み、症状が回復していき自然に活動する意欲が湧き始めたら、少しずつ復職に向けた準備を進めていく。
- うつ病で休職する方が利用できる支援制度には「傷病手当金」以外にも、「自立支援医療制度」「障害年金」「精神障がい者保健福祉手帳」などがある。
休職期間中は、適切な治療を受けることに加えて、周囲の理解とサポートも不可欠です。主治医だけでなく、家族や職場にもしっかりと相談して、自分の状態や必要なサポートについて共有することも大切にしてください。
心身の回復にとって重要なステップですので、無理をせず、ゆっくりと過ごすことを心がけましょう。