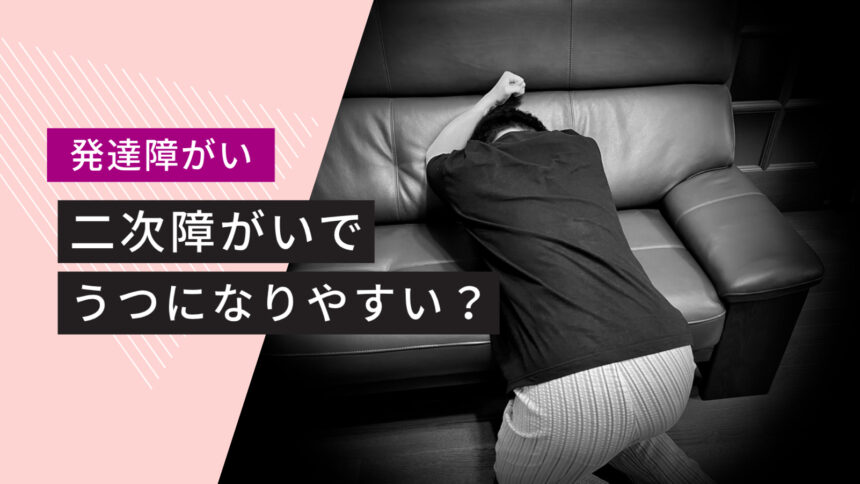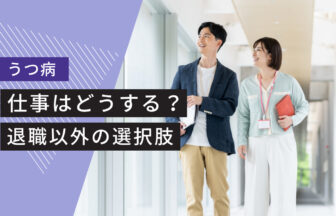「発達障がいと精神障がいを抱えているけど、治せるのかな…」
この記事を読んでいるあなたは、このような疑問はありませんか?
ADHDやASDなどの発達障がいを抱える方が、うつ病や不安障がいなどの精神障がいを併発するケースは珍しくありません。こういった発達障がいが原因となってうつ病などの精神障がいを発症することを「二次障がい」と呼ぶことがあります。
- 発達障がいの二次障がいとは
- 発達障がいだと受けやすいストレス
- 二次障がいの予防や対処法
- 発達障がいのある方が利用できる相談先
について解説していきます。
発達障がいの二次障がいとは?
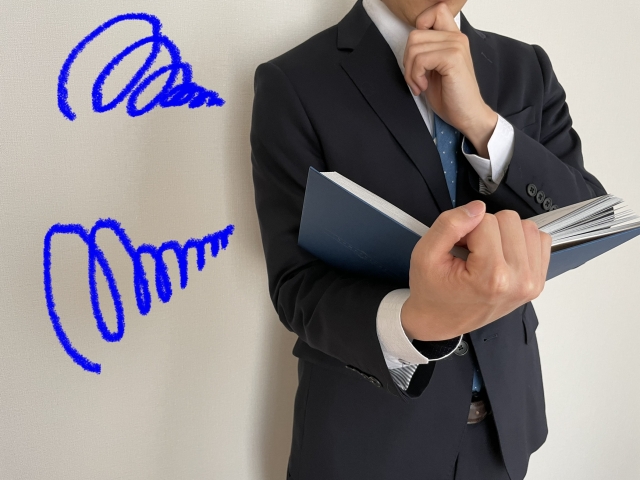
発達障がいとは、何らかの要因により脳機能の発達に偏りが発生することで、仕事や日常生活においてさまざまな困難が出てしまう先天的な障がいの総称です。
しかし、発達障がいは目に見えない障がいであるため、周囲の方から理解されにくかったり、ほかの人と比べて自分の能力が劣って見えたりして自尊心の低下や大きなストレスを抱えることがあります。
このような背景から、発達障がいの方は強いストレスや疲労を感じやすく、精神疾患の併発や精神症状の悪化を招く「二次障がい」と呼ばれる問題に直面しやすくなります。
二次障がいは医学的な専門用語や診断名ではなく、発達障がいの特性が原因で起こりうる精神疾患などのさまざまな問題の総称です。二次障がいを防ぐためには、できるだけ早く発達障がいの特性を把握し、適切な支援を頼ることや生活環境の調整を行うことが大切です。
発達障害ごとの特性とストレス要因

発達障がいは大きく下記の3種類に分けられます。
- 注意欠如・多動症(ADHD)
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 学習障がい(LD)
二次障がいとして考えられる要因は、発達障がいの種類によっても異なります。この項目では、障がいの種類ごとに受けやすいストレスや発生しやすい問題を解説します。
ADHD(注意欠如・多動症)
ADHD(注意欠如・多動症)は、「不注意」「多動性」「衝動性」という3つの特性が表れる発達障がいです。これらの特性はすべて表れる方もあれば、1つまたは2つだけが強く表れることもあります。
仕事においては、下記のような問題が生じることがあります。
- 指示や持ち物をすぐ忘れる
- 注意力のコントロールが難しく、不注意によるミスが多い
- じっとしていられない
- よく考えずに行動してしまう
ADHDの特性による仕事上の問題は、自力での対処が難しいことが多く、そのため「自分の努力不足」と感じてしまい、大きなストレスを抱えることがあります。
ASD(自閉スペクトラム症)
ASD(自閉スペクトラム症)は2013年に統一された診断名で、以前は「広汎性発達障がい」「アスペルガー症候群」などと呼ばれていた発達障がいです。ASDの方は表情や視線、身振り・手振りのような非言語コミュニケーションや、曖昧な表現を理解しづらく、特定の物事に対する強い興味・関心を持ちやすい傾向があります。
仕事においては、下記のような問題が生じることがあります。
- 言葉や文章でのコミュニケーションが難しい
- こだわりが強く、自分のやり方やルールに固執しやすい
- 他人の感情に気づきづらい
自閉スペクトラム症の特性は多岐にわたっており、人とのコミュニケーションが難しく周囲から孤立する方もいれば、人との適切な距離感が掴めず接触しすぎてしまう方もいます。
LD(学習障がい)
LD(学習障がい)は、「読む」「書く」「計算する」など、特定の基礎的な学習能力において困難がある発達障がいです。軽度の場合は自覚することが難しく、適切な支援を受けられない方も多い傾向にあります。
仕事においては、下記のような問題が生じることがあります。
- 書類や指示書などをスムーズに読み書きすることが難しい
- メモを取ることが難しい
- 時間やお金の計算が難しい
また、LDは知的障がいとは異なり、知的発達に遅れがない場合に診断されます。診断が無い状態では、自分の能力に不安を感じたり自尊心の低下を招いたりすることがあります。
発達障がいで発生しやすい2つの二次障がい

発達障がいの二次障がいは大きく分けて「内在化障がい」と「外在化障がい」の2つに分けられます。
この項目では、具体的な症状やどのような問題が起きるのかを解説していきます。
内在化障がい
発達障がいの二次障がいのうち、「イライラや精神的な葛藤」などが自分自身に影響を与えて発生する症状や問題を「内在化障がい」と呼びます。
具体的には、下記のようなものがあります。
- 抑うつ
- 双極性障がい
- 不安障がい
順に解説していきます。
抑うつ(うつ病)
抑うつとは、気分が落ち込み、何もなくても常にストレスを感じ続けたり、集中ができなくなったりするなどの精神症状が表れる状態です。
症状の表れ方は人それぞれで、些細なことで怒りっぽくなる方もいれば、逆に感情の起伏が少なくなり反応が鈍くなる方もいます。また、抑うつ状態が慢性的に続いたり、症状が重いために生活に著しい支障が出たりすると「うつ病」やその他の精神障がいと診断されることがあります。
双極性障がい
双極性障がいは、活動的になる躁状態と、気分が落ち込む抑うつ状態が繰り返される障がいで、「躁うつ病」とも呼ばれます。抑うつ状態ではうつ病と同じような症状が出るものの、躁状態では目に見えて元気にあふれ、気分が高揚して衝動的な行動が目立つようになります。
気分の波は誰にでもあるものですが、双極性障がいの場合は周りから見ても様子や行動が明らかに変化するという特徴があり、気分の落差の大きさから生活に支障が出やすくなることが多いです。
不安障がい
不安障がいは、自分自身でコントロールできないような不安に駆られて、苦痛や恐怖を感じたり、動悸や呼吸困難などが起きたりする精神障がいの総称です。
ここでは代表的な3つの症状を紹介していきます。
- パニック発作(パニック障がい)
パニック発作は、強い恐怖や苦痛が突然発生するものの短時間で治まる発作です。
症状が重い場合は、激しい動悸や呼吸困難(窒息感)、意識障がいなどの身体症状が数分でピークに至ります。
多くの場合30分以内に収まることが多いですが、発症に伴う精神的混乱や恐怖が症状の悪化を加速させることもあります。 - 強迫性障がい
特定の行動をやめられず、日常生活に支障が及ぶことがあります。
具体的には、必要以上に手洗いや戸締り確認をしたり、何かの本数や数字を数えたりしないと強い不安感に襲われるなどがあげられます。 - 限局性恐怖症
不安症の1つで、一般的に「○○恐怖症」のような名称で知られているものです。
動物恐怖症や高所恐怖症、先端恐怖症など、特定のものや状況に対して大きな不安感や恐怖を感じ、ときに非現実的な想像によってパニック発作を引き起こすこともあります。
外在化障がい
発達障がいの二次障がいのうち、「イライラや精神的な葛藤」などが他者や周りの環境に影響を及ぼして発生する行動や問題を「外在化障がい」と呼びます。
具体的には、下記のような行動や問題があります。
- 暴力や暴言
- 家出
- 他社に対する敵意、攻撃性
- 反抗挑戦性障がい
- 行為障がい
- 感情不安定
- 非行などの反社会的行動
外在化障がいは、周囲からの理解を得られなかったり、自分では努力しているのに報われなかったりなどの経験が問題につながりやすいといわれています。また、内在化障がいが外在化障がいを引き起こすこともあり、逆に外在化障がいが内在化障がいを引き起こすこともあります。
二次障がいを防ぐには?3つの対処法

二次障がいは発達障がいによって引き起こされる後天的なもので、適切な対応をすれば予防することができます。
発達障がいがある方のすべてが二次障がいを発症するわけではありませんが、厚生労働省が発表した研究によると、発達障がいを抱える成人のうち約46%がうつ病を経験し、約24%が不安障がいを経験するとされています。
この項目では、二次障がいの治療や予防する方法を解説していきます。
医療機関での治療を行う
発達障がいの二次障がいにより、生活への支障が大きい場合は、医療機関で治療を受けることができます。抑うつや気分の落ち込み、強い不安感が続くなど、不調や異変を感じたら、迷わず精神科や心療内科を受診しましょう。
二次障がいの治療法には、
- 物事の考え方や受け止め方を見直して、ストレスに対応できるようにする「認知行動療法」
- うつ病や不安障がいなどの症状や、発達障がいの困りごとを薬で緩和するための「薬物療法」
- 家族とのコミュニケーションや関係性を見直して、症状や問題の改善を図る「家族療法」
などがあります。
日常生活で心と身体を健康にする
二次障がいを防ぐには、心身の健康を保つことも大切です。発達障がいの特性から、気がつかないうちに疲労がたまっていたり、ストレスが蓄積したりするかもしれません。
健康的な食事や、適度に休むなど、生活習慣の改善を行うことで、二次障がいの予防や症状の緩和につながることがあります。
家族や友達に相談する
1人で抱え込まず、家族や友達などの信頼できる方に頼ることも大切です。特に障がいの特性が関わる問題は、周囲のサポートや合理的配慮が必要になります。
また、発達障がいを抱える方は自己肯定感が低い傾向があり、「周りに迷惑をかけたくない」「みんなが頑張っているから、自分も頑張らないと」と考えて孤立しがちです。
孤立しまうと、うまくいかないことも多いでしょう。困ったときはなるべく早めに誰かに相談しましょう。ほかにも、公的機関や支援機関などで専門家に相談することもできます。
次の項目では、発達障がいの二次障がいについて相談できる支援機関を紹介します。
発達障害の二次障害を相談できる支援機関5選

発達障がいや二次障がいのある方が利用できる支援機関を紹介していきます。
ここで述べる機関では、発達障がいによる二次障がいに関係する悩みや問題はもちろん、ご家族も含めてより良い生活を送るためのサポートやアドバイスを受けることができます。利用を検討してみると良いでしょう。
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、発達障がいのある方が総合的な支援を受けられる専門的な機関です。発達障がいそのものや二次障がいについての悩みの相談を受け付けており、必要に応じて医療機関を受診するためのサポートも行っています。
発達障害者支援センターで受けられる支援は、相談以外にも下記のようなものがあります。
- 発達障がいの検査や、障がいの特性に合わせた支援計画の作成
- 発達障がいを抱える方の就労のサポートや、支援機関との連携
- 発達障がいに関する研修や講演会の開催
また、発達障がいがある方ご本人だけでなく、ご家族の相談も受け付けており、周囲のサポート体制を整えやすいという利点があります。
発達障害者支援センターについては、下記の記事でも解説しています。
相談支援事業所
相談支援事業所とは、障がい者の日常にまつわるさまざまな相談に専門的な対応を行う福祉サービスです。
相談支援事業所で受けられる支援は、下記のものがあります。
- 障がいのある方や、その家族からの相談に応じ、情報やアドバイスの提供
- 障害福祉サービスを利用するためのサポート
- 専門機関の紹介
利用したい場合は、お住まいの自治体に設置されている障害福祉窓口で紹介してもらうのが良いでしょう。
また、市区町村の障害福祉窓口でも相談支援を受け付けています。
精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは、精神的な悩みや精神医療についてのさまざまな相談を受け付ける支援機関です。障がいの有無に関わらず、誰でも利用可能です。
専門員による面談を通じて、状況に応じたアドバイスや支援制度の紹介をします。
また、必要に応じて医療機関や福祉サービスとの連携を図り、問題解決へのサポートを行います。
障害者就業・生活支援センター
障がい者就業・生活支援センター(なかぽつ)は、障がいがある方の仕事と生活の両面でサポートする支援機関です。
発達障がいの二次障がいを抱えている方も対象になるため、就職から日常生活まで幅広い相談と支援を受けることができます。
障がい者就業・生活支援センターについては、下記の記事で解説しています。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、主に一般就労を目指す障がい者の支援を目的とした支援機関ですが、その一環として生活支援も行っています。
そのため、発達障がいの二次障がいで苦しんでいて、「今はまだ就職はちょっと考えられない」という方でも、相談することで生活上の問題を改善するためのサポートから受けることができます。
障がい者手帳が無くても、医師の診断書さえあれば利用可能です。以下はおすすめの就労移行支援事業所です。無料見学も受け付けているので、気になる方はチェックしてみてください。
ココルポート
ココルポートは、温かく包み込むような支援スタイルが特徴の就労移行支援事業所です。発達障がいの二次障がいを抱えている方も安心して通えるよう、一人ひとりの心境に配慮した、無理のないペースでのプログラムを提供しています。
基本的なPCスキルからグループワークまで、多様な活動を通じて「できること」を増やし、社会参加への自信を育んでくれます。相談しやすい環境が魅力です。
atGpジョブトレ 発達障害コース
atGpジョブトレ 発達障害コースは、発達障がいのある方に特化した就労移行支援事業所です。発達障がい者に対するサポート実績が豊富なので、発達障がいの二次障がいについても、具体的なアドバイスやサポートをしてもらえます。
専任のスタッフが、こまめな個別面談を通じてあなたの問題の対処法について一緒に考えてくれます。もちろん就労についてのサポートも手厚いので、利用できれば社会復帰もスムーズです。
まとめ|発達障がいの二次障がいとしてのうつと対処法や支援機関
- 二次障がいは、発達障がいの特性が周囲から正しく理解されず、自分の能力が劣って見えることによるストレスから発生することが多い。
- 発達障がいの二次障がいには、自分自身に影響を及ぼす「内在化障がい」と、周りに影響を及ぼす「外在化障がい」が存在する。
- 発達障がいによる二次障がいを予防するには、自分での対策だけでなく周りのサポートも大切。
- 発達障がいや二次障がいがある方は、発達障害者支援センターや相談支援事業所、精神保健福祉センター、障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)など、さまざまな支援機関を利用することができる。
発達障がいがある方のストレスは、自分1人で解決するには難しいことも多いでしょう。
しかし、適切なサポートと理解があれば、二次障がいを予防したり、その症状を軽減したりすることができます。日常生活や仕事上で問題を抱えている場合は、無理せず周りに相談してみましょう。
この記事が少しでも参考になりましたら幸いです。