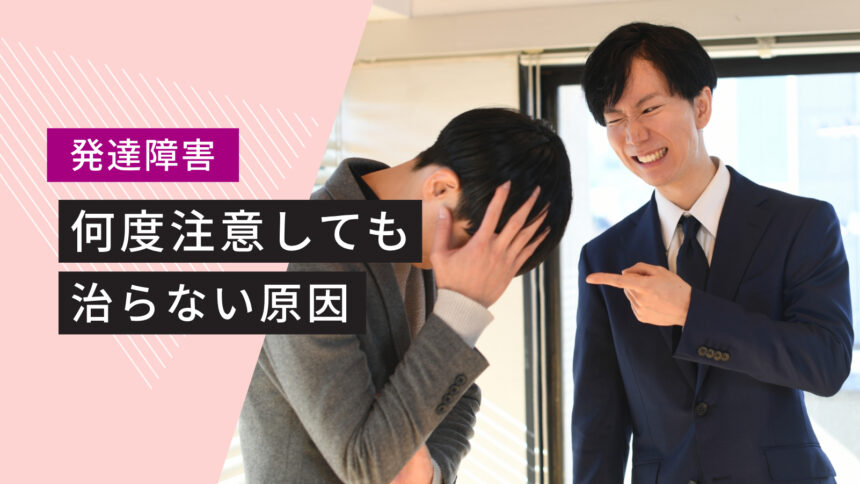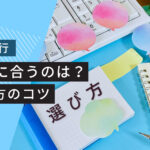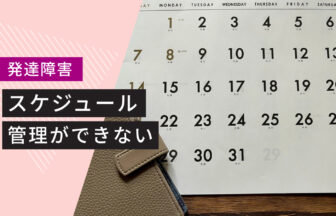この記事にたどり着いたあなたは
「この前注意したばかりなのに、あの人はなぜ同じミスを繰り返すのだろうか?」
など、職場にこのような部下や同僚がいて悩みを抱えてはいませんか?
日本人の約7~8%は発達障害の傾向を持っていると言われています。
昨今では、発達障害であることを公表している有名人が増加しており、メディアで発達障害について取り上げられることが増えた背景などからも、発達障害は非常に身近な障がいの1つと言えるでしょう。
ですが、発達障害の認知度が高まる一方で、「発達障害の方との接し方がわからない」ということが悩みの種になってしまうケースもありますよね。
- 何度言っても分からない、注意しても治らない人は発達障害なのか?
- 発達障害の方に上手く伝えたり注意したりする方法
- 発達障害の方がコミュニケーションの中で注意すること
について解説していきます。
発達障害の傾向がある方と職場でどのように接していけばいいのかについて、一緒に考えていきましょう。
何度言っても注意してもわからない、原因は大人の発達障害?

発達障害とは、生まれつきの脳機能の発達の偏りによって、日常生活や社会生活に困難が発生してしまう障がいです。
発達障害は大きく分けて、以下の3つに分類されています。
ADHD(注意欠陥・多動症)
「不注意」「落ち着きがない」「衝動的な行動」という3つの傾向があらわれやすい発達障害です。
「ケアレスミスが多い」「マルチタスクができない」などの形で仕事に影響をきたすことがあります。
ASD(自閉スペクトラム症)
「コミュニケーションがうまく取れない」「特定の物事に強いこだわりや興味を持つ」という傾向があらわれやすい発達障害です。
「曖昧な指示を理解できない」「自分のやり方・ルールに固執してしまう」などの形で仕事に影響をきたすことがあります。
LD(学習障害)
知的発達の遅れや視覚・聴覚に問題がないにも関わらず、「読み書き」「計算」などの特定の作業に困難を抱えてしまう症状がみられる発達障害です。
「文章による指示を理解できない」「メモを取ることが苦手」などの形で仕事に影響をきたすことがあります。
これらの特性から、「何度言っても分からない」「注意してもミスを繰り返す」という方が発達障害を抱えている可能性は十分にあり得るでしょう。
一方で、発達障害の特性は誰にでも少なからず当てはまるものです。そのため、安易に「仕事ができない=発達障害」と決めつけてしまうのは、レッテル貼りに繋がることもあるため注意が必要です。
次の項目では、職場で「この人は発達障害なのではないか?」と思った時や、部下や同僚から発達障害であることのカミングアウトを受けた場合、どのように接していけばよいのか解説していきます。
何度言ってもわからないのは話の伝え方に原因がある?

あなたがこのように感じている時、同時に発達障害を持つ相手は、
このように感じているかもしれません。
つまり、コミュニケーションにすれ違いが起こっている可能性があるのです。
次の項目では、発達障害の方とのコミュニケーションのすれ違いを防ぐ方法について紹介します。
曖昧な表現を避けて、具体的な指示をする
発達障害の中でも特にASDの特性を持つ方は「言葉通りに物事を捉えやすい」ため、言葉の裏に隠れた真意を想像することが苦手な傾向があります。そのため、「いい感じに」「多めに・少なめに」といった曖昧な表現の理解を苦手とすることがあるのです。
一方で、このような特性は「余計な推測はしない」というプラスの側面も持っているため、具体的な指示を心がけることが大切です。
例えば、
という指示ではなく、
というように、可能な限り指示の内容を具体化することで明確な意図が伝わります。
LINEなどのチャットやメールで指示を送る
ADHDや読み書きに困難を抱えるLDの方はメモを取る作業を苦手とする傾向があり、
- 会話に集中しすぎてメモを取り忘れる
- メモを取るのに集中しすぎて会話を聞き逃す
- スムーズにメモをとることが難しい
などの事態に直面しやすいのです。そのため、口頭で指示をすると内容に抜け漏れが発生する可能性が高くなります。
これらの配慮事例として実際に、発達障害の人に対してなるべく口頭での指示ではなくチャットやメールで指示を送る、という対策を行うことで以前よりも円滑なコミュニケーションが可能になったという事例は数多くあります。
チャットやメールであれば「文章を読んで理解してから返信を考える」という工程を経ることができるため、指示の内容のズレや誤解が生じにくいのです。文字として記録に残るため、仕事中に指示の内容を何度でも見返すことができる点も大きなメリットです。
言葉だけでなくイラストや図を用いて伝える
私たちは発達障害の有無を問わず脳の特性に個人差があり、言葉で情報を聞いた方が理解しやすい「聴覚優位」の方と、視覚で得られる情報の方が理解しやすい「視覚優位」の方がいます。
つまり、人それぞれ理解しやすい伝え方が異なっているのです。それに加えて、ADHDやASDの方は「聴覚優位」や「視覚優位」の特性がはっきりと表れやすい傾向があります。
そのため、文字や言葉での説明に「フローチャート」や「イラストや図による補足」を付け加えることで、仕事の手順の説明や指示がよりスムーズに行えるようになるのです。
このような工夫は、発達障害の方に対する配慮に繋がると同時に、新入社員などに対する教育を効率化できるなどのメリットもあります。
発達障害の方を注意するときの上手な伝え方

同じミスを繰り返す部下や同僚にイライラが溜まってしまうと、つい厳しい口調で叱責してしまうこともありますよね。ですが、このような対応の中に発達障害の方がミスを繰り返してしまう原因が隠れている可能性があるのです。
発達障害の方は「コミュニケーションの苦手」「強いこだわり」などの特性から、怒られることに強い抵抗を感じることが多いのです。
そのため、叱責されると極端な自己否定の状態に陥ってしまい、「頭が真っ白になる」「思考停止してしまう」ことがあります。
発達障害の方が同じミスを繰り返しやすい原因には、注意欠如の傾向以外にも上記のような理由があるため、怒られると極端にプレッシャーを感じてパフォーマンスが低下しやすいのです。
「注意しても治らない・ミスが減らない=やる気がない・話を聞いていない」ということではありません。発達障害の方に「ミスを指摘する」「直してほしいことがある」などの場合、いきなり怒るのではなく「ミスの原因を特定して具体的な改善策を提案する」意識を持つことが大切です。
発達障害の当事者が気を付けたいコミュニケーションのポイント
発達障害の方が「あの人の言っていることがわからない」と感じた時、そこには何かしらの事情があることもありますよね。
ですが、そこで「本当は違うんだ」「そんな言い方をする必要はないだろう」という思いからつい反発をしてしまうと、話が余計にこじれたりお互いに嫌な思いしたりする原因となります。
上司や同僚からの注意や指摘を受けた時、まずは相手に「受け止めています」という反応を返すことが大切です。いきなり「発達障害だから仕方がない」という態度で言い返してはいけないのです。
- 「ミスをしてしまい申し訳ありません」などの謝罪の言葉
- 「指摘いただきありがとうございます」などの感謝の言葉
- 「おっしゃる通りです」などの相手に同調する言葉
などのワンクッションを挟むことが、お互いに歩み寄ったコミュニケーションを取ることに繋がります。
上司や同僚と日常的に冷静な話し合いができる関係を構築することは、「話の内容に不明点があった時の再確認」や「発達障害の特性に対する配慮を求めたい」という時に役立ちます。
もし、こうしたコミュニケーションの難しさが原因で現在の仕事が続けられなかったり、これから仕事に就くことに強い不安を感じたりするなら、専門的なサポートも有効です。
atGPジョブトレは、発達障害専門の就労移行支援です。まさにそうした方が新しい職場で円滑に働くために、苦手としやすいコミュニケーションや仕事の進め方に対し、集中的なトレーニングを提供しています。実際の業務を想定したプログラムで、ご自身の特性と向き合いながら働くスキルが身に付きます。
まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。
まとめ
- 「何度言ってもわからない」「注意しても治らない」という人が発達障害である可能性はあり得るが、必ずしも原因が発達障害にあるとは限らないため注意が必要。
- 発達障害の方が何度言っても分からない場合はコミュニケーションにすれ違いが発生している可能性があるため、「曖昧な表現を避けて具体的な言葉で伝える」「連絡手段にチャットやメールを用いてみる」「説明の時にイラストや図を用いる」などの対策が効果的である。
- 発達障害の方が注意しても治らない場合、「話の内容で理解できていないポイント」「ミスの原因」などを特定して「具体的な改善策を提案する」ことが大切。
- 発達障害の当事者が注意や指摘を受けた時は、まず相手の言葉を「受け止めています」という反応を返してお互いに歩み寄って冷静なコミュニケーションを取れるように心がけることが大切。
職場に発達障害の方がいるのは決して珍しいことではありません。そのため、職場の部下や同僚から発達障害のカミングアウトを受けることや、「あの人は発達障害ではないか?」と感じることも珍しいことではないのです。
ですが、今回の記事を通して「あの人には話が伝わっていないよな…」と感じた時でも、少しの工夫をすることで円滑にコミュニケーションを取る方法があるということを知って頂ければ幸いです。