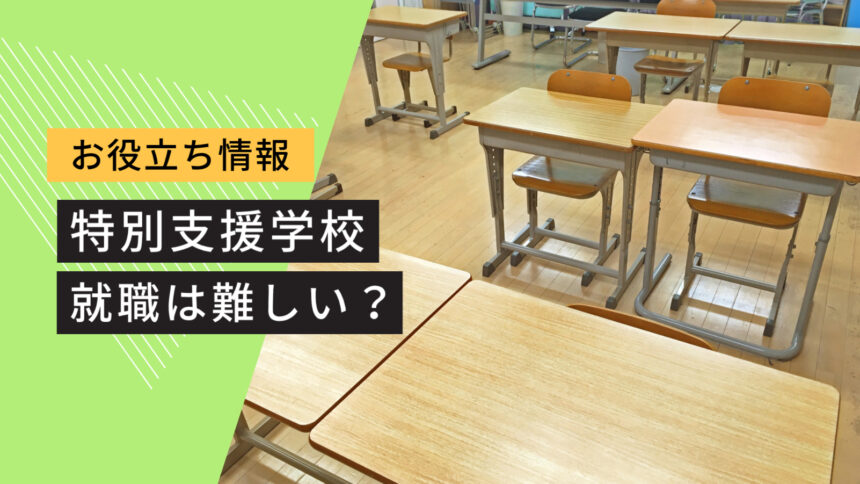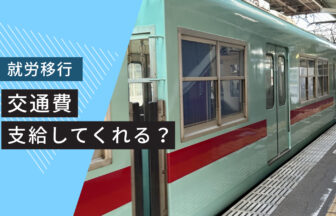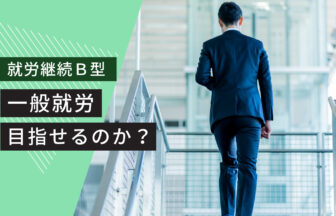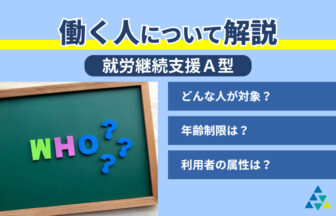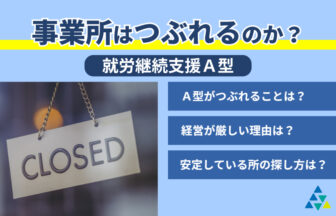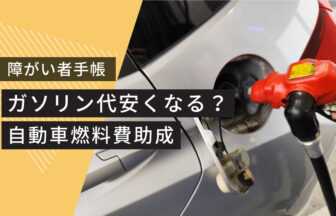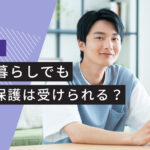この記事を開いているあなたは、
「卒業後は自立した生活を送りたいけど、支援を受けられないのも不安……」
このような悩みを抱えてはいませんか?
特別支援学校の生徒やその家族の中には、「卒業後の進路」について大きな不安を抱えている方が沢山いらっしゃいます。ですが、実際には特別支援学校を卒業した後も、様々な進路の選択肢や利用できる支援制度が用意されています。
そこで、
- 特別支援学校からの就職実態について
- 特別支援学校を卒業した後に5つの進路とは
- 卒業後も利用できる支援制度5選
について解説していきます。
特別支援学校からの就職実態とは?

「特別支援学校からの就職は難しい」と思われがちですが、実際はどうなのでしょうか?
以下では、
- 特別支援学校卒業後の就職率はどれくらい?
- 一般企業に就職できる可能性はあるのか?
について解説します。実際のデータから就職実態を正しく理解して、あなたに合った進路を考えていきましょう。
特別支援学校卒業後の就職率はどれくらい?
文部科学省の「学校基本調査」によると、令和4年度における特別支援学校高等部の卒業生の就職率は「31.2%」と発表されています。一方、一般高校の就職希望者の就職率は約98%となっており、この数字を比べると特別支援学校の卒業生がいかに就職で苦戦しやすいかがわかります。
実際に、特別支援学校の卒業生は、
「卒業後に支援を受けながら働く方法がわからない」
などの悩みを抱えやすいのが現状です。
そのため、特別支援学校から就職を目指す場合は、卒業後の進路や利用できる支援制度を把握することが大切です。
一般企業に就職するのは難しいのか?
先述の「就職率31.2%」という数字を見ると不安になるかもしれませんが、特別支援学校を卒業した後でも一般企業への就職は十分可能です。
その大きな理由が「障がい者雇用枠」の存在です。
障がい者雇用枠とは、企業が障がい者を採用するために設けている特別の雇用枠のことを指します。 国の法律によって、一定規模以上の企業には障がい者を雇用する義務(法定雇用率)が定められており、この仕組みを利用することで特別支援学校を卒業した後も安定した環境で働けるチャンスが広がります。
現在、多くの企業は 法定雇用率を達成するために障がい者採用を積極的に進めており、特別支援学校の卒業生を受け入れるケースも増えています。特に、製造業やサービス業などの業界では、障がい者雇用の取り組みが広がっています。
そのため、障がい者雇用枠を活用すれば、「働きやすい環境」で「安心して長く働く」ことも十分に可能と言えるでしょう。「特別支援学校からの就職は難しい」と思い込まず、自分に合った働き方を見つける視点を持つことが将来への一歩になります。
障がい者雇用については、以下の記事でも詳しく解説しております。
以下では、特別支援学校卒業後に選べる具体的な進路について詳しく解説していきます。
特別支援学校を卒業した後の5つの主な進路

特別支援学校を卒業した後の進路には、どんな選択肢があるのでしょうか?
「一般企業で働くのは難しいのでは?」
と考えている人も多いですよね。しかし、特別支援学校を卒業した後の進路は、一般就職だけではなく、就労支援サービスの利用や進学など、さまざまな道があるのです。
卒業後の主な進路については、次の5つが存在します。
- 障がい者雇用枠での就職
- 一般雇用での就職
- 就労支援サービスの利用
・就労継続支援A型(A型事業所)
・就労継続支援B型(B型事業所)
・就労移行支援 - 在宅ワーク
- 進学
順に紹介いたします。
障がい者雇用枠での就職
先述している障がい者雇用枠での就職は、特別支援学校を卒業した人の多くが選ぶ進路の1つです。
障がい者雇用枠には、
- 病気や障がいに対して理解のある企業への就職ができる
- 病気や障がいの症状に対して、合理的な配慮を求めながら働ける
という特徴があります。そのため、企業側の「業務内容や業務量の調整」「適切な休憩時間の確保」「困りごとを相談できる担当者の配置」などの工夫により、無理のない働き方を実現しやすい大きなメリットがあります。
「自分のペースで社会に慣れていきたい」
このように考えている人にとって、障がい者雇用枠での就職は特におすすめの選択肢と言えるでしょう。
ただし、障がい者雇用枠を利用するには原則として障がい者手帳の取得が必要になります。卒業後に就職を目指す場合は、早めに主治医や自治体の障害福祉課などに相談して、手続きを進めておくことが大切です。
一般雇用での就職
特別支援学校を卒業した後は、障がい者雇用枠を使わず「一般就労」での就職を目指す進路もあります。
一般就労の場合は、障がいの有無に関係なく一般の採用枠で就職することになるため、
- 障がい者雇用よりも給与や待遇面が良い
- 「やりたい仕事」「専門的な仕事」に挑戦できる可能性がある
- 正社員以外にも契約社員やアルバイトなどの選択肢があり、仕事の選択肢が多い
などのメリットがあります。特に、「職業訓練を受けて専門的なスキルを持っている」などの人にとって、一般就労は現実的な選択肢となるでしょう。
一方で、一般就労には以下のような注意点があります。
- 障がいへの配慮が受けられない場合が多い
- 業務内容や責任の重さは、他の社員と同じレベルを求められる
- 採用試験や面接では、スキルや実績重視になる傾向が強い
そのため、自分の特性や体調、働く環境との相性をしっかり見極めることが大切です。
就労支援サービスの利用
特別支援学校を卒業した後、すぐに就職することに不安がある場合は、「就労支援サービス」を利用するという選択肢もあります。
福祉的就労は主に、以下で紹介する 「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労移行支援」 の3つがあります。それぞれ、どのような支援が受けられるのか見ていきましょう。
就労継続支援A型(A型事業所)
就労継続支援A型とは、雇用契約を結んだ上で障がいに配慮を受けながら働ける場所を提供している就労支援サービスです。週5で4~6時間程度の時短勤務に従事するのが一般的ですが、利用者には最低賃金が保証されるため、安定した収入を得ながら働くことができます。
業務内容は、企業から請け負った軽作業(部品の組み立てや梱包、製品の検品など)が中心ですが、昨今では「プログラミング」「カフェの運営」「農作業」など様々な仕事を扱う事業所も増加しています。
作業量やペースは体調や特性に合わせて調整してもらえるため、
「体力やスキルにはある程度自信があるから、働いて自立した生活を目指したい」
このように考えている人には、就労継続支援A型はおすすめの進路の1つです。
就労継続支援B型(B型事業所)
就労継続支援B型とは、障がいに配慮を受けながら雇用契約を結ばずに働ける場所を提供している就労支援サービスです。就労継続支援A型と比較すると、より「社会福祉サービスを受ける場所」としての意味合いが強くなるため、生活面や就労面で手厚い支援が期待できます。
作業内容は、内職的な軽作業・手工芸・農作業・清掃などが多く、スキルや体力に自信がない人でも働きやすい環境が整っています。ただし、最低賃金は保証されていないため、月の賃金は貰える賃金は1~2万円程度であることが一般的です。
就労継続支援B型は、
「体調や精神面に不安があるから、まずは働く練習をいたい」
このように考えている人におすすめされている進路です。
就労移行支援
就労移行支援とは、一般企業(障害者雇用を含む)への就職を目指す人の就職活動を支援するための就労支援サービスです。通所しながら最大2年間、就職に必要な知識やスキルを学ぶことができます。
プログラム内容は事業所ごとに異なりますが、例えば以下のような支援があります。
- ビジネスマナーやPCスキルの講座
- 履歴書の作成や面接練習
- 企業での職場実習(インターン)
- 職後の定着支援(職場に馴染めるようサポート)
また、就職活動の相談から実際の就職先探し、応募書類の添削まで、専門スタッフがマンツーマンでサポートしてくれるのも大きな魅力です。
就労移行支援は、
「社会人として必要な知識やスキルを身に着けて、自信を持って働きたい」
このように考えている人には、特におすすめの進路です。
どんな事業所があるのか気になる方は、以下のおすすめの就労移行支援事業所を参考にしてみてください。
就労継続支援A型・B型や就労移行支援については、以下の記事でも詳しく解説しております。
在宅ワーク
特別支援学校を卒業した後の働き方として、「在宅ワーク」という選択肢もあります。昨今ではインターネット環境の普及に伴い、「通勤が不要」「自宅の慣れた環境で働ける」などのメリットがある在宅ワークは、障がい者にとってもおすすめの働き方であるとして注目されるようになりました。
在宅ワークには、次のような仕事があります。
- データ入力
- Webライター・ブログ執筆
- イラスト・デザイン制作
- 動画編集
- プログラミング
- ハンドメイド作品のネット販売
パソコンやITに関わるスキルを身に着けることで、活躍のばを広げることができるでしょう。
ただし、在宅ワークでは「作業ごとの歩合給」「成果報酬型」などの形態がとられることが多いため、安定して働けなければ収入が安定しないというデメリットがあります。在宅ワークを視野に入れる場合は、先述している就労支援サービスの利用などと合わせて慎重に検討することが大切です。
進学
「専門的に学んでみたい分野がある」という人は、特別支援学校を卒業した後に大学・短期大学・専門学校などへの「進学」という道もあります。進学をすることで、専門的なスキルや資格取得に繋がれば、将来の就職先の選択肢を大きく広げることができるでしょう。
ただし、進学を希望する場合は、
- 受験勉強や面接対策が必要になるため、事前準備が必要
- 入学金や授業料などの学費が大きな負担となる場合がある
- あなたの体調や障がいの特性に合わせて、学業についていけるかの判断が必要
このような注意点があります。
進学先によっては、障がいを抱える学生への支援や配慮を実施している場合があるため、希望する学校への問い合わせやオープンキャンパスへの参加を行い情報収集を行うことが大切です。
卒業後も利用できる支援制度5選

と不安を抱えている人もいらっしゃるかと思います。
ですが、卒業後もさまざまな支援制度を活用できます。仕事で困った時・生活での支援が必要な時・経済的に厳しい時などに、適切な支援制度を利用することで安心して生活を送ることができるのです。
卒業後も利用できる支援制度は、主に次のようなものが存在します。
- ジョブコーチ支援
- 3つの経済的支援制度
- 3つの経済的支援制度
・生活保護
・障害年金
・特別障害者手当
順に紹介いたします。
ジョブコーチ支援
ショブコーチ支援とは、就職したばかりの障がい者が、職場に慣れて安定した就労を継続するために実施される支援のことです。
ジョブコーチ支援は主に以下の3つの支援を実施します。
- あなた自身から、仕事の悩みや生活状況の課題を聞き取り、状況に応じた助言を行う
- 職場を訪問して、障がいの特性を周知させて働きやすい職場環境の調整を求める
- 家族に対して、あなた自身の社会生活を援助するための助言を行う
利用期間は最長で8か月となっており、この期間内に安定した社会生活を送るための土台を作ることが1つの目標となります。
また、ジョブコーチ支援は無料で利用できるため、
という人は、申し込み窓口であるハローワークや地域障害者職業センターに問い合わせるとよいでしょう。
ジョブコーチについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
障がい者グループホーム
障がい者グループホームとは、障がい者が専門スタッフのサポートを受けながら、複数の利用者と一緒に共同生活を送る住まいのことです。障がい者の自立や社会的孤立の防止などの役割を持つため、特別支援学校を卒業した後に「実家を出て暮らしたい」「親元を離れて働くことになった」などの人にとって、障がい者グループホームへの入居は1つの選択肢となるでしょう。
障がい者グループホームでは、
- 料理、洗濯、掃除、金銭管理などの生活支援
- 料理の提供、通院、服薬管理などの健康維持に必要な支援
などの支援が受けられるため、安心した環境で暮らしながら生活スキルを身に着けることができます。
また、家賃・食費・光熱費などは自己負担になるため、生活費として月額4~6万円程度の費用が発生する点には注意が必要です。ですが、一般的なアパートに入居した場合の生活費は15万~17万円程度であるため、障がい者グループホームへの入居は月々の支出が抑えられる点は大きなメリットになります。
障がい者グループホームについては以下の記事で詳しく解説しています。
3つの経済的支援制度
障がい者が働く場合、
「収入が少なくて生活が厳しい……」
このような悩みから、日々の暮らしに不安を抱えてしまうことは珍しくありません。
そこで、以下では特別支援学校を卒業した後に利用できる経済的支援を3つ紹介します。制度を正しく理解して、あなたの経済的不安の解消にお役立てください。
生活保護
生活保護は、収入や資産が少なく生活が難しい人を支えるための公的制度です。生活に困った時のセーフティネットと呼ばれる通り、毎月必要な最低限の家賃・生活費などの給付が受けられるほか、医療費や税金の免除が受けられます。
ただし、利用するには「収入・資産の状況」「家族からの支援の有無」などを調査された上で審査が必要になるため、生活に困窮する前に自治体の担当窓口に相談することが大切です。
「生活保護を受けるのは恥ずかしいこと」
という誤解が多い制度ですが、生活が厳しい時は誰でも遠慮せず利用できる制度です。
特別支援学校の卒業後、「働けない」「収入が少なく生活ができない」という場合には、生活保護が利用できる可能性があります。困った時は、早めに相談してみましょう。
障害年金
障害年金は、障がいによって生活や仕事が制限されている人に支給される公的年金です。
障害年金は原則として20歳から利用できる制度であるため、特別支援学校在学中(18歳未満)には利用できない点に注意が必要です。また、申請には医師の診断書が必要になるほか、複雑な手続きもあるため、年金事務所などの専門機関に相談しながら進めると安心でしょう。
障害年金には「仕事に制限があるため思うように収入が得られない」という人を支援する目的があるため、働きながら受給することができます。特別支援学校を卒業した後は、積極的に活用したい制度の1つです。
特別障害者手当
特別障害者手当は、重度の障がいによって常に介護や見守りが必要な人を支援するための公的手当です。障がいの種類(精神・身体・知的)を問わず、日常生活に著しい制限がある人を対象に、令和6年時点では「月額28,840円」が支給されます。
特別障害者手当は、支給されたお金の使い道に制限はなく、生活費・医療費・介護にかかる費用など、必要な支出に自由に使うことができます。障害年金と同時に利用できるため、重度の障がいがある場合は併用することで生活の大きな支えとなるでしょう。
まとめ
- 特別支援学校からの就職率は令和4年度で「31.2%」となっており、「希望の仕事に就くことができない」「支援を受けながら働く方法がわからない」などの問題を抱える人が多い
- 昨今では障がい者採用を積極的に行う企業が増加しており、障害者雇用枠を利用することで一般企業への就職は十分に可能である
- 特別支援学校を卒業した後の進路には、「障害者雇用枠での就職」以外にも、「一般雇用での就職」「就労支援サービスの利用」「進学」など様々な選択肢がある
- 就職後に「安定して働き続けられるか不安」という人は、ジョブコーチ支援の利用がオススメ
- 親元を離れて働くなどの場合には、生活費を抑えて支援を受けながら生活できる障がい者グループホームへの入居がオススメ
- 収入が安定せず生活が厳しい場合は、「生活保護」「障害年金」「特別障害者手当」などの経済的支援制度を積極的に活用することが大切
今回の記事では、「特別支援学校からの就職は難しいのか?」という点を中心に、卒業後の進路や利用できる支援制度について解説しました。
この記事を、あなたの将来の不安解消にお役立て頂ければ幸いです。