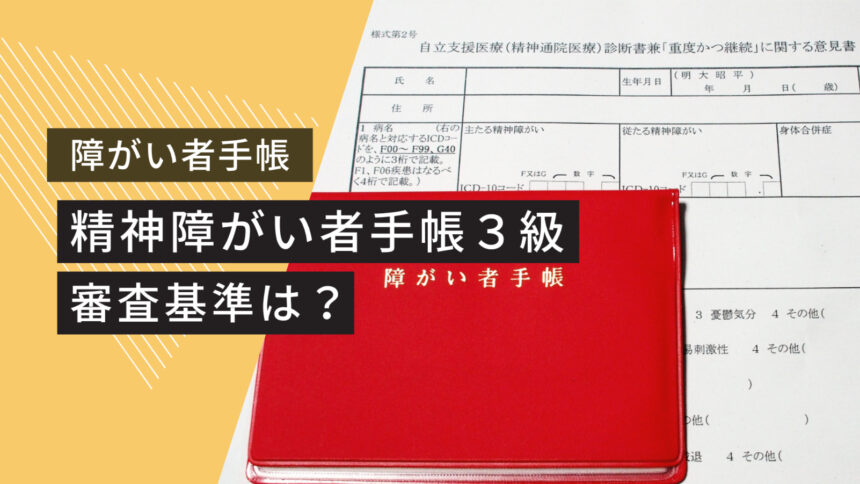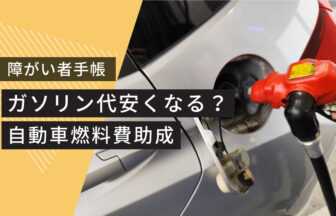「なんで審査で落とされたのかわからない…」
「精神障がいで生活に困っているのにどうして?」
この記事を開いたあなたは、このような悩みや不安、不満を感じたことはありませんか?
障がい者雇用による就労をはじめ、障がいのある方が必要な援助を受けるために必要になるのが障害者手帳です。
手続きも決して楽ではないので、「必要だ」と思っていざ申請して落ちたとなると、気分が重くなってしまいますよね。
- 精神障がい者手帳3級の審査に落ちた理由
- 取得できるのはどの程度の障がいなのか
- 審査はどの部分を見て行われているのか
- 審査は甘いのかそれとも厳しいのか
- 再申請は可能なのか、可能であれば次に落ちないためにはどうすればいいのか
について解説していきます。
障がい者手帳は基本的に一度落ちても再申請が可能です。審査に落ちた理由を押さえていれば再申請の際にも役立つので、ぜひ最後までご一読ください。
精神障がい者手帳3級の審査に落ちた3つの理由

精神障がい者手帳3級の審査基準は、厚生労働省が示す下記の定義に従って決められています。
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの引用:精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について|厚生労働省
そのため、精神障がい者手帳3級に関する次の要素の有無を問われます。
- 対象となる精神疾患の診断を受けているか?
- 精神疾患による症状の程度
- 精神疾患による生活能力への支障の程度
あなたが審査に落ちたのは、この上記3つについて証明できていなかったり、情報が不十分だったりしていた可能性が高いです。
「対象となる精神疾患」とは?
「精神障がい者」とは、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律で下記のように定義されています。
この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条|e-GOV法令検索
そのため、
- 統合失調症
- 躁うつ病
- てんかん
- 認知症
- 発達障害
などのすべての精神疾患・精神障がいが精神障がい者手帳3級の対象です。
一方で、これら精神疾患の診断がない、もしくは診断を受けていても証明ができないという場合は、障がい者手帳の申請ができないため注意が必要です。
「精神疾患による症状の程度」とは?
対象の精神疾患の有無は診断によってはっきりわかるものですが、一体どの程度の症状が見られて生活能力に支障をきたしていれば精神障がい者手帳3級の対象になるのでしょうか?
厚生労働省が示す判断基準の詳細を基に確認していきましょう。
精神疾患ごとの症状の程度による基準
精神障がい者手帳3級が認められる症状の程度は、精神疾患ごとに目安となる基準が存在しています。下記はそれを要約したものです。
- 統合失調症
症状がある、もしくは治療等によって落ち着いても症状が残っている状態で、人格の変化はあまり無いものの、思考障がいやその他の妄想・幻覚等の異常体験がある - 気分障がい(躁うつ等)
症状は深刻ではないものの、持続していて頻繁に繰り返している - 非定型精神病(統合失調症と気分障がいの複数の症状が見られ診断が難しい場合の診断名)
統合失調症と気分障がいの双方に準ずる - てんかん
頻繁ではないが発作がある、もしくは知能障がいやその他の精神神経症状(眠れない、イライラする、物忘れが増えたなどの症状のこと)がある - 中毒精神病(アルコールや薬物等)
認知能力に著しい低下は見られないが、その他の精神神経症状がある - 器質性精神障がい(認知症や外傷による脳損傷等)
記憶障がい、遂行機能障がい、注意障がい、社会的行動障がいのいずれかがあり、いずれも軽度である - 発達障がい
高度ではないが主症状があり、その他の精神神経症状がある - その他の精神疾患
上記1~7に準ずる
あなたがお持ちの精神疾患が上記の条件をある程度満たしていれば、対象だと言えるでしょう。
もっとも対象の精神疾患の診断を受けた段階で満たしていそうな条件ばかりなので、この点はほとんど精神疾患の有無とイコールであるように見えます。
「生活能力への支障の程度」とは?
精神障害者手帳3級に該当する生活能力の程度については、同様に厚生労働省が公開している実際の診断書の記入欄が参考になります。
- 適切な食事摂取
- 身辺の清潔保持、規則正しい生活
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達・対人関係
- 身辺の安全保持・危機対応
- 社会的手続きや公共施設の利用
- 趣味・娯楽への関心、社会的活動への参加
これらのうちいくつかが「自発的にできるが援助が必要」もしくは「おおむねできるが援助が必要」以上に困難な状態であれば、対象であると考えられます。
ちなみに「いくつか」となっているのは、判断基準の詳細に「いくつか」としか書かれていないためです。
ただしその代わりに基本的なとらえ方として参考になる一例が記載されています。下記はその要約です。
- 適切な食事摂取について
日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化すると困難が生じてくることもある
(おおむねできるが援助が必要) - 身辺の清潔保持、規則正しい生活について
清潔保持は困難が少ない - 金銭管理と買い物について
金銭管理はおおむねできる - 通院と服薬について
普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい
(通院と服薬をあまり必要としない) - 他人との意思伝達・対人関係について
対人交流は乏しくなく、行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる - 身辺の安全保持・危機対応について
一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である
(自発的にできるが援助が必要) - 社会的手続きや公共施設の利用について
自主的な行動や、社会生活の中で発言が適切にできないことがある
(おおむねできるが援助が必要) - 趣味・娯楽への関心、社会的活動への参加について
引きこもりがちではなく、社会生活の中で不適当な行動をとってしまうことは少ない
こういった場合でも精神障がい者手帳3級の対象となる場合があります。実際の判断や解釈は市町村によって異なるため確実ではありませんが、参考として知っておくと良いでしょう。
「過去2年間に認められた症状」と「今後2年間に予想される症状」が問われる
実は「精神障がい者が生活に制限を受けている」という状態の定義には、「支障が長期間続くこと」が条件に含まれています。
厚生労働省の「精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項」の生活能力に関する項目には、
現時点のみでなく、これまでおおむね2年間に認められ(高次脳機能障害の場合は現疾患発症以降に生活能力の低下が生じたことを確認する)、また、おおむね今後2年間に予想される生活能力の状態も含めて判定し記載する
精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項 ⑥生活能力の状態|厚生労働省
と書かれています。
精神疾患が原因で「過去から2年以上支障が続いている」「今後も2年以上支障が続くと予想される」場合は、精神障がい者手帳の取得に有利に働くと考えて良いでしょう。
生活上の支障が診断書に反映されていたか確認しよう

精神障がい者手帳の審査は、各所の精神福祉保健センター職員が申請者の情報を確認して、審査基準を満たしているかどうかが判断されます。
申請者の情報として確認されるのは主に主治医が作成する診断書です。診断書の作成には、これまでの問診の記録だけでなく、あなた自身からの申し出による症状や生活上の支障も重要な情報になります。
「基準は満たしているはずなのに…」という方は少し考えてみてください。
問診の際に、例えば、
- 食事を作る気力がなくインスタント食品ばかり食べているため、食事の管理が難しい
- 気分の落ち込みが激しく外出できない日があり、仕事や買い物に支障がある
など、外見からでは把握できないあなたの生活上の支障について、主治医にしっかりと伝えられていたでしょうか?
このような情報が診断書に反映されていなかった場合、「精神疾患はあるけれど生活に問題はない」と判断されてしまい、審査に落ちてしまう可能性があります。精神障がい者手帳を取得できなかった場合は、診断書の内容を改めて確認することが大切です。
診断書の2つの期間は大丈夫?見落としやすいポイント

精神障がい者手帳を申請するための診断書には有効期間があり、
- 精神疾患の初診日から「6か月以上経過」した時点で発行されていること
- 作成されてから「3か月以内」の診断書で申請を行うこと
上記2つの条件を満たす必要があります。
初診日とは、「現在の精神症状を理由に始めて医療機関を利用した日」のことです。
「初診日から6か月以上の経過が必要」という期間については、厚生労働省の「精神障がい者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項」に明確な記述があります。
6か月以上というのは、生活能力の把握と精神疾患の正確な診断に必要とされる期間です。なので、初診日から6か月経たないうちに作成された診断書では、先述している「支障が長期間続くこと」という条件を満たしていないと判断され審査を通りません。この点は特に重要であり医師も理解しているはずなので、通常であれば診断書を書いて欲しいと頼んでも時期がくるまでは待つように勧められます。
「発行日から3か月以内」という期間については、厚生労働省の留意事項では確認できませんが、多くの自治体ホームページ内の精神障害者福祉手帳の項目にて記述があります。
例:精神障害者保健福祉手帳|埼玉県
時間経過によって状態が変化しやすい精神疾患を抱えている場合は、診断書の有効期間内であっても現在の状態を正確に反映していないと判断される可能性があります。
精神障がい者手帳3級の審査は甘い?厳しい?

ここまで精神障がい者手帳3級の審査基準について解説してきました。
審査は甘いとも厳しいとも言われていますが、はたしてどちらでしょうか?
実際は審査の過程に関わってくる方たちによって変わってくるとは思いますが、情報を総合すると下記のように考えられます。
- 対象となる精神疾患の有無の審査については、きちんとした診断が必要なだけで厳しくも甘くもない
- 対象となる症状の程度の審査については、基準は2級よりは甘く精神疾患の有無とほぼ同等
- 対象となる程度の生活能力の審査については、基準が明らかに甘いが「支障が長期間続くかどうか」に注意が必要
- 審査に必要な診断書には注意点が多く、甘く見てはいけない
結論としては、審査自体は甘い部類ではあるものの、準備段階に注意点があり手間も時間も必要なため、厳しく感じる方がいてもおかしくはありません。
ほとんどのハードルは審査よりも医師の診断を受ける段階に存在します。厳しいか甘いかは、そこへ向けてきちんと準備できるかどうかに懸かっていると言えるでしょう。
精神障がい者手帳は落ちても再審査が可能!

冒頭で述べている通り、精神障がい者手帳3級の審査は1度落ちても再申請が可能です。手順も1度目と同じで、お住まいの地区町村にある障がい福祉課にて精神障がい者保健福祉手帳申請書を発行してもらい、診断書と証明写真を添えて所定の窓口へ提出すれば1〜2か月程度で結果が返ってきます。
しかし、手続きには手間がかかりますし、診断書の用意もタダではありません。特に精神疾患で本当にお困りの方は準備にかかる労力を負担に感じているでしょう。
そこで、ここまでまとめた審査基準を鑑みて、再申請の際に気を付けたいポイントを3つ紹介します。
事前に情報をまとめておく
精神障がい者手帳3級の審査に関する基準と注意点を知っているのと知っていないのとでは審査の難易度が大きく変わってきます。
特に診断書を作成する前にしっかりと確認しておきましょう。
- 精神疾患の有無
- 症状の程度
- 生活能力の程度
- 診断書の期間
(精神症状の初診日から6か月以上経過している、発行日から3か月以内に申請する)
最低でも上記4つの要点を押さえることができれば、過不足なく自身の状況を反映した診断書を作成できて、安心して申請に臨むことができるはずです。
主治医との情報共有をしっかり行う
診断書の内容が審査の結果を大きく左右します。主治医に「精神障がい者手帳3級の基準を満たしている診断書」を作成してもらう必要があるため、見栄を張ってできないことを隠したり誤魔化したりせず、正確な情報を伝えましょう。
もし現在の主治医の方とのコミュニケーションが不安であれば、付き添いのご家族やパートナー、後述する支援機関の方の協力を得るのもオススメです。第三者の視点があると診断書の内容も説得力が増します。
また、主治医との相性そのものに不安がある場合は主治医や医療機関そのものを変えてみるといったことも考えてみると良いでしょう。医師によって診断書の書き方や症状の解釈が異なるケースも多いため、医療機関の変更によって審査に通る可能性があります。
第三者が関わるサービスを利用する
以下の障害福祉サービスは、利用していると精神障がい者手帳3級の取得に関してサポートが得られます。
- 精神科訪問看護
- 精神保健福祉センター
- 就労移行支援事業所
「精神科訪問看護」は、精神疾患のある方もしくは心のケアが必要な方に対して、専門職の方が直接自宅へ訪問し、病状の管理から正しい日常生活を送るための支援を行うサービスです。自宅での様子を観察した看護師を通じて主治医に情報が共有されるので、正確な診断書を書いてもらうことができます。
「精神保健福祉センター」は、精神保健の向上及び精神障がい者の福祉の増進を図るために各地に設立されている公的な機関です。精神福祉保健全般の相談を受け付けているため、しっかりしたサポートが期待できます。
「就労移行支援事業所」は、精神疾患などの障がいを抱える方の一般企業への就職を助ける福祉サービス機関です。就労支援の一環として障がい者手帳の取得をサポートしているため、障がいの状況整理や医師への説明などを助けてくれます。
必要だと感じた場合はぜひご検討ください。
まとめ|精神障がい者手帳3級の審査に落ちる理由と基準
- あなたが障がい者手帳3級の審査に落ちた理由は「対象となる精神疾患」「対象となる程度の症状」「対象となる程度の生活能力」についての証明が不十分であった可能性が高い。
- 精神障がい者手帳3級の対象となる精神疾患は統合失調症や躁うつ病に加え、てんかん、認知症、発達障がいなどが含まれる。
- 精神障がい者手帳3級の対象となる程度については、厚生労働省が示す判断基準の詳細に記されている。
- 精神障がい者手帳3級の審査は診断書の内容をもとにして行われている。
- 精神障がい者手帳3級の審査自体は甘い部類ではあるものの、準備段階に注意点があり手間も時間も必要なため厳しく感じる方がいてもおかしくはない。
- 精神障がい者手帳3級の審査に落ちても再申請は可能、次に落ちないためには「事前に情報をまとめておくこと」「主治医との情報共有をしっかり行うこと」「第三者サービスを利用すること」の3つが考えられる。
精神障がい者手帳3級の審査に落ちる理由と、再度審査を受ける際に落ちないための方法について解説してきました。
審査は診断書の内容で決まります。診断書には主治医が知っている範囲のことしか書けません。主治医に症状の程度や生活能力について言いづらい場合は、メモなどに書いて読んでもらうのも良いでしょう。
審査の準備とあわせて、今後の働き方を考える方もいらっしゃるでしょう。一般就労を目指す方を支える就労移行支援は、手帳がなくても利用できる場合があります。
例えば「ミラトレ」もその一つ。働くためのスキルや自信を高めるトレーニングを通じて、就職活動から職場に慣れるまで、手厚いサポートを受けられます。
まずは情報収集として、どんな支援があるか見てみませんか?