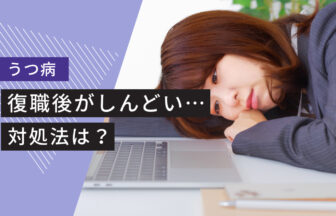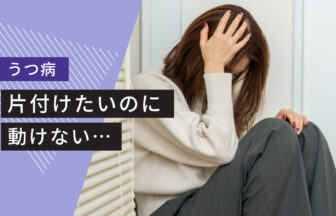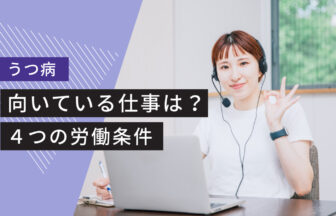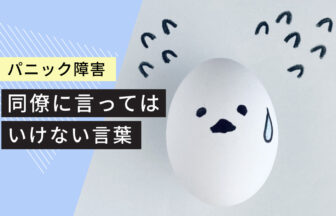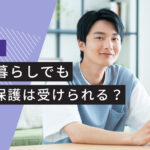うつ病が原因で無職の期間が長くなると
「このままじゃダメだ・・・でも、一体どうしたらいいんだろう・・・」
と焦りの気持ちになる方が多いです。
この記事を読んでいるあなたも、うつ病で無職の今、焦りと不安で押しつぶされそうな日々を送っていませんか?
うつ病で無職の状態が続くと、金銭面や将来への焦りや不安が大きくなりますよね。しかし、焦りは禁物です。うつ病が回復していない状態での就職活動は、心身の負担を増やして症状を悪化させる可能性があります。
一方で、うつ病の回復に専念して正しいステップを踏むことで、少ない負担で社会復帰することができます。
うつ病で無職になり焦りを感じている方に向けて
- うつ病が回復する前に就職活動してはいけない3つの理由
- 無職で焦らないための対処法3選
- うつ病で無職の方が利用できる経済支援とは?
- うつ病で無職の方が利用できる就労支援とは?
について解説します。
この記事が、あなたの不安を軽減させ、再出発への一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
うつ病が回復する前に就職活動してはいけない3つの理由

無職の期間が続くと「そろそろ働かなきゃ…」と焦ってしまいますよね。しかし、うつ病が回復しきる前に就職活動を始めると、うまくいかずに余計に自信を失うことになりかねません。
ここでは、うつ病が回復する前に就職活動をしてはいけない理由を3つ解説します。
再発のリスクが高まる
うつ病の回復途中で就職活動を始めると、うつ病の再発リスクが高まります。
就職活動は、情報収集や面接など心身のエネルギーを要します。回復が不十分な状態では、これらのストレスに対処しきれず、症状が悪化してしまう可能性が高いです。
厚生労働省のうつ病に関する調査によると、うつ病の再発率は約60%もあり、その後、再発を繰り返すと再発率が高くなるとされています。焦って就職できたとしても、仕事内容や人間関係のストレスから再発し、結果的に長期的な就労が難しくなってしまうかもしれません。
まずは、焦らずにうつ病の回復に専念しましょう。「もう大丈夫」と感じても、主治医と相談しながら、慎重にステップを踏むことが大切です。
ミスマッチにつながる
回復が不十分な状態での就職活動は、「早く就職しなければ」という焦りから冷静な判断を鈍らせ、ミスマッチを引き起こしやすくなります。
具体的には、
- 雇用条件
- 企業文化や働き方
- 業務内容
- スキルや能力
- 人間関係
など、様々な要素でミスマッチが生じる可能性が考えられます。
中小企業庁の調査(2015年版)によると、中小企業での採用後3年間の離職率は、中途採用では約3割、新卒採用では4割を超えるという結果もあります。
焦りから自己分析や企業研究を十分に行わずに就職してしまうと、「こんなはずではなかった」と早期離職につながり、さらなる精神的な負担を抱え込むことになるかもしれません。
自己肯定感が低下する可能性がある
うつ病は、ネガティブ思考になりやすく、「どうせ自分なんて…」と自己否定的な考えに囚われがちです。この状態で焦って就職活動を始めても、ネガティブ思考が邪魔をし、面接などで本来の力を発揮できない可能性があります。
不採用が続けば、「やっぱり自分はダメなんだ…」と自己肯定感が著しく低下し、さらなる悪循環に陥ってしまうかもしれません。
無職で焦らないための対処法3選
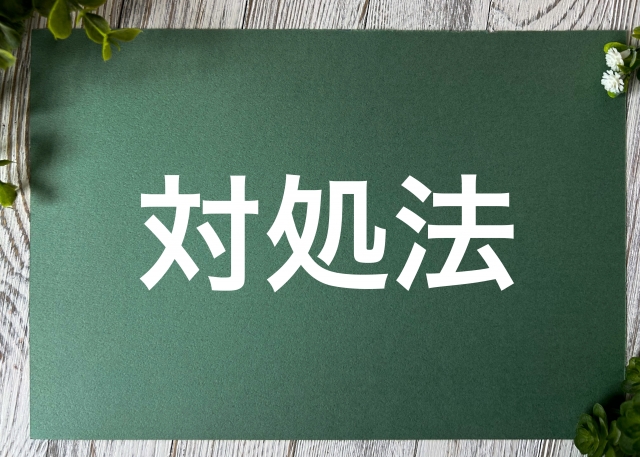
焦りは禁物とわかっていても、不安や焦燥感に駆られてしまうのは当然のことです。ここでは、焦燥感を和らげ、心の余裕を取り戻すための具体的な対処法を3つ紹介します。
周囲の人と比べるのをやめる
SNSなどで同年代の活躍を目にすると、「自分だけ取り残されている…」と焦ってしまうかもしれませんね。しかし、うつ病からの回復には個人差があり、社会復帰のタイミングも人それぞれです。
他人と比較するのではなく、
- SNSから距離を置く
- 規則正しい生活リズムを心がける
- 軽い運動を取り入れる
など、今の自分にできることに集中することが大切です。
焦りを感じることもあると思いますが、「今は自分にできることをやろう」と前向きな気持ちで、一歩ずつ進んでいきましょう。
焦りの原因を整理する
漠然とした焦燥感の正体を突き止め、具体的な対策を立てることで、気持ちが楽になることがあります。
例えば、
- 経済的な不安が大きい場合は、経済支援制度を調べる
- 社会復帰への不安が大きい場合は、就労支援制度を調べる
など、焦りの原因を具体的にすることで、解決策が見えやすくなります。解決策が見つかれば、すぐに行動に移せなくても構いません。解決策があるという安心感を持つだけでも、気持ちは楽になるはずです。
まずは、自分が何に不安を感じているのか原因を整理し、解決策はないか考えてみてください。
「今できること」に目を向け、小さな積み重ねを実感する
無職の焦りは、「何もしていない」と感じることから生じることが多いです。 焦りの気持ちを軽減させるには、「今できること」を見つけて、小さな一歩を踏み出すことが大切です。小さな一歩を踏み出すと言っても、簡単なことで構いません。
例えば、
- 生活リズムを整える
- 趣味や運動をしてみる
- 情報収集をする
など、どんな小さなことでも構いません。「前に進んでいる」という実感は、自信につながり、焦燥感を和らげてくれるでしょう。
うつ病で無職の方が利用できる経済支援とは?

「生活の不安が大きくて焦る…」
そんな悩みを抱えていませんか? うつ病で無職の状態が続くと、経済的な不安が大きくなってしまいますよね。
ここでは、うつ病で無職の方が利用できる経済支援を3つご紹介します。
自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、うつ病などの精神疾患の治療にかかる医療費の自己負担額を軽減する制度です。
通常、医療機関で支払う医療費の自己負担額は3割ですが、自立支援医療制度を利用することで、自己負担額が1割に軽減されます。この制度により、通院や薬代などの経済的負担が大幅に軽減されることで、安心して治療に専念することができます。
より詳しい情報や申請方法については、
- お住まいの市区町村の役所
- 精神保健福祉センター
などの窓口に相談してみてください。
自立支援医療制度については、以下の記事でも詳しく解説しております。
また、全国の精神保健福祉センターは、以下のリンクから調べることができます。
障害年金
障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出た場合に支給される年金です。 うつ病で一定の障がい状態にあると認められた場合に支給されます。
障害年金は、障がいの程度によって1級から3級までの等級があり、支給額が異なります。無職の方でも、過去に厚生年金や国民年金を納めていた期間があれば、受給できる可能性があります。
具体的な金額は
障害基礎年金の金額(令和7年度)
| 障害等級 | 金額 |
|---|---|
| 1級 | 1,039,625円(月額 86,635 円)+ 子の加算 |
| 2級 | 831,700円(月額 69,308 円)+ 子の加算 |
| 障害等級 | 金額 |
|---|---|
| 1級 | 1,039,625円(月額 86,635 円)+ 子の加算 |
| 2級 | 831,700円(月額 69,308 円)+ 子の加算 |
障害厚生年金の金額(令和7年度)
| 障害等級 | 金額 |
|---|---|
| 1級 | 障害基礎年金(1,039,625 円+子の加算) + 報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金 |
| 2級 | 障害基礎年金(831,700円+子の加算) + 報酬比例の年金+配偶者加給年金 |
| 3級 | 報酬比例の年金(最低保障623,800円(月額51,983 円)) |
| 障害手当金 | 報酬比例の年金の2年分(最低保障1,247,600円)※一時金 |
| 障害等級 | 金額 |
|---|---|
| 1級 | 障害基礎年金(1,039,625 円+子の加算) + 報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金 |
| 2級 | 障害基礎年金(831,700円+子の加算) + 報酬比例の年金+配偶者加給年金 |
| 3級 | 報酬比例の年金(最低保障623,800円(月額51,983 円)) |
| 障害手当金 | 報酬比例の年金の2年分(最低保障1,247,600円)※一時金 |
障害年金の請求は、年金事務所または市区町村役場の窓口で行います。また、請求には医師の診断書や病歴や就労状況等申立書などの書類が必要です。
より詳しい情報は、日本年金機構のウェブサイトや年金事務所で確認できるので確認してみてください。
生活保護
生活保護は、病気やケガなどで働くことができなくなり、収入が最低生活費を下回る場合に、国が生活を保障する制度です。特に、うつ病などの精神疾患は、症状により就労が著しく困難となるケースも少なくありません。経済的な不安は、病状を悪化させる要因にもなり得るため、生活保護は安心して療養に専念するための重要な選択肢となります。
生活保護の金額の目安としては、
- 単身者の場合:月額10万円~13万円程度
- 夫婦2人世帯の場合:月額15万円~18万円程度
となります。
ただし、これらの金額はあくまで目安であり、実際の支給額は個別の状況によって異なります。より正確な情報を知りたい場合は、厚生労働省のサイトや地域の福祉事務所へ問い合わせてみると良いでしょう。
生活保護の詳しい情報が気になる場合は、下記のサイトを参考にしてください。
生活保護を検討する際、「自分なんかが申請して良いのだろうか…」と、生活保護の利用に対して、ためらいや不安を感じるかもしれません。
しかし、一人で悩まず、福祉事務所の相談窓口に相談してみてください。専門の相談員が、あなたの状況に合わせた適切なアドバイスと支援を提供してくれますよ。
うつ病で無職の方が利用できる支就労支援とは?

「うつ病が回復しても社会復帰できるか心配…」「スモールステップで働く力を身につけたい」そんな悩みを抱えている場合は、就労支援を検討してみてください。
就労支援はサポート体制が整っているため、少ない負担で社会復帰を目指すことができます。ここでは、うつ病で無職の方が利用できる就労支援を3つご紹介します。
ハローワーク
ハローワークは、厚生労働省が運営する全国規模の就職支援機関で、就労支援の一環としてさまざまなサポートを提供しています。うつ病などの疾患を抱える方や、長期間無職の方に対しても支援制度が整っているため、少ない不安で社会復帰を目指すことが可能です。
ハローワークで受けられる主な就労支援は、次のものがあります。
職業相談、職業紹介
職業相談や職業紹介では、求職者の状況に応じて適切な仕事を紹介してくれます。体調や希望に合わせた働き方の相談が可能です。
障がい者雇用支援
障がい者雇用支援では、障がい者向け求人の紹介や職場定着のサポートを受けることができます。
職業訓練(ハロートレーニング)
職業訓練では、再就職に向けたスキルアップの機会を提供してくれます。無料または低額で、パソコンスキルや資格取得を目指せるため金銭的な負担も少ないですよ。
生活支援(求職者支援制度)
生活支援では、一定の条件を満たすことで給付金をもらいながら職業訓練を受けることができます。給付金をもらうことができれば、心の余裕を保ちながら無理なくスキルを習得し就職や再就職を目指すことができます。
トライアル雇用
トライヤル雇用では、一定期間(原則三ヶ月)お試しで働きながら企業との相性を確認できる制度です。仕事の適性や会社の雰囲気を確認しながら働けるため、ミスマッチを防ぐことができ、安心して働くことが可能です。
上記で紹介したハローワークの支援を活用することで、少ない不安で社会復帰を目指せるでしょう。
就労のことで不安なことや知りたいことがあれば、ホームページを確認したり、ハローワークに相談したりしてみましょう。経験豊富な職員の方が適切なアドバイスをしてくれます。
トライアル雇用については、以下の記事でも詳しく解説しております。
就労移行支援
「働きたいけれど、自信がない」「体調に波があり、安定した就労が難しい」と感じている方には、就労移行支援をおすすめします。
就労移行支援とは、障がいや病気を抱える方が一般企業への就職を目指すための支援を受けられる福祉サービスです。
就労移行支援では、専門スタッフのサポートを受けながら、
- ビジネスマナー
- PCスキル(Word、Excel、PowerPointなど)
- 生活スキル(生活リズムの確立、体調管理、金銭管理など)
- 職場体験・実習
- 就職活動(必要書類の書き方、面接など)
など、働く上で必要なスキルを幅広く学ぶことが可能です。
就労移行支援の利用料は、原則として利用したサービス費用の1割を利用者が負担する仕組みです。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されており、多くの方が無料で利用しています。 自治体によって助成制度もあるため、まずはお住まいの地域の ハローワークや相談支援事業所 に相談してみるのがおすすめです。
就労移行支援を活用すれば、焦らずに「自分に合った働き方」を見つけることができます。無理なく社会復帰を目指したい方は、ぜひ検討してみてください。
就労継続支援A型・B型
「サポートを受けながらお金を稼ぎたい」という場合は、就労継続支援がおすすめです。就労継続支援とは、障害や難病などにより一般の会社での就労が困難な方が、働くための訓練や支援を受けられる福祉サービスです。
一定の支援を受けながら少ない負担で働けるので、「いきなり正社員で働くのは怖い」「自分のペースで働きたい」という方でも安心して働けますよ。
就労継続支援をうまく活用することで、
- 働くことへの自信
- 生活リズムの改善
- コミュニケーション能力の向上
- 就労スキルの向上
などを得ることができます。
また、就労継続支援にはA型とB型の2種類があります。A型とB型の違いは下記の表でまとめていますので、参考にしてください。
| A型事業所 | B型事業所 | |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | なし |
| 収入 | 月額7〜8万円が給与として支払われる (最低賃金が保証されている) |
月額2〜3万円が工賃として支払われる (令和4年度の工賃の全国平均は時間額243円) |
| 業務内容 | 清掃・封入発送・農作業・カフェ・動画編集、 PC業務など |
パンやお菓子の製造、 販売・農作業清掃作業・梱包など |
| 対象者 | 一般就労は困難だが雇用契約を結んで働ける人 | 雇用契約を結んで働くことが難しい人 |
| 年齢制限 | 原則として18歳から65歳未満 | 年齢制限なし |
| A型事業所 | B型事業所 | |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | なし |
| 収入 | 月額7〜8万円が給与として支払われる (最低賃金が保証されている) |
月額2〜3万円が工賃として支払われる (令和4年度の工賃の全国平均は時間額243円) |
| 業務内容 | 清掃・封入発送・農作業・カフェ・動画編集、 PC業務など |
パンやお菓子の製造、 販売・農作業清掃作業・梱包など |
| 対象者 | 一般就労は困難だが雇用契約を結んで働ける人 | 雇用契約を結んで働くことが難しい人 |
| 年齢制限 | 原則として18歳から65歳未満 | 年齢制限なし |
実際にサービスを開始するためには、医師の診断書や市区町村などの自治体から発行される受給者証の交付が必要です。詳しく知りたい方は、お住まいの市区町村の障がい福祉窓口に相談してみると良いでしょう。
就労移行支援や就労継続支援A型・B型については、以下の記事でも詳しく解説しております。
まとめ
- うつ病回復前に就職活動をすると、うつ病の再発や企業とのミスマッチ、自己肯定感が低下する可能性があるため、焦らず回復に専念することが大切
- 焦燥感を抑えるためには、周囲の人と比べない、焦りの原因を整理する、今できることに目を向け小さな積み重ねを実感する方法があり、少しずつ実践することが大切
- うつ病で無職の人が利用できる経済支援として、医療費負担を軽減する「自立支援医療制度」、日常生活や仕事に支障がある場合に支給される「障害年金」、最低生活費を下回る場合に生活を保障する「生活保護」がある
- うつ病で無職の人が利用できる就労支援として、職業相談や職業訓練を提供する「ハローワーク」、一般企業への就職を目指す訓練を行う「就労移行支援」、雇用契約を結び働く訓練を行う「就労継続支援A型・B型」がある
無職の期間が続くと「自分なんかダメだ…」とネガティブな気持ちになりやすいですが、まずは症状を回復させることに専念することが大切です。
また、今回ご紹介した対処法に取り組んだり制度を活用したりして焦りを少しずつ減らしていけると良いですね。