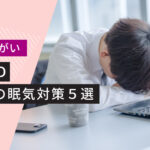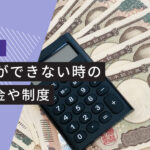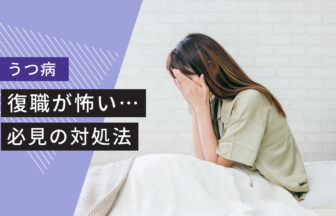うつ病は目に見えにくい病気であるため、身近な親や家族に理解してもらえないことがありますよね。
この記事を開いているあなたは、
「うつ病は甘えだと言われ続けて、自分が悪いと思うようになった……」
このような辛い経験をしていませんか?
- どうしてうつ病は理解されにくいのか
- 親にうつ病を理解してもらうための伝え方
- うつ病でも家族と良好な関係を築くために伝えるべき事
- うつ病の人が利用できる相談口
を解説していきます。
親や家族に理解してサポートをしてもらうことは、うつ病の治療や回復に欠かせません。
この記事を通して、あなたや親族の方に少しでも役立つ情報になれば幸いです。
うつ病が理解されない4つの理由

うつ病は、本人だけでなく周囲の人々にとっても理解が難しい病気です。 特に、身近な親や家族に理解してもらえないと、孤独感や焦燥感が募り、症状を悪化させてしまうこともあります。
なぜ、親や家族にうつ病を理解されにくいのでしょうか?
以下では、4つの理由について解説していきます。
症状が周りには分かりにくい
一つ目は「症状が分かりにくいこと」です。
例えば、風邪であれば咳や発熱といった症状が見られます。ですが、うつ病の場合は気分の落ち込みや意欲の低下といった内面的な変化が中心です。
そのため周囲からは、「少し疲れているだけ」「気持ちの問題だ」と軽く見られてしまうことがあります。
誤解されやすい症状が多い
二つ目の理由は、「うつ病には誤解されやすい症状が多い」ことです。
うつ病の症状は日によって変動することが多いため、調子の良い日には普段と変わらないように見えることがあります。「ぼーっとしてしまう」「無気力になる」などの症状は周囲の人からわかりにくいため、誤解を招きやすいのです。
そのため、親から見ると「以前と変わらない」「元気そうに見える」と感じられ、病気であることを信じてもらえないことがあります。
本人も「うつ病」である自覚がない
うつ病は、初期段階では目立った症状が現れにくく、「最近、気分が落ち込みやすい」「何をするにも億劫だ」と感じても、それを病気のサインだと自覚できないことがあります。
また、「自分がうつ病であるはずがない」「こんなことで病院に行くのは恥ずかしい」といった気持ちから、受診をためらってしまう人も珍しくありません。そのため、親に相談するタイミングを逃してしまい、結果的に理解を得るのが遅れてしまうことがあるのです。
うつ病の症状については、以下の記事でも詳しく解説しております。
親に打ち明けづらい
うつ病であることを親に打ち明けるのは、勇気のいることです。
「迷惑をかけたくない」
「親に否定されるのではないか」
といった不安から、なかなか言い出せないという方もいるでしょう。
特に、親子関係があまり良好でない場合や、過去に親御さんから否定的な言葉を言われた経験がある場合は、打ち明けることへの抵抗感が強くなります。自分がどういった苦しみを抱えているかについて、なかなか打ち明けることができないという方も少なくありません。
その結果、あなたがうつ病であると認識をしてもらえないこともあります。
親にうつ病を理解してもらう伝え方3選!

親にうつ病を理解してもらうことは、治療を進める上で非常に重要です。しかし、どのように伝えれば良いのか悩んでしまう方も多いでしょう。
ここでは、親にうつ病を理解してもらうための効果的なアプローチを3つご紹介します。
病気の症状や治療の仕方を伝える
一つ目は「病気の症状や治療の仕方を伝える」ことです。
うつ病がどのような病気なのか、具体的にどのような症状が現れるのかを親に理解してもらうことが大切です。
単に「気分が落ち込む」と伝えるのではなく、
「今まで楽しめていた趣味に全く興味がわかない」
「食欲がなくて、何を食べても味がしない」
「夜中に何度も目が覚めて、ぐっすり眠れない」
といった具体的な症状を伝えましょう。
具体的にどんな症状で苦しんでいるかを伝えることで、親もあなたの状態を理解しやすくなります。
また、「薬を飲んでいること」や「カウンセリングに通っていること」など、具体的な治療法を可能な範囲で説明することも大切です。うつ病はすぐに治る病気ではなく、治療には時間が必要で、症状が良くなったり悪くなったり繰り返すことも伝えられると安心でしょう。
親の正しい理解を得て家庭に安心できる居場所を築けると、うつ病の治療に効果的です。
主治医や専門家の意見を伝える
2つ目は「主治医や専門家の意見を伝える」ことです。
診察の結果や今後の治療方針について医師から説明を受けた場合は、その内容を親御さんに伝えましょう。医師の言葉は、とても強い説得力を持ちます。
また主治医に相談して、親宛の手紙を書いてもらったり、診断書を渡したりするのも有効な手段です。もし手紙を書いてもらえる場合は、あなたの病状や治療の必要性、そして家族の協力が不可欠であることなどを記載してもらうと良いでしょう。
なお、専門医に相談する場合は、実際に現れている症状の傾向に合った病院等へ行くことが重要です。
以下の記事でも詳しく解説しておりますので、併せて読むことをオススメします。
診察や専門家による支援の場に同席してもらう
3つ目は「診察や専門家による支援の場に同席してもらう」ことです。
直接、医師から病状や治療方針の説明を受けることで、客観的な視点からあなたの状態を理解しやすくなります。受診の際、親に同席をしてもらい病気の症状や今後の治療方針を共有することで、あなたや親の疑問や不安を解決できます。
また、家族向けのカウンセリングを受けてもらうのも効果的です。家族向けのカウンセリングを通してうつ病に対する誤解や偏見を解消できると、あなたと親の間のコミュニケーションが円滑になり、家庭内でも適切なサポートを受けられるようになるでしょう。
うつ病をわかってもらえない時に伝えるべきこと3選

「親にうつ病をわかってもらえない……」と悩んでいる時は、伝えるべき内容を整理することが大切です。ここでは、家族と良好な関係を築くために、特に伝えるべき3つのことについて解説します。
出来ること・出来ないことを伝える
今のあなたが「出来ること」と「出来ないこと」を明確に伝えるよう意識しましょう。うつ病の症状によって、今まで当たり前にできていたことが難しくなる場合があります。
例えば、以前は毎日こなしていた家事が、全く手に付かなくなったり、集中力が続かず仕事に支障が出たりすることもあるでしょう。「今は料理を作るのが難しい」「掃除ができない」など、具体的に何ができないのかを伝えることが大切です。
同時に、無理なくできることを伝えてみましょう。例えば、「洗濯ならできる」「短い時間なら話すことができる」など出来ることを話すことで、親や家族はどのようにサポートすれば良いのかをイメージしやすくなります。
助けて欲しいことを伝える
2つ目は、あなたが「何を助けてほしいのか?」を伝えることです。
単に辛いと伝えるだけでは、具体的にあなたがどういった支援を求めているのか理解してもらえない場合があります。
「不安に思っていることの話を聞いてほしい」
「一緒に病院に行ってほしい」
など、具体的なお願いをすることで、家族はあなたをサポートしやすくなります。
うつ病で助けを求めることは、決して恥ずかしい事ではありません。 むしろ周りにサポートしてもらうことで、うつ病の早期回復に期待できます。遠慮せずに、本当に困っていることを伝えるようにしましょう。また、助けてもらった際には、感謝の気持ちを伝えることも大切です。
うつ病の症状で理解して欲しいことを伝える
3つ目に「うつ病の症状で理解して欲しいこと」を伝えてみましょう。
うつ病の症状には以下の様なものがあります。
- 一人になりたい
- 急に怒りっぽくなってしまうことがある
- 些細な事で泣き出してしまうことがある
- 引きこもりがちになってしまうことがある
あなたにもこのような症状がある場合は、事前に説明し理解を求めることが大切です。理解を得られると、家族はあなたを責めることなく、温かく見守ってくれるでしょう。 無理強いせず、あなたのペースに合わせて接してくれるようになることで、安心して治療に専念できる環境が整います。
また、休養が必要になった際には、家族からの理解も含めて休み方も重要になってきます。
以下の記事でも詳しく解説しておりますので、併せて読むことをオススメします。
うつ病のある人が利用できる相談窓口を5つ紹介!

うつ病を抱えていると、
「うつ病の治療や今後の生活はどうするべきか、正しい情報を得たい」
と感じることがあるでしょう。
そんな時に頼りになるのが、様々な相談窓口です。
ここでは、うつ病のある人が利用できる相談窓口をいくつかご紹介します。それぞれの窓口には特徴があり、あなたの状況やニーズに合わせて選ぶことができます。
精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは、各都道府県・指定都市に設置されている専門機関です。
うつ病を含む精神疾患に関する相談や、社会復帰に関する支援を行っています。精神科医や精神保健福祉士などの専門家が在籍しており、専門的な知識に基づいたアドバイスを受けることができます。また、地域における精神保健福祉活動の拠点としての役割も担っており、様々な研修会やイベントなども開催されています。
以下のリンクから、全国の精神保健福祉センターそれぞれのサイトへとアクセスできます。自分の住む地域の最寄りの施設へとお問い合わせください。
保健所
保健所は、地域住民の健康をサポートする行政機関です。
うつ病に関する相談も受け付けており、保健師や医師などが相談に応じてくれます。精神保健福祉センターと同様に、専門的な知識に基づいたアドバイスを受けることができます。
また、必要に応じて医療機関の紹介や、地域の福祉サービスに関する情報提供も行っています。地域に密着した相談窓口であり、気軽に相談しやすいのが特徴です。
役所の障がい福祉課
役所の障がい福祉課は、障がい者手帳の申請や、障がい福祉サービスの利用に関する相談を受け付けている窓口です。
うつ病によって日常生活や社会生活に困難が生じている場合、障がい者手帳を取得することで、様々な福祉サービスを利用できる可能性があります。
障がい福祉課では、手帳の申請手続きや、利用できるサービスについて詳しく教えてくれます。
こころの健康相談ダイヤル
こころの健康相談ダイヤルは、うつ病の悩みや不安を電話相談できる窓口です。専門の相談員があなたの気持ちを受け止めて、アドバイスを提供してくれます。
匿名で相談できるため、誰にも相談できない悩みを抱えている場合に、気軽に利用することができます。24時間体制で対応している窓口もあり、緊急時の相談にも対応しています。
家族会や当事者会
家族会や当事者会は、うつ病を抱える本人や、その家族が集まり、互いに支え合うためのグループです。同じような悩みや経験を持つ人々と交流することで、孤独感を解消したり、新たな視点を得たりすることができます。
また、情報交換の場としても活用されており、治療や生活に関する有益な情報を得ることができます。
まとめ
- うつ病が理解してもらいにくい要因は、主に「症状が周りには分かりにくい」「周りからは重症に見えなく、怠けていると勘違いされる」「本人もうつ病である自覚がない場合がある」という要因がある
- 親にうつ病を理解してもらうために「病気の症状や治療の仕方を伝える」「主治医や専門家の意見を伝える」「診察や専門家による支援の場に同席してもらう」という工夫をすることで、理解を得やすくなる
- うつ病でも家族と良好な関係を築くためには「出来る事・出来ないこと」「助けて欲しいこと」「うつ病の症状で理解して欲しいこと」を伝えると良い
- うつ病のある人が利用できる相談窓口は「精神保健福祉センター」や「保健所」「役所の障害福祉課」などがある
ここまでの記事を読んでいかがだったでしょうか?
うつ病は、ストレス社会と呼ばれる現代では珍しい病気ではなく、誰にでも発症する可能性があるものです。
しかし、うつ病は目に見えにくい病気であるが故に、周りの人や親に理解してもらえないことがあります。
それでも、根気強く、そして丁寧にあなたの気持ちを伝えていく事が大切です。あなたが思っていることを、隠さず正直に伝えてみましょう。
また、うつ病の発症に、発達障がいなど別の疾患が関係している場合もあります。
以下の記事でも詳しく解説しておりますので、併せて読むことをオススメします。
この記事で、あなたとご家族が心を通わせ、より良い関係を築くための一歩となれば幸いです。