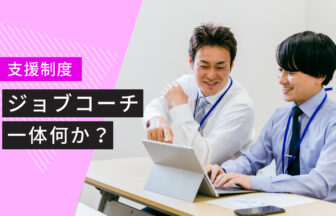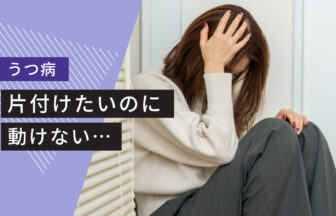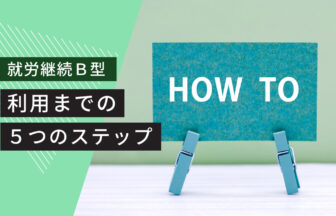うつ病は仕事や生活に深刻な影響を与えてしまうため、発症してしまうと「仕事ができなくなる」という方が少なくありません。働けなくなると、収入面で困ってしまいますよね。
「助けてほしいけれど、どこに頼ればいいのかもわからない…」
あなたは、こういった悩みを抱えていませんか?
- うつ病で働けないときに利用できる経済支援制度
- 支援制度の受け方がわからないときの相談先
- 経済支援制度を受けても生活が苦しい場合はどうすればいいか
- 社会復帰を助けてくれる支援機関
について解説していきます。
うつ病で働けない時に利用できる、経済的支援制度は?

うつ病で働けなくなったときに利用できる経済的支援制度には、下記のようなものが設けられています。
- 傷病手当金
- 労災保険
- 失業保険
- 障害年金
- 特別障害給付金
- 精神障がい者保健福祉手帳
制度によって受給・利用できる条件や期間などに違いがあるため、あなたの状況に合った適切な支援制度を利用しましょう。
傷病手当金
傷病手当金とは、
被保険者が病気やケガで仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給される給付金です。引用:傷病手当金|病気やケガで4日以上会社を休んだ時|全国健康保険協会
この記事では全国健康保険協会で説明されているものを解説します。
保険を扱う組織ごとに独自の制度や計算方法が行われている場合があるので、詳しくは各自が加入している保険を参照してください。
傷病手当金は「休職中の方」を対象とした制度であり、支給条件は下記の通りです。
- 健康保険料を払っている(国民健康保険の加入者は対象外)
- 業務外の病気や怪我で療養中である(労災保険の対象外で、健康保険が適用される治療であること)
- 療養のために働けない
- 4日以上休んでいる
- 給与の支払いがない(一部支給されている場合は傷病手当金から給与支給分を減額して支給可能)
申請期限は上記の条件を満たしてから2年以内です。申請が通れば最大1年6か月間、もともとの給与額の約3分の2を受け取ることができます。後述する失業保険のように年齢ごとの上限額はありません。
休職中でも収入が断たれる心配がなくなるため積極的に利用したい制度です。ただし、支給期間中に発生した社会保険料の自己負担分は払い続ける必要があることに注意しましょう。
労災保険
労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。引用:労災補償|厚生労働省
うつ病の原因が「過剰な長時間労働」や「ハラスメント」である場合は、労災保険の申請をするのも1つの選択肢です。
一般的にうつ病などの精神障害による労災認定は厳しいといわれていますが、
- 証拠が揃っている(タイムカードや日記・日報など)
- 複数人が被害を訴えている
などの状況であれば申請が通る可能性があります。
申請が通れば状況に応じた補償を十分に受けられるので、休職期間中の収入問題を大きく解決できるかもしれません。心当たりがある場合は、一度管轄の部署に連絡してみましょう。
失業保険
失業保険とは、雇用保険に加入していた方が原因を問わず失業した場合に、失業期間中の生活を維持するための金銭給付が受けられる制度です。
失業した方は、下記の条件を満たしていれば雇用保険の対象です。
- 働ける状態であるにもかかわらず就職がすぐにできない
- 失業から30日以上が経過している
- 離職してから2年間以内に、被保険者期間が通算12か月以上ある
通常、失業保険の申請期限は1年間です。ただし、うつ病で働けない状態(働ける状態でなければ失業保険は受けられない)であれば離職から30日経過した後の30日以内に「受給資格を3年間延長する」ための申請が可能です。
失業保険は申請が通れば、雇用保険の加入期間や離職理由に応じて90~360日の間受給ができます。
また、受給できる金額は、
となっています。
例えば、月の賃金が概ね20万円前後であれば15万円程度、30万円前後であれば20万円程度となります。
ただし、
- 傷病手当金との同時受給は不可
- 受け取れる金額には年齢ごとの上限がある
といった点があるのでご注意ください。
就業促進定着手当
もし、再就職し再就職先での賃金が離職前の賃金より低い場合、「就業促進定着手当」が受けられる場合があります。
支給の対象となるには、条件があります。
- 再就職手当の支給を受けている
- 再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されている
- 所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が離職前の日額を下回る など
うつ病が軽くなり、再就職した場合にこのような制度が利用できる場合があります。再就職後にも受けられる制度がある事を覚えておくと良いでしょう。
障害年金
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。引用:障害年金│日本年金機構
障害基礎年金と障害厚生年金は同じ障害年金制度ですが、利用できる対象や金額等が異なります。
障害基礎年金
条件
- 初診日
国民年金の加入期間か、20歳前、または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に、障がいの原因となる病気やけがの初診日があること。 - 障がいの状態
障害認定日(または障害認定日以後に20歳に達した日)、障害等級表の1級または2級に該当。 - 保険料の納付
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金の保険者期間、共済組合の組合員期間含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、納付の条件は不要。
年金の支給額(年額)
- 1級
1,039,625円 - 2級
831,700円
生計を維持されている子供がいる場合、加算あり
障害厚生年金
条件
- 初診日
厚生年金保険の被保険者期間の間に、障がいの原因となる病気やけがの初診日があること。 - 障がいの状態
障害認定日に、障害等級表の1~3級のいずれかに該当。ただし、障がいの状態が障害認定日後に重くなった場合、障害厚生年金を受け取れる場合がある。 - 保険料の納付
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金の保険者期間、共済組合の組合員期間含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
年金の支給額(年額)
- 1級
(報酬比例の年金額)×1.25+〔配偶者の加給年金額(239,300円)〕※ - 2級
(報酬比例の年金額)+〔配偶者の加給年金額(239,300円)〕※ - 3級
(報酬比例の年金額)
※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合加算
上記は2025年度4月時点での情報です。条件や支給額に変更がある場合もあるため、最新の情報は日本年金機構のホームページを確認してください。
障害年金の申請には障害認定日以降に発行された診断書が必要です。障害認定日は基本的に、障がいの原因となった病気・けがの初診日から1年6か月を過ぎた日を指します。そのため、原則として初診日から1年6か月を経過している必要があります。
うつ病での申請の場合、障害等級は2級または3級と判断されることが多く、症状が回復するまでは年金が受給できます。
ただし、障害年金の障害等級は、後述する障害者手帳とは基準が異なり、手間がかかる厳しい審査が行われるため、障害者手帳が取得できたからといって、障害年金も必ず受給できるとは限りません。また、失業保険との同時受給は可能ですが、先述した傷病手当金と同時に受給する場合、傷病手当が減額されるため、注意が必要です。
障害年金の申請を考えている場合は、年金事務所や年金相談センターなどの専門窓口に相談してみましょう。
特別障害給付金
特別障害給付金は、初診日に国民年金に任意加入していなかったことで障害年金を受給できない方の救済措置として金銭を給付する制度です。ただし、受給できる方は限られており、昭和61年度に国民年金への強制加入が義務化される以前に任意加入していなかった方が対象者となります。
特別障害給付金の対象となる方は下記の通りです。
- 昭和61年4月~平成3年3月以前に初診日があり、国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった被用者等(会社員や公務員など)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日がある方
上記のいずれかに当てはまり、65歳になる前に障害年金の1〜2級相当の状態となった方であれば受給することができます。
2025年度時点での支給額は、下記のようになっています。
| 障害基礎年金1級相当の方 | 基本月額56,850円 |
|---|---|
| 障害基礎年金2級相当の方 | 基本月額45,480円 |
| 障害基礎年金1級相当の方 | 基本月額56,850円 |
|---|---|
| 障害基礎年金2級相当の方 | 基本月額45,480円 |
障害年金よりも少額ですが、条件に当てはまる可能性がある方は年金事務所などに相談すると良いでしょう。
精神障がい者保健福祉手帳
精神障がい者保健福祉手帳は、一定程度の精神障がいの状態にあることを認定するものです。
精神障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。引用:精神障害者保健福祉手帳|障害者手帳│厚生労働省
精神障害者保健福祉手帳は、てんかんや発達障がいを含む、うつ病などの何らかの精神障がいで日常生活や社会生活に支障がある方を対象に発行される、障がいがある事の証明書です。
精神障がい者保健福祉手帳には、1~3級までの等級があり、障がいの状況によって定められます。
直接経済的な支援を受けられるものではありませんが、所持、または必要に応じて提示することで、下記のような支援・サービスを受けられます。
- 税金の控除・減免
- 電車・バスなどの公共交通機関の料金割引
- 医療費の助成
- 福祉手当の受給 など
上記に挙げたものは手帳の所持によって受けられるサービスの一例です。自治体や事業者によっては実施していない場合や、利用条件が限られている場合があるため、よく確認しましょう。
精神障がい者保健福祉手帳の申請は、初診日から6か月が経過していれば申請することができます。取得条件は先述した障害年金などと比較すると容易ですが、診断書の発行は健康保険の対象外であり、お金がかかります。
病院の主治医やケースワーカーの方と相談しつつ、取得を検討しましょう。
うつ病の治療に役立つ医療費助成制度

うつ病の治療には継続した通院が必要になるため、医療費の負担が大きくなる場合があります。
ここでは、継続した通院が必要な際に医療費の負担を抑えられる制度を2つ紹介します。
自立支援医療制度
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。引用:自立支援医療制度の概要|厚生労働省
うつ病の方も利用できる制度であり、
- 保険適用内の治療にのみ利用可能
- その月の医療費が一定額以上にならなかった場合の負担額は1割引になる
- 1か月の間に一定額以上の医療費がかかった場合、以降自己負担する必要がなくなる
という医療費の助成が受けられます。
利用する医療機関を登録して制度を利用します。うつ病の方の場合、通院している精神科・心療内科や薬局、精神科デイケアなどで利用できます。
自己負担の上限額はあなたの状況によって異なります。詳しくは下記をご覧ください。
自立支援医療制度については、下記の記事でも解説しています。
心身障害者医療費助成制度
心身障害者医療費助成制度とは、各都道府県などの自治体が行っている、障がい者を対象とした医療費助成制度です。
名称や利用できる条件は自治体によって異なりますが、多くの場合、精神障がい者保健福祉手帳の交付が基準の1つとなっています。助成される内容や給付方法も地域によって異なるため、詳しくはお住まいの地域にある医療保険や障害福祉の専門窓口への相談がオススメです。
支援制度の受け方がわからないときの相談先は?

多種多様な支援制度が存在しますが、条件や申請方法が複雑なことが多く、1人では難しいことも多いでしょう。うつ病を抱えている状態であればさらに難易度は上がります。
そのため、この項目ではそういった場合に相談できる機関をまとめました。参考にしていただけましたら幸いです。
病院の医師やカウンセラー・ケースワーカー
うつ病の方の場合、精神科や心療内科のような病院への通院をされていることでしょう。
まずは病院の医師やカウンセラーへ、障がい者手帳の取得や障害年金の受給などの生活支援制度を受けたい旨を話しましょう。
精神科や心療内科の場合、ケースワーカー(精神保健福祉士)が所属している場合があるため、ケースワーカーと相談しながら必要な支援へつなげてもらうことができます。ケースワーカーが所属していない場合でも、必要に応じてケースワーカーや、後述する支援機関を紹介してもらえます。
県外の病院へ通っている場合でも、状況に応じて対応してもらえるので、まずは相談がオススメです。
精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは、精神的な悩みについて幅広く相談できる支援機関です。
センターには基本的に医師が常駐しているため、うつ病の症状に悩んでいることを相談した場合、現在の状況に応じた具体的なアドバイスをもらうことができます。
「本当にどうすればいいのかわからない」、「何から始めればいいの?」といった場合の最初の1歩としてオススメです。
全国の精神保健福祉センターは下記から調べることができます。
全国の精神保健福祉センター|厚生労働省
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、障がい者の職業生活における自立を図る目的で全国に設置されている支援機関です。令和7年度4月時点で、全国338か所に設置されています。真ん中に「・」が入ることから「なかぽつ」と呼ばれることもあります。
就業と生活の両面での支援を行うために、ハローワークなどの支援機関と数多く連携しており、相談することで適切な自立支援を受けることができます。どこを利用すればいいか悩んでいる場合にはこちらへ相談してみましょう。
障害者就業・生活支援センターについては、下記の記事でも解説しています。
経済支援制度を受けても生活が苦しい場合の選択肢

ここまで、うつ病の方が利用できる支援制度について解説してきました。
しかし、これらの制度を可能な限り活用しても、生活が苦しいという方はいらっしゃるでしょう。生活が苦しいままでは、うつ病からの復帰もうまくいきません。
そういった場合は、下記の2点を検討してみましょう。
- 自立相談支援事業に相談する
- 生活保護を申請する
自立相談支援事業所
自立相談支援事業所とは、生活の苦しい方やその家族・関係者からの相談に応じ、個別の状況に合った計画を作成したうえで、
- 就労準備支援事業
- 居住確保給付金
- 一時生活支援事業
- 子どもの生活・学習支援事業
などの、相談者に必要な支援機関・制度の活用を案内してくれる支援機関です。
関係機関への同行や、就労支援員による就労支援、就労訓練の紹介などを受けることができます。
さまざまな相談に対応できるよう、包括的に事業を実施しているため、うつ病によって生活が苦しくなってしまった方でも適切な支援を受けられることが期待できます。必要に応じて、後述する生活保護の利用も相談できるため、生活が苦しくなったらなるべく早く、お住まいの自治体が設けている相談窓口を頼りましょう。
生活保護
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。引用:生活保護制度|厚生労働省
生活保護制度は、
- 資産を持っていない
- 病気やケガなどが理由で働けない
- ほかに利用できる公的制度がない
- 近親者の経済的支援が期待できない
のような条件を満たしていると認められた方を対象として、日常生活、医療サービス等に必要な費用の支給を行っている制度です。そのため、うつ病で生活が厳しくなった場合、利用すれば当面の金銭的不安を感じずに療養に専念することが可能です。
「生活保護を申請すると、怒られて追い返されると聞いた事がある…」
このような不安がある時は、生活保護の申請に詳しい方へ事前に相談したり、同伴を求めたりすると良いでしょう。
生活保護は世間的な風当たりが強いですが、その申請も利用も憲法によって保障された国民の権利です。あなたが本当に困っている場合は負い目に思わず、積極的に活用しましょう。
生活保護の利用については、先述した自立相談支援事業所や、お住まいの自治体の福祉事務所へ相談しましょう。
生活保護を申請したい方へ|厚生労働省
社会復帰を助けてくれる支援機関3選

この項目では、うつ病で働けなくなってしまった方の社会復帰を助けてくれる支援機関を3つご紹介します。
就労継続支援A型・B型事業所
就労継続支援事業所は、一般企業への就職が現状困難な障がい者の方へ、就労の機会を提供している支援機関です。A型とB型が存在しており、それぞれ雇用形態などが異なります。
賃金は一般企業よりも低いですが、障がい者への配慮がされている状況で働くことができるため、うつ病からの社会復帰の足掛かりとして適しています。「ひとまず働き始めたい」という場合は利用を検討してみましょう。
A型とB型の違いなど、就労継続支援事業所については下記の記事で解説しています。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、主に一般企業への就職を目指している障がい者の方へ、
- 職業訓練
- 就活支援(面接練習、履歴書の添削など)
- 生活支援(日々の体調管理)
などを提供している支援機関です。また、それらの一環として制度の利用に必要なサポート(書類作成の案内や診断書作成のための通院同行など)を受けられる場合もあります。
事業所によって異なりますが、生活支援と就労移行支援にサービスが分かれている場合が多く、「まだ社会復帰の見通しが立たない」という方でも生活支援から始めることができるので、幅広い状況での利用が可能です。
「とりあえず動き出したいけれど、どうしよう」と考えている方は、まず電話やメールなどで相談してみると良いでしょう。
就労移行支援事業所については下記の記事でも解説しています。
参考として、下記でおすすめの就労移行支援事業所についてもご紹介します。
ココルポート
ココルポートは、障がいを抱えた方がリラックスして通える、温かな雰囲気づくりを大切にしている就労移行支援事業所です。
うつ病で多くの不安を抱えている方も、個々の障がいに配慮した少人数制のプログラムや個別相談を通じて、少しずつ社会との接点を増やしていくことができます。
ミラトレ
ミラトレは、企業が求めるスキルを効率的に習得できる実践的なプログラムが魅力の就労移行支援事業所です。
うつ病で自信を失ってしまった方も、ビジネスマナーやチームワークを実践的に学ぶことができるので、働くことへの自信を取り戻せます。
NeuroDive
NeuroDiveは、IT・Web分野の専門スキルを身につけ、その道のプロを目指せる就労移行支援です。
うつ病の症状が出にくい静かで集中できる学習環境と、専門知識を持つスタッフが、あなたの背中を力強く後押ししてくれます。
ハローワーク
ハローワークは、雇用に関わるさまざまなサービスを提供している国営の支援機関です。
全国各地に設営されており、多様なニーズに応えるために専門的な窓口がいくつも設けられており、障がい者手帳を持っている方のための職業相談窓口もあります。
先述した失業保険の手続きや、職業紹介だけでなく、職業訓練や就職に関する相談などが可能です。うつ病の方が社会復帰を目指すうえでは欠かせません。社会復帰を目指すときは、積極的に利用しましょう。
まとめ|うつ病で仕事ができず、お金に困ったときの補助金・制度
- うつ病で働けずお金に困っている場合、支援が受けられる場合がある。収入・生活費に関しては「傷病手当金」「労災保険」「雇用保険」「障害年金」「特別障害給付金」、医療費に関しては「自立支援医療制度」「重度心身障害者医療費助成制度」の利用を検討しよう。「精神障がい者保険福祉手帳」を受けることで公共交通の割引が受けられることもある。
- 支援制度の受け方がわからないときは、自分の状況に応じて「病院の医師やカウンセラー、ケースワーカー」「精神保険福祉センター」「障害者就業・生活支援センター」へ相談を。
- 各種の経済支援制度を受けても生活が苦しい場合は「自立相談支援事業所」に相談するか「生活保護」を活用しよう。
- 社会復帰を目指すときは「就労継続支援事業所A型・B型」「就労移行支援事業所」「ハローワーク」で支援を受けられる。
うつ病が原因で仕事ができない場合、傷病手当金などの制度を利用することで生活費を得ることができます。ただ、精神障がい者保健福祉手帳や、障害年金などは、実際に利用できるようになるまで時間がかかることもあります。
医療費で生活が厳しい場合など、必要に応じて自立相談支援事業所や、各自治体に設置されている障害福祉窓口の活用も検討しましょう。
この記事があなたの助けになることを願います。