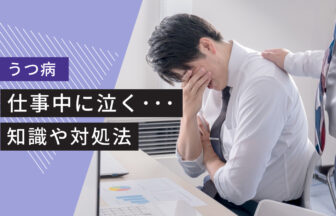うつ病の治療が一段落して社会復帰を考えるとき、ハローワークの利用を検討する方も多いでしょう。その一方で、うつ病を抱えて再就職することに不安に思う方もいらっしゃいます。
この記事を読んでいるあなたも
「病気の事を理解して、自分に合う求人探しや再就職を支援してくれるのかな?」
このような不安を感じていませんか?
うつ病を経験された後、社会復帰、特に再就職に向けて一歩を踏み出すのは、とても勇気がいることですよね。病気のこと、これからの仕事のことなど、一人で抱え込んでしまうと、心が重くなってしまうかもしれません。
しかし、安心してください。ハローワークは、あなたが再び社会で活躍するための一歩を支援してくれる公的な機関です。うつ病など病気を抱える方への専門的な支援体制も整っており、再就職を目指す多くの方が利用しています。
うつ病からの再就職で、ハローワークの利用を考えているあなたに向けて、
- ハローワークとは
- うつ病でもハローワークは利用できるのか
- うつ病の方がハローワークで受けられる具体的な就労支援
- ハローワークを利用するメリットとデメリット
- うつ病の方がハローワークで再就職・求人を探す際のポイント
- ハローワーク以外にも利用できる就労支援機関
について詳しく解説します。
この記事を読むことで、うつ病から再就職に向けたハローワークの活用方法や自分らしい働き方、そして社会復帰への道筋を見つけるためのヒントが見つかります。
ぜひ最後まで読んで、次の一歩を踏み出す力にしてください。
ハローワークってどんなところ?

ハローワークという名前は聞いたことがあるけれど、具体的にどんな場所で、どんな役割を持っているのか、まだ、利用したことがない方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に、病気を抱えながら仕事を探す場合、その基本的な機能や特徴を理解しておくことが、安心して利用するための第一歩となります。
ここでは、ハローワークが持つ公的な役割と、仕事探しをサポートする基本的な機能について解説します。
ハローワークは国が運営する仕事の相談所
ハローワークとは、「公共職業安定所」の愛称で、厚生労働省が全国各地に設置・運営する公的な機関です。
主な目的は、仕事を探している人(求職者)と働き手を求めている企業(求人者)を結びつけ、国民全体の雇用の安定を図ることです。また、公的な機関であるため営利を目的とせず、職業紹介や相談などの主要なサービスを無料で提供している点が大きな特徴です。
求職者にとっては、経済的な負担なく、仕事探しに必要な情報やサポートを得られる「国民のための仕事の相談所」とも言えるでしょう。
ハローワークの基本的なサポート内容
ハローワークを利用することに特別な条件はなく、仕事を探している方なら誰でも利用できます。新卒者から中高年、パートタイム希望者、そして病気や障がいを抱えながら再就職を目指す方まで、幅広い層の就職をサポートしています。
提供される主なサポート内容は以下の通りです。
- 求人情報の検索・閲覧
全国ネットワークを活かした膨大な求人情報にアクセスできます。 - 職業紹介
専門の相談員が、あなたの希望や状況に応じて、仕事探しのアドバイスや求人の紹介を行います。 - 失業保険の手続き
離職された方が、失業中の生活を支える給付金を受け取るための手続きを行います。 - 職業訓練の案内や申込
就職に必要なスキルや知識を身につけるための様々な訓練コースを紹介し、申し込みを受け付けています。
これらの基本的なサポートを通じて、ハローワークは求職者一人ひとりの状況に応じた就労支援を展開しています。
なお、一部の手続きについては、お住まいの地域を管轄しているハローワークで行う必要がある点にご注意ください。具体的には、雇用保険(失業保険)の受給手続きや、ハローワークへの本登録(初めて利用する場合など)がこれに該当します。
うつ病でも利用できる?ハローワークの障がい者専門窓口

うつ病の治療を経て再就職を目指す際、就職活動に不安を感じる方は多いのではないでしょうか。そんなときに頼りになるのが、ハローワークの「障がい者専門窓口」です。この窓口は、うつ病を抱えている方も利用できます。
この章では、これらのハローワークのサポート体制について、詳しく解説していきます。
うつ病の方も利用できる専門窓口
ハローワークには「障がい者専門窓口(専門援助部門)」という窓口があります。この窓口は、うつ病などの精神障がいを含めた、病気や障がいを抱えている方が就職相談をできる専門窓口です。
ハローワークにとって、病気や障がいを持つ方の就労を支援することは、国民全体の雇用の安定を図る上で非常に重要な役割の一つとされています。この専門窓口では、病気や障がいの特性に関する知識を持った相談員が、個々の状況に合わせたきめ細やかなサポートを提供しています。
また、相談内容が外部に漏れるのではないかと心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、ハローワークの相談員には守秘義務が課せられているため安心です。個人的な病状や家庭の事情など、話された内容が本人の許可なく第三者に伝わることはありませんので、安心して利用できます。
障がい者専門窓口の利用に必要なもの
障がい者専門窓口を利用するにあたって、「障がい者手帳を持っていないと利用できないのでは?」と思われるかもしれませんが、必ずしも手帳の所持が必須条件ではありません。原則として、医師の診断書や意見書など、ご自身の状態を客観的に示すことができる書類があれば、障がい者専門窓口を利用できます。
また、診断書に記載してもらうと良い具体的な情報(症状の程度、就労上の配慮事項など)について、事前にハローワークに尋ねておくと、より安心して手続きを進められるでしょう。
まずは最寄りのハローワークに問い合わせて、専門窓口の利用について相談してみることをお勧めします。
うつ病の方が障がい者専門窓口で受けられる4つの支援

では、うつ病の方がハローワークの障がい者専門窓口を利用するとき、実際にどのようなサポートが受けられるのでしょうか。
具体的には、主に以下のようなサポートが受けられます。
- 専門員による個別相談と職業紹介
- ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)
- 失業保険の手続きや相談
- 職場定着支援
ここでは、うつ病の方が特に活用できるハローワークの具体的な支援内容について、詳しく見ていきましょう。
専門員による個別相談とあなたに合った職業紹介・求人紹介
ハローワークの障がい者専門窓口を初めて訪れる方にとって、まず中心となるサポートが、専門の相談員による「個別相談」です。ここでは、あなたと一緒にキャリアプランや具体的な仕事探しの進め方を考えていくために、相談員が個別にヒアリングを行います。
例えば、以下のような内容を話し合います。
- これまでの職務経験
- 現在の病状、体力面で考慮してほしいこと
- 興味のある分野
- 勤務時間、仕事内容、職場の環境などの希望する働き方
このヒアリングをもとに、相談員はあなたに合った無理のない目標設定や活動計画を一緒に考え、安心して働けそうな求人を探すお手伝いをしてくれます。
また、障がい者専門窓口では、障がいを抱えている方への理解や配慮がある「障がい者専用求人」の情報が豊富にあります。もちろん、一般の求人の中からでも、必要に応じて企業へ配慮事項を相談してくれる場合もありますので、安心して仕事探しを進めることができます。
ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)
ハローワークでは、新しい仕事に挑戦したい方や、必要なスキルや実務経験に不安を感じている方に向けた「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」の案内や申し込みの受付をしています。
ハロートレーニングとは、仕事を探している方が、希望する職業に就くために必要なスキルや知識を習得できる公的な制度のことです。ハローワークを通じて手続きを行い、専門の訓練校などで実践的な学びが得られます。
ハロートレーニングには、主に以下のような種類があります。
ハロートレーニングの種類と基本情報
| 種類 | 公共職業訓練 | 求職者支援訓練 |
|---|---|---|
| 主な対象者 | 主に雇用保険を受給している方 | 主に雇用保険を受給できない方 (加入期間不足、自営業廃業など) |
| 訓練期間の目安 | 3か月~2年程度 (コースによる) |
2か月~6か月程度 (コースによる) |
| 学べる内容 | 専門知識・技能 (事務、IT、Webデザイン、 製造、介護サービス等) |
基礎スキル、 特定の職種に必要な入門的な知識・技能 |
| 主な実施施設 | 都道府県立の職業能力開発校、 ポリテクセンター (高齢・障がい・求職者雇用支援機構)など |
国が認定した民間の教育訓練機関 (専門学校、各種スクール、NPO法人など) |
| 受講料 | 無料 (教材費等は自己負担の場合あり) |
無料 (教材費等は自己負担の場合あり) |
| その他 | 収入などの要件を満たす場合、 「職業訓練受講給付金」が支給される制度あり |
| 種類 | 公共職業訓練 | 求職者支援訓練 |
|---|---|---|
| 主な対象者 | 主に雇用保険を 受給している方 |
主に雇用保険を 受給できない方 (加入期間不足、 自営業廃業など) |
| 訓練期間の目安 | 3か月~2年程度 (コースによる) |
2か月~6か月程度 (コースによる) |
| 学べる内容 | 専門知識・技能 (事務、IT、Webデザイン、 製造、介護サービス等) |
基礎スキル、 特定の職種に必要な 入門的な知識・技能 |
| 主な実施施設 | 都道府県立の職業能力開発校、 ポリテクセンター (高齢・障がい・ 求職者雇用支援機構)など |
国が認定した 民間の教育訓練機関 (専門学校、各種スクール、 NPO法人など) |
| 受講料 | 無料 (教材費等は 自己負担の場合あり) |
無料 (教材費等は 自己負担の場合あり) |
| その他 | 収入などの要件を満たす場合、 「職業訓練受講給付金」が 支給される制度あり |
ハローワークの障がい者専門窓口では、こうした様々なハロートレーニングの中から、あなたの状況やご希望、体調などを考慮し、最適なコースを見つけるためのお手伝いをしてくれます。
費用については、公共職業訓練、求職者支援訓練ともに、受講料は原則として無料で利用できますが、教材や実習で必要な作業着などは別途自己負担となる場合があります。また、一部有料のコースも存在する場合がありますので、詳細は窓口でご確認ください。
具体的な費用や、どのようなコースが提供されているのか、また、ご自身の状況や目指すキャリアに適した訓練は何かなど、不明な点や関心のあることがあれば、まずは窓口の相談員に遠慮なく尋ねてみましょう。あなたに合った訓練探しを丁寧にサポートしてくれます。
ハロートレーニングのうち、障がい者職業能力開発校については、下記の記事でも解説しています。
失業保険の手続きや相談
仕事を辞めて、まず心配になるのが生活費のことではないでしょうか。安心して治療に専念したり、落ち着いて再就職活動をしたりするためにも、経済的な安定はとても大切です。
ハローワークでは、「失業保険(雇用保険の基本手当)」を受け取るための手続きや相談を行っています。障がい者専門窓口では、あなたが受給資格があるか、どうすれば受け取れるのかなどを確認できます。特に、うつ病などの療養ですぐには働けない場合、「受給期間延長」という制度が利用できる可能性があります。
これは、本来の受給期間(原則1年間)を、申請によって3年間の延長(合計4年間)できる制度です。これにより、焦らずに体調を整え、回復してから再就職探しを始めることができます。
ご自身の病状や働くことへの不安なども含めて、気兼ねなく相談員に伝えてみましょう。利用できる制度をきちんと活用し、経済的な心配を少しでも軽くしながら、再就職への次のステップに進む準備をすることが大切です。
就職後も安心をもたらす職場定着支援
ハローワークのサポートは、仕事を見つけることだけでなく、あなたが新しい環境で安心して働き続けられるように「職場定着支援」というサポートも用意されています。これは、再就職をゴールとするのではなく、その職場であなたが能力を発揮し、長く活躍できるためのサポートです。
具体的な支援内容としては、以下のような支援を受けられます。
- 定期的な連絡・面談
就職後も相談員が連絡を取り、仕事上の悩みや困りごとがないかなどを確認します。 - アドバイスの提供
確認した悩みや困りごとに対し、適切なアドバイスを行います。 - 職場との連携・調整
場合によっては、相談員があなたと職場の上司や同僚との間に入り、より働きやすい環境を整えるための調整を行ってくれることもあります。
このように、ハローワークは他の専門機関とも連携を取りながら、あなたが新しい職場で安定して活躍できるように継続的なサポートを提供しています。
再就職後も頼れる相談先があることは、大きな安心材料になるはずです。
ハローワークを利用するメリット5選

ハローワークは、うつ病を抱えながら仕事を探す方にとって、多くのメリットがある公的機関です。
ここでは、具体的にどのようなメリットがあるのか確認していきましょう。
- 無料で利用できる
職業相談や職業紹介、求人情報の提供など、基本的なサービスはすべて無料で受けられます。 - 全国ネットワークと地域密着性
全国の窓口を通じて、Uターン・Iターン就職を含む幅広い地域の求人情報にアクセスできます。また、地元の求人情報にも詳しいため、地域に根差した仕事探しも可能です。 - 豊富な求人情報
公的な職業紹介機関であるため、多くの企業から求人が集まりやすいです。特に、障がいを抱えている方への理解や配慮がある「障がい者専用求人」の情報が豊富な点は、うつ病の方にとって心強いポイントです。 - 安心感と信頼性
国が運営しているため、個人情報の取り扱いや情報の信頼性に関して安心感があります。 - 多様な支援メニュー
仕事探しだけでなく、職業訓練(ハロートレーニング)や失業保険の手続き、就職後の定着支援など、就職活動全体をサポートする様々なメニューが用意されています。
これらのメリットを上手に活用することが、ハローワークを有効に使うためのポイントです。
ハローワークを利用するうえでのデメリットと対処法

メリットが多いハローワークですが、利用する際にはいくつか注意しておきたい点もあります。ここでは、主な注意点に加えて、それらへの対処法もあわせてご紹介しましょう。
あらかじめ知っておくことで、ハローワークをより快適に活用できるはずです。
混雑と待ち時間
公的な無料サービスということもあり、時間帯や時期によっては窓口が混雑し、相談までに時間がかかることがあります。特に、失業保険の認定日などは混み合う傾向があります。
混雑への対処法として、以下の方法を試してください。
- 比較的空いている午前中の早い時間帯などを狙う
- 事前に電話で混雑状況を確認する
- 時間に余裕を持って訪問する
- 可能であれば相談予約を利用する
混雑をうまく避け、少ないストレスで相談できると良いでしょう。
相談員との相性
相談員の方も様々ですので、時には「少し話しにくいな」「もっと親身になってほしいな」と感じることがあるかもしれません。また、説明が分かりにくいと感じる可能性も、残念ながらないとは言えません。
職員と相性が合わないと感じた場合は、窓口で相談し、担当者の変更をお願いすることも可能です。ご自身の状況を理解してもらい、安心して相談できる相手を見つけることも大切ですので、遠慮せずに伝えてください。
うつ病の方がハローワークで仕事を探す際の3つのポイント

うつ病を経験された方の仕事探しでは、「早く仕事を見つけなければ」という焦りや、「以前のように元気に働けるだろうか」といった不安を感じやすいかもしれません。
ですが、ここで何よりも大切にしていただきたいのは、ご自身の心と体の状態を最優先し、無理なく、長く続けられる働き方を見つけることです。
ここでは、ハローワークで求人情報を探す際に特に意識していただきたい、3つの大切なポイントについて詳しく解説していきます。
焦らず自分のペースで進めること
まず、何よりも大切にしていただきたいのは、ご自身の体調を最優先に考え、焦らずご自身のペースで再就職活動を進めることです。
「仕事をしていない期間が長引くと不利になるのでは」
といった焦りは、うつ病の回復にとっては、かえって負担になってしまうこともあります。
また、体調が不安定な時に無理に活動量を増やしたり、面接をたくさん入れたりすると、体調が悪化したり、回復が遅れたりすることにもつながりかねません。
求職活動は、想像以上に体力や精神力を使うことがあります。ご自身の主治医ともよく相談しながら、現在のあなたの状態(活動できる時間、集中力、ストレスへの耐性など)を客観的に把握することが大切です。
その上で、
「1日に応募するのは〇社までにする」
といった、ご自身にとって無理のないペースを設定するのも良いでしょう。
疲れたと感じたら、勇気を出して休むことも大切です。休むことも回復への大切な一歩と捉え、焦らず、ご自身のペースを大切に進めていきましょう。
障がい者専用求人を積極的に検討する
うつ病の方がハローワークで求人を探す際は、「障がい者専用求人」を積極的に検討してみることをおすすめします。
障がい者専用求人とは、障がいを抱えている方の雇用を前提とした求人のことであり、うつ病などの精神疾患のある方も対象となります。
障がい者専用求人の大きなメリットは、企業側が病気や障がいの可能性を前提としているため、必要な配慮について相談しやすい点です。入社前から、あなたの病状や体力面で考慮してほしいことや、必要なサポートなどについて相談しやすく、安心して働くための環境を整えやすいと言えるでしょう。これは、再就職後の定着にも繋がります。
障がい者手帳をお持ちでなくても応募できる求人もあるため、まずは相談員に「障がい者専用求人についても詳しく教えてほしい」と気軽に尋ねてみることをおすすめします。
障がい者専用求人については、以下の記事で詳しく解説しています。
自分に合った職場環境を明確化し、相談員に伝える
長く安定して働くためには、あなたにとって「働きやすい」と感じられる職場環境を明確にすることが重要です。
ハローワークの相談員に具体的な希望を伝えるためにも、まずはご自身がどのような環境であれば安心して働けそうか、具体的に考えてみましょう。
例えば、以下のような点を整理してみるとよいでしょう。
- 業務内容:集中力が必要な作業か、人と関わる業務か、単独で進める作業か
- 職場の雰囲気:静かな環境か、活気のある環境か、チームワークを重視するか
- 働き方:通勤時間、勤務時間(短時間勤務、フレックスタイムなど)、休憩の取りやすさ
- サポート体制:上司や同僚に相談しやすいか、困ったときに頼れる人がいるか
- その他:急な体調不良時に休みやすいか、業務量の調整は可能か
うつ病の当事者が特に配慮してほしい可能性のある項目を追加しました。
このように、ご自身が重視する点や、逆に「これは避けたい」と思う点を具体的にしておくことで、求人を探す際の軸が明確になります。入社後のミスマッチを防ぎ、あなたが無理なく安心して働ける職場や求人を見つけるためにも、ご自身の希望をしっかりと相談員に伝えることが大切です。
ハローワークのほかに利用できる就労支援

ここまでは、ハローワークの障がい者専門窓口について紹介してきましたが、実は、障がいを抱えている方の就労をサポートする機関は、ハローワーク以外にもあります。
具体的には、以下のような支援機関が挙げられます。
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所(A型・B型)
- 障がい者就業・生活支援センター
- 地域障がい者職業センター
これらの支援機関は、それぞれ専門性や特徴が異なりますが、多くの場合、ハローワークと連携したり、併用したりすることが可能です。
例えば、「ハローワークで求人情報を探しつつ、就労移行支援事業所で再就職に向けた具体的なスキル訓練を受ける」「障がい者就業・生活支援センターで生活面の相談をしながら、ハローワークで職業相談をする」といった活用が考えられます。
このように、複数の支援機関を上手に組み合わせることで、より手厚く、ご自身の状況に合ったサポートを受けることができます。
ここでは、それぞれの支援機関の特徴や受けられるサポートについて、詳しく見ていきましょう。ご自身の状況や目指したい働き方に合わせて、最適なサポートを見つけるための参考にしてみてください。
就労移行支援
就労移行支援は、一般企業への就職に向けて専門的なサポートを受けられる障がい福祉サービスの一つです。多くの場合、「就労移行支援事業所」という専門の施設でサポートが提供されます。
ここでは、履歴書の添削や模擬面接といった就職活動の具体的なサポートから、就職後の職場定着支援まで、安心して次のステップに進めるよう、トータルで支えてくれます。また、体調管理の方法やストレスへの対処法を学んだり、コミュニケーション訓練を通じて対人関係の不安を和らげることも可能です。
就労移行支援の利用期間は原則として2年間ですが、一人ひとりの状況に合わせて利用計画が立てられます。
焦らずに、でも着実に社会復帰を目指したいと考えているうつ病の方にとって、就労移行支援は心強い選択肢の一つとなるでしょう。
就労継続支援事業所(A型・B型)
就労継続支援は、現時点で一般企業への就職が難しいと感じる方や、特定のサポートを受けながら働きたいと考える障がいのある方向けの福祉サービスです。
このサービスには「A型」と「B型」の2種類があり、特徴は以下の通りです。
就労継続支援事業所(A型・B型)の特徴
| A型 | B型 | |
|---|---|---|
| 契約 | 事業所と雇用契約を結ぶ | 事業所と雇用契約は結ばない |
| 報酬 | 給料 | 工賃 |
| 働き方 | 比較的規則正しい勤務 | 体調に合わせて柔軟な日数・時間で利用する |
| 主な対象者 | 原則18~64歳、一般就労を目指す方 | 年齢制限なし、就労機会や生産活動の場を求める方 |
| A型 | B型 | |
|---|---|---|
| 契約 | 事業所と雇用契約を結ぶ | 事業所と雇用契約は結ばない |
| 報酬 | 給料 | 工賃 |
| 働き方 | 比較的規則正しい勤務 | 体調に合わせて 柔軟な日数・時間で利用する |
| 主な対象者 | 原則18~64歳、 一般就労を目指す方 |
年齢制限なし、 就労機会や生産活動の場を 求める方 |
活動内容は事業所によって多岐にわたりますが、一般的には以下のような仕事があります。
- A型事業所:事務作業やPC業務、飲食店での調理・接客補助、清掃業務など
- B型事業所:簡単な部品の組み立てといった軽作業やリサイクル業務、農作業や手芸など
まずは働くことを通じて自信を取り戻したい方や、社会参加への確かな一歩を踏み出したいと考える方にとって、この就労継続支援は心強い選択肢となるでしょう。
就労移行支援と就労継続支援については、以下の記事でも詳しく解説しております。
障がい者就業・生活支援センター
障がい者就業・生活支援センターは、その名の通り、障がいを抱えている方の就業面と生活面の両方から一体的なサポートを提供する身近な相談窓口です。全国各地に設置されており、「なかぽつ」といった愛称で呼ばれることもあります。
仕事に関する相談だけでなく、日常生活を送る上での困りごとについても相談できるのが大きな特徴です。
具体的には、以下のようなサポートを行っています。
- 就業面:就職相談、職場実習のあっせん、就職後の定着支援、職場との関係調整など
- 生活面:自己管理(健康、金銭など)に関する助言、住居や年金に関する情報提供、余暇活動の支援など
仕事のことだけでなく、生活全般の悩みも一緒に相談できるため、安心して就職活動や就労継続に取り組むことができます。
障がい者就業・生活支援センターについては、以下の記事で詳しく解説しています。
地域障がい者職業センター
地域障がい者職業センターは、障がいを抱える方の一人ひとりに合わせた、より専門的な職業リハビリテーションサービスを提供する機関です。
特に、以下のような専門的なサポートが必要な場合に頼りになります。
- 職業評価
カウンセリングや作業検査で、職業能力や適性、課題等を客観的に評価し、今後の方向性を明確にします。 - 職業準備支援
働く上で必要な基本的スキル(対人関係、作業遂行能力等)を向上させるためのプログラムを提供します。 - 職場定着支援
就職後も職場に定着できるよう、職場への配慮依頼、定期的な面談、職場訪問等を通じてフォローします。
ハローワークでの相談だけでは解決が難しい専門的な課題がある場合や、より詳細な職業評価、職場への適応支援を受けたい場合に、活用を検討してみるとよいでしょう。
専門家の視点からのアドバイスやサポートは、就職への道をより確かなものにしてくれるはずです。
地域障がい者職業センターについて、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
- ハローワークは国が運営する無料の職業相談所で、求人検索や職業相談、失業保険手続き、職業訓練案内など、仕事を探す人なら誰でも利用できる。
- ハローワークにはうつ病の方も利用可能な「障がい者専門窓口」があり、専門知識を持つ相談員が守秘義務を守って対応してくれるため安心である。利用は障がい者手帳がなくても医師の診断書などで可能な場合がある。
- うつ病の方が専門窓口で受けられる支援には、個別相談・職業紹介、ハロートレーニング、失業保険手続き・相談、職場定着支援など多岐にわたるサポートがある。
- ハローワーク利用のメリットは、無料で利用できる、全国の求人情報にアクセスできる、豊富な障がい者求人がある、公的機関としての安心感がある、多様な支援を受けられること。一方でデメリットとして、混雑や相談員との相性が合わない可能性、求人のミスマッチの可能性が挙げられる。
- うつ病の方がハローワークで仕事を探す際は、体調優先で焦らず自分のペースで進めることや、障がい者専用求人の検討、自分の考えを相談員に伝えることが大切。
- ハローワーク以外にも、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、障がい者就業・生活支援センター、地域障がい者職業センターといった就労支援機関があり、状況に応じて活用できる。
うつ病を抱えながら仕事を探すことは、多くの不安や戸惑いを伴うかもしれません。
しかし、ハローワークにはうつ病の方を専門的にサポートする「障がい者専門窓口」があり、安心して相談できる体制が整っていますので安心してください。
また、ハローワーク以外にも様々な就労支援が存在します。これらの公的なサポートを積極的に活用し、ご自身のペースで社会復帰への道筋を見つけることが大切です。
この記事が、あなたが安心してハローワークを利用し、自分らしい働き方を見つけるための一助となれば幸いです。