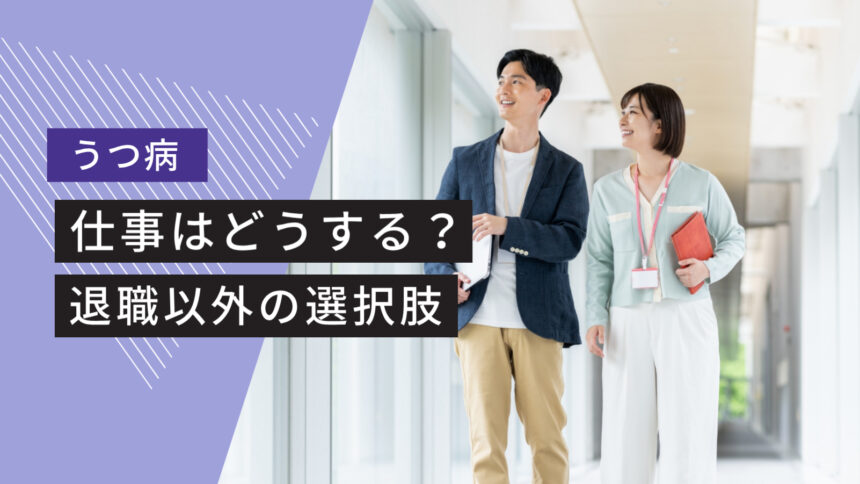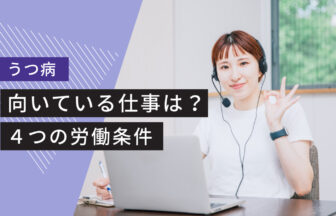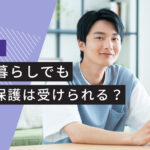「うつ病の診断を受けてしまったけれど、仕事どうしよう…」
などの悩みや不安はありませんか?
うつ病は心の風邪とも呼ばれており、誰にとっても身近な病気です。発症してしまうと日常のさまざまな場面で支障をきたします。特に、在職中の方は仕事を続けるのが難しくなってしまうので、とてもつらいですよね。
しかし、無理に仕事を続けてしまったり、休んでも収入が減る不安からストレスを感じたりして、さらにうつ病を悪化させてしまう、といったことは避けなければいけません。
- うつ病と診断されたら仕事はどうするべきか
- うつ病で仕事を休職・退職した場合に収入を支えてくれる制度
- うつ病の方が仕事や収入について相談できる支援機関
- 仕事を休む方、続ける方どちらにもオススメのうつ病克服のコツ
を解説していきます。
仕事でうつ病になったら仕事はどうするの?

うつ病とは、悲しみを感じたり、活動に対する興味や喜びが減少したりする症状がその人の社会生活を困難にするほど強くなり、病気になった状態です。引用:うつ病|10.心の健康問題 気分障害|MSDマニュアル家庭版
あなたは通勤や業務に際して「気分が落ち込み、身体が思うように動かない」といった症状はありませんでしたか?うつ病は不眠などの症状で冷静な判断力を失ってしまうことが多いため、「仕事をどうするか?」は自己判断ではなく専門医と相談して決めることが大切です。
在職中の方がうつ病と診断された場合、大きく「仕事を続ける」「休職」「退職」という3つの選択肢があります。
仕事について適切な判断をするには、
- 症状はどれくらい重いのか
- 主な要因は何か
- 治療にどの程度の期間が必要か
という3つのポイントを意識して、あなた自身の状態をきちんと把握する必要があります。
「どうするべきかわからない」という方は、専門医の意見や診断書をまとめて、勤務先に配置されている産業医や顧問医に相談するのがオススメです。産業医は従業員の健康状態を見極めて休職の助言をしたり、医療機関を紹介したりする役割の医師なので、適切な判断をしてもらえます。
産業医や顧問医がいない場合、主治医や定期検診を行っている医療機関へ相談するのが良いでしょう。
【働けそうなら】無理のない形で仕事を続ける
主治医から「無理のない範囲であれば働ける」と診断された上で、あなたに働き続ける意思や心の余裕があれば、仕事を継続することができます。
収入を絶やさずにうつ病の治療を進められるメリットは大きいので、できれば仕事を続けたいという方もいらっしゃいますよね。
そのような場合は、主治医と職場の双方と相談をして、
- 時短勤務に切り替える
- 負担の少ない部署に変えてもらう
- 在宅勤務にする
- 負担に感じる業務は他の人に回してもらう
など、職場環境の調整を行いましょう。あらかじめストレス要因をきちんとまとめておくと周囲に伝えやすく、合理的な配慮を受けやすいはずです。
ただし、無理は禁物です。うつ病を我慢して働き続けると、症状を悪化させてしまい仕事が続けられなくなる危険があります。そのため、働くのがつらい場合、迷わず休職に入ることが大切です。
【仕事がつらいなら】無理をせず休職する
早めの休養・療養はうつ病治療の近道です。
あなたの状況が、下記に当てはまるのであれば、迷わず休職することをオススメします。
- うつ病の原因が職場や仕事内容にあり、なおかつその環境の改善が困難
- 「現状働ける状態ではない」と診断された
- あなた自身が「働くのが本当につらい」と感じている
休職制度は各事業者が就業規則に基づいて独自に定める制度です。利用できれば退職とは異なり、ある程度復職の猶予が得られます。ただし、内容は会社によって異なります。詳細はあなたの勤めている会社へご確認ください。
休職までの大きな流れは下記の通りです。
- 就業規則を確認して、会社の休職制度について確認する
- 休職したい旨を主治医に相談して、休職手続きに必要な診断書を作成してもらう
- 上司や人事部に診断書を提出して、休職する旨を伝える
休職には主治医や職場との連携が必要なので、双方と相談しながら「休職期間」「復職の条件」などを調整しなければいけません。トラブルの発生やストレスを避けるためにも、独断で即断即決するのはやめましょう。
辛い状況で無理をして働いてしまうと、うつ病の悪化や統合失調症など、うつ病とは異なる精神疾患の発症につながる恐れもあります。
休職には、「収入がなくなる※」「社会保険料の支払いは継続する」などのデメリットはありますが、これらの問題は後述する制度で解決できる可能性があります。休職中に利用できる支援もあるため、治療に専念することが早期の社会復帰に効果的であることは覚えておきましょう。
うつ病で休職・退職しても収入を支えてくれる4つの制度

うつ病での休職・退職で一番ネックになるのはやはり収入面です。
「休みたいけれど、お金がなければ日々の生活を維持するのも治療を継続するのも難しくなってしまうので休みにくい」と考えていませんか?
大丈夫です。そういったときに助けになる制度が4つあります。
ご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
労災保険制度
労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。引用:労災保険制度とは|労災補償|厚生労働省
厚生労働省は精神障がいで労災認定を行う場合の条件を、下記のように公表しています。
精神障害が労災認定されるのは、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限ります。
仕事によるストレス(業務による⼼理的負荷)が強かった場合でも、同時に私⽣活でのストレス(業務以外の⼼理的負荷)が強かったり、重度のアルコール依存があるなどストレスに対する反応しやすさ(個体側要因)に顕著なものがある場合には、どれが発病の原因なのかを医学的に慎重に判断します。引用:精神障害の発病についての考え⽅|精神障害の労災認定|厚生労働省 都道府県労働局・労働基準監督署
そのため、うつ病の原因が「過剰な長時間労働」や「いじめ・ハラスメント」である場合は、労災保険制度から給付金を受け取れる可能性があります。「証拠が揃っている」「複数人が被害を訴えている」などの状況では、労働基準監督署などに相談するのも1つの手段です。
精神障がいでの労災は「仕事のストレスで発症したこと」との因果関係を証明するハードルが高く、一般的な労災認定よりも難しくなります。ですが、労災認定が通れば状況に応じた補償を十分に受けられるので、心当たりがある場合は一度管轄の部署に連絡してみましょう。
傷病手当金
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会 協会けんぽ
傷病手当金は、制度上、労災保険の条件に入らない傷病者が給付を受けられるものです。
「健康保険の傷病手当」と「雇用保険の傷病手当」の2種類が存在しますが、今回は「健康保険」の傷病手当について説明します。うつ病で休職・退職したときでも、下記の条件をすべて満たしているのであれば傷病手当の対象です。
- 健康保険料を払っていること
(全国健康保険協会などの健康保険、または社会保険に加入していること) - 業務外の病気や怪我で療養中である
(労災保険の適用範囲外が対象、ただし、健康保険適用外治療のための療養は非対象) - 療養のため仕事に就くことができない
- 連続する3日間の休業を含む4日以上休んでいる
(休職に入った最初の3日間を除き、4日目から支給対象となる) - 休んだ期間中、給与の支払いがない
(一部支給されている場合、傷病手当金の額から支給分を減額した差額が支給される)
申請期限は2年です。申請が通れば最大1年6か月間、もともとの給与額の約3分の2相当を受け取ることができます。後述する失業保険のように年齢ごとの上限額はありません。支給を受けている間も社会保険料の自己負担額分を払い続けなければならない制約はありますが、収入がすぐに断たれることはないので安心できます。
全国健康保険協会や企業・業界独自の健康保険組合など、加入している健康保険は場合によって異なります。また、組合によっては独自の給付制度が設けられている場合もあるので、加入中の保険を確認してみると良いでしょう。
雇用保険の傷病手当については、下記のリンク先をご確認ください。
傷病手当について|基本手当について|ハローワークインターネットサービス
失業保険(基本手当)
原因を問わず、失業した方は下記の条件を満たしていれば失業保険の対象です。
- ケガや病気などはなく、働く意思と就職できる能力があるにもかかわらず、就職がすぐにできない「失業状態」にある
- 失業から30日以上が経過している
- 離職の日以前から2年間以内に、被保険者期間※が通算12か月以上ある
※被保険者期間:雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月と計算。
申請が通れば最大で1年近く、
の額を受け取ることができます。大まかな目安として、賃金が月収20万円であれば15万円程度、月収30万円であれば20万円程度の支給額となります。
ただし、下記のような注意点があります。
- 傷病手当との同時受給は不可
- 受け取れる日額は年齢ごとに上限がある※ため、傷病手当よりも総額が少なくなる可能性がある
- 申請期限は「なるべく早期に」と不明瞭であり、大体の場所で失業30日目以降から1か月以内とされている
| 30歳未満 | 7,065円 |
|---|---|
| 30歳以上45歳未満 | 7,845円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,635円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,420円 |
令和6年8月1日時点
| 30歳未満 | 7,065円 |
|---|---|
| 30歳以上45歳未満 | 7,845円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,635円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,420円 |
令和6年8月1日時点
また、基本手当を受けるには、原則として4週間に1回の認定日に、失業認定を受ける必要があります。
なお病気やケガ等で働けない期間がある場合は、申請期限内に申し出ることにより支給の開始を最大3年間まで延期できるので、傷病手当が切れた段階で失業保険に切り替えることが可能です。
うつ病による休職・退職で失業保険が必要になった際は、こちらについても離職票を提出する際に窓口で相談してみると良いでしょう。
障がい厚生年金
うつ病であっても、下記の条件を満たしていれば障がい厚生年金の申請ができます。
- 厚生年金保険の加入期間中に、障がいの原因となった病気やケガの初診日がある
- 障がいの状態が障がい認定日に、障がい等級表※の1〜3級いずれかに該当している(のちに状態が重くなった場合でも受給可能な場合がある)
- 初診日がある月の初診日前日から前々月までの期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上ある
申請には障がいを証明するための正式な診断書(初診日から6か月経過したもの)が必要で、手続きにも少し手間がかかります。審査も厳しく、必ず審査に通るというわけではありません。
しかし、審査に通れば期間の制限なく、症状が回復するまで等級に応じた金額の受給が可能です。
(詳細:障害厚生年金の年金額(令和6年4月分から)|日本年金機構)
傷病手当や失業保険との同時に受給することもできます。症状が重い場合は障害厚生年金について、年金相談センター等、専門の窓口へ相談してみましょう。
うつ病の方が仕事や収入について相談できる支援機関4選

うつ病で仕事を休むとしても、働きながら回復を目指すとしても、
「制度を活用したいけど、申請がむずかしい…」
といった気持ちが少なからずあるでしょう。
そういった方は、下記の4つの支援機関へ相談してみましょう。
- 精神保健福祉センター
- 障がい者就業・生活支援センター
- 就労移行支援事業所
- ハローワーク
仕事をどうすればいいかのアドバイスをもらえたり、会社・病院とのコミュニケーションが必要なときに間に入って協力してもらえたり、障がい年金や失業保険を申し込む際に必要な手順を詳しく教えてもらえたりします。
支援機関とのつながりを持っておくことは、うつ病が治ってから社会復帰を目指す際にも復職や再就職の支援をスムーズに受けられるため非常に役立ちます。
機関によって手段は異なりますが、就労に向けた支援を受けられるので、積極的に利用を検討しましょう。
【仕事を休む方も続ける方もオススメ】うつ病克服の5つのコツ

仕事を続ける方も、休んで療養に専念する方も、できるだけ早くうつ病を克服したいですよね。
そこで、この項目では、すぐに始められるうつ病克服のコツを5つご用意しました。ぜひ参考にしてください。
気分の浮き沈みについて把握する
- 午前中はいつも調子が悪いが午後には良くなってくる
- 雨の日は気分が重くなるが、晴れの日に陽を浴びると少し軽くなる など
うつ病は、上記のように日時や周囲の環境によって気分の浮き沈みが生じる病気です。どのような状況で変化が起きるのかをきちんと把握しておきましょう。
わかっていれば、業務量や出勤時間をそれに合わせて工夫するなど、対策を取ることができます。
かかりつけ医の指示をよく聞き、薬をきちんと飲む
専門医はどうすればうつ病が回復するのか、多くの知識を持っています。その意見は最も重要視すべきです。
また、うつ病は投薬治療が効果的な病気なので、処方される薬を指示通り飲めるかで回復の速さが変わってきます。気になることはすぐ質問し、服薬の指示や生活習慣の指導がある場合はよく聞いて、それに沿った行動を心がけましょう。
朝日を浴びる
うつ病は幸福に関わる神経伝達物質が不足することで起こるとされていますが、日光を浴びると神経伝達物質が分泌されます。
特に朝日はうつ病の方が乱れがちな体内時計の調整や、生活リズムを整えることにも役立つのでオススメです。朝目が覚めたらカーテンを開け、陽の光をいっぱいに取り込んでみましょう。
ビタミンの多い食事をバランス良く摂る
うつ病だと食欲不振などで食生活が乱れやすく、栄養のバランスが偏りやすくなります。栄養バランスが乱れていると、回復も遅くなってしまいます。
- 野菜やきのこ
- レバー
- 肉、魚介類
など、栄養の豊富な食べ物をバランス良く摂ることを心がけましょう。
栄養が脳内の神経伝達物質のもとになり、うつ病の回復につながります。
周囲と悩みを共有する
自分以外の誰かに悩みを共有するだけでも、うつ病の不安感を緩和することができます。
うつ病になってしまうとどうしても「どうせ理解してもらえない」「相手の迷惑になりたくない」と塞ぎ込んでしまい、孤独感を募らせてしまいがちです。
最初は難しいかもしれません。しかし、少し話すだけでも心はふっと軽くなるはずです。うまくできない場合は医師やカウンセラーにまず相談してみてください。そのうえで少しずつ、悩みを打ち明けてみましょう。
まとめ|仕事でうつ病になったら?退職以外の選択肢と役立つ情報
- 在職中の方がうつ病と診断された場合は、自身の症状を把握し、医師と相談のうえで体調優先で「仕事を続ける」か「休職」「退職する」かを決めたほうが良い。
- うつ病で休職・退職しても「休職制度」「労災保険」「傷病手当」「失業保険」「障がい年金」など、収入を支える制度がある。
- うつ病の方が仕事や収入について悩んだ場合「精神保健福祉センター」「障がい者就業・生活支援センター」「就労移行支援事業所」「ハローワーク」などの支援機関に相談できる。
- うつ病で仕事を休む方も続ける方も「気分の浮き沈みについて把握する」「かかりつけ医の指示を聞き、薬を指示通り飲む」「朝日を浴びる」「ビタミンの多い食事をバランス良く摂る」「周囲と悩みを共有する」などのコツを押さえれば症状の克服に近づく。
うつ病は1人で抱え込まないことがとにかく大切です。
あなたの負担にならない程度に周囲の方に相談して、ストレスを溜め込まないように心がけましょう。