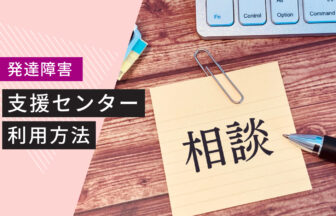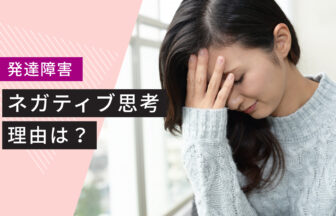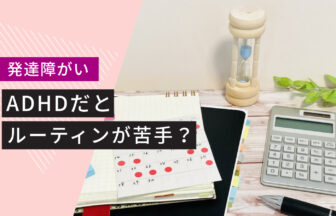あなたには、「友達と仲良く過ごしていたのに、気がつくと連絡がつかなくなった」という経験がありませんか?
発達障害の特性の影響により、友人との関係がうまく築けなくて悩んでいる方は少なくありません。
「何か悪いことしたかな?」
「どうしたらうまく友達と付き合えるの?」
せっかく友達ができたのに、連絡がこなくなっては悲しいですよね。
- 発達障害の方から友達が離れていく原因
- 発達障害の方によくある友達とのトラブル
- 発達障害の方が友達とうまく付き合う方法
- 発達障害の方の友達のつくり方
について解説していきます。
友達が離れてしまう原因を知り、特性とうまく付き合いながら両校友人関係を築く方法を探っていきましょう。
大人の発達障害の方から友達が離れていく5つの原因

発達障がいを抱える方は、周囲とのコミュニケーションや人間関係に困難を感じる場合があります。
特に、友人関係を維持するには細かな気配りや空気を察する力が重要であるため、発達障害の特性によっては難しいことがあるでしょう。
友達が離れてしまう原因となりうる、具体的な特性について紹介していきます。
コミュニケーションをとるのが苦手
発達障害者にとって、言語や非言語のコミュニケーションは、特有の難しさがあります。
具体的には、下記のような点が挙げられます。
- 会話の流れを理解できない
- 相手の意図がうまく読み取れない
- 感情を理解するのが難しい
- 自分の気持ちがうまく伝えられない
このため意思疎通がうまくできずに、誤解が生じたり、友達を無意識に傷つけてしまうことがあります。
空気を読んで行動することが難しい
その場の雰囲気や暗黙のルールを理解し、適切な行動をとることは友人関係において非常に重要です。しかし、発達障害の方にとっては、特性の影響でこれが難しい場合があります。
その場にふさわしくない発言や行動をしてしまう
このような言動は、周囲の人を不快にさせて、友人関係を悪化させるかもしれません。
不注意・多動性
特にADHDの方に多く見られる特性が、「不注意・多動性」です。
- 友達との約束を忘れる
- 友達に借りたものを何度も無くした
- 忘れ物が多い
これが続くと、友達との信頼関係も揺らぐかもしれません。
自己肯定感が低い
発達障害の方は、今まで社会にうまく溶け込めなかった経験から、極端に自己肯定感が下がってしまっていることが少なくありません。
- 自分のことをダメだと考えてしまう
- 相手の言ったことをネガティブに変換する
- 何でも自分が悪いと思ってしまう
このような思考が続くと友達も不安に思うでしょう。
興味・関心に偏りがある
特にASDの方は、興味のある物事に偏りがある傾向にあります。
- 自分の興味のあることについては熱く語るが、興味のない話題には無口になる
- 一方的な話ばかりになり、相手の話に耳を傾けない
このような態度は、友達を窮屈にさせてしまうでしょう。
以上5点が、発達障害の方から友達が離れていく主な原因として考えられます。どれか当てはまる原因はありましたか?
次の章では具体的なトラブルをみていきましょう。
大人の発達障害の方に起こりやすい人間関係のトラブル

前章では、大人の発達障害の方から友達が離れていく5つの原因をみていきました。
この章ではより具体的な事例を通して、それぞれのトラブルがどのように発生し、影響を与えるのかを詳しく解説します。
コミュニケーションでのトラブル
事例1:子供の見守り
友達から「ちょっと出かけるから子どもを見ておいて」と頼まれた。しばらくして、子どもが熱いやかんに近づいてしまった。
危ない状況になったにもかかわらず、指示通り「見る」ことしかできなかった。
問題点
- 前後の文脈や状況を理解し、適切な判断をするのが苦手
- 抽象的な表現を(見る=世話もする)理解するのが難しい
影響
- 子どもに迷惑をかけ、友人関係を損なう可能性がある
- 子どもが危険にさらされる
対処法
- 具体的な指示を求める
- 事前に想定される危険な状況をリストアップしてもらい、対応できるようにする
社会性でのトラブル
事例2:電車内での大声
混雑した電車内で大きな声で友達に話しかけてしまった。周りの方に嫌な顔をされた。
問題点
- 周囲の状況に配慮ができない
- 社会的なルールやマナーを守るより自分が優先になってしまう
影響
- 周囲の方に迷惑をかけ、友達の評判を落とす可能性がある
対処法
- 周囲が混雑した時は、声のトーンを調整する
- 社会的なルールやマナーを確認する
不注意とこだわりでのトラブル
事例3:約束を忘れてしまう
好きなゲームに集中しすぎて、友達との約束を忘れていた。
問題点
- 注意力が散漫で、物事を忘れやすい
- 計画性や時間管理が苦手
影響
- 友達に迷惑をかけ、信頼関係を維持できない
※こだわりが強いことで「仕事に集中できる」メリットにもなります。
一方で強くなり過ぎてしまうと計画を忘れ、デメリットの一面にもなります。
対処法
- スケジュール帳やTODOリストを見える位置におく
- アラーム機能を活用して、指定時間に忘れないようにする
これらはあくまで一例ですが、自分の特性を理解していないと友人関係を維持するのが難しいです。
次の章ではどのようなステップで友達とうまく付き合えるのかを考えてみましょう。
大人の発達障害の方が友達とうまく付き合う方法

前章では、具体的なトラブル例と対処法を解説しました。
この章では友人関係をうまく築き、維持するためのポイントを解説します。
自己理解を深め、受け入れる
自分にはどのような特性があるか自己分析してみましょう。
- 時間が守れない
- 人の話を長く聞けない
- 自分をうまく表現できない
など、発達障害ではさまざまな特性があります。
大切なのは自分の特性を理解し、受け入れることです。無理に周囲のペースに合わせず、自分なりのペースで付き合える友人を関係を築くことが大切です。
離れてしまった友達とは、無理に関係を続けない
時間管理が苦手なのに、時間に厳しい方と無理に関係を続けようとすると、お互いにストレスが溜まります。離れて行ってしまった友達の中には、自分の特性と合わなかった方もいるかもしれません。
そうならば、潔く関係を断ち、自分と合う新しい関係を築くことも大切です。
距離を置くことで、離れた友達ともう一度仲良くなる場合もあります。その時は快く受け入れてあげてください。あなたが連絡しても疎遠だったのは、友達がたまたま忙しかったのかもしれません。
マルチタスクを避ける
発達障害者は、複数の作業を同時に行う(マルチタスク)が苦手です。
例えば
- 予定は1日に1つにする
- 一度にたくさんの友達と連絡を取らない
など、目の前のことに集中して取り組むように意識しましょう。
発言・行動の前に考える
思ったことをすぐに言ってしまう。これではその場では相応しくない行動や発言をするかもしれません。
発言や行動をする前に少し時間を置きましょう。そして、本当にこの場に適切かどうか考えてみましょう。
カミングアウトは慎重に
友達に「発達障がいであること」をカミングアウトするか悩む方も多いでしょう。
メリット
- 相手に自分の特性を理解してもらえる
- 発達障がいを踏まえて友達関係を維持できる
デメリット
- 発達障がいを知られることで友達が離れていく可能性がある
- 友達ではない周囲の方にも知られる可能性がある
これらを踏まえるとカミングアウトは慎重に判断し、家族や専門家に相談してから決めることをおすすめします。
大人の発達障害の方が友達をつくる方法

前章では、友人関係をうまく続けるポイントを解説していきました。
この章では、もう一度友達をつくるための方法につてい解説します。
友達の定義を見直す
大人になってからの友達づくりは、子ども時代より難易度が高く感じる方が多いでしょう。学生時代のように学校や遊びを通して自然と人に関わり、友達が増えていく経験は大人になると少なくなります。さらに、仕事や家事などで時間が奪われ、友達との時間も制限されます。
また友達の定義が人によって異なります。あなたが「友達が離れてしまった」と思っていても、相手は忙しかっただけで友達と思っているかもしれません。
まずは、自分にとって「友達」とはどういう存在なのかを見直し、そのハードルを下げることも大切です。
同世代にこだわらない
実際に友達を探していく上で、年齢が近い方だけが友達ではありません。
「気が合えば何歳であろうと友達」です。年齢だけで判断していては、本当に自分に合う方は見つかりにくいでしょう。
幅広い世代の人々と交流することで、新しい発見や刺激を得られるかもしれません。
共通の趣味を持つ人と交流する
共通の趣味を持つ方と出会うことは、友達をつくる上で非常に有効な手段です。
自分の趣味の活動に参加したり、新しい趣味にチャレンジすることで、共通の話題をもつ方と交流することができます。
趣味を共有することで、会話も弾みやすく、より深い関係を築きやすくなります。
支援を活用する
話すことが苦手だったり、友達づくりが不安であれば1人で考え込まないでください。積極的に支援を活用しましょう。
コミュニケーションに不安のある発達障害の方には、次のような支援がおすすめです。
ソーシャルスキルトレーニング(SST)
人とうまく話すのが苦手な場合は、SSTと呼ばれるコミュニケーションスキルトレーニングを受けることをおすすめします。
SSTでは具体的な場面を想定したロールプレイングやグループワークを通して、コミュニケーション能力を向上させる練習をします。
医療機関や就労支援センターで実地されることが多いので、自分に合うプログラムを探してみましょう。
発達障害者支援センター
具体的な一歩を踏み出したい場合は、発達障害支援センターの窓口に相談してみるのも良いでしょう。
発達障害者支援センターでは、相談支援員があなたの状況やニーズを丁寧に聞き取り、自分に合ったコミュニティーや活動を紹介してくれます。
こちらの記事でも詳しく解説しています。参考にしてください。
atGPジョブトレ 発達障害コース(就労移行支援)
「atGPジョブトレ 発達障害コース」は、株式会社ゼネラルパートナーズが運営する発達障害の方に特化した就労移行支援事業所です。
発達障害に特化した事業所のため、グループワークで同じ障害を持つ人と意見を交わしたり、悩みを相談し合う中で、自分の障害や対策への理解を深めることができます。
- 発達障害で自分に自信がなく働いていけるか不安
- 自分に向いている仕事がわからない
- 障害者採用で就職したいが自分の障害特性をうまく説明できない
といった方は、こちらの利用を検討してみてもよいでしょう。
オンラインコミュニティ
人と直接会って話すことに抵抗がある場合は、オンラインコミュニティを活用するのも方法です。
最近では、発達障害者向けのオンラインアプリも増えてきており、同じ悩みを持つ仲間と交流したり、情報交換したりすることができます。
まずは、オンライン上で友人関係を気付き、徐々にリアルな場での交流へと繋げていくことも可能です。
大切なのは焦らず自分のペースで自分に合った方法を見つけていくことです。
必要に応じて支援を活用することで、より効率的に友達つくりを進めることができます。
まとめ|友達が離れる原因と対処
- 大人の発達障害者が友達との関係がうまく築けない原因には、コミュニケーションの困難や注意力の欠如など、発達障害者の特性が原因のものがある。
- 大人の発達障害者が友達との間で起きるトラブルは、特性によって様々である。その対象方も先に理解することで未然にトラブルを防げる可能性がある。
- まず自己理解を深めることが大切。次に、共通の趣味を持つ方と交流したり、多様なサービスを利用して友人関係をうまく築く方法がある。
いかかだったでしょうか?この記事では発達障がいを抱えている方が友達が離れていく原因について解説してきました。
上記のようなポイントを理解して自分の特性と向き合えば、発達障害の方でも長く続く友達関係を築いていくことができるでしょう。この記事が参考になりましたら幸いです。