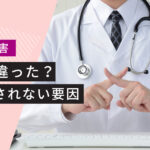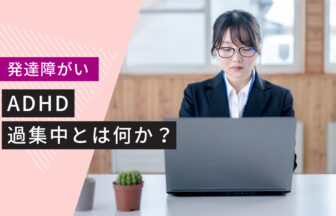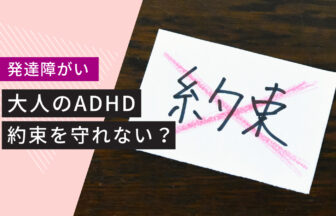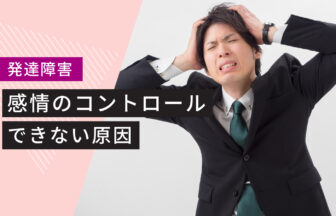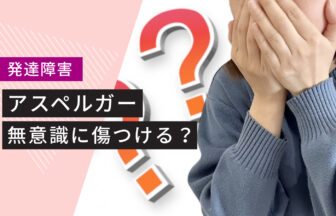「なんとなく生きづらい…。病院へ行くべき?」
「発達障害の診断を受けたらどうなるの?デメリットはあるの?」
近年、大人の発達障害が注目され、よく耳にするようになりました。
「障がいの診断を受けること」はイメージしにくいですし、発達障害の受診先である精神科・心療内科はあまりなじみのない診療科なので、少し怖いですよね。
このような悩みをお持ちの方へ向けて、
- 大人が発達障害の診断を受けるデメリットとメリット
- 大人が発達障害の診断を受ける目安
- 発達障害の診断の流れ
以上をわかりやすく解説していきます。
大人の発達障害とは?
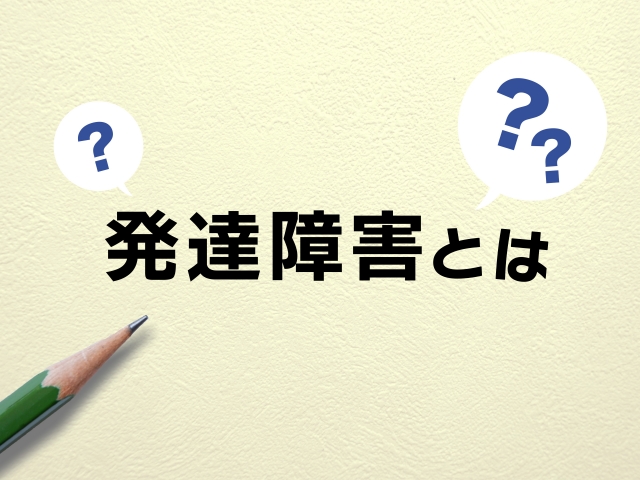
発達障害とは、脳神経の発達に不具合があるため著しい能力の偏りが起こり、日常生活を送るのに困ってしまう状態のことを指します。さまざまな種類がありますが、「自閉スペクトラム症(ASD)」「注意欠如・多動症(ADHD)」「限局性学習症(SLD)」はご存じの方も多いでしょう。
通常、発達障害は幼い頃から何らかの特性が現れますが、程度や環境によっては幼少期に大きな問題とならず見過ごされる場合があります。このような方が大人になってから生きづらさを抱えて、障がいに気づくことを「大人の発達障害」と呼びます。
大人の発達障害による困りごと
大人の発達障害による困りごとには、下記のようなものが挙げられます。
- 優先順位がわからずスケジュール管理ができない
- 興味のある仕事に集中しすぎてしまい、ほかの業務を忘れる
- 書類の誤字脱字が多い
- 職場の暗黙のルールがわからない
- 気を付けていても同じミスを繰り返してしまう
- 人とかかわることが極端に苦手で報連相がうまくいかない
- 冗談や比喩がわからず誤解が生じてしまう
- 接待や飲み会の場が苦しい
大人の発達障害では、学生までと違う社会人独特の性質と障害特性が掛け合わさり、困難さが生まれることが多いです。
周りからは「怠けている」「努力不足」と誤解されやすく、ストレスから適応障害やうつ病、依存症などの二次障害引き起こしてしまう場合もあります。
大人は発達障害の診断を受けるべきか
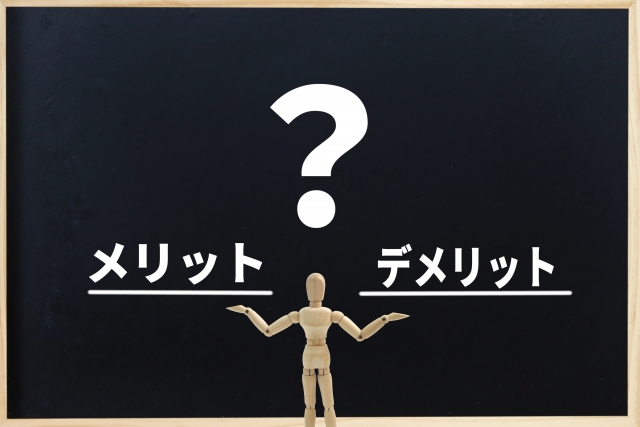
障がいの診断を受けることは、あなたにとって大きなターニングポイントとなるかもしれません。デメリットとメリットを一度、整理してみましょう。
発達障害の診断を受けるデメリット
発達障害の診断を受けるデメリットや注意点には、下記のものが挙げられます。
- 診断後は保険に入ることが難しくなる
- 「障がい」の診断を受けたことがずっと残る
- 診断には時間と費用が掛かる
- 誤診される可能性もある
- 発達障害の緩和は自らの努力と根気が必要
順に詳しく見ていきましょう。
診断後は保険に入ることが難しくなる
生命保険や医療保険は加入時に審査があり、病歴、服薬名、就業状況のほか、発達障害に関することを告知する義務があります。
発達障害はその特性から「怪我をしやすい」「体調悪化に気づかず重大な病気に罹患しやすい」「二次障害になりやすい」などと予想されるため、保険会社に「将来保険金が高額になるリスクが高い」と判断されれば、加入を断られてしまいます。
条件が緩く入りやすい保険もありますが、一般のものに比べて料金が割高です。
「障がい」の診断を受けたことがずっと残る
診断を受けた方の中には、「障がい者」になったことを受け止めきれずにショックを受けたり、怒り出す方もいます。発達障害は根本から治すことはできないため、一度診断を受けたら「障がい」の診断名はずっと残ってしまいます。
そのため、日常生活で困っていないのにもかかわらず「発達障害の傾向があるので白黒つけたい」という理由だけで受診すると、生きづらさの緩和まで至らず、診断名に振り回されてしまう事態につながりかねません。
診断には時間と費用が掛かる
発達障害の診断は医師による問診がメインですが、病院によっては補助診断としていくつかの心理検査を実施します。
検査は1つ1~2時間程度かかるため、問診から結果説明まで複数回通うことが多いです。心理検査には保険適用が可能なものとそうでないものがあります。
例として、発達障害診断時の検査として代表的なWAIS-IVは適用可能なため、病院で検査の必要性が認められれば自己負担額は3割(自立支援医療受給者は1割)となります。必要性がないと判断された場合や自由診療のクリニックでは全額自己負担です。
診断時にかかる費用の目安は下記の通りです。
| 診断の種類 | 費用 |
|---|---|
| 初診(3割負担) | 2,300~2,700円 |
| 再診(3割負担) | 1,400~1,600円 |
| 心理検査(3割負担) | 300~1,500円 |
| 心理検査(自己負担) | 10,000~20,000円 |
計15,000~50,000円ほどと、見積もると良いでしょう。
誤診される可能性もある
発達障害の診断は後述する基準をもとに行われますが、基準を満たしているかの判断をするのは医師です。ほとんどの精神科・心療内科で発達障害の受診自体は可能ですが、医師や病院にもそれぞれ分野があり、大人の発達障害を専門にしているとは限りません。
また、本人の体調次第で検査結果が変わったり、話すのが苦手な特性ゆえに困りごとや幼少期の様子をうまく伝えられず、情報が不足することも考えられます。
そのため、特に発達障害グレーゾーンにあたる方は病院によって診断結果がばらつきやすく、適切な診断を受けるにはいくつかの医療機関へ行かなければならない可能性もあります。
発達障害の緩和は自らの努力と根気が必要
病院へ行って薬を飲めば終わる風邪などと違い、発達障害は生まれつきの脳の特性であるため、治るわけではありません。
病院で受けられる薬やカウンセリングなどの治療はあくまで補助であり、障がいや自身について理解を深めたり、困りごとの対処法を一つずつ学んだりといった自らの地道な努力が必要とされます。
また、精神科・心療内科再診の所要時間は5~10分程度で、近況や薬の確認で終わってしまうことも多いです。生きづらさ緩和のために診察以外の手助けが必要であれば、自分で行動し、ほかの支援機関と連携しなければなりません。
発達障害の診断を受けるメリット
発達障害の診断を受けるメリットには、下記のものが挙げられます。
- 自分の状態を知ることができる
- 病院で治療を受けることができる
- さまざまな支援を受けることができる
- 会社に合理的配慮を求めることができる
順に詳しく見ていきましょう。
自分の状態を知ることができる
大人になって発達障害の診断を受けた方の中には、「周りと違い、普通ができないことに昔から悩んでいた。努力不足ではなく、生まれ持った脳の性質が原因だとわかって良かった」という意見も少なくありません。
また、特性を学び理解すると、苦手なことに対しての対処法が探しやすくなります。
自分の身体の状態を論理的に知り、弱みを受け入れることは、人生を前向きに生きるきっかけにもなるでしょう。
病院で治療を受けることができる
発達障害の治療方法は、薬物療法と生活療法の2つが中心です。薬物療法は主にADHDに対して用いられ、症状である「不注意」「多動性」「衝動性」の緩和が見込めます。
生活療法は、障がいについての自己理解を深めるための「心理教育」、場面の受け取り方や行ったことについて考え直す「認知行動療法」、コミュニケーション力の向上を目指す「ソーシャル・スキル・トレーニング(SST)」などがあります。
主治医がいることで、二次障害などの体調悪化時にすぐ相談ができるのもメリットの一つです。
さまざまな支援を受けることができる
診断を受けると、障害福祉サービスを利用できるようになります。
障害福祉サービスには、一般企業への就職に向けて必要なスキルや知識を得る「就労移行支援」、現状で一般企業での就職が困難な方へ就労の機会を提供する「就労継続支援」などがあり、障害の程度や体調と合わせて働き方を見つめなおすことが可能です。
全国には多様な就労移行支援事業所があります。例えば、発達障害専門の「atGPジョブトレ」では、個々の特性に合わせた実践的なトレーニングを提供しています。
こうした支援に関心があれば、まずは利用条件について情報収集をしてみるのも良いでしょう。
会社に合理的配慮を求めることができる
合理的配慮とは、障がい者とそうでない方との間に機会や待遇の差ができないよう、事業者に対して環境整備や配慮を求めることです。
例えば、発達障害の場合「指示はあいまいな表現を避け、書面でもらう」「気が散らないようパーテーションを机に置く」などが挙げられます。
「改正障害者雇用促進法」に基づいて、事業者は過度な負担とならない範囲で合理的配慮に応じる義務があります。合理的配慮は、障害者手帳の有無にかかわらず求めることが可能です。
また、障害者手帳を取得すれば、企業の障害者雇用枠を受けられるようにもなります。
発達障害の診断を受けたくないなら?

発達障害の傾向があっても、困っていなければ診断を受ける必要はありません。ASDおよびADHDの診断基準には「社会や職業、その他の機能に明らかに支障をきたしている」という項目があります。
そもそも、発達障害のような特性は人間の誰もが持ち得るものであり、濃淡はあっても「正常」「異常」の明確な区切りがない、グラデーションになっています。
このグラデーションのなかでも特に濃く苦しんでいる方たちを、便宜的に「障がいがある状態」と名付け、医療・福祉の面から支援していこう、と考えられているためこのような基準が設けられているのです。
したがって、特性と周囲の環境がマッチしていたり、困りごとが多少あっても自分で対処できる範囲内であれば無理に診断を受けなくてかまいません。
診断を検討する目安としては、
「仕事が長続きせず転職を繰り返してしまう」
「仕事で疲れすぎて休日はずっと寝ている」
「適切な睡眠や家事を行うのが難しく規律正しい生活を送ることができない」
このように、発達障害の特性と思われるものが原因で日常生活に支障をきたしている場合は受診をおすすめします。
いきなり病院へ行くことに抵抗がある場合は、次のような相談窓口を利用すると良いでしょう。
- 障害者就業・生活支援センター
- 発達障害者支援センター
- 精神保健福祉センター
発達障害の受診と診断の流れ

心理検査は支援機関でも受けることができますが、発達障害の診断ができるのは医療機関のみです。
受診先は精神科・心療内科となります。電話やWebサイトで「発達障害の診断を受けられるか」を事前に確認しておきましょう。
診断までの流れは下記の通りです。
①問診・診察
医師によって、現在困っていることや幼少期の様子などの聞き取りがあります。伝えたいことをメモにまとめたり、母子手帳や小学校の通知表などを用意しておくと役立ちます。
②検査
発達検査、知能検査、人格検査などの心理検査を行います。心理検査をしないケースもあり、病院の方針や医師の判断によって実施する種類が違います。発達障害以外の病気が疑われる場合は、脳波検査や画像検査を行うこともあります。
③診断
検査結果や診察で得られた情報を元に総合的に判断し、診断を行います。
発達障害の診断基準は?
発達障害の診断基準は、アメリカ精神医学会が作成した精神疾患の診断・統計マニュアル「DSM-5」、WHOが作成した国際疾病分類「ICD-10/ICD-11」に基づきます。
「DSM-5は精神疾患」「ICD-10/ICD-11は全ての疾病」について書かれているという違いであるため、2つの基準には大きなずれはなく、医療現場ではどちらも診断の参考にされています。
発達障害の診断書はいつ必要?
下記の場面では、発達障害の診断書が必要になります。
- 自立支援医療の申請
- 障害者手帳の取得
- 障害年金の申請
- 合理的配慮の依頼
合理的配慮の依頼時は任意ではありますが、職場から提出を求められる場合があります。
診断書の料金は4,000~10,000円程度で、発行には1~2週間ほどかかります。診断書の有効期限は3か月とされていますので、社会保障や福祉制度を利用する際はあらかじめ準備しておくと良いでしょう。
それぞれの場面については、下記のページでも詳しく解説しております。
自立支援医療の申請
障害年金の申請
合理的配慮について
まとめ
- 大人の発達障害では、社会人独特の性質と障害特性が掛け合わさり、困難さが生じる。
- 発達障害の診断は「生きづらさが改善されるきっかけ」にもなるが、「障がい者という立場になる」「時間と費用が掛かる」「結局は自分の努力が必要」という注意点もある。
- 発達障害の傾向があっても、周囲の環境とマッチしていたり、困りごとが対処できる範囲内であれば無理に診断を受けなくても良い。
- 発達障害の診断は国際的な基準をもとに問診によって行われるが、検査の有無や種類、掛かる時間と費用は病院によってさまざま。
いかがでしたか?
診断を受けても受けなくても、自分自身や周囲の環境を見つめなおし、将来について悩んでいるこの時間はきっととても意味あるもののはずです。
あなたの人生がより良くなるよう、祈っています。