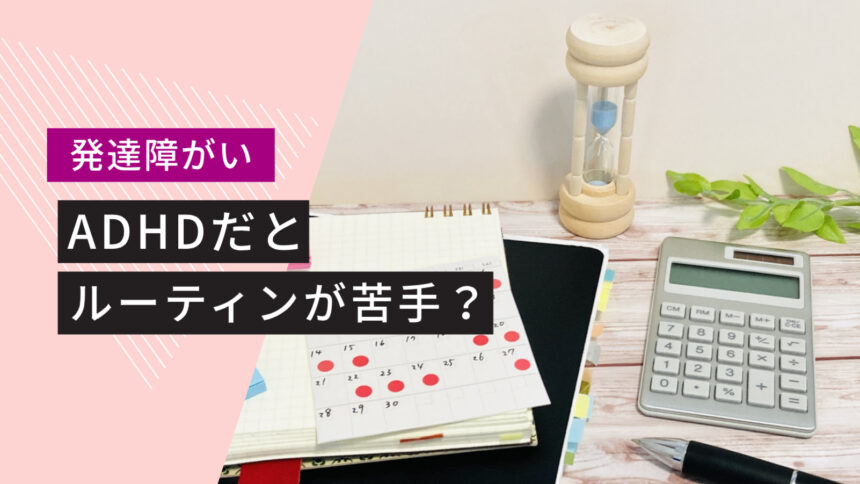ADHDの方の中にはルーティンワークができないことで困っている方がいます。
この記事を読んでいるあなたも
「頑張っているのに、ルーティンワークがこなせない…」
などといったように、朝の支度や仕事の定型業務、毎日の家事など、決まった手順をこなすことが苦手で自己嫌悪に陥っていませんか? ルーティンワークが苦手だと仕事でうっかりミスが増えたり、家事が溜まって生活が回らなくなったりするので辛いですよね。
そこで、ルーティンワークが苦手だと感じているあなたへ
- ADHDだとルーティンが苦手な3つの理由とは?
- ルーティンワークができないADHDの3つの困りごと
- ADHD向け!ルーティンワークをこなすためのコツ7選
- ADHDのルーティン化に役立つツール3選
- ルーティンワークができない自分と上手に付き合う考え方
について解説します。
この記事を読むことで、前向きに生活を送るための具体的なヒントが見つかるはずです。
ADHDだとルーティンが苦手な3つの理由とは?

周りの人が当たり前にできているように見えるルーティンが、自分には苦痛で仕方ないと思うことはありませんか?
それは、あなたの努力不足や性格の問題ではありません。ADHD(注意欠如・多動症)の特性がルーティン化を阻む原因となっている可能性があります。
ここでは、ADHDの方がルーティンを苦手だと感じる3つの理由を解説します。
注意が散りやすく、集中が続きにくい
ADHDの特性である注意散漫さや集中力の維持の難しさが、ルーティンを困難にさせる理由の一つです。
ルーティンは基本的に同じ作業の繰り返しです。しかし、ADHDの脳は外部の刺激や内部の思考に注意が向きやすく、一つの作業に意識を集中させ続けることが得意ではありません。そのため、決まった手順をこなしている最中に、他のことが気になってしまい、タスクが中断されがちになります。
例えば、
- 朝の支度をしている最中に、ふと窓の外の景色が気になって眺めてしまう
- スマホの通知が目に入ってついチェックしてしまい、気づいたら予定の時間を過ぎていた
ということが起きやすいです。
このように、注意があちこちに飛びやすい特性が、決まった手順を最後まで安定してやり遂げるルーティンを難しくしているのです。
単調な繰り返しが退屈で耐えられない
新しい刺激を求める特性や単調な作業に対する飽きっぽさも、ルーティン化を阻む理由の一つです。
ADHDの脳は、神経伝達物質ドーパミンの働きに関連して、常に目新しさや変化、強い刺激を求めやすい傾向があると言われています。 同じことの繰り返しであるルーティンは、この脳の特性からすると「退屈」で「つまらない」ものと感じやすく、継続するモチベーションを保つのが難しいのです。
昨日まで意気込んで始めたストレッチのルーティンが、今日は全く面白く感じられずやる気が起きなかったり、決まった手順の書類整理よりも、突発的に思いついた新しいアイデアについて調べたくなったりすることがあります。
そのため、変化や刺激を好む特性が、単調になりがちなルーティンを継続する意欲を自然と削いでしまうのです。
計画を立てて実行するのが難しい
物事を順序立てて計画し、それを着実に実行していく「実行機能」と呼ばれる脳の働きに課題があることも、ルーティンが苦手な理由の一つです。
ルーティンを確立するには、「何を」「いつ」「どの順番で」「どのように」行うか具体的に計画し、それを日々継続して実行する必要があります。 しかし、ADHDのある人にとっては、この計画立案、時間管理、優先順位付け、行動の開始・維持といったプロセス自体が大きなハードルとなることがあります。
例えば、「毎晩寝る前に15分間だけ部屋を片付ける」というルーティンを立てても、いざその時間になると疲れていて始められなかったり、どこから手をつければ良いか分からなくなってしまったり、そもそも計画通りに進めること自体がストレスに感じられたりします。
このように、計画を立てて段階的に実行していく能力に関する困難さが、ルーティンを生活に定着させる上での大きな壁となっているのです。
各特徴については、以下の記事でも詳しく解説しております。
ルーティンワークができないADHDの3つの困りごと

ルーティンが苦手だと、具体的にどんな場面で困ってしまうのでしょうか。「自分だけじゃないかな?」と感じているその悩み、実は多くのADHD当事者が経験していることかもしれません。
ここでは、ルーティンワークができないことで起こりがちな具体的な困りごとを3つの側面から見ていきましょう。共感できる部分もきっとあるはずです。
仕事でのミスや遅れが増える
ルーティン化の苦手さが、仕事の正確性やスピードに影響を与え、ミスや遅延につながることがあります。
多くの仕事には、日々行うべき定型業務や、守るべき手順、時間管理が含まれます。ADHDの特性により、これらのルーティンワークを安定してこなすことが難しいため、確認漏れや手順の間違い、期限に間に合わないなどが起こりやすくなります。
例えば、
- 毎朝のメールチェックやタスク整理を忘れて重要な連絡を見逃す
- 定例報告書の提出が毎回ギリギリになる
- 集中力が途切れてケアレスミスが増える
といった状況があります。
こうしたミスや遅れが続くと、業務効率が低下するだけでなく、職場での評価や信頼関係にも影響を与えかねません。
家事や身の回りのことが滞る
日常生活を支える基本的な家事やセルフケアといったルーティンがうまく回らず、生活基盤が不安定になりがちです。 日常生活には、掃除や洗濯、料理、片付け、服薬、入浴、就寝準備など、多くのルーティンが潜んでいます。
ADHDの方は、計画性の問題や先延ばし癖、飽きっぽさなどから、これらのタスクをコンスタントにこなすことが難しく、気づけば手が付けられない状態になっていることがあります。
具体的には、
- 洗濯物が山積みになる
- 食器がシンクに溜まる
- 部屋が散らかって探し物ばかりしている
- 食事の時間がバラバラ
- 処方された薬を飲み忘れる
- 夜更かしして朝起きられない
などが挙げられます。
生活環境の乱れはストレスの原因になるだけでなく、健康管理にも影響を及ぼし、「自分の生活をコントロールできていない」という無力感につながることもあります。
ADHDの先延ばし癖については、以下の記事でも詳しく解説しております。
自己肯定感が下がってしまう
ルーティンをこなせない経験が積み重なることで、自己肯定感が低下してしまう可能性があります。
ルーティンをこなせないと
「こんな簡単なことも続けられないなんて、自分はダメな人間だ」
といった思考に陥りやすくなります。
また、周囲からの期待に応えられないことや、時には注意を受けることで、さらに自信を失ってしまうこともあります。
ルーティンが苦手という特性そのものよりも、それによって引き起こされる「自分はできない」という否定的な自己認識が、精神的な負担となり、前向きな行動をさらに妨げてしまう悪循環を生んでしまうのです。
ADHD向け!ルーティンワークをこなすためのコツ7選

ルーティンが苦手な理由や困りごとがわかったところで、いよいよ具体的な対策を見ていきましょう。
ここでは、ADHDの特性を踏まえ、「これならできそう!」と思えるような、簡単で続けやすい7つのコツをご紹介します。 完璧を目指さず、まずは試せそうなものから気軽に取り入れてみてください。
- 完璧を目指さず、超スモールステップで始める
- 「時間」より「順番」を意識する
- 「見える化」でやるべきことを忘れない
- ご褒美を設定してモチベーションUPさせる
- 飽きない工夫を取り入れる
- やる気が出なくても「5分だけ」やってみる
- 周りの人に協力をお願いする
上から順番に解説いたします。
完璧を目指さず、超スモールステップで始める
最初に設定するハードルを極限まで下げ、「これなら絶対にできる」レベルから始めることが継続の最大のコツです。
ADHDの方は、完璧主義の傾向があったり、逆に「どうせできない」と諦めやすかったりします。最初から高い目標を設定すると、できなかった時の挫折感が大きくなり、継続意欲を失いやすいです。そのため、小さな成功体験を積み重ねることが重要になります。
例えば、
- 「毎日30分運動する」→「毎日1回だけスクワットをする」
- 「寝る前に15分片付ける」→「寝る前に1つだけ物を定位置に戻す」
などです。
「ばかばかしい」と思うくらい簡単なステップから始めることで、「できた!」という達成感を得やすくなり、次のステップに進むモチベーションが自然と湧いてきます。
「時間」より「順番」を意識する
時間管理が苦手な場合は、「何時になったらやる」ではなく、「〇〇が終わったら次に△△をやる」というように、行動の順番だけを決める方が実行しやすくなります。
ADHDの方は時間感覚が独特だったり、予定通りに進めるのが難しかったりすることがあります。行動の連鎖で習慣を作る方が、脳への負担が少ない場合があります。
具体的には、
- 「朝7時に着替える」ではなく、「歯を磨いたら着替える」
- 「夜10時に日記を書く」ではなく、「お風呂から上がったら日記を書く」
といった形です。
前の行動が、次の行動のきっかけになります。 時間に縛られず、行動の流れでルーティンをこなせるようになるため、より柔軟に、そして確実にタスクを実行しやすくなります。
「見える化」でやるべきことを忘れない
やるべきことや手順を頭の中だけで管理せず、目に見える形にしておくことで、注意散漫さや忘れっぽさをカバーする方法です。
ADHDの特性として、ワーキングメモリ(作業記憶)の容量が少ない傾向があり、複数の手順やタスクを記憶しておくのが苦手な場合があります。視覚的な情報は、記憶への負担を減らし、行動を促す助けとなります。
「見える化」の具体的な方法としては、
- やることリストを紙に書き出して目につく場所に貼る
- ホワイトボードに手順を図解する
- スマホのリマインダー機能で通知する
- スマートスピーカーに声でリマインドしてもらう
などです。
視覚的な手がかりがあることで、「何をすればいいんだっけ?」と思い出す手間が省け、スムーズに行動に移しやすくなります。
ご褒美を設定してモチベーションUPさせる
ルーティンを実行できたら自分に小さなご褒美を与えることで、行動への意欲が高まり継続しやすくなります。
ADHDの脳は報酬系(ドーパミン)の働きに関連があり、即時的な報酬に対して反応しやすいと言われています。そのため、単調になりがちなルーティンに「楽しみ」を結びつけることで、脳が「やりたい!」と感じやすくなります。
ご褒美の設定方法としては、
- 朝の支度が時間通りにできたら、好きな音楽を1曲聴く
- 週5日、決めた時間に薬を飲めたら、週末に好きなお菓子を食べる
- タスクリストを全部クリアしたら、15分好きな動画を見る
など、自分にとって嬉しいご褒美を設定しましょう。
ポジティブな感情とルーティンを結びつけることで、面倒なタスクも「ご褒美のためなら頑張れる」という気持ちになり、楽しく続けられるようになります。
飽きない工夫を取り入れる
単調さに飽きてしまう特性に対応するため、ルーティンの中に変化や楽しむ要素を取り入れる工夫です。
新しい刺激を求めるADHDの脳にとって、全く同じことの繰り返しは苦痛になりがちです。少しやり方を変えたり、他の活動と組み合わせたりすることで、飽きを防ぎ、新鮮な気持ちで取り組みやすくなります。
運動系のルーティンなら、日によって場所を変えてみる(公園、ジム、自宅など)。単調な作業(皿洗い、洗濯物たたみなど)は、好きな音楽やポッドキャストを聴きながら行う「ながら作業」にするなどがおすすめです。
ルーティン自体を固定しつつも、そのやり方にバリエーションを持たせることで、飽きっぽさをカバーし、継続のハードルを下げることができます。
やる気が出なくても「5分だけ」やってみる
「どうしてもやる気が出ない…」という時でも、「とりあえず5分だけ」と決めて手をつけてみることが、行動を開始するきっかけになります。
ADHDの方は、行動を開始すること自体にエネルギーが必要な場合があります。一度始めてしまえば、意外と集中できたり、作業興奮(やっているうちにやる気が出てくる現象)が起きたりすることがあります。
具体的には、
- 部屋の片付けが億劫でも、タイマーで5分だけやる
- 勉強や仕事に取り掛かれない時も、最初の1問だけ解く
- メールを1通だけ書くと決めて始めてみる
「5分で終わっていい」と思うと、始めることへの心理的抵抗が格段に下がります。 たとえ5分で終わっても、全くやらないよりは前進です。そして多くの場合、5分以上続けられるものです。
周りの人に協力をお願いする
自分一人で抱え込まず、家族やパートナー、信頼できる友人などに協力をお願いすることも有効な手段です。
ルーティン化の難しさは、本人の努力だけで解決できるとは限りません。外部からのサポートや声かけがあることで、忘れ防止になったり、モチベーション維持につながったりします。また、理解者がいることで精神的な負担も軽減されます。
家族にサポートを得られるならば、
- 朝、7時に声をかけてほしい
- 寝る前に薬を飲んだか確認してほしい
- 週末に一緒に掃除をする時間を作ろう
など、具体的にどんなサポートをしてほしいかを伝えます。
周囲の理解と協力を得ることで、一人で頑張るよりもずっと楽に、そして確実にルーティンを継続しやすくなる環境を作ることができます。
ADHDのルーティン化に役立つツール3選

「頭ではわかっているけど、どうしても忘れちゃう…」「計画通りに進められない…」という場合もあるかもしれません。 そういった場合は、ルーティン化に役立つツールを活用するのも良い手段ですよ。
ここでは、ルーティン化に役立つツールを3つご紹介します。
リマインダーアプリ
指定した時間にやるべきことを通知してくれるリマインダーアプリは、ADHDの忘れっぽさをカバーするための最も基本的かつ強力なツールです。
ADHDの特性として、他のことに気を取られているうちに、やるべきタスクをすっかり忘れてしまうことがあります。リマインダーアプリは、設定した時間にアラームや通知で知らせてくれるため、「うっかり忘れ」を防ぐのに非常に効果的です。
具体的には、
- スマートフォンの標準搭載のリマインダー
- タスク管理アプリの通知機能
- スマートスピーカー(AlexaやGoogle Homeなど)でリマインド設定する
などの方法があります。
リマインダーアプリは、視覚的・聴覚的な通知によって行動を促してくれるため、ルーティンタスクの実行漏れを大幅に減らすことが可能です。
タスク管理ツール
やるべきことをリスト化し、進捗を管理できるタスク管理ツールは、頭の中の混乱を整理し、達成感を得やすくするのに役立ちます。
ADHDの方は、多くのタスクやアイデアが頭の中で渋滞し、「何から手をつければいいか分からない」状態に陥りがちです。 タスク管理ツールを使ってやるべきことを書き出し、優先順位をつけたり、完了したらチェックを入れたりすることで、思考が整理され、行動に移しやすくなります。
- かんばん方式でタスクを視覚的に管理できるTrello
- シンプルなリスト形式のTodoist
- プロジェクト管理にも使えるAsana
などが人気です。
もちろん、手帳やノートに手書きするアナログなチェックリストも有効です。朝の支度リスト、仕事の定型業務リストなどを作成しておくと便利です。
以下のリンクから、各アプリページへと進むことができます。これ等をはじめとし、数々のアプリが存在しますので、自分に合ったものを見つけてみましょう。
タイマーアプリ
時間を区切って作業に取り組む際に役立つタイマーアプリは、集中力の維持や時間管理の苦手さをサポートしてくれます。
ADHDの方は、集中力が持続しにくかったり、逆に過集中になって時間の感覚を失ったりすることがあります。 タイマーを使って作業時間と休憩時間を明確に区切ることで、メリハリをつけてタスクに取り組むことができます。また、「〇分だけやる」と決めることで、行動開始のハードルを下げる効果もあります。
タイマーは、シンプルなキッチンタイマーやスマートフォンの標準タイマー機能など、あなたが使いやすいもので構いません。 時間という目に見えないものをタイマーで可視化することで、作業への取り組みやすさを向上させ、効率的にルーティンを進める手助けとなります。
ルーティンワークができない自分と上手に付き合う考え方

たくさんのテクニックやツールを試しても、やっぱりルーティンがうまくいかない日もあるかもしれません。そんな時、「またダメだった…」「どうして自分はできないんだ…」と落ち込んでしまうのは、とても苦しいですよね。
でも、そこで自分を責め続けてしまうと、ますます自信を失い、悪循環に陥ってしまいます。大切なのは、ルーティンができない自分を否定するのではなく、その自分とどう上手に付き合っていくか、という視点を持つことです。
ここでは、心が少し軽くなるような考え方のヒントを3つお伝えします。
「できたこと」に目を向けて自分を褒める
たとえ完璧にできなくても、少しでも実行できたことや、努力した自分自身に焦点を当て、積極的に認めて褒めることが重要です。
ADHDの方は、できていない部分やマイナス面に意識が向きやすく、自己評価が低くなりがちです。しかし、「できたこと」に意識的に目を向けることで、小さな成功体験を積み重ね、自己肯定感を育むことができます。
例えば、
「一つだけでもタスクを完了できた!」
と、できた部分を見つけて「よくやった!」と自分を褒めてあげましょう。 毎日100点を目指すのではなく、10点でもできたら上出来くらいの気持ちでいることが大切です。
「できたこと探し」を習慣にすることで、自分に対する見方が変わり、ネガティブな思考のループから抜け出しやすくなります。そして、それが次の「やってみよう」という意欲につながるのです。
失敗しても大丈夫。原因を探って次に活かす
ルーティンが計画通りにいかなかった時、それを単なる「失敗」と捉えず、原因を客観的に分析し、改善策を見つけるための「貴重な学びの機会」と捉えましょう。
「失敗=自分のせい」と短絡的に結論づけてしまうと、自己嫌悪に陥り、再挑戦する気力を失ってしまいます。 しかし、うまくいかなかった背景には、必ず何らかの理由(体調、環境、方法など)があるはずです。それを冷静に分析することで、より自分に合ったやり方を見つけるヒントが得られます。
例えば、リマインダーをセットしたのに無視してしまった場合、
「もっと気づきやすい通知方法はないかな?」
と考えてみることをオススメします。
失敗体験を人格否定と結びつけず、行動や環境を改善するための「データ」として活用する意識を持つことで、建設的に前進し続けることができます。
ルーティンは目的ではなく手段と心得る
本来、ルーティンはこなすこと自体は目的ではなく、それを通して達成したい目的(生活をスムーズにする、心身の健康を保つなど)を常に意識することが大切です。 ルーティン化そのものに固執しすぎると、「ルールを守ること」が最優先になってしまい、かえってストレスが増大したり、本来の目的を見失ったりする本末転倒な状況に陥ることがあります。
ルーティンは、あくまでより良く生きるための「道具」の一つにすぎません。
例えば、毎日完璧に部屋を掃除するというルーティンが負担なら、「快適に過ごせる空間を保つ」という本来の目的に立ち返り、
「ロボット掃除機を導入する」
など、他の手段も検討してみると良いでしょう。 ルーティンに縛られすぎず、目的達成のためのより柔軟な方法を探しましょう。
ルーティンは絶対的なものではなく、状況や自分の状態に合わせて見直したり、時には手放したりしても良い、と考えることで、不必要なプレッシャーから解放され、より楽な気持ちで日々を過ごせるようになります。
まとめ
- ADHDの方がルーティンを苦手とする理由は、注意が散りやすく、集中が続きにくい、単調な繰り返しが退屈で耐えられない、計画を立てて実行するのが難しいなど、脳の特性によるものが大きい
- ルーティン化への第一歩は、達成可能な目標を「超スモールステップ」で設定し、時間ではなく行動の「順番」を意識したり、やるべきことをリストなどで「見える化」したりする簡単な工夫から始めてみるとよい
- 単調さに飽きやすい特性には、場所を変える、好きな音楽を聴きながら行う「ながら作業」を取り入れる、完了後に自分への「ご褒美」を用意するなど、楽しみながら継続できる仕組みづくりが効果的
- どうしてもやるべきことを忘れてしまう、計画通りに進められない場合は、リマインダーやタスク管理ツール、タイマーアプリなどを活用し、苦手な部分をテクノロジーの力で補うことで実行のハードルを下げることが大切
- もしルーティンが崩れても「失敗=ダメな自分」と捉えず、原因を探って次に活かす学びの機会と前向きに考え、自分にとって心地よいやり方を見つけることが重要
ADHDの方にとってルーティンをこなすことは、簡単ではありません。しかし、今回ご紹介した方法や考え方を取り入れることで、今より前向きに生活できるようになります。
無理なく改善させていくために、自分にできそうな部分から取り組んでみてください。
また、ADHDをはじめとする発達障がいと自己肯定感の関係性は本記事で解説した通りですが、こちらでも詳しく解説しておりますので、併せて読むことをオススメします。
加えて、「ひとりでは改善が難しい」と感じている方には、「atGPジョブトレ 発達障害者コース」のような就労移行支援事業所の利用もおすすめです。個々の発達障がい者に合わせたカリキュラムが用意されているので、ルーティンワークについても実践的な訓練ができます。
障害者手帳がなくても、医師の診断書や自治体の判断などがあれば利用可能です。無料で見学もできるので、気になる方はぜひ一度確認してみましょう。