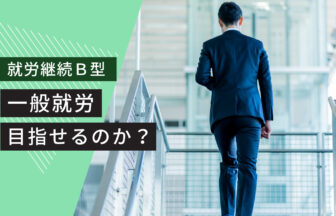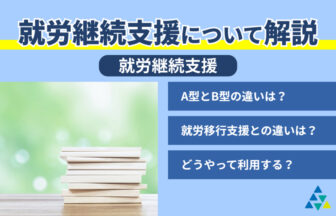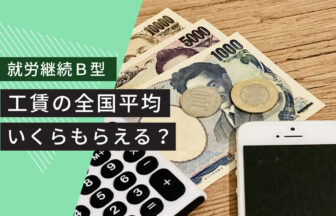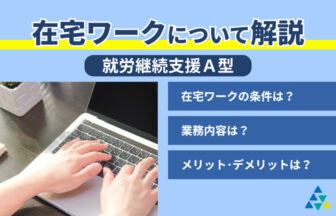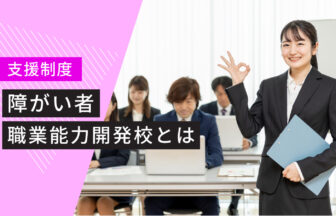電車や街中などで、赤地に白の十字とハートマークがついたストラップをカバンに付けた方を見かけたことはあるでしょうか?
これは「ヘルプマーク」という、周囲の方に支援や配慮を求めやすくするためのマークです。
「障がい者手帳が無くても、ヘルプマークはもらえる?」
「ヘルプマークの自作は禁止されているのかな?」
などの疑問を持ったことはありませんか?
- ヘルプマークとは
- ヘルプマークの対象者
- ヘルプマークをもらえる場所
- 自作をしても良いのか
について解説していきます。
ヘルプマークとは?

ヘルプマークは、外見ではわかりにくい障がい・病気・事情がある方が、周囲からの援助や配慮を受けやすくする、および助けを求めやすくするために作られたマークです。
2012年(平成24年)に東京の地下鉄で始まり、2017年(平成29年)に正式に案内用図記号に追加されてから全国に広まりました。ヘルプマークのデザインは全国共通で、赤地に白色の十字とハートが描かれており、公共交通機関の優先席などでヘルプマークが描かれたポスターを見かけることがあります。
ヘルプカードとの違い
ヘルプマークに近いものとして、「ヘルプカード」もあります。
こちらは主に財布やカバンの中に入れて携帯するもので、ヘルプマークには記載できない個人情報や連絡先、必要な支援内容などを記載します。緊急時や、コミュニケーションが難しいときに提示することで、どんな支援が必要かを伝えることができます。
配布場所および対象者などはヘルプマークと同じで、ヘルプマークと一緒にもらうことができます。
自己申告だけでOK!ヘルプマークのもらい方

「障害者手帳が無くても、ヘルプマークはもらえるのか?」という疑問がある方もいらっしゃるでしょう。実はヘルプマークをもらうときに障害者手帳や診断書は不要です。ヘルプマークが必要と判断した時に、自己申告だけでもらうことができます。
この項目では、どのような方がもらえるのか解説していきます。
ヘルプマークの対象者
ヘルプマークの対象者は明確に決められているわけではなく、「障がい・病気・事情によって支援や配慮を必要としている人」であれば誰でももらうことができます。
ヘルプマークを所持している方の代表例は下記の通りです。
- 義足や人工関節を使用している方
- がんや難病、内部障害がある方
- 妊娠初期の方
- 言語や聴覚、視覚障害の方
- 発達障害や精神障害、知的障害がある方
もっとも、上記はあくまで代表例なので、「ヘルプマークをもらうかどうか?」はあなた自身で判断することになります。
ヘルプマークのもらい方
ヘルプマークは、各都道府県の配布場所にて申し出ることで、無料で受け取れます。配布場所によっては「ヘルプマーク交付申請書」という簡単な書類を書くことがありますが、障がいや病気などを証明する書類などが必要になることはありません。
予備はもらえる?
どの都道府県も、ヘルプマークの交付は原則「1人1個」としていますが、配布場所によっては複数個もらうこともできるそうです。カバンの付け替えや紛失時などのために予備のヘルプマークが欲しい方は、もらうときに相談してみると良いかもしれません。
ヘルプマークの配布場所

この項目では、ヘルプマークの詳しい配布場所について解説していきます。
ヘルプマークは駅でもらえる?配布場所について
ヘルプマークは全国の都道府県で配布されています。
主な配布場所は下記の通りです。
- 都道府県庁・市区町村役場の担当課窓口(福祉課など)
- 各都道府県事務所・地域福祉事務所
- 保健所・保健センター
- 福祉センター・市民センター・障害者相談センター
また、ヘルプマークは代理人に受け取ってもらうこともできます。
一部の自治体によっては郵送での配布に対応しているので、配布場所へ直接行くのが難しい場合、家族や支援者にお願いするのも良いでしょう。
もらえる駅やバス停もある
東京都や北海道札幌市、宮城県仙台市などの一部自治体では、公共交通機関の駅や医療機関の窓口でもヘルプマークが配布されています。
東京都を例に挙げると、下記のような場所で配布されています。
- 都営地下鉄駅
- 都営バス停営業所
- 都電荒川線営業所
- 多摩モノレール駅事務室
- 日暮里・舎人ライナー駅事務室
- 都立病院などの一部医療機関
など
注意点としては、すべての駅で配布しているわけではないので、事前にWebサイトなどで配布しているかを確認しましょう。
ヘルプマークは自作禁止じゃない!作成方法を解説

事情により配布場所にもらいに行けない場合は、自作しても良いのでしょうか。
結論として、ヘルプマークの自作は「一定の要件を満たす場合に、自由に作成・使用できる」とされています。
この項目では、作成方法や注意事項について詳しく解説していきます。
作成方法
作成には、東京都福祉局障害者施策推進部企画課が公開している「ヘルプマーク作成・活用ガイドライン」を使用します。一部自治体のWebサイトでもヘルプマークの台紙をダウンロードできます。その後、ダウンロードしたガイドラインをフルカラーで印刷します。
ヘルプマークが載っているページがあるので、該当部分を切り取って利用しましょう。
禁止事項
自作するにあたって、いくつかルールも存在します。東京都福祉局が公開している「ヘルプマーク作成・活用ガイドライン」に記載されている主な要件や禁止事項は下記の通りです。
- ヘルプマークの主旨に沿って使用すること
- 都が提供するヘルプマークの画像を使い、デザインを変更しないこと
(色や縦横比、「✚」「♥」の配置や大きさを変更しない、マーク上に文字や絵等を記載しないなど) - 身に着けるものとして使用する場合は、ヘルプマークの周囲に余白を入れること
(本体:余白=1:2 程度)
デザインの著作権は東京都に帰属しており、商標登録されています。
詳しい条件は下記のガイドラインをご確認ください。
自作したヘルプマークがガイドラインの内容に沿っているか不安な場合や、使用について疑問がある場合などは、東京都福祉局の障害者施策推進部 企画課 社会参加推進担当へお問い合わせください。
まとめ|ヘルプマークの入手
- ヘルプマークとは、周囲からの援助や配慮を受けやすくするためのもの。近いものとして、個人情報や連絡先が記載してあるヘルプカードもある。
- ヘルプマークは、障がい者手帳や診断書が無くても、自分で必要と判断したら自己申告するだけでもらうことができる。
- ヘルプマークは、全国の役場や地域事務所、地域サポート施設などで配布されている。また、一部自治体では公営交通の駅や営業所でも受け取ることができる。
- 自作する場合は、「ヘルプマーク作成・活用ガイドライン」のルールを守って作成すること。
ヘルプマークを身に付けると、見た目ではわかりにくい事情を抱えていても配慮を求めやすくなります。
障がい者手帳や診断書に関わらず無料で受け取れるので、必要に感じた方はぜひ活用してはいかがでしょうか。
ちなみにもし、ヘルプマークに関する助言だけでなく、障がい者手帳の取得や、配慮のある職場への就職などにも興味がある場合は、「ココルポート」のような就労移行支援事業所を利用してみるといいかもしれません。
就労移行支援事業所では就労支援の一環として生活に関するサポートも行っているので、それら全てに対応してくれます。
障害者手帳がなくても、医師の診断書や自治体の判断などがあれば利用可能です。所得によっては利用の際の費用負担もありません。気になる方はぜひ一度、確認してみましょう。