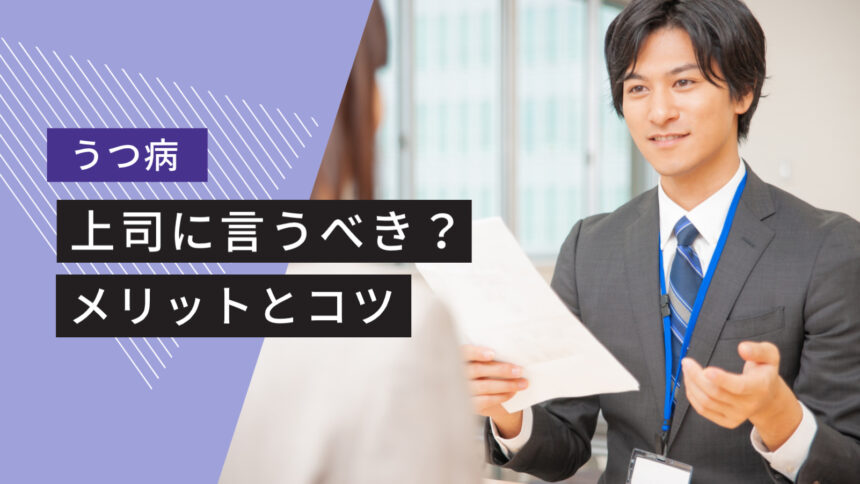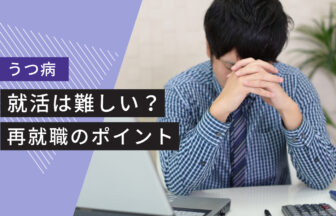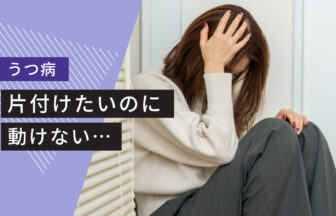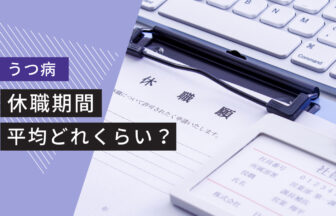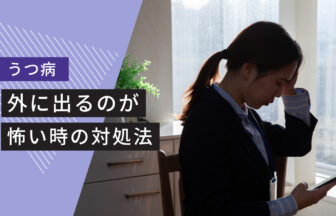ストレス社会と呼ばれる現代では、うつ病を発症してしまうことは決して珍しくありません。うつ病を抱えていると、会社でどう振舞うべきか迷うことがありますよね。
この記事を開いているあなたは、
「どうやって伝えればいいの?理解が得られるか不安……」
このような疑問や悩みを抱えてはいませんか?
うつ病について、会社や上司から理解を得られると働きやすくなる可能性がありますが、「評価に影響しないか」「周囲の目が気になる」と不安を感じることもあるでしょう。
そこで、
- うつ病は上司に報告すべきなのか
- うつ病を上司に報告するメリット
- 上司に伝えるときのポイント
- うつ病のある人が利用できる相談窓口
について詳しく解説します。
伝えるべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
うつ病は上司に報告すべき?迷ったときの判断基準

うつ病を抱えながら働く中で、「上司に報告すべきか?」と悩む方は多いです。
ここでは、うつ病について、
- 上司等への報告の義務はあるのか
- 伝えるべきかどうかの判断基準は何か
について解説していきます。
上司等への報告の義務はあるのか
うつ病を上司に報告する義務は基本的にありません。労働契約や就業規則で特別な定めがない限り、個人の健康状態を職場に開示する必要はないのです。
ただし、仕事に支障が出る場合や、勤務時間の調整が必要な場合は、伝えておくほうがスムーズです。また、休職や時短勤務を利用する際には、医師の診断書が求められることがあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
抵抗がなければ伝えたほうが良い
報告は義務ではありませんが、抵抗がないのであれば伝えたほうが良い場合もあります。上司に伝えることで、業務の配慮を受けやすくなったり、治療を進めやすくなったりする可能性があるからです。
また、周囲の理解が得られることで、精神的な負担が軽減されることもあります。
詳しいメリットについては、次の章で解説します。
こんな場合は報告しないのもOK
以下のようなケースでは、無理に報告しなくても問題ありません。
- 業務に大きな支障がなく、今のまま働くことができる
- 職場の環境や人間関係に不安があり、報告によって不利益を受ける可能性が高い
- 上司に信頼できる人がいないと感じる
特に、職場の対応に不安がある場合は、主治医や人事担当者、外部の相談機関を活用しながら慎重に判断することをおすすめします。
うつ病を上司に報告する4つのメリット
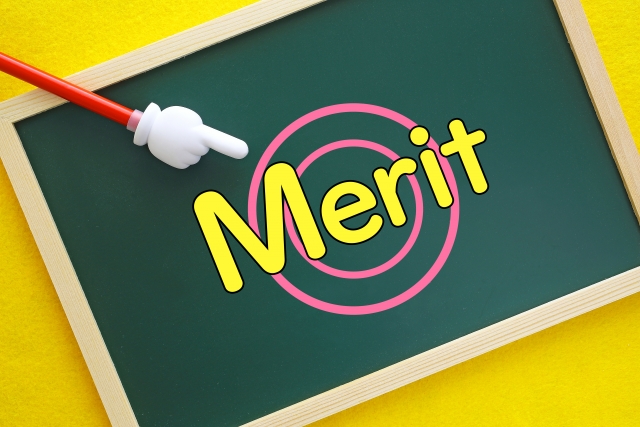
上司にうつ病を報告することには、不安や抵抗を感じる方も多いでしょう。しかし、適切に伝えることで職場でのサポートを受けやすくなり、仕事と治療の両立がしやすくなる可能性があります。
ここでは、上司に報告することで得られる4つのメリットを紹介します。
- 職場に配慮を求めやすくなる
- 無理せず治療と仕事を両立できる
- 周囲の理解が得られ、サポートを受けやすくなる
- 職場のストレスから解放される可能性がある
順番に解説いたします。
職場に配慮を求めやすくなる
1つ目は、「職場に配慮を求めやすくなる」ということです。
うつ病の症状によっては、集中力の低下や疲れやすさを感じることがあります。上司に状況を伝えておけば、業務量の調整や負担の軽減を相談しやすくなります。
例えば、
- 残業を減らしてもらう
- 業務内容を調整してもらう
- リモートワークを認めてもらう
など、働き方に柔軟な対応をしてもらえる可能性があります。
うつ病の人に向いている業務内容や働き方は、以下の記事でも詳しく解説しております。
無理せず治療と仕事を両立できる
2つ目は「無理せず治療と仕事を両立できる」ということです。
うつ病の治療には、定期的な通院や服薬の継続が必要です。上司に病状を伝えておけば、通院のための勤務時間の調整や休暇の取得を相談しやすくなります。
また、会社によっては休職制度や時短勤務の制度が用意されているため、必要に応じて活用することも可能です。
「うつ病を隠したまま無理に仕事を続けて症状を悪化させてしまう」ことを防ぐために、治療と仕事を両立させるのは非常に大切です。上司にうつ病であることを伝え、治療について相談しやすい環境を作ることは大きなメリットでしょう。
周囲の理解が得られ、サポートを受けやすくなる
3つ目は「周囲の理解が得られ、サポートを受けやすくなる」ということです。職場でうつ病について理解してもらえれば、業務上のサポートを受けやすくなるだけでなく、精神的な負担も軽減されます。
例えば、突然の体調不良で仕事を抜ける必要がある場合も、周囲の理解があれば安心して休むことができます。また、周囲があなたの体調の変化に気づきやすくなることや、困っていることを周囲に相談しやすいという点もあります。
職場のストレスから解放される可能性がある
4つ目は「職場のストレスから解放される可能性もある」ということです。
うつ病の原因が職場の人間関係や過重労働にある場合、上司に報告することで部署異動や業務内容の変更など、環境を改善できる可能性があります。また、ハラスメントが原因で症状が悪化している場合は、会社のコンプライアンス窓口や人事部と連携しながら、適切な対応を求めることも可能です。
うつ病の原因から離れることができれば、症状の改善や予防にもつながります。
上司に伝えるときのポイント4つ
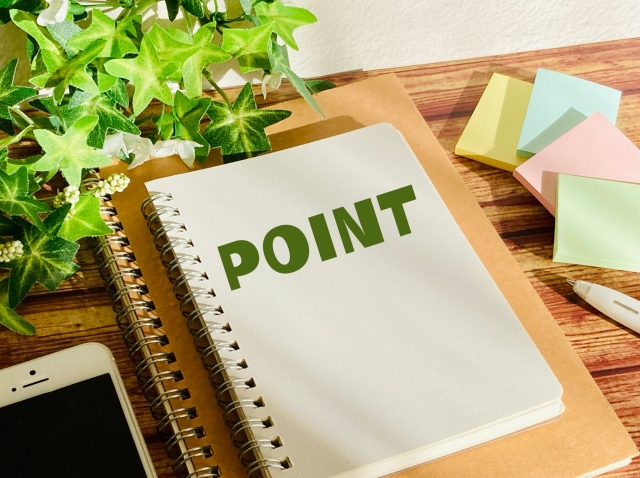
うつ病を上司に報告する際は、どのように伝えるかが重要です。伝え方を工夫するだけでも会社や上司の理解を得やすくなり、必要な配慮やサポートを受けやすくなります。
ここでは、上司に報告する際の4つのポイントを解説します。
- 診断書を準備しておくと安心
- 誰に伝えるか慎重に考える
- 自分の症状を整理し、的確に伝える
- どんな配慮が必要なのかも一緒に伝える
順番に解説いたします。
診断書を準備しておくと安心
1つ目は「診断書を準備しておく」ということです。
うつ病の診断を受けている場合は、医師が発行する診断書を用意するとスムーズです。診断書には、病名や治療の必要性、仕事への影響などが記載されているため、客観的な証拠として活用できます。
また、休職や時短勤務を申請する場合、診断書の提出が必要になることもあるので、事前に準備しておくと安心です。
誰に伝えるか慎重に考える
2つ目は「誰に伝えるか慎重に考える」ということです。
伝える相手は上司だけでなく「職場の誰に伝えるか」というのは、あなたが決める事ができます。
- 上司
- 所属長
- 人事部
- 社内の相談窓口 など
上司に直接伝えるのが難しい場合は、人事部や信頼できる別の管理職に相談するのも選択肢の一つです。特に、上司との関係が良好でない場合や、職場環境に不安がある場合は、人事部や社内相談窓口を通じて伝えたほうが安全なケースもあります。
誰に伝えるのがベストか慎重に考え、必要に応じて第三者のサポートを活用しましょう。
自分の症状を整理し、的確に伝える
上司に報告する際は、うつ病の診断を受けたことだけを伝えるのではなく、具体的な症状や仕事への影響を簡潔に説明することが大切です。
例えば、
- 朝の出勤がつらく、遅刻しがちになっている
- 集中力が続かず、作業効率が落ちている
- 気分の波があり、急に不安になることがある
といった形で、具体的に伝えると理解されやすくなります。
周囲があなたの症状や仕事への影響を理解することによって、上司にも的確な説明ができるでしょう。
どんな配慮が必要なのかも一緒に伝える
4つ目は「会社に求めたい配慮を伝える」ことです。上司に報告するときは、「~~~のため、こうして欲しい」など、あなたがサポートを必要とすることを一緒に伝えましょう。
例えば、
- 通院があるため、週に1回(月に1回)勤務時間を調整して欲しい
- 体調を崩しやすいため、残業を減らして欲しい
- 集中力が続かず作業効率が落ちているため、業務の負担を少し軽減して欲しい
といった形で、具体的な要望を伝えることで、上司も対応しやすくなります。
また、すぐに対応が難しい場合でも、「相談しながら調整していきたい」と伝えることで、話し合いながら職場環境を調整していけるでしょう。
症状や影響について正確に伝えることの重要性は、以下の記事でも詳しく解説しております。相手が上司か親かの違いはありますが、こちらも参考にしてみてください。
うつ病のある人が利用できる相談窓口5選

うつ病を抱えていると、誰かに相談したい、情報を得たいと感じることがあるでしょう。そのような時は、以下で紹介する相談窓口を頼ることがおすすめです。
それぞれの相談窓口には特徴があり、得意としている支援内容も異なるため、あなたの状況やニーズに合わせて選ぶことが大切です。
精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは、うつ病を含む精神疾患に関する相談や、社会復帰に関する支援を行っている専門機関であり、各都道府県・指定都市に設置されている専門機関です。精神科医や精神保健福祉士などの専門家が在籍しており、専門的な知識に基づいたアドバイスを受けることができます。
また、地域における精神保健福祉活動の拠点としての役割も担っており、様々な研修会やイベントなども開催されています。
以下のリンクから、全国の精神保健福祉センターそれぞれのサイトへとアクセスできます。自分の住む地域の最寄りの施設へとお問い合わせください。
保健所
保健所は、地域住民の健康をサポートする行政機関です。うつ病に関する相談も受け付けており、保健師や医師などが相談に応じてくれます。
精神保健福祉センターと同様に、専門的な知識に基づいたアドバイスを受けることができます。また、必要に応じて医療機関の紹介や、地域の福祉サービスに関する情報提供も行っています。
地域に密着した相談窓口であり、気軽に相談しやすいのが特徴です。
役所の障がい福祉課
役所の障がい福祉課では、障がい者手帳の申請や、障害福祉サービスの利用に関する相談を受け付けています。うつ病によって日常生活や社会生活に困難が生じている場合、障がい者手帳を取得することで、様々な福祉サービスを利用できる可能性があります。
障がい福祉課では、手帳の申請手続きや、利用できるサービスについて詳しく教えてくれます。
こころの健康相談ダイヤル
こころの健康相談ダイヤルは、電話による相談窓口です。
専門の相談員が、うつ病に関する悩みや不安を受け止め、アドバイスを提供してくれます。匿名で相談できるため、誰にも相談できない悩みを抱えている場合に、気軽に利用することができます。
24時間体制で対応している窓口もあり、緊急時の相談にも対応しています。
家族会や当事者会
家族会や当事者会は、うつ病を抱える本人や、その家族が集まり、互いに支え合うためのグループです。同じような悩みや経験を持つ人々と交流することで、孤独感を解消したり、新たな視点を得たりすることができます。
また、情報交換の場としても活用されており、治療や生活に関する有益な情報を得ることができます。
まとめ
- うつ病を会社や上司に報告するのは義務ではないが、伝えることで「合理的配慮が受けられる」「仕事と治療を両立させやすくできる」というメリットがある
- うつ病を会社や上司に伝えると、働き方や職場環境を調整できる場合があるため、職場のストレスから解放されて働きやすさが向上する可能性がある
- 上司に伝えるときは、「診断書を準備しておく」「誰に伝えるかを慎重に考える」「自分の症状を整理し、的確に伝える」「どんな配慮が必要なのかも一緒に伝える」というポイントを意識することが大切
- うつ病のある人が利用できる相談窓口は、「精神保健福祉センター」「保健所」「役所の障害福祉課」などがある
本記事では、「うつ病になったら会社や上司に伝えるべきか?」という点を中心に、うつ病の症状の伝え方や利用できる相談窓口について解説しました。
うつ病を抱えながら働く中で、「上司に報告すべきか?」と悩むのは自然な事です。相手が理解しやすいように工夫して伝えることによって、働きやすい環境と整えることも可能です。
うつ病は自分一人で解決することが難しい病気です。さらにうつ病を抱えながら働くということはもっと大変なことで、周りからサポートをしてもらうことはとても大切な事です。職場や上司の対応に不安があり、相談することに抵抗がある場合でも決して一人で悩むことがないよう、相談機関等を利用してみましょう。
また、治療のために休職や退職をするという選択肢もあります。仮にそうなった場合、支援をしてもらえる制度や機関を利用することをオススメします。詳しくは、以下の記事をお読みください。