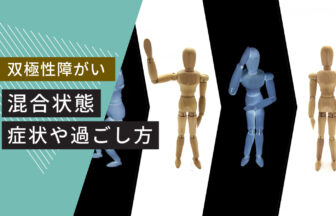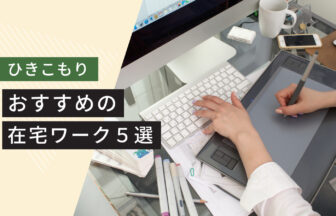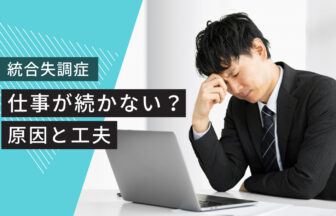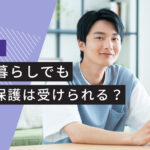「偏食や強い食事へのこだわりを治したい…」
などの疑問やお悩みはありませんか?
また、「苦手な食べ物が多く、食事が偏ってしまう」「食事へのこだわりが強くて、相手を困らせてしまう」という経験はありませんか?
発達障がいを抱えている方は、普段の生活で何かと気を使うことも多いと思いますが、食事でも悩まれている方がいることでしょう。
- 発達障がいと偏食・食事へのこだわりの関係性
- 偏食・食事へのこだわりによる困りごとや問題
- 偏食・食事へのこだわりを改善する方法
について解説していきます。
偏食や食事へのこだわりが起こる原因を知り、健康的で楽しい食生活を送る方法を探っていきましょう。
発達障がいと偏食・食事へのこだわりとの関係性

まず結論から申し上げますと、発達障害と偏食や食事へのこだわりには関係があると考えられています。
特にASD(自閉スペクトラム症)の特性が強い方は、「感覚過敏」や「こだわりが強い特性」の影響により、
- 食べるものが特定される
- 食べる時間が決まっている
- 食べる順番が決まっている
- 食べ方が決まっている
といった特徴、要するに「偏食・食事へのこだわり」が強くなります。
また、発達障害の方は「過去の嫌な経験が記憶に残りやすい」という特性を持っていることも偏食につながります。
これらの特性は、年齢を重ねると和らぐ場合も多いのですが、成人しても続くことがあります。
それでは、下記の3つの特性
- 感覚過敏
- こだわり特性
- 過去の嫌な経験が記憶に残りやすい
について、具体的な例を順に見ていきましょう。
感覚過敏
感覚過敏とは、人の五感(味覚・触覚・嗅覚・視覚・聴覚)に大きな偏りがあるという、ASDの方に多くみられる特性です。これにより、刺激に対して感覚が過敏に反応してしまいます。
この感覚過敏が、偏食を起こしやすくするのです。
具体的には、次のような状態が見られることがあります。
- 味覚過敏の場合、苦い・甘い・しょっぱい・辛いなど刺激のあるものが苦手になる
- 触覚過敏の場合、さくさく・ねばねば・どろどろとした触感のものが苦手になる
例1)コロッケなどの揚げ物の衣が、口の中を刺すように感じて食べられない
例2)金属製の食器の感触が苦手で、それに盛り付けられてあると食べられない - 嗅覚過敏の場合、生臭い・青臭い・すっぱいものなどが苦手になる
例1)マヨネーズの匂いが苦手
例2)食べ物同士の匂いが混ざり合った弁当が食べられない - 視覚過敏の場合、食べ物の見た目に過剰に反応して恐怖を感じてしまい、苦手になる
例)イチゴの表面にある、いくつものつぶつぶが怖くて食べられない - 聴覚過敏の場合、物を噛む音が気持ち悪くて耐えられない
こうして食べられないものが増えることで、偏食が生まれてしまうのです。
こだわり特性
こだわり特性とは、ある物や場所など特定の対象に、非常に強い執着を見せ、それが変化することを異常に嫌ったり、気に入った言動を繰り返したりするという、ASDの方に多くみられる特性です。
こだわり特性があると、特定の味や食感のものしか食べられないことがあります。
- スープは温かくないと飲まない
- 同じ食品でも特定のメーカーのものしか食べない
- 決まった場所や時間にしか食べない
- 食べる順番が決まっている
- 食器が決まっている
といった、食事に関するマイルールにこだわることになるでしょう。
結果として、こだわりが食事の機会を逃すことにつながり、偏食を生み出してしまうのです。
過去の嫌な経験が記憶に残りやすい
発達障害の方は、「嫌なことが記憶に残りやすい」という特性を持つ場合があります。
この特性では、これまでの経験から「全てそうである」と思い込んでしまう「白黒思考」になってしまいます。
例えば、「白い食べ物はおいしい・赤い食べ物はまずい」と見た目で条件付けしたり、「過去に魚を食べて骨が刺さった」など嫌な出来事から、毎回それがあると思い込んでしまうのです。
幼少期にこうした食べ物に関する嫌な経験をしていると、大人になっても克服できず、結果として偏食になってしまう場合があります。
偏食・食事へのこだわりによる困りごとや問題点

では、偏食や食事へのこだわりによって、どんな困りごとや問題が生じるのでしょうか?
主に下記の3つが考えられます。
- 過食とそれによる肥満
- 栄養不足による体調不良
- コミュニケーション不足
順に見ていきましょう。
過食とそれによる肥満
感覚過敏やこだわり特性は、過食とそれによる肥満を引き起こす可能性があります。
なぜかというと、「満腹」という感覚を利用して、他の苦手な感覚を緩和しようとするためです。また、満腹になるため手に取る食べ物は、自分の食べやすい決まったものになるので、偏食も進むことになります。
さらに、「必ずお茶碗2杯は米を食べる」など食事への強いこだわりを持っていると、それを守るために食べ過ぎてしまう場合もあるでしょう。
過食が進むと、体重が増加し肥満になります。肥満になると生活習慣病のリスクも上がるので、健康上良くありません。
栄養不足による体調不良
偏食が続くと栄養バランスが崩れ、体調に悪影響を及ぼします。特にビタミンやミネラルは体調やメンタルを整える上で重要な栄養素ですが、現代の簡易的な食事ではこれらが不足しがちです。
ビタミンやミネラルが不足すると、主に次のような影響が生じます。
- 疲労を感じやすくなる
- 集中力が低下する(=ミスを起こしやすくなる)
- 情緒不安定になる
- 不眠になる
- 足元がおぼつかなくなる
- 骨がもろくなる
- 貧血になりやすくなる
これに加えてタンパク質も不足すると、免疫機能や体力の低下、抜け毛、肌荒れなどの症状が出ることがあります。また、そもそもの食事量が少ないと、脱水症状が現れたり、食欲不振になったりすることもあります。
栄養バランスの良い食事をしっかり摂ることは、心身の健康を保つ上でとても重要です。
コミュニケーション不足
偏食と食事へのこだわりから、食事の時にお互い気をつかうため、他の人と食事をする機会が減ってしまう可能性もあります。
具体的な例を挙げると、苦手な食べ物が出てきた場合、その場で嘔吐してしまったり、苦しそうな表情をしてしまったりするので、相手を不快にする可能性があります。
また、こだわりの強さにより、普段は食べる順番を決めているため、複数の品目が並べられていると、どこから手をつけて良いかわからなくなってしまいます。
このようにして、人と食事することを避けるようになるため、食事によるコミュニケーションの機会は減っていくでしょう。
偏食・食事へのこだわりを改善する方法8つ

ここまで、食事へのこだわり・偏食による困りごとや問題を解説しました。では、どのようにすれば対処できるのでしょうか?
ここでは8つの方法をご紹介します。
- 食べられない原因を確認する
- 食べられる調理法を考える
- 少しずつ食べる量を増やす
- 習慣に新しいものを加える・見直す
- 食事に自分から係わる
- 別の方法で栄養補給する
- 食事を楽しめる環境をつくる
- 成功体験を積む
順に見ていきましょう。
食べられない原因を確認する
まずは、食べられない原因を確認しましょう。
感覚過敏が原因の場合は、五感の内どの感覚が苦手か確認します。複数の苦手な食材がある場合は、共通点が見えてくるでしょう。
食べられる調理法を考える
次に、食べられる調理法を考えましょう。例えば、苦手なものをすりおろしたり、細かく刻んだりして他の食べ物に混ぜることが考えられます。
また、食感を変えるために、揚げる、煮る、固めるといった工夫をしてもよいでしょう。この時の揚げ方も、衣なしにする、揚げてからある程度時間をおいて、柔らかい食感にするなどの工夫が必要です。
見た目が苦手な場合には、ミキサーにかけてしまうことも有効でしょう。
少しずつ食べる量を増やす
そして実食となりますが、初めから多くの量を食べることに挑戦するのは難しいでしょう。
したがって、まずは一口食べることから始め、徐々に量を増やして慣らしていきましょう。
習慣を見直す・新しいものを加える
こだわりが原因の場合は、あえてそのこだわり(習慣)を利用してみましょう。食事の習慣は変えずに、新しい食品をほんの少し加えていきます。
こだわり(習慣)を見直すのであれば、こだわりの内容を一気に変えず、少しずつ変えるのがよいでしょう。例えば、週4日食べていたものを2日に減らすといった具合にします。
また、食事の時間はなるべく一定の時間に定めるようにして、間食は控えましょう。空腹の時間を作ることで、自然と食事に向かいやすくなります。どうしても間食が必要な場合は、「間食=甘い物・スナック菓子」という思い込みを捨て、果物やスティック野菜などを食べると良いでしょう。
食事に自分から関わる
食事に自分から関わるようにしましょう。例えば、自分で食事を作っていない方は、自分で料理をすると良いでしょう。自分で料理をすることで、食材・食への興味が高まります。
さらに環境が許すのであれば、ベランダ菜園を設けるなどして野菜を育てるのも良いでしょう。そうすることで食材に愛着が湧き、食べることに前向きになります。
別の方法で栄養補給する
上記の対処法でも偏食が治らない場合は、別の方法での栄養補給を考えることも必要です。
苦手な食材と似た栄養素のある食材を使ったり、サプリメントを補給したりすることで偏食による栄養不足を補います。無理に食べようとして偏食を悪化させてしまっては、元も子もありません。
食事を楽しめる環境をつくる
そして「食事は楽しく」摂ることを心がけましょう。食事の際にストレスを感じず、リラックスできる環境にすることで、食に対する興味を引き出し「おいしさ」を感じられるようにします。
そのためには、例えばテレビやタブレット・スマートフォンから離れたり、事前に運動してリフレッシュしたりして、食事に集中できる環境を整えることが必要です。
また、食事の際は自分の体調をチェックして、無理のない範囲で食べ方を調整したり、相手がいる場合であれば、事前に自分の「こだわり」について相談したりすることも心がけましょう。
成功体験を積む
発達障害の方にとって成功体験は重要です。
偏りなく食事が摂れたときは、「食事ができた自分はえらい」と自分を褒めることや、自分への「ごほうび」を与えると良いでしょう。
まとめ|発達障がいの偏食と改善方法
- 発達障がい者の中でも、ASDの特性を持つ方は偏食になりやすい。これは、感覚過敏という特性により、五感に強い刺激を受けると恐怖を感じてしまうことや、こだわり特性により、決まった食べ物や食べ方しか受け付けなくなっていることが大きい。
- 発達障がい者は、過去の嫌な経験が記憶に残りやすいため、それが原因で食べられない物が増える場合もある。
- 偏食を続けると、過食による肥満から生活習慣病のリスクが上がる。栄養不足にもなりやすく、中でもビタミン・ミネラルが不足すると心身ともに不調になる。
- 食事へのこだわりが原因で人と食事することが少なくなり、コミュニケーション不足になることもある。
- 偏食や食習慣を改善するためには、食べられない原因を確認し、もし原因が感覚過敏であれば、食べられる調理法を考えた上で、少しずつ食べることが大切。原因がこだわり特性であれば、既存の食習慣の中に新しい食べ物を加えるなどする。
- 食事に集中し、楽しめる環境をつくることや、自分から食事に係わることも重要。偏食せずに食べられたときは自分を褒めることも効果的。
いかがだったでしょうか?この記事では、発達障がいを抱える方の偏食や食事へのこだわりについて解説してきました。
上記のようなポイントを押さえて食事と向き合い、健康的で楽しい食生活を送れるようになりましょう。
この記事が参考になりましたら幸いです。
なお、どうしてもお一人では改善が難しいと感じる場合は、医師への相談と並行して「atGPジョブトレ 発達障害者コース」のような就労移行支援事業所を利用するといいかもしれません。
「就労移行」という名前ですが、就労支援の一環として生活支援も行っており、発達障害者の支援についてたくさんのノウハウを持っています。あなたのお悩みにも具体的なアドバイスやサポートをしてもらえる可能性が高く、おすすめです。
障害者手帳がなくても、医師の診断書や自治体の判断などがあれば利用できます。気になる方はぜひ一度、確認してみましょう。