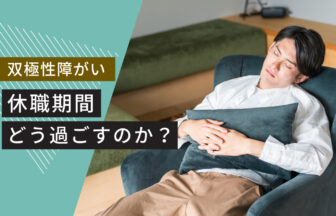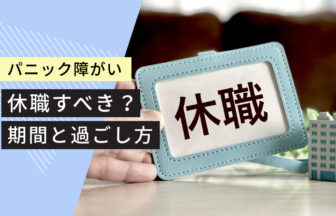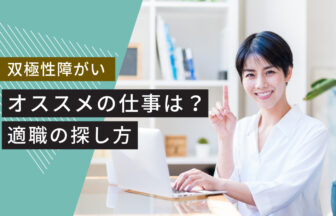この記事を開いているあなたは、
「感情の波や人間関係のことで、いつも仕事がうまくいかない…」
「安心して働ける職場を見つけるには、どうしたらいいの?」
といった悩みや疑問を抱えてはいませんか?
境界性パーソナリティ障がいの特性は理解されにくく、孤独を感じている人も多くいます。 特に、20代・30代という将来の働き方を真剣に考える時期には、自分らしく働く方法が見えず、不安になることもあるでしょう。
- 境界性パーソナリティ障がいの方の特徴
- 仕事に影響する境界性パーソナリティ障がいの特性
- 境界性パーソナリティ障がいの方におすすめの職種
- 自分にぴったりの仕事と出会うための5つのコツ
- 境界性パーソナリティ障がいの方が利用できる支援制度
について解説しています。
この記事が、境界性パーソナリティ障がいと向き合いながら自分らしい働き方を探しているあなたの、仕事探しの悩みを少しでも軽くし、新たな一歩を踏み出すためのヒントになれば幸いです。
境界性パーソナリティ障がいの方の特徴

「境界性パーソナリティ障がい」とは、感情や対人関係、自己イメージなどが不安定になりやすい精神疾患の一つです。その特性は、仕事や日常生活に影響を与えることがあり、ご自身を責めてしまったり、周囲との関係に困難を感じたりすることも少なくありません。
境界性パーソナリティ障がいには、主に以下のような特性があります。
- 感情のコントロールが難しい
- 対人関係が不安定になりやすい
- 自分についてのイメージが揺らぎやすい
- 衝動的な行動をとりやすい
まずは、これらの主な特徴を理解し、仕事選びや働き方にどう関わるかを見ていきましょう。
感情のコントロールが難しい
境界性パーソナリティ障がいの最も顕著な特徴の一つが、感情の波が激しく、コントロールが難しいことです。
主に、以下のような状態を経験することがあります。
- 気分や感情が数日にわたって急激に変化することが多く、特に対人関係に強く反応しやすい
- 些細なことで異常なほどの激しい怒りを感じ、それを爆発させてしまう
- 何をしても満たされない、心が空っぽな感覚(慢性的な空虚感)を常に抱えている
こうした感情の不安定さは、仕事のパフォーマンスや職場での人間関係に影響を与えやすく、ご自身でも「どうしてこんなに感情が揺れ動くのだろう」と苦しむ原因になります。
対人関係が不安定になりやすい
境界性パーソナリティ障がいの方は、対人関係において以下のようなパターンが見られることがあります。
- 相手に見捨てられることへの強い恐怖心(見捨てられ不安)があり、それを避けるために必死になる
- 相手を極端に理想化したり、逆に些細なことで幻滅し、激しく非難したりする
- 親密な関係を求める一方で、相手を疑ったり、距離を置いたりするなど、不安定な人間関係を繰り返しやすい
職場では、上司や同僚との関係がギクシャクしやすく、孤立感を深めたり、トラブルに発展したりする可能性があります。「嫌われたくない」という思いが強いあまり、過剰に相手に合わせて疲弊してしまうこともあります。
自分についてのイメージが揺らぎやすい
「自分とは何か」「何がしたいのか」といった自己像が曖昧で、不安定であることも境界性パーソナリティ障がいの特徴です。
- 自分の目標や価値観、性的指向などが状況や相手によって変わりやすく、一貫した自己像を持ちにくい
- 「自分がない」という感覚から、常に何かで自分を満たそうとし、それが衝動的な行動に繋がる
仕事においては、「どんな仕事が自分に向いているのか分からない」「キャリアプランが立てられない」といった悩みに繋がりやすく、頻繁な転職を繰り返す原因の一つにもなり得ます。
衝動的な行動をとりやすい
感情のコントロールの難しさや慢性的な空虚感から、以下のような衝動的な行動が見られることがあります。
- 浪費や過食、アルコール・薬物の乱用、無謀な運転などの自己破壊的な行動
- 感情の苦しさを和らげたり、助けを求める手段としての自傷行為や自殺企図
これらの行動は、仕事の継続や社会生活において深刻な問題を引き起こす可能性があります。衝動を抑えることが難しく、後悔することも少なくありません。 これらの特徴は全ての人に当てはまるわけではなく、症状の現れ方や強さも人それぞれです。
しかし、こうした特性を理解することは、ご自身に合った仕事や働き方を見つけるための重要な第一歩となります。
仕事に影響する境界性パーソナリティ障がいの特性

境界性パーソナリティ障がいの特性は、仕事の様々な場面で影響を及ぼすことがあります。 どのような困難が生じやすいのかを具体的に知ることで、対策を考えたり、自分に合った環境を選んだりするヒントになります。
この項目では、特性と仕事のミスマッチが起きている可能性を考えてみましょう。
一度就いた仕事が長続きしない
境界性パーソナリティ障がいの方には、仕事を長期的に続けるのが困難な傾向にあります。
以下のような理由が考えられます。
- 感情の波が激しく、モチベーションの維持が難しい
- 職場の些細な出来事に過敏に反応し、人間関係のストレスを感じやすい
- プレッシャーやトラブルに弱く、衝動的に退職してしまう
- 自己評価が低く、わずかな否定で仕事への意欲を失いやすい
これらの要因が複雑に絡み合い、結果として「どの仕事も長続きしない」という経験を繰り返してしまうことがあります。
職場での人間関係がストレスになりやすい
境界性パーソナリティ障がいの方は、コミュニケーションにおいて、本人の意図とは裏腹に誤解を生んだり、相手を困惑させたりすることがあります。
- 白黒思考により、相手の意図を誤解しやすい
- 些細な言動に敏感に反応し、感情的になりやすい
- 見捨てられ不安から、過剰に依存・試す・突き放すといった行動をとってしまう
こうしたコミュニケーションのパターンは、職場での人間関係を不安定にし、孤立感を深めてしまう要因になり得ます。
感情の波が集中力やパフォーマンスに影響する
感情や気分の状態によって、仕事のパフォーマンスに大きな波が出やすいのも境界性パーソナリティ障がいの方に見られる特徴です。
- 不安や気分の落ち込みで集中力が低下する
- 気分が高揚すると落ち着きを欠き、作業に集中できない
- 不安定な状態では、ミスや判断力の低下が起こりやすい
- 気分の変動で、仕事への意欲や取り組み方が一定しない
このようなパフォーマンスの波は、自己評価をさらに下げてしまうだけでなく、「周りに迷惑をかけているのではないか」という罪悪感や、「いつまた調子が悪くなるのだろう」という不安を強めることがあります。
境界性パーソナリティ障がいの方におすすめの職種5選

境界性パーソナリティ障がいを抱えていても、自分らしく働ける職場を見つけることは十分に可能です。
ここでは、境界性パーソナリティ障がいの特性に配慮しながら、安心して取り組める仕事の例とその理由を具体的にご紹介します。
注意点として、境界性パーソナリティ障がいの症状や程度は人それぞれ大きく異なるため、必ずしもすべての方に当てはまるわけではありません。ご自身の状態や興味、強みなどを総合的に考慮し、主治医や専門家とも相談しながら、慎重に検討することが大切です。
タイプは、大きく5つに分けられます。
- クリエイティブ系
- 専門職系
- ルーチン・軽作業系
- 対人支援系
- 自然・動物系
順に紹介いたします。
【クリエイティブ系】豊かな感受性や創造性を活かせる職種
境界性パーソナリティ障がいの方の中には、感情の振れ幅が大きい分、人一倍豊かな感受性や、深い洞察力、独自の美的感覚を持つ方もいます。
こうした特性は、創造的な分野の仕事において力を発揮する可能性があります。
- Webデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー
- ライター(ブログ、コピーライティング、小説など)、編集者
- 動画クリエイター、音楽家、写真家、ハンドメイド作家
向いている理由
- 豊かな感受性や独自の視点を、作品作りを通して表現し、強みにできる
- 一人で集中して作業する時間が多く、対人関係のストレスを調整しやすい
- 創造的な活動は、内面の感情を昇華させ、心の安定に繋がることもある
働く上で気をつけること(注意点)
- 評価や収入の不安定さが、感情の波や自己評価に影響しやすい点に注意
- 納期などのプレッシャーが、感情のコントロールを難しくさせることがある
- 症状が不安定な時期は、この職種が逆にストレスになる可能性もある
【専門職系】専門知識や技術スキルを活かせる職種
一つのことに集中したり、特定のスキルを深く極めたりするのが得意な方もいます。客観的なスキルを身につけることで、自信や安定感につながることもあるでしょう。また、専門職は成果物で評価されることが多く、感情的なやり取りが少ないため、対人関係のストレスを感じにくい環境と言えます。
- プログラマー、システムエンジニア(SE)
- データサイエンティスト、リサーチャー、アナリスト
- 翻訳家、テクニカルライター
- 経理・会計(専門知識を要する業務)
向いている理由
- 専門スキルが評価されるため、感情の波に左右されにくい安心感がある
- 論理的な思考が求められ、感情に振り回されにくい状態で仕事に臨める
- 成果やスキルが明確で、達成感や自己肯定感を得やすい
働く上での注意点
- 高い集中力が持続的に求められ、気分の波がある時は負担に感じやすい
- 完璧を求めすぎると、ミスへの過度な自己批判に繋がりやすい
【ルーチン・軽作業系】落ち着いて一人で集中できる職種
変化が少なく予測可能な業務は、境界性パーソナリティ障がいの方が抱えやすい不安感を軽減し、精神的に安定して取り組みやすい環境を提供してくれることがあります。
感情が不安定になりやすい方にとって、安心して続けやすい働き方と言えるでしょう。
- 事務職(データ入力、ファイリングなど特定の定型業務)
- 工場でのライン作業、検品作業、軽作業
- 清掃業務、ビルメンテナンス
- 図書館の書庫整理、資料整理
向いている理由
- 作業手順が決まっており、変化が少ないため、見通しが立ち安心して働ける
- 一人で黙々と進められる作業が多く、対人関係のストレスを軽減できる
- 日々の作業で小さな達成感を積み重ねやすく、自信に繋がりやすい
働く上での注意点
- 単調な作業が、人によっては刺激不足や空虚感に繋がる可能性がある
- モチベーション維持のために、自分なりの目標設定などの工夫が必要になる
【対人支援系】人の役に立つことでやりがいを感じる職種
境界性パーソナリティ障がいの方は、共感性が高く、他者の感情に敏感な一面を持つことがあります。
「誰かのために何かをしたい」という気持ちを活かせる仕事は、「自分は必要とされている」という実感につながり、自己肯定感や安定感を支える助けになることがあります。
- 福祉・介護施設のサポート業務(事務、清掃、レクリエーション補助など)
- 教育現場での補助業務(学童保育補助、教材準備など)
- NPO・NGO団体での事務やイベント運営補助
- 動物保護・環境保護施設のスタッフ(有償ボランティア含む)
- 共感性の高さを活かし、相手に寄り添った温かい関わりができる
- 「誰かの役に立っている」という実感が、自己肯定感や働く意欲を高める
- 人からの感謝が、精神的な安定や満足感に繋がりやすい
働く上での注意点
- 相手の感情に深く共感しすぎて、精神的に疲弊しやすい点に注意が必要
- 対人関係での理想化や幻滅など、不安定なパターンに陥らないよう意識する
【自然・動物系】動物や自然と関わる職種
人間関係の複雑さから離れ、純粋な対象と関わることで癒やしを得られる仕事は、境界性パーソナリティ障がいの方にとって安心感や精神的な安定につながる可能性があります。
対人関係で過敏になりやすい方にとって、感情の揺れを引き起こしにくい環境で過ごせることは、大きな安心材料になるでしょう。
- トリマー、ペットシッター、動物看護助手
- 動物園や水族館の飼育補助
- 農業、酪農、林業の作業員
- ガーデニング関連作業、公園管理、花屋のバックヤード業務
向いている理由
- 人間関係の複雑さから離れ、純粋な対象と関わることで心が癒やされる
- 穏やかな環境で、感情の波が刺激されにくい中で働きやすい
- 適度な身体活動が、ストレス解消や生活リズムの安定に繋がる
働く上での注意点
- 動物の病気や死など、命を扱う責任から精神的な負担を感じることがある
- 体力的な負担や、天候など環境の変化への適応が求められる
長く続けられる、自分にぴったりの仕事と出会うための5つのコツ

向いている仕事の例を知っても、実際にどのように仕事を選べばよいか迷う方も少なくありません。また、新しい職場で長く安心して働き続けたいと願っている方も多いでしょう。
ここでは、境界性パーソナリティ障がいの特性をふまえながら、自分に合った仕事を見つけ、長く続けるための5つのコツを紹介します。仕事選びで後悔しないためのヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
自分の特性を深く理解する
自分に合った仕事を見つけるには、まず自分自身をよく知ることが大切です。どんなときに感情が揺れやすく、何がストレスになるのかを振り返りましょう。
また、気持ちが落ち着く環境や、やりがいを感じる瞬間にも目を向けることがポイントです。こうした気づきをもとに、自分の得意なことや苦手なことを整理し、無理のない範囲で自分の特性を活かせる仕事を探す視点を持ちましょう。
一人での判断が難しいときは、主治医やカウンセラーに相談し、客観的な意見をもらうのも有効です。
職場環境と必要な配慮を慎重に確認する
安心して働くには、仕事内容だけでなく職場環境も自分に合っているか確認することが大切です。 境界性パーソナリティ障がいの方は環境の影響を受けやすいため、無理のない職場選びが長く働くポイントです。
以下のような点を意識して、職場の情報を集めてみましょう。
- 職場の人間関係や雰囲気を知る
- 一人作業とチーム作業のバランスを確認する
- 通勤時間や職場の騒音・照明など物理的環境をチェックする
職場選びの際は、できるだけ多角的に情報を集め、自分の心と体が無理なく過ごせる環境かどうかを丁寧に見極めることが大切です。
働きやすい配慮を整理して伝える
安心して働くためには、自分にとってどのような配慮があれば働きやすくなるのかを具体的に整理し、企業側に伝える準備をしておくことが大切です。
例えば、以下のような点について考えてみましょう。
- 定期的な短い休憩の必要性
- 指示を出す際の具体的な方法(口頭だけでなくメモも併用するなど)
- 集中できる静かな作業スペースの確保の可能性
面接時や入社時には、これらの必要な配慮を「できないこと」としてではなく、「こうしていただけると、より能力を発揮できます」という前向きな姿勢で伝えることが重要です。
伝え方に不安がある場合は、事前に支援機関のスタッフに相談し、アドバイスをもらうと良いでしょう。
完璧を目指さず、できることから始める
新しい職場では「周囲の期待に応えたい」「理想の自分でありたい」と、つい頑張りすぎてしまうかもしれませんね。
でも、最初から完璧を目指すと、かえって心が疲れてしまいます。まずは「できなくても大丈夫」と捉え、できることからあなたのペースで一歩ずつ進めていきましょう。
例えば、以下のことを事を行うと効果的です。
- 職場環境に慣れること、継続して出勤することを最初の目標にする
- 日々の業務の中で「できたこと」に目を向け、小さな成功体験を積み重ねる
- 体調や気分の波があることを受け入れ、調子が優れない時は無理をせずに周りに相談できる関係性を築く
焦らず、自分のペースで仕事に慣れていくことが、長期的に働き続けるためには重要です。うまくいかないことがあっても、「自分はダメだ」とすぐに結論づけるのではなく、状況を客観的に振り返る習慣をつけましょう。
困ったときに頼れる相談相手を見つける
職場での悩みや不安を一人で抱え込んでしまうと、気づかないうちにストレスが積み重なり、働き続けることが難しくなってしまうこともあります。
安心して仕事を続けるためには、職場内に信頼できる人を見つけておくことがとても重要です。たとえば、ちょっとした悩みを気軽に話せる同僚や、困ったときに理解を示してくれる上司がいれば、気持ちがぐっと軽くなることがあります。
最初から無理に打ち解けようとする必要はありませんが、日々の挨拶やちょっとした会話を通じて、少しずつ関係を築いていくことが、安定して働くための土台となります。
境界性パーソナリティ障がいのある方が利用できる支援制度6選

境界性パーソナリティ障がいがあると、就職や仕事を続ける中で「一人で頑張らなきゃ」と抱え込みがちです。そのため、無理を続けずに安定して働くためには、周囲の支援や制度を上手に活用し、働きやすい環境を整えることが大切になります。
この項目では、境界性パーソナリティ障がいのある方が利用できる主な支援制度を6つご紹介します。
精神障がい者保健福祉手帳
精神障がい者保健福祉手帳は、精神障がいの状態を公的に認定する手帳で、「精神障がい者手帳」とも呼ばれています。境界性パーソナリティ障がいの診断名だけで手帳の認定を受けることは難しいケースが多いですが、うつ病や不安障害といった他の精神疾患を併存している場合では、総合的な判断のもとで認定される傾向があります。
精神障がい者手帳を取得すると、以下のようなメリットがあります。
- 障がい者雇用枠への応募が可能になる
- 就労支援事業所を利用がしやすくなる
- 公共料金の割引や税金の控除
最終的な認定は、お住まいの自治体の判断や、申請時の医師の診断書の内容によって大きく左右されます。
そのため、手帳の申請を検討される場合は、まず主治医や精神保健福祉士、市区町村の障害福祉担当窓口にご相談いただくことをお勧めします。
障がい者雇用での就職
障がい者雇用とは、企業が障がいのある方を対象に設けている特別な採用枠のことです。
以下の障がい者手帳をお持ちの方が対象になります。
- 身体障がい者手帳
- 療育手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳
一般枠に比べ、病状や特性に応じた合理的配慮(業務内容の調整、労働時間の配慮など)を受けやすいのが特徴です。
障がいへの理解がある職場で、必要な配慮を受けながら働くことで、安心して仕事に取り組める環境を見つけやすくなり、安定した就労につながります。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、一般企業への就職を目指す65歳未満の障がいのある方を対象に、職業訓練、就職活動のサポート、そして就職後の職場定着までをトータルで支援する通所型の福祉サービスです。
「働く自信がない」「何から始めればいいか分からない」という方に適しています。
ビジネスマナーやPCスキルなどを学びながら、自分に合った仕事探しや就職後のサポートも受けられるため、段階的に就労を目指せます。
就労継続支援事業所(A型・B型)
就労継続支援事業所は、一般企業での就労が難しい障がいのある方に、働く機会や生産活動を通じた訓練を提供する通所型の福祉サービスです。
A型事業所
事業所と雇用契約を結び、支援を受けながら働くことができます。最低賃金以上の給与が保障されるのが特徴です。
B型事業所
雇用契約は結ばず、体調や能力に合わせて比較的短時間から、自分のペースで作業を行うことができます。工賃(作業対価)が支払われます。
どちらのタイプも、安定した環境で働く経験を積んだり、生活リズムを整えたりする場として活用できます。
障がい者就業・生活支援センター(なかぽつ)
障がい者就業・生活支援センター(愛称「なかぽつ」)は、障がいのある方の「働くこと」と「生活すること」を一体的にサポートしてくれる、地域に密着した相談機関です。
仕事の悩みだけでなく、金銭管理、健康管理、住まいのことといった生活面での課題についても相談に乗ってくれ、必要な支援につなげてくれます。ハローワークや福祉事務所、医療機関などとも連携を取りながら支援を進めてくれるため、多角的なサポートが期待できます。
ハローワークの障がい者専門窓口
各地域のハローワーク(公共職業安定所)には、障がいのある方の就職を専門にサポートする窓口が設置されています。
この窓口は、境界性パーソナリティ障がいの方や、障がい者手帳を持っていない方も利用できます。専門の相談員が、障がい者雇用枠の求人紹介だけでなく、職業相談や職業訓練の案内など、個々の状況に合わせたきめ細やかなサポートを提供してくれます。
どこに相談したら良いか分からない場合でも、気軽に足を運び、どのような支援が受けられるかを確認してみるのがおすすめです。
まとめ
- 境界性パーソナリティ障がいは、感情や対人関係の不安定さが特徴で、日常生活や仕事に影響を及ぼしやすい精神疾患
- 境界性パーソナリティ障がいの方は、感情の波が激しかったり、人間関係のトラブルが起きやすかったりするため、職場でストレスを抱えやすくなる
- 自分のペースで働ける、人との関わりが少ない、短時間や短期で働ける、といった点が境界性パーソナリティ障がいの方に合った仕事の特徴
- 境界性パーソナリティ障がいの方の仕事選びには、対人ストレスの少なさや働き方の柔軟さ、自分に合った環境かどうかを見極めることが大切
- 境界性パーソナリティ障がいの方は、就労継続支援や就労移行支援、精神障害者保健福祉手帳などの制度を活用することで、無理のない就労が可能になる
大切なのは、完璧を目指さず、ご自身のペースで、一歩ずつ進んでいくことです。焦らず、諦めず、ご自身の「得意」と「心地よさ」を大切にしながら、あなたらしい働き方を探していきましょう。
この記事で紹介した情報が、あなたが安心して社会参加を果たし、自分らしいキャリアを築いていくための一助となれば幸いです。