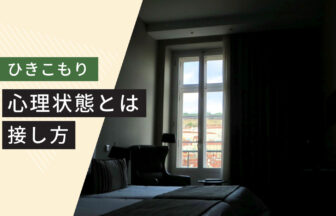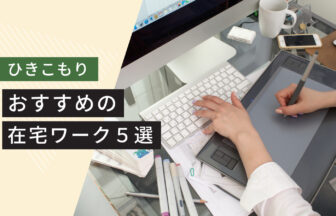「このままじゃいけないのは分かってるけど、不安で一歩踏み出せない…」
現在引きこもり状態にある方、このようなお悩みはありませんか?
引きこもりになる前は、自分がそうなることを想像しない人が大半ですが、引きこもりは誰にでも起こり得ます。
引きこもりは、自分の心がこれ以上傷つかないようにするための防衛本能が働いている状態です。一生このまま過ごすわけにはいかないと理解していても、「どうせ何をやってもうまくいかない」「もう傷つくのは嫌だ」という思いが、立ち直るきっかけを奪っていくのです。
引きこもりから立ち直ることができれば、一般の人と同じように仕事ができるようになります。社会復帰に向けてできることを一緒に考えていきましょう。
- 引きこもりから立ち直るきっかけ
- 引きこもりから脱出する方法
- 引きこもりが相談できる機関
について解説します。
引きこもりとは?

引きこもりとは、さまざまな要因によって社会的な活動に参加する機会が少なくなり、学校や仕事に行かない自宅での生活が長期化している状態のことを指します。
内閣府は、外出する機会がコンビニやスーパーマーケットへの買い物しかなく、それが半年以上続いている状態を引きこもりと定義しています。全国には、引きこもり状態にある方が約146万人いると推計されています。
引きこもりの方は、家族以外との交流を持たない状況にあることが多いです。
引きこもりの原因とは
ある日突然引きこもりになることはありません。受験や就職活動での挫折、学校でのいじめや職場でのパワハラなど、辛い経験を重ねていくうちに心が消耗していきます。
心にダメージを抱えた状態で休暇に入ったことが引き金となり、社会に戻る気力を失うのです。
昨今のコロナウイルスの影響で、これまで我慢して出社していた人々が在宅で働くようになりました。これをきっかけに元の生活に戻れなくなり、引きこもりになってしまうケースが数多くありました。
引きこもりから立ち直るには、傷ついた心を回復させ、失った自己肯定感を取り戻す必要があります。
しかし、引きこもりの方の多くは社会から「甘えている」「現実から逃げている」と非難され、家族からも「他の人はもっと頑張っている」と言われてしまう環境にいます。
家庭や社会に傷ついた心を癒す力が無いことが原因で引きこもりの方は立ち直るきっかけを失い、さらに引きこもりを悪化させてしまうのです。
引きこもりから立ち直るきっかけ

あなたが引きこもっている中でも、周囲の環境は変化し続けています。そこに引きこもりから立ち直るきっかけが隠れているかもしれません。また、自分からきっかけを作るために働きかけるだけでも、現状を変える可能性があります。
引きこもりから立ち直るきっかけには、どのようなものがあるか見ていきましょう。
年齢を重ねることに対する焦り
引きこもりになってから年数が経つと、誰しも「このままではいけない」という思いは感じるでしょう。ですが、心の底には「まだ外へ出たくない」「まだ大丈夫だよな…」という思いが存在していることも事実だと思います。
ある日、引きこもりの私の元に学生時代の友人から結婚式の招待状が届きました。その時20代後半だった私は、「ああ、もうそんな年齢だよな」と自分だけが置いて行かれている感覚をはっきりと実感しました。
年齢を重ねることに対する焦りが、引きこもりから立ち直るきっかけとなる場合があります。
小さな成功体験を積み上げていく
引きこもりが長期化すると、自己肯定感が低くなります。そのような状態から社会復帰への一歩を踏み出すことはとてつもなく大変です。そのため、小さな成功体験の積み重ねによって自信を取り戻していくことが、引きこもりから立ち直る第一歩になります。まずは、自分の部屋の掃除から始めてみてはいかがでしょうか?
それから料理や洗濯などの家事に挑戦するとよいでしょう。次に、スーパーマーケットへ買い物に行く、身だしなみを整えるために床屋へ行くなど、外に意識を向けていく事が大切です。
外出する機会が増えると、一般の方との関わりも増えていきます。元々できていたことに取り組むことで少しずつ成功体験を積み上げ、社会復帰に向けたリハビリを行っていきましょう。
家族との関係を改善する
あなたと家族の間に、気持ちのすれ違いはありませんか?
「〇〇君、就職したみたいだぞ」「お前はいつまで怠けているんだ」といった言葉が、あなたの心の大きな負担になってはいないでしょうか?
引きこもりから立ち直らせたいと考える家族の気持ちが強すぎる結果、このような言葉をかけられることは珍しくありません。それがあなたにとってプレッシャーとなるなら、改善するよう働きかけるのも一つの手段です。
あなたの引きこもりから立ち直りたい素直な気持ち、悩みや不安を家族に打ち明けることが現状を変えるきっかけになる可能性があります。面と向かって言葉にできない場合は、手紙やメモのような形にまとめて渡してみてもよいでしょう。
私が引きこもりから立ち直ったきっかけ
私は25歳の頃から、仕事を離職して貯金を切り崩しながらの引きこもり生活をしていました。いよいよ貯金が底をつきそうになった時、私は地元の祖母の家に転がり込みました。
部屋にこもってゲームとネットに入り浸るだけの毎日。それでも祖母は優しかったのです。毎日決められた時間においしい食事が用意され、少ない年金からお小遣いも出してくれました。
「そろそろ仕事を探さなきゃ」と私が言った時、「もっとゆっくり休めばいいよ、ずっと面倒みるから」と祖母は言いました。
自分がダメな人間である事を自覚していたからこそ、祖母の優しさは私の心を深くえぐりました。ひたすらに自分を受け入れてくれる祖母の優しさが辛かったのです。
祖母のために自分が稼いだお金で孝行をしたいと思ったことが、私が引きこもりから立ち直るきっかけでした。
引きこもりから脱出する方法

引きこもりから立ち直りたいという思いさえあれば、誰でも現状から脱出できます。ですが、何から行動を起こせばいいのかわからない方も多いでしょう。
私も実践した、引きこもりからの脱出方法を紹介します。
趣味を持つようにする
引きこもる間はなかなか趣味が手につかなくなる方も多いでしょう。私が引きこもりだった期間は、惰性でネットサーフィンやゲームばかりしていました。
あなたはどうでしょうか?私と同じような状況にあるのなら、まずはパソコンから離れる時間を作ることが大切です。趣味を持つことが、外出のきっかけにもなります。
どうしても趣味が見つからないという人には、次の2つがオススメです。
- 散歩
- 読書
散歩は有酸素運動として効果的で、外の空気を吸うことが気分転換にもなります。長らく引きこもりをしていると、近所を歩くだけでも新しい発見があるかもしれません。
読書も、自分を新しい世界に連れて行ってくれる魅力的な趣味です。本を読むことで知的好奇心が刺激され、自分の時間に浸ることができます。
人と触れ合う機会を作ってみる
引きこもりが長期化すると、自分の先入観を通して人を見るようになってしまいます。
誰とも関わる機会が無いと、引きこもり特有のネガティブ思考によって「この人も自分のことをバカにしてるんだろうな」と思い込むようになってしまうのです。
そのような状態で人に話しかけるのは怖いですよね?
私はまず、家族への挨拶から始めました。すると、母から「おはよう、今日は朝早いね?」と意外な言葉をかけられたことに驚きました。引きこもりの自分に嫌悪感があった私は、どうせ家族も自分のことを嫌っているのだと過度に思い込んでいたのです。
そこから、周りの方たちは引きこもりの自分に特別マイナスな感情を持っているわけではなく、私が自分の殻を破って再びアクションを起こすまで、気長に待ってくれていたのだろうと思えるようになりました。
それ以来、少しずつ学生時代の友人に連絡を取り、疎遠になっていた関係を修復することができました。
このように、コミュケーションの機会を作ることで、少しずつながら状況を改善できるようになるので、まずは可能な範囲で実行していきましょう。
なお、引きこもりからの脱出は、体力づくりをすることでより効率的に進めることができます。体力づくりについては、以下の記事で詳しく解説しております。
引きこもり脱出を相談できる支援機関

引きこもりから脱出するには、辛い気持ちを周囲に発信して助けを求めることも大切です。引きこもりが社会問題として受け止められている昨今では、引きこもりの方が利用できる支援機関や相談窓口はたくさんあります。その一例を確認していきましょう。
引きこもり地域支援センター
引きこもり地域支援センターは、行政が運営していて各都道府県に設置されている相談窓口です。
社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を持つスタッフが中心となり、社会復帰への第一歩となる居場所づくりから就職関係まで、幅広い支援を行っています。
基本無料(一部例外あり)で利用できる点も大きなメリットです。
引きこもり専門のNPO法人
NPO法人とは非営利団体のことで、「世の中のため、誰かのため」になりたいと考えている方が集まって形成されています。
引きこもり専門のNPO法人は、引きこもりの当事者と家族を交えて問題解決を進めることを得意としています。同じ引きこもりの境遇に置かれた方と交流する機会が得られることも特徴です。
ただし、非営利団体とはいえ利用には料金がかかる場合がほとんどであるため、注意が必要です。
心療内科や精神科などの医療機関
引きこもりの方は、うつ病などの精神疾患を発症していることが多いです。そのため、引きこもりの方を対象としたデイケアを行っている心療内科や精神科があります。
- 寝つきが悪く、昼夜逆転の生活になった
- マイナス思考になって将来に対して希望が持てない
- 働く気力が湧いてこない
このような症状がある時は、心療内科や精神科の治療を受けることで改善する可能性があります。
また、精神疾患の有無を問わず、カウンセリングを受けることにより、身近な人に言えない悩みを相談することができるため、他者と関わるためのリハビリとしても効果的です。
精神科デイケアにつきましては、下記の記事で詳しく解説しております。
就労移行支援
就労移行支援は、主に障がいを抱えている方に対して、生活支援と就職支援を行っている支援機関です。生活リズムを整えながら就職の準備ができるため、引きこもりの方が立ち直るきっかけとして適しています。
「ひきこもりの背景にうつ病や不安障害などの精神疾患がある」と診断されている方は、就労移行支援を利用できる可能性があります。
障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書や自治体の判断によって利用が認められることがあるので、気になる方は各相談窓口へ相談してみましょう。
なお、「どんな就労移行支援があるか気になる」という方は、以下の3つを参考にしてみてください。
ココルポート
ココルポートは、利用者一人ひとりのペースに合わせた個別支援計画が特徴の就労移行支援事業所です。「働きたいけど、何から始めたらいいかわからない」「社会に出るのが不安」といった、ひきこもりやニートの状態にある方の気持ちに寄り添い、丁寧なカウンセリングから支援を進めてくれます。
- ビジネスマナー
- PCスキル
- コミュニケーション能力
これらを高めるトレーニングも充実しており、社会参加への第一歩を踏み出すための準備から就職活動、職場定着まで、専門スタッフがトータルでサポートしてくれるので、安心して次のステップへ進めます。
ミラトレ
ミラトレは、実践的な職業訓練と豊富な求人紹介で、就職に強いと評判の就労移行支援事業所です。特に企業との連携を重視しており、実際の職場環境に近い形でのトレーニングやインターンシップの機会を提供しています。
ひきこもりやニート期間が長く、働くことへのブランクがある方でも、仕事の感覚を取り戻しやすいのが魅力です。多様な職種に対応したプログラムが用意されているため、自分の興味や適性に合った仕事を見つけられます。
NeuroDive
NeuroDive(ニューロダイブ)は、特に発達障がいのある方の特性に合わせた専門的な支援を提供している就労移行支援事業所です。コミュニケーションや集団行動に苦手意識を感じている方でも、理解のある環境で安心して訓練に取り組めます。
IT・Web分野に特化したカリキュラムが充実しており、プログラミングやデザインなど、専門スキルを身につけたいと考えている方におすすめです。
まとめ|引きこもりから立ち直るきっかけと脱出方法
- 引きこもりから立ち直るには、「小さな成功体験を積み重ねる」「家族に悩みを打ち明ける」といったきっかけが必要
- 引きこもりから脱出するには、「趣味を見つける」「人と触れ合う機会を増やす」といった方法が効果的
- 引きこもりの方が相談できる支援機関はたくさんある。こうした施設や周囲の人に助けを求めることが社会復帰への近道となる
引きこもりは、誰にでも起こり得る社会問題の一つです。引きこもりから立ち直るためには、傷ついた心を癒し、自己肯定感を取り戻すことが必要です。
しかし、引きこもり当事者だけの力で立ち直ることは簡単ではありません。
自分の辛い気持ちをしっかりと理解し、周囲に「助けて」と発信することが、引きこもりから立ち直る近道です。