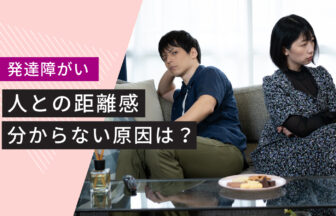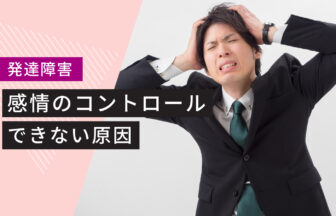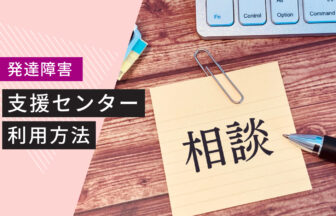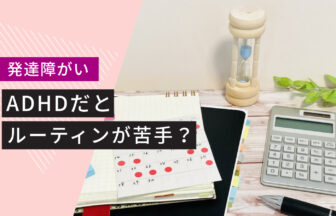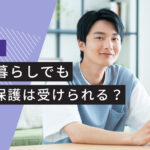発達障がいの特性を持つあなたは、
「私って嫌われやすい?何がいけないのかな?」
日々の生活の中で、そんな風に感じてしまうことはありませんか?
発達障がいを抱えていると、周りの人と「何かが違う」と感じたり、コミュニケーションが上手くいかなかったりすることがありますよね。
そういったお悩みを解決するために、
- 発達障がいの特性で誤解されやすい言動とは?
- 「嫌い」ってどういうこと?相手の気持ちを理解するヒント
- 今日からできる!コミュニケーションをスムーズにする3つのステップ
- もうひとりで悩まない!頼れる相談先リスト
これらについて解説します。
ひとりで悩まず、一緒に解決策を見つけていきましょう。
発達障がいの特性で嫌われやすい5つの言動パターン

発達障がいの中でも、特にADHD(注意欠如・多動性障害)とASD(自閉スペクトラム症)の特性を持つ人は、言動を周囲から誤解されやすく「嫌われているのなか?」と感じてしまうことがあります。
ここでは、よくある5つのパターンとその理由を解説します。
空気が読めないと思われてしまう
ASDの特性を持つ人は、場の雰囲気や相手の感情を読み取るのが苦手です。空気が読めない発言で、「え、今それ言う?」と、相手を困惑させてしまうことがあります。
よくある場面
- 会議中、みんなが真剣に議論しているのに、的外れな冗談を言ってしまった
- 友達が落ち込んでいるのに、いつも通りに接してしまい、「冷たい人」と思われた
言葉の裏にある意味やニュアンス、表情や声のトーンから相手の感情を読み取るのが難しい傾向にあり、場に合わないことを言ってしまう傾向にあります。そのため、相手からは「状況を理解していない」「人の気持ちを考えていない」と思われてしまいます。
こだわりが強く、融通がきかないと思われがち
ASDの特性を持つ人は、特定の物事へのこだわりが強く変化を嫌う傾向があり、「融通がきかない」「頑固だな…」と思われ、周囲をイライラさせてしまうことがあります。
よくある場面
- 仕事の手順が少し変わっただけで、パニックになってしまった
- いつもと違うやり方を嫌がり、自分のやり方を押し付けようとしてしまった
急な予定変更や、いつもと違う状況への対応が苦手という側面があるため、相手からは「わがまま」「協調性がない」と思われてしまいがちです。
症状については、以下の記事でも詳しく解説しております。
正直すぎて、相手を傷つけてしまう
ASDやADHDの特性を持つ人は、思ったことをストレートに口にしてしまいがちです。「思ったこと言いすぎ!」「デリカシーがない」と思われ、相手を傷つけてしまうことがあります。
よくある場面
- 友達の服装を見て、「太った?」とつい言ってしまった
- 友達が新しく買ったカバンを見て、「似合ってない」と言ってしまい、場の空気が悪くなった
ASDの人は、相手の気持ちを推し量ることが苦手であり、またADHDの人は、発言する前にそれが適切かどうかを考えるのが苦手です。それが、相手に対しての失礼・無神経な発言につながることがあります。
症状については、以下の記事でも詳しく解説しております。
一方的に話して、会話が続かない
ASDやADHDの特性を持つ人は、自分の興味のあることを一方的に話してしまいがちです。相手に「話を聞いてくれない」と思われ、会話が続かないことがあります。
よくある場面
- 相手が話しているのに、自分の話したいことを話し始めてしまった
- 相手の質問に答えず、自分の話ばかり続けてしまう
ASDの人は、相手の話題に興味を持ちにくく、会話のペースを合わせるのが苦手な人が多いです。また、ADHDの人は自分の興味のあることに夢中になり、相手の話を聞き逃してしまいがちです。これらが原因で、「自分勝手な言動」や「人の話を聞かない傾向」として現れるのです。
症状については、以下の記事でも詳しく解説しております。
忘れ物や約束を破りがちで、ルーズだと思われる
ADHDの特性を持つ人は、注意欠如や衝動性、実行機能の困難さから、「ルーズな人」と誤解されることがあります。
よくある場面
- 大事な会議の時間を忘れてしまった
- 提出物の締め切りを守れず、怒られた
不注意で必要なものや情報を忘れてしまったり、実行機能の困難さ故に、計画を立てて時間通りに行動するのが苦手だったりすることがあります。これらは、相手からすると「だらしない」「責任感がない」などというように映ります。
症状については、以下の記事でも詳しく解説しております。
「嫌い」ってどういうこと?相手の気持ちを理解するヒント

そもそも「嫌われる」とはどんな状態なのでしょうか? 実は、「嫌い」という感情はとても主観的なものです。ここで少し、相手の立場になって考えてみましょう。それが、より良い人間関係を築く第一歩になります。
「嫌い」は人それぞれ
同じ言動でも、人によって「嫌い」と感じるかどうかは違います。
人はそれぞれ、育ってきた環境、考え方、大切にしているものが違うからです。だから、ある人にとっては全く気にならないことが、別の人にとってはすごく嫌なこと、という場合もあります。
具体例
- 静かな場所で、大声で話す人がいたら
→ 集中したい人にとっては「迷惑!嫌い!」
→ 賑やかな方が好きな人にとっては「別に気にならない」 - 締め切り直前に、何度も質問をされたら
→ 余裕を持って仕事を進めたい人にとっては「もう、嫌!」
→ 協力して仕事を進めたい人にとっては「頼ってくれて嬉しい」
どんな時に「嫌」と感じる?場面別にチェック!
人によって「嫌」と感じるところが違うことを理解して相手を知れば、トラブルを未然に防ぐことができます。
よくある場面と、相手の気持ち
- 職場
集中している時に話しかけられる → 「邪魔しないで!」
会議中に私語が多い → 「真面目に聞いて!」
締め切り直前に仕事を頼まれる → 「もっと早く言って!」 - 友人関係
相手が忙しい時に長電話をする → 「今は時間がないの!」
約束の時間に遅れる → 「待たされるのは嫌!」
愚痴ばかり言う → 「私も疲れているのに…」
嫌われないコミュニケーションをするための3ステップ

「嫌われるのは発達障がいだから、仕方ない…」と諦めないでください。コミュニケーションは少し工夫するだけで、スムーズに行うことができます。
ここでは、今日から実践できる3つのステップを紹介します。
【ステップ1】自分を知ることから始めよう
あなたの得意なこと、苦手なことを知り、ありのままの自分を受け入れることが大切です。
具体的に何をすればいいか
- 自分の特性を書き出す
・得意なこと、苦手なこと
・好きなこと、嫌いなこと
・どんな時に困ることが多いか
・どんな時に褒められることが多いか
などを、ノートやスマホに書き出してみましょう。 - 過去の経験を振り返る
・どんな時に「嫌われたかも…」と感じたか
・どんな時に「うまくいった!」と感じたか
を思い出し、具体的に書き出してみましょう。 - 信頼できる人に聞いてみる
家族、友人、先生、カウンセラーなど、信頼できる人に、自分の印象を聞いてみましょう。
客観的な意見を聞くことで、新たな発見があるかもしれません。
自分を受け入れるとは
完璧主義を手放し、「ありのままの自分」でOK!と認めることです。「私は私でいい」「これが私の個性」など、自分を肯定する言葉を、口に出したり、心の中で唱えたりしてみましょう。「できないこと」を責めるのではなく、「できること」に目を向けましょう。
【ステップ2】相手に寄り添った言葉を選ぼう
発達障がいの特性によるコミュニケーションのすれ違いは、言葉選びや伝え方の工夫で、ぐっと減らすことができます。できる事から試してみましょう。
具体的な工夫と会話例
- 言葉の裏を読むのが苦手な場合
NG例:「あれ取って」と言われて、何のことかわからず間違ったものを取ってしまう。
OK例:取る前に「すみません、あれってそこの赤いペンのことですか?」と聞く
困った時は:「〇〇って、どういう意味ですか?」と、具体的に質問する - 自分のやり方にこだわってしまう場合
NG例:いつもと違うやり方が嫌で、自分のやり方を人に押し付けてしまう
OK例:「ひとまず、やってみます」(納得していなくても、一度考える時間を作る)
困った時は:何が嫌だと感じているのか、一旦考えてみる
(そこに「いつもと違うから」以外の理由がない場合は、
やってみることですんなり受け入れられる可能性あり) - 思ったことを口にしてしまう場合
NG例:相手の服装を見て「太った?」(相手を傷つけてしまうかも…)
OK例:「その服、素敵ですね。どこで買ったんですか?」(褒め言葉から会話を始める)
心がけ:発言する前に一呼吸置き、「これは言っても大丈夫かな?」と自問自答する - 一方的に話してしまう場合
NG例:相手が話しているのに、自分の話したいことを話し始める
(相手は「話を聞いてくれない」と感じる)
OK例:相手の話を最後まで聞き、「それで、〇〇さんはどう思ったんですか?」など
質問を挟む(会話のキャッチボールを意識する)
心がけ:相手の話に耳を傾け、質問をしたり、相槌を打ったりする - 忘れ物が多い、約束を守れない場合
工夫:メモやリマインダーを活用する。難しい場合は、事前に周囲に伝えておく
「すみません、忘れっぽいので、〇〇の件、リマインドしていただけると助かります」
【ステップ3】素直に頼って、助け合おう
すべてを完璧にこなす必要はありません。「できないこと」は素直に伝え、周りの人に頼ることも、大切なコミュニケーションスキルです。
具体的にどうすればいいか
- 「できないこと」を伝える
「〇〇が苦手なので、△△していただけると助かります」
「〇〇が難しいので、××を手伝っていただけませんか?」
「申し訳ありませんが、〇〇ができません。代わりに、△△ならできます」 - 頼る時のポイント
・感謝の気持ちを伝える:「ありがとうございます」「助かります」
・相手の負担を考慮する:「もしご迷惑でなければ…」
・できる範囲で、自分も協力する姿勢を見せる:「私も〇〇を頑張ります」
発達障がいで悩んだ時に頼れる6つの相談先

「誰に相談すればいいか分からない…」そんなあなたのために、発達障がいに関する相談ができる窓口をまとめました。気になるところがあったら、お住まいの地域にあるかどうか確認してみましょう。
相談窓口は、主に以下の6つとなります。
- 発達障がい者支援センター
- 相談支援事業所
- 精神保健福祉センター
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所
- 医療機関(精神科、心療内科)
順番に紹介いたします。
発達障がい者支援センター:困った時の総合窓口
発達障がい者支援センターとは、発達障がいのある人やその家族からの相談に応じ、専門的なアドバイスや支援を行う機関です。日常生活・仕事・学校生活での悩みや、発達障がいについての相談等を受け付けております。
以下の記事でも詳しく解説しておりますので、併せて読むことをオススメします。
相談支援事業所:地域のサービスにつなげてくれる
相談支援事業所とは、障がいのある人が地域で安心して生活できるよう、さまざまな相談に応じる機関です。福祉サービスや生活の困りごと、虐待や差別被害等の相談を受け付けている他、障がい福祉サービスの利用や支援についてなどの情報提供やカウンセリングも行っています。
また、市町村や都道府県の指定によって「特定相談支援事業所」「一般相談支援事業所」の2種類に分けられます。
自分に合ったサービスについての相談は「特定相談支援事業所」、地域で生活を続けていくための支援(地域定着支援)等については「一般相談支援事業所」をオススメします。
精神保健福祉センター:心の専門家に相談できる
精神保健福祉センターとは、心の健康に関する相談に応じ、専門的なアドバイスや支援を行う機関です。
心の病気や精神的な悩み等がある人、社会復帰について相談したい人等は、こちらをご利用ください。また、地域における精神保健福祉活動の拠点としての役割も担っており、様々な研修会やイベントなども開催されています。
全国の精神保健福祉センターは、以下のリンクから調べることができます。
就労移行支援事業所:就職の悩みを解決できる
就労移行支援事業所とは、障がいのある人の就職をサポートする機関です。仕事を探している人や、就職活動で悩んでいる人、働くためのスキルを身に着けたい人にオススメです。
就労移行支援事業所については、以下の記事でも解説しております。
また、「実際にどんなものがあるのか気になる」という人のために、以下でオススメの就労移行支援事業所をご紹介します。無料で見学もできるので、気になる場合は気軽にチェックしてみてください。
atGpジョブトレ 発達障害コース
atGpジョブトレ 発達障害コースは、発達障がいのある方に特化した就労移行支援事業所です。発達障がい者に対するサポート実績が豊富なので、あなたのお悩みについても具体的なアドバイスやサポートをしてもらえます。
専任のスタッフが、こまめな個別面談を通じてあなたの問題の対処法について一緒に考えてくれます。もちろん就労についてのサポートも手厚いので、利用できれば就職活動も安心です。
ココルポート
ココルポートは、温かく包み込むような支援スタイルが特徴の就労移行支援事業所です。発達障がいをお持ちの方でも安心して通えるよう、一人ひとりの心境に配慮した、無理のないペースでのプログラムを提供しています。
基本的なPCスキルからグループワークまで、多様な活動を通じて「できること」を増やし、社会参加への自信を育んでくれます。相談しやすい環境が魅力です。
ミラトレ
ミラトレは、実際の企業が求めるスキルや人物像を意識した実践的な訓練に強みがある就労移行支援事業所です。発達障がいで働くことにブランクがある場合でも、模擬職場やインターンシップを通じて仕事の感覚を取り戻せます。
就職活動を有利に進めるためのサポートが充実しており、多くの卒業生が希望の職場で活躍しています。「就職したい」という気持ちが強い人にとってはとても心強いでしょう。
就労継続支援事業所:自分に合った働き方を見つけよう
就労移行支援事業所とは、障がいのある人に働く場所を提供する機関です。一般企業で働くのは難しい人や、自分のペースで働きたい人、働くことを通して社会とのつながりを持ちたい人等にオススメです。
こちらは、A型とB型に分けられます。障がいや状況の度合いによって、オススメする事業所が異なります。
A型とB型の違いなど、就労継続支援事業所については、以下の記事で解説しております。
医療機関(精神科、心療内科):診断や治療の相談もできる
医療機関では、発達障がいの診断、治療、薬物療法など、医学的なサポートを受けることができます。 発達障がいの疑いがある人・治療を受けたい人や、薬について相談したいこと等がある人は、こちらを利用するのがオススメです。
発達障がいの診断については、以下の記事でも詳しく解説しております。
【Q&A】よくある質問と回答

最後に、「発達障がいのせいで嫌われてしまう」といった悩みを抱えている人によくある質問とその回答についてまとめました。
-
大人になってから発達障がいと診断されることはありますか?診断されたらどうすれば良いですか?
はい、あります。まずは、自分の特性を理解することが大切です。専門機関に相談し、適切なサポートを受けながら、自分に合った生き方を見つけていきましょう。
-
発達障がいの特性は、「個性」として受け入れるだけではダメですか?
日常生活や社会生活に困りごとがある場合は、専門家のサポートが必要なこともあります。無理せず、相談してみましょう。
-
発達障がいの人は、どんな仕事に向いていますか?
人それぞれですが、例えば、
- ASDの人:正確さや集中力を活かせる事務職、研究職、プログラマーなど
- ADHDの人:行動力や発想力を活かせる営業職、企画職、クリエイターなど
が向いていると言われています。自分の得意なことや好きなことを仕事にできるのが理想ですね。
それぞれが向いている仕事については、以下の記事でも詳しく解説しております。
-
薬物療法って、どんな効果があるのですか?副作用は?
薬で、不注意、多動性、衝動性などの症状を和らげることができます。ただし、発達障がいそのものを治すものではありません。副作用には、食欲不振、吐き気、不眠などがあります。
必ず医師と相談し、指示に従って服用しましょう。
まとめ|あなたらしく輝くために
- 発達障がいの人は、「空気が読めない」「こだわりが強い」「思ったことを口にしてしまう」「一方的に話してしまう」「忘れ物が多い」等の理由で、反感を買いやすい。
- 「嫌い」は主観的な感情。嫌われやすい状況を相手の立場で考えることが重要。
- コミュニケーションを円滑にするには、「自分の特性を知り、受け入れること」「相手に伝わるコミュニケーションを意識すること」「できないことは素直に伝え、協力を求めること」が挙げられる。
- 困ったときは、できるだけ早く「発達障がい者支援センター」「相談支援事業所」などどいった支援機関を頼るのが、問題解決への早道。
発達障がいの特性は、時に周囲の人に誤解され、「嫌われやすい」と感じてしまう原因になることがあります。 しかし、発達障がいの特性は「弱み」ばかりではなく、工夫次第ではあなたの「個性」や「強み」にもなりえます。
「嫌われるかも…」と恐れず、できることから行動を起こしていきましょう。