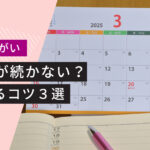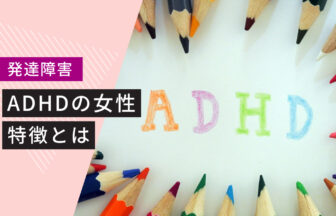あなたは「フラッシュバック」という言葉をご存知でしょうか?突然過去の記憶が思い出されたり、夢に出てきたりする現象のことです。本来はいい記憶も嫌な記憶も含みますが、心理学的には主にトラウマと呼ばれるような嫌な記憶が思い出される意味合いで使われています。
いい記憶なら幸せな気分になれますが、嫌な記憶だとつらいですよね。
「気分が落ち込むから思い出したくないのに…」
なんて、つい1人で悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
フラッシュバックは、極度のストレスによって引き起こされると言われていますが、実は発達障がいの方が起こしやすい現象でもあるのです。
- 発達障がいの方がフラッシュバックを起こしやすい原因
- フラッシュバックの回数やつらさを軽減する工夫
- つらい場合は専門医に相談したほうが良い理由
について解説していきます。
お悩みの方はぜひご一読ください。
発達障がいの方がフラッシュバックを起こしやすい3つの原因
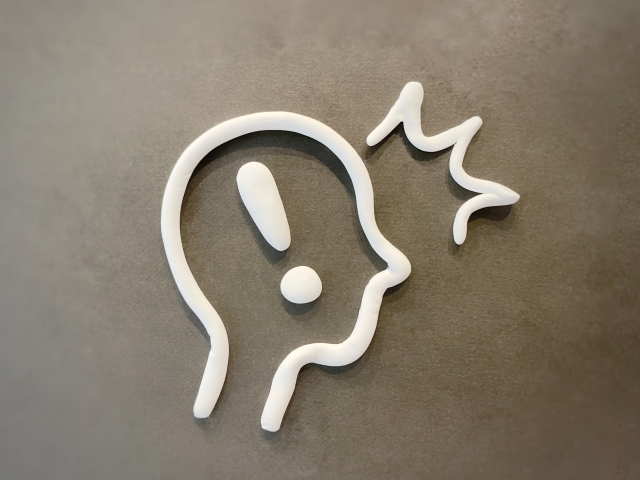
発達障がいの方がフラッシュバックを起こしやすいのは、特性によって「トラウマを生み出しやすい」からだと考えられます。発達障がいとは、脳の発達に偏りがあるために思考や行動に問題が発生してしまう障がいです。
中でも、ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如・多動症)に分類されるものは、フラッシュバックを起こしやすいとされています。
- ASD(自閉スペクトラム症)
・思考と想像に偏りがある
・人間関係に苦労しやすい - ADHD(注意欠如・多動症)
・「多動性」「不注意性」「衝動性」の3つの特性
発達障がいの方は子供の頃から下記のような問題を抱えて経験を積んでいく方が多いため、人一倍フラッシュバックを起こしやすいと考えられています。
- 感覚過敏
- 対人不安
- 極端な思考
順番に見ていきましょう。
ASD・ADHDに多い「感覚過敏」
発達障がいの方がフラッシュバックを起こしやすい理由の1つとして、五感情報(視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚)の過敏があります。ASDやADHDの方によく見られる特性です。五感が過敏だと得られる情報量も多くなるため、あらゆる物事の解像度が増して鮮明に記憶しやすくなります。
この特性は、一部のASDの方に見られる、物事を写真のように瞬間的に記憶する「カメラアイ」と呼ばれる能力も同様と言われています。
一見すると「記憶力が高い」とも取れる能力ですが、鮮明な記憶はなかなか忘れられないため、ふとした瞬間にフラッシュバックする原因にもなります。それがトラウマになるような記憶であれば多大なストレスを受けてしまうのです。
「対人不安」がフラッシュバックを増やす
発達障がいの方は対人不安を抱えている場合もあり、フラッシュバックを増やす原因の1つとなっています。
脳の発達に偏りがあると物事の受け止め方や思考パターンも偏りやすく「相手の言葉で傷つきやすい」「ネガティブな考えが浮かびやすい」などの傾向が見られやすくなります。物事の受け止め方や思考パターンが原因で、コミュニケーションに失敗したり、人から笑われたりする経験に繋がることも少なくありません。
結果として対人関係で嫌な経験が増える、人と話す際に過去の失敗がフラッシュバックして落ち込んでしまう、といったことの増加につながってしまうのです。
ASDの「極端な思考」もフラッシュバック増加の要因に
過去の失敗にこだわってしまうと、なかなかその記憶を忘れられませんし、繰り返し思い出してしまいますよね。発達障がいの方の中にはそういった傾向が強く、思考が極端なためにフラッシュバックを生んでしまう場合があります。
例えば、ASDの方に多く見られる「白黒思考」と呼ばれる特性があります。この思考があると物事を白か黒か、0か100かで極端に捉えてしまうため中間的な思考をすることができず、「楽しく過ごせていた100の時間が、一度の失敗ですべて0になってしまった」などと捉えてしまう場合があります。
こういった考え方だと一度の失敗が非常に重くなります。台無しになった原因は、忘れたくても忘れられません。その結果、トラウマとして残りやすくフラッシュバックの増加に繋がってしまいます。
【今からできる】フラッシュバックを減らす工夫6選

フラッシュバックはすぐに良くなるものではありません。治療以外にも今よりもトラウマを増やさず、今までのトラウマをケアできる状態を保つ必要があります。
この項目ではフラッシュバックの原因の1つであるストレスを溜めない工夫を主に紹介します。発達障がいによって生じる悩みの緩和にも通じるものなので、実践してみましょう。
朝起きたらまず日光を浴びてみる
日光は体内時計と関連があり、起きてすぐに浴びることで心身の健康に重要な睡眠のリズムを整える効果があるため、フラッシュバックの原因となるストレスの増加を抑えられます。
また、日光は浴びるだけで幸福感と関連のある脳内物質が分泌されると言われており、ADHDの多動性など、脳内物質の乱れによって生じる発達障がいの特性にも有効です。
スポーツなどで身体を動かす
運動はストレスの解消が期待できるほか、ストレスに強い心身を作るといった面もあるためフラッシュバックの対策として効果的です。継続することで脳内物質の供給も安定するので、ポジティブな思考が生まれやすくなります。
一度行うだけでなく習慣にすることが重要なので、あなたの好きなスポーツから始めてみませんか。発達障がいの特性によっては通常よりも大きな効果が得られるかもしれません。
スポーツに苦手意識がある、ちょっとハードルが高いと感じる方は、サイクリングや近所を散歩するだけでも効果があります。
ヨガ・瞑想などのリラクゼーション
ヨガや瞑想などのリラクゼーションはフラッシュバックの対策として効果的でしょう。心身を落ち着かせ自律神経を整える効果がある他、深く落ち着いた呼吸で行うので、不安なときに浅くなりがちな呼吸を改善し、強張っていた身体をほぐす効果もあります。
脳のオンオフを意識的に行う訓練にもなるので、「切り替えが苦手」な場合が多い発達障がいの方には特に効果が期待できます。
フラッシュバックが起きやすい状況を避ける
フラッシュバックの治療にはトラウマと向き合う必要がありますが、それは安全が確保された状態で行われるべきものです。
運転中や横断歩道を渡る最中など、危険な状況で起きてしまえば命に関わります。日常生活では、フラッシュバックが起きやすい状況を避けることを心がけましょう。
信頼できる人に相談
「親や兄弟、友人などが理解してくれている」といった安心感は、非常に多くのケースでフラッシュバックの改善に貢献しています。身近だからこそ明かしにくいと思うかもしれません。しかし、話せば力になってもらえることも多いので、少しずつ考えてみましょう。
フラッシュバックの不安を軽減する手段の用意
フラッシュバックを起こしてしまったときは、深呼吸などの一般的な落ち着くための動作に加え、できる限り五感で自身の安心を体感できる状態を作ることが効果的です。特に感覚過敏の特性がある方は、過敏気味な部分で何か「安心できるな」と思える感覚を得られるといいかもしれません。
- 安心できる音(聴覚)
- 安心する匂い(嗅覚)
- 安心する感触のもの(触覚)
- 安心する画像(視覚)
- 落ち着く味のするお茶(味覚)
など、不安を軽減できるものを見つけて、いつでも手の届く場所に用意しておくと良いでしょう。
フラッシュバックは治せる!つらい時は専門医への相談を

フラッシュバックは時間がかかるものの治療が可能です。
どうしてもフラッシュバックがつらいと思ったら早めに専門医へ相談しましょう。あなたが「嫌なこと」として抱え込むほどに、治療は難しくなってしまいます。
嫌な記憶は誰かに話す際、どうしても思い出すことになります。あまり明かしたくない内容である場合も躊躇われますが、それ以前に思い出したくないので話しにくいですよね。
しかし、病院であれば医師以外が知ることはありませんし、必ず親身になって話を聞いてくれます。「治したい」「つらい」と思うのは治療を始める1つのきっかけです。一歩踏み出してみましょう。
この項目では、フラッシュバックに効果的とされる3つの治療法を紹介します。
認知行動療法
認知行動療法は「人の感じ方や振る舞い方は経験をどう解釈するかによって決まる」という考え方に基づいて行われる精神療法の一種です。
フラッシュバックに対しては、「フラッシュバックする記憶をどう解釈するか」に焦点を当てて行われます。
例えば、どれだけつらい記憶でも「そのおかげで上手くいったことがある」と考えられたらどうでしょう?少しだけ過去を肯定できて、「嫌だ」以外の解釈が生まれるのではないでしょうか?
そういった形で記憶に対する解釈を広げていくことで症状を緩和し、克服していくのがこの療法です。単純な考え方の工夫でもあるので、フラッシュバックが軽度な場合は個人で行っても問題ありません。「リフレーミング」という名前で就活などでの自己分析に使われることもあります。参考にしてみてください。
暴露療法
暴露療法は医師の指示の下、安全と安心を確保しながら、フラッシュバックする記憶と似た状況を想像することで、思い出すたびに生じる感情を克服していく治療法です。前述した認知行動療法のうちの1つで、基本的にはセットで用いられます。
もちろん嫌な記憶を掘り下げるため、強い不安感を伴います。成立させるためには支えられていると感じられて、適切なペースで進められる環境が必須です。行う場合は必ず専門医の協力のもとで行ってください。
薬物療法
フラッシュバックに対する薬物療法は、精神的負担を和らげる目的で抗うつ剤などが用いられています。
薬を飲むことで実際に症状は緩和されますが、飲むだけではフラッシュバックそのものは治らないので、精神療法を並行して行っていくことが大切です。薬物が関わる以上専門医のサポートが必要なので、個人判断で薬の増減などを行うことは絶対にやめましょう。
まとめ|発達障がいの方がフラッシュバックを起こしやすい理由と対策
- 発達障がいの方がフラッシュバックを起こしやすい理由は「感覚過敏」「対人不安」「極端な思考」の3つの特性を子供のころから抱えて生活するため、トラウマを抱えやすいことにある。
- 発達障がいがあってもフラッシュバックを減らせる工夫として、ストレスを溜めないように「朝起きたら日光を浴びてみる」「スポーツで身体を動かす」「ヨガや瞑想などのリラクゼーションを行う」「フラッシュバックが起きやすい状況を避ける」「近親者に相談する」「フラッシュバックの不安を軽減するものを用意する」などがある。
- フラッシュバックは時間はかかるものの治療可能で、治療法は主に「認知行動療法」「暴露療法」「薬物療法」の3つがある。どうしてもつらいと思ったら早めに専門医へ相談することが治療への近道。
発達障がいの方が悪い記憶のフラッシュバックを起こしやすい理由や、その対処法と対策について解説してきました。
フラッシュバックも発達障がいと同じく周囲に理解してもらうことが助けになります。1人で悩まず、できる限り誰かを頼ってみてください。
ご自身での対処や専門医の治療と並行し、フラッシュバックと向き合いながら就労を目指すなら「ココルポート」も1つの選択肢です。自分のペースで通所し、500種以上のプログラムからストレス対処法や働くスキルを習得することができます。
安心して就職への準備を整えたい方は、詳細を確認してみてはいかがでしょうか。