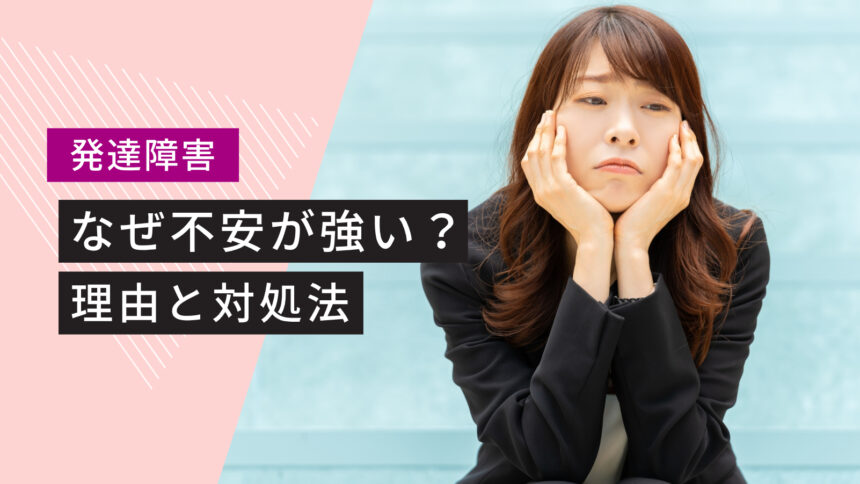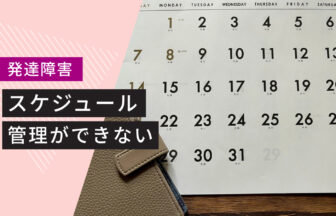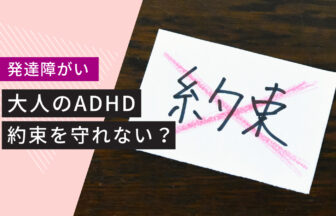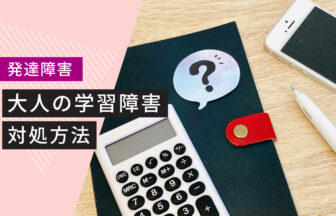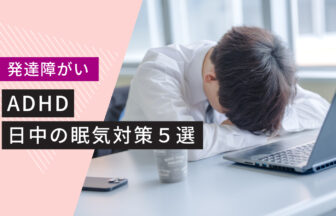「不安になったときの対処法を知りたい!」
「不安になったら、どこに相談すればいい?
などの疑問や悩みはありませんか?
現在、発達障害の方の中には、一般企業に勤めていたり、他の人と変わりない日常生活を送ったりしている方も多いでしょう。
しかし中には、嫌な出来事が頭の中でぐるぐる回り、夜も眠れない程の不安や、仕事でミスをしていないか心配で休日も不安になってしまうなど、絶えず不安に悩まれている方も少なくないと思います。
- なぜ発達障害だと不安を強く感じるのか?
- 不安を強く感じたときの対処法
- 不安を感じにくくするための対処法
- 不安を強く感じたときの相談先
について解説していきます。
不安な気持ちと折り合いをつけてうまく付き合えるようになれば、日々の生活を穏やかに送れるようになる可能性もあります。この記事が少しでも参考になれば幸いです。
なぜ発達障害は不安が強いのか?

そもそも「不安」とは、何かストレスにさらされたとき、不安を感じてその原因を避けようとする、本来は自分の身を守るために必要な機能です。
ではなぜ、発達障害だと不安を強く感じやすいのでしょうか?これには3つの要素があります。
- ネガティブな思考に陥りやすい
- 変化に対応することが難しい
- 先天的に「不安」や「ストレス」を感じやすい
順に見ていきましょう。
ネガティブな思考に陥りやすい
発達障害の特性が原因で、失敗体験が多く成功体験が少ないと、良いイメージをしづらくなります。
「また失敗するかもしれない」「怒られたり笑われたりするかもしれない」と不安な気持ちが生まれると、繰り返し考え続けてしまいます。その結果、ネガティブな感情が強まって抜け出せなくなり、どんどん不安が高まるのです。
特に、ASD(アスペルガー症候群など)の場合は、一度失敗したことが自分の中でパターン化してしまい、「こうなるだろう」の思考で固まってしまって、がんじがらめになり不安になりやすくなってしまいます。
また、ADHDの場合は、頭の中の思考が多くあるので、一つ不安になると派生的に不安な思考が広がってしまいます。
ADHDの思考の特性については、下記の記事で詳しく解説しています。興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
変化に対応することが難しい
発達障害の方は、自分のこだわりやルーティンを崩されることが苦手なので、「予定外の事態での切り替えが難しい」という特性があります。
よって、急な予定の変更で行動を切り替えなければいけなかったり、そもそも予定が立っていない出来事に対応しなければならなかったりすると、不安な気持ちがどんどん強まってしまうのです。
セロトニンが少なく不安やストレスを感じやすい
発達障害の方は最近の研究で、脳の中に分泌される「セロトニン」という精神や感情を安定させる物質が、先天的に少ないと明らかになっています。
その影響から、不安やストレスを感じやすい脳を持っているので、マイナスな気持ちを持ちやすくなってしまうのです。
大人の発達障害が感じる不安の具体例

上記では、発達障害の方が不安を強く感じやすい理由を解説してきました。
では、どのような時に、発達障害の方は不安を感じるのでしょうか?
ASDの場合
ASDの方の場合は、変化に対して大きな不安を感じます。
具体的には、下記のようなものがあります。
- 毎日使うものが、いつも置いてある場所から勝手に移動されている
- 電車が時刻通りに来なかったり、約束の時間に相手が来なかったりする
- 特定の店で同じメニューが食べられない
決まったルーティンを作ることで、安心感を得ている場合、予想外の場面に遭遇すると、強いストレスを感じます。見通しの立っていない状況や急な予定の変化があると「何か大きな失敗をしてしまうのではないか?」と不安を感じてしまうのです。
ADHDの場合
ADHDの方の場合は、やりたいのにできないことに大きな不安を感じます。
具体的には、下記のようなものがあります。
- 人前で話すことを考える
- 会議中など「じっとする必要がある場面」に出くわしたとき
- 欲しいものが手に入らないとき
物事の運びが、自分にとってスムーズと感じる状況にないとき、不安を感じることがあります。
また、頭の中でさまざまなことを同時に考えていると、休日でもふとした瞬間に仕事のことを思い出して「もっとこうしておけばよかった」「あのミスが原因で、休み明けに大変なことになるのでは」と考え始め、不安な考えが頭の中をぐるぐると回って寝不足になってしまう場合があります。
不安を強く感じたときの対処法

上記で、不安を感じる時の具体例を紹介してきました。
強い不安を抱えたままでは、生活を送る上で心身共に影響が出てきてしまいます。
では、不安を強く感じたとき、どのような対処法があるのでしょうか?
ここでは主な対処法を3つご紹介します。
- 不安を書き出す
- 人と話す
- 気分転換をする
順にそれぞれを見ていきましょう。
不安を書き出す
予期せぬ出来事に対して不安に思ったときは、紙に書き出して、情報を整理・可視化してみましょう。
- 不安を1つずつ切り分けて書き出し、「やるべきこと」として名前をつけて書き出す。
- 書き出したら「これはこう対処する、あれはこう対処する」という風に一つずつ行動として順に並べ、整理する。
という順で進めてみてください。
書き出すことで、もし途中で予定が変わっても「変わったのは一部分だけだから、大きな変更ではない」と気持ちを落ち着けることができ、目の前のことに対処しやすくなります。
また、次に何をするかを書き出しておくことは、仕事のチェックリストとしても有効です。終わった順にチェックを入れていけば「ここまで終わらせることができた」ということがわかり、見通しが立たないことから起こる不安な気持ちを和らげることができます。
人と話す
不安に思ったときは、周囲の方に相談することも有効です。
人と話すことで、自分の思考の整理ができると同時に、相手から自分にはないものの見方を教えてもらい、新たな対処法に気づくことができる場合もあります。
話す前は考えがまとまらなかったり、漠然とした不安があったりしても、話しているうちにスッキリしていくこともあるので、身近な人やかかりつけ医などに、積極的に話をしていきましょう。
気分転換をする
不安なことが起こったときは、気分転換をしましょう。ここでは、3つの方法をご紹介します。
深呼吸をする
まず、一番手軽にできる深呼吸をしてみましょう。
深くゆったりとした呼吸をすると、心を穏やかにさせる副交感神経が働きます。さらに、新鮮な酸素を取り入れることができるので、血流の巡りも良くなります。その結果、リフレッシュ効果が期待できます。
香りを嗅ぐ
嗅覚は脳へ刺激を届けることができる感覚機能です。香りを嗅ぐことで、すぐに脳に変化が現れ、落ち着きを取り戻すことができます。
特に、ラベンダーや柑橘系の香りはリラックス効果が高いとされています。香りに敏感な方は、ご自身が安心できる香りを見つけておくと良いでしょう。
口の中を潤す
緊張や不安が高まってくると、自然に口が乾いてきます。そこで、食べる・飲むなど、口に何かを入れて潤すことを意識してみましょう。
ストレスなどを感じると交感神経が優位になり、ネバネバとした唾液になってしまいます。
水などを飲んで物理的に口の中を潤すことで、体をリラックス状態に戻します。ミント系のタブレットや酸っぱい味のものなど、より刺激が感じられるものも、唾液を出すことに繋がるのでオススメです。
不安を感じにくくするための対処法

上記では、不安を強く感じたときの対処法を解説してきました。
では、そもそも不安を感じにくくするには、どのような方法があるのでしょうか?
ここでは、対処法を3つご紹介します。
- 考え方にルールをつくる
- 成功体験を積む
- セロトニンを増やす
順に見ていきましょう。
考え方にルールをつくる
不安をつくらないよう、考え方に一定のルールを作りましょう。
まずは、割り切りの考えを持つことです。
悩みごとに優先順位をつけて、自分に関係のあることだけ悩むようにします。他人の問題や自分だけでは対処できない問題は割り切って、自分に関係ないことは考えないようにしましょう。
また、未来の起こっていないことに関しては、あれこれと考えないようにすることが大切です。
考えたところで「終わってみれば何も起きなかった」ことのほうが多いので、意識的に考えないようにしてみましょう。
成功体験を積む
不安は、「○○になったらどうしよう」「失敗したくない」などのマイナスな感情から生まれます。そこで、小さなことからでも成功体験を積むことで、不安になりにくくなります。
不安に思っていることがあれば、対策を打ったうえでチャレンジしてみましょう。そこで「できた!」という自信を身に付けることができれば、いつの間にか大きな成功体験を積むことに繋がります。
セロトニンを増やす
発達障害の方は脳内のセロトニンが少なく不安を感じやすいので、セロトニンを増やすことも対処法になります。
セロトニンを増やすポイントは、食生活、適度な運動、日光を浴びる、睡眠の4つです。
食生活
まず食生活を見直しましょう。
セロトニンの原料となる、トリプトファンを多く含む食品を摂取するようにしてみてください。
具体的には、下記のようなものがあります。
- バナナ
- 鶏肉
- 豆腐
- 卵
- 乳製品
- 豆類
- 赤身魚
さらに、炭水化物と一緒に摂ることで脳内に取り込まれやすくなるので、バランスよく積極的に摂取していきましょう。
適度な運動
適度な運動をすることを心掛けましょう。
運動によって、セロトニンの分泌が促進されます。ただし、いきなり激しい運動をすることは避けてください。特に、普段から運動をしない方は、大きな怪我に繋がります。
まずは、ラジオ体操のような手軽にできる運動がオススメです。
また、運動は継続することが一番重要になります。ご自身の体力や生活リズムに合った方法を探していきましょう。
日光を浴びる
日光にはセロトニンを増やす作用があるので、太陽の光を浴びることを心掛けましょう。
特に、午前中の15分~30分程度の日光を浴びることが、最も効果的とされています。また、日光を浴びると、骨粗鬆症予防ができるビタミンDが生成されることも分かっているので、通勤する時に歩いてみたり、天気のよい日は散歩をしてみたりすることがオススメです。
睡眠
睡眠もまた、セロトニンの分泌を促します。十分な睡眠をとりましょう。
慢性的な睡眠不足が続くと、「睡眠負債」といって、様々な負債が身体に蓄積されている状態になってしまいます。
睡眠負債の精神的な症状には、下記のようなものがあります。
- 抑うつ状態
- 判断力が鈍る
- 感情が不安定になる
睡眠不足の影響から、小さな失敗を繰り返し自信が無くなってしまうと、不安が強くなることもあります。
日常的なダメージは、確実に蓄積します。日々当たり前すぎて疎かにしがちな「睡眠」は、人間の体にとって、実はとても重要な役割を担っているのです。
睡眠前は、スマートフォンを見る時間を少なくするか時間を決めて使い、ストレッチや瞑想をする時間を設けてみるなどして、快適な睡眠を心掛けましょう。
発達障害の方が不安を強く感じた時の相談先

ここまで、個人でできる不安への対処法を解説してきました。しかし、それでも不安が解消できない場合は、どこに頼ったら良いのでしょう?
ここでは、主に5つご紹介します。
- 自治体の福祉窓口
- 発達障害者支援センター
- 精神保健福祉センター
- 医師・カウンセラー
- 就労移行支援事業所
順にそれぞれ見ていきましょう。
自治体の福祉窓口
自治体の福祉窓口は、障がいを抱えていて困っている方の相談を広く受け付けています。
どこを頼ったらいいのかわからない場合はまず、自分が住んでいる自治体の福祉窓口に出向いてみましょう。どのようなサービスがあなたに合っているのか、詳しく教えてもらえるはずです。
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、発達障害のある方への支援を総合的に行う、地域の拠点となる機関です。
関係機関とも連携し、発達障害のさまざまな相談に応じているので、気になることがあったら積極的に聞いてみるとよいでしょう。
精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは、心の問題や病気で困っている本人や家族、関係者から相談を受け、心の健康や精神科医療についてのサポートをしてくれる機関です。主に精神的な不安感が強い場合、相談することで様々なアドバイスが貰えます。
下記、全国の精神保健福祉センター一覧です。気になる場合は確認してみてください。
全国の精神保健福祉センター
医師・カウンセラー
医師やカウンセラーの診断を受け、認知行動療法(物事の極端な捉え方を見直すことにより、そこから生まれる“感情”や“行動”に働きかけ、生きづらさやストレスを軽くしていく治療法)を行ったり、セロトニンを増やす治療を受けたりするという方法もあります。
不安が強すぎると、日常生活に支障が出てしまい、精神疾患になってしまう可能性も高くなります。少しでも改善したいと思う方は、動けるうちに早めに行動を起こして、病院を受診してみましょう。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、一般企業への就職を目指す障がい者を支える福祉施設として有名ですが、その前段階として生活支援も行っています。
障害者手帳がない場合でも、医師の診断や自治体の判断により利用できることがあるので、気になる方はお住まいの地域の相談窓口や就労移行支援事業所に直接相談してみましょう。
なお、以下では「実際にどんな事業所があるのか知りたい」という方のために、おすすめの就労移行支援事業所をご紹介します。ぜひチェックしてみてください。
ココルポート
ココルポートは、障がいを抱えた方がリラックスして通える、温かな雰囲気づくりを大切にしている就労移行支援事業所です。不安感の強い発達障害の方でも、ココルポートが行っている少人数制のプログラムや個別相談を通じて、少しずつ状況を改善していくことができます。
「なにから始めればいいかわからない」という方も、まずは相談から始めてみるとよいでしょう。
atGPジョブトレ 発達障害コース(就労移行支援)
「atGPジョブトレ 発達障害コース」は、株式会社ゼネラルパートナーズが運営する発達障害の方に特化した就労移行支援事業所です。コミュニケーションや感情調整の方法から、仕事の進め方まで、実践的な訓練を提供しており、不安感の強い発達障害の方には心強い味方と言えます。
発達障害で自分に自信がなく働いていけるか不安な方、自分に向いている仕事がわからない方、障害者採用で就職したいが自分の障害特性をうまく説明できない方などは、こちらの利用を検討してみてもよいでしょう。
まとめ|発達障害と不安
- 発達障害の方が不安を強く感じやすいのは、発達障害の特性から、失敗経験が多くネガティブ思考になったり、変化に対応することが難しかったりするため。また、セロトニンが少なく、不安やストレスを感じやすいといった要因もある。
- 不安を強く感じたときは、不安なことを一つずつ書き出したり、人に話したりするなどして、不安を吐き出すことが効果的。また、深呼吸や香りを嗅ぐなど気分転換してみることもオススメ。
- 不安を感じにくくするには、普段からセロトニンを増やす生活習慣を心がけることが効果的。食生活や適度な運動、日光を浴びることや睡眠がとても大切。
- 一人で解決できないほど不安が強いときは、自治体の福祉窓口や発達障害者支援センター、精神保健福祉センター、就労移行支援事業所などに相談をする。また、医師やカウンセラーの専門的な治療を受けると、生活を送りやすくなる可能性がある。
いかがだったでしょうか?
不安とは、本来人間がもつ防衛本能なので、そもそも誰でも当たり前にあり、完全になくすことは難しいものです。
ですが、不安によって日常生活が送り辛くなっているのであれば、対策が必要になってきます。上記のような原因と対策を知って、少しずつ不安を飼いならせるようにして、穏やかな生活を目指していきましょう。
この記事が参考になれば幸いです。