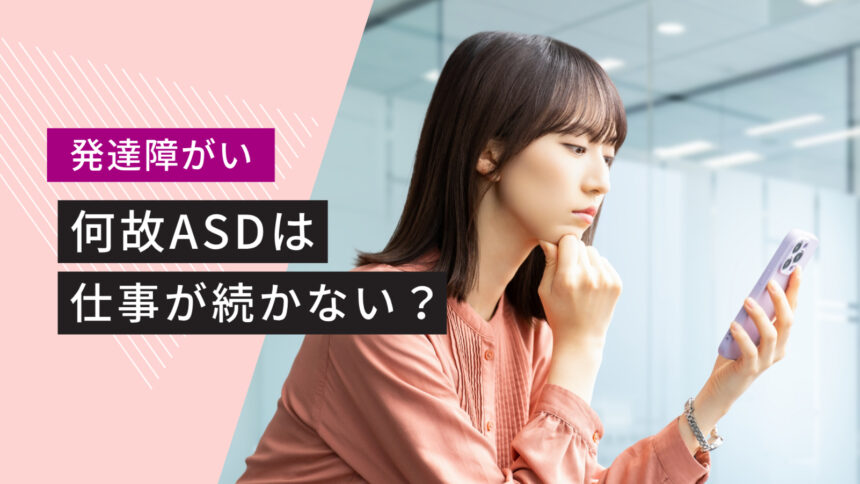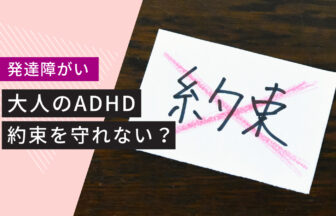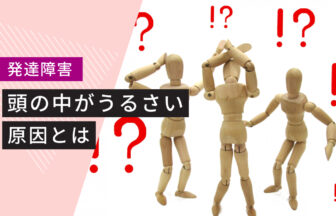ASDを抱えている方の中には、自身の特性に振り回されて仕事が続かない方や、仕事が合わず転職を繰り返している方が少なくありません。
「これ以上転職を繰り返したくないけど、仕事を続けていける自信がない」
という悩みを抱えている方もいるでしょう。
仕事が続かないと、自分は仕事ができない人間なのではないか、と落ち込んでしまいますよね。
しかし、ASDがあっても自分の特性に向き合い、苦手な部分に合わせた工夫や対策を考えることができれば、仕事を長く続けられるでしょう。
- ASDの方はなぜ仕事が続けられないのか
- ASDの方が直面する仕事での困りごと
- ASDでも無理なく仕事を長続きさせるための仕事術8選
- 仕事が続かないASDの方にオススメな支援制度
どうすれば仕事を長続きできるようになるのか、一緒に考えていきましょう。
ASDの方はなぜ仕事が続けられないのか

ASDの方が仕事を続けられないのはなぜなのでしょうか。この原因として、ASDの特性が大きく影響しています。
ASDには、社会生活を送るうえで困難に直面しやすい特性が多い傾向があります。学生時代までは困らなかったものの、社会人になってから表面化して困りごとを抱えてしまう方は少なくありません。
この項目では、具体的にはどのような特性が仕事を続けられない原因となってしまうのか、順番に見ていきましょう。
社会的コミュニケーションが難しい
ASDの方は、コミュニケーションに難しさを感じる方が多いです。ASDには相手の気持ちを想像しにくい特性があるため、コミュニケーションがうまくいかないことがあります。
特に、相手の態度や雰囲気から感情を理解したり察したりするのが苦手なため、余計なことを言って相手を怒らせてしまう場面も少なくありません。場合によっては、周囲との関係を悪化させてしまうこともあります。
加えて、曖昧な表現やたとえ話を理解することも難しいため、具体的な説明でなければ何をしていいのかわからなくなることも珍しくありません。
こうしたコミュニケーションの難しさから周囲と良好な関係を築けず、業務にも支障をきたすこともあり、仕事が続けられなくなる場合もあります。
柔軟な対応が難しい
ASDがある方は、物事に柔軟に対応することが難しい傾向が強いです。これには、ASDの特性の1つであるこだわりの強さが影響しています。
こだわりが強いために自分が決めた順序やパターンの行動に固執しやすく、急な変化を目の当たりにするとストレスを感じたり、パニックに陥ったりすることも珍しくありません。決まったルールがなければ、自分がどう動けばいいのかわからない方も多くいます。
臨機応変な対応を迫られたり、状況の変化が激しかったりする職場は、この特性との相性が非常に悪いです。仕事を辞めてしまう原因にもなってしまうことがあります。
感覚過敏、または感覚鈍麻
ASDの方の中には光や音、匂いなどに過敏に反応する方や、逆に感覚が鈍く自身の不調などに気づきづらい方も少なくありません。周囲の環境に過敏に反応してしまう特性がある方は、職場環境によっては非常に耐えがたい思いをすることになります。結果、余計な疲労を感じてしまい、仕事にも集中できなくなってしまうでしょう。
また、感覚が鈍く体調が悪いことに気づきづらい方は、疲労があるのにも関わらず作業をし続けてしまい、職場で倒れてしまう場合があります。周囲の音に気付きづらく、痛みを感じにくいために、仕事中に何か問題があっても問題が起こるまで気づかず、仕事に大きな影響が出ることもあります。
ASDの方が直面する仕事での困りごと

では、先ほど解説した特性のために職場で起こる困りごとにはどんなものがあるのでしょうか。
- 職場内でコミュニケーションがうまく取れない
- 明記されていないルールや暗黙の了解がわからない
- 手元の仕事にのめり込んでしまう
- マルチタスクが苦手
- 急な予定変更や人事異動に適応できない
- 二次障害を発症してしまう
特に起こりやすいものを順番に解説していきます。
職場内でコミュニケーションがうまく取れない
ASDの方が直面してしまう困りごととして、職場内でコミュニケーションが上手くとれないことが挙げられます。
先ほども解説した通り、ASDの方は社会的なコミュニケーションが苦手です。そのため、職場内でも報告・連絡・相談といった意思疎通や人間関係の構築を上手くできない方が多い傾向にあります。
相談をする際に相手の都合を確認せずに話しかけてしまい怒らせてしまった経験をした方や、相談内容を上手く相手に伝えることができず1人で悩みを抱えこんでしまう方もいるでしょう。
曖昧な表現も苦手なため、指示が具体的でないと理解できず、業務に支障をきたしてしまう方も少なくありません。
また、ASDの方が同僚と雑談をするとき、たとえ話や冗談と本気の区別がわからず、どう話していいのか困ってしまう場面があります。こういったことから、周囲からコミュニケーションを取りづらい人だと思われやすく、良好な人間関係を築けない方もいます。
こうしたことが重なると、仕事だけでなく職場にいること自体が大きなストレスとなってしまうでしょう。
明記されていないルールや暗黙の了解がわからない
ASDの方の多くは、明記されていないルールや暗黙の了解が分からない場合があります。原因として、場の空気を読むのが苦手なことや、「なぜそのルールがあるのか」「何がダメなのか」を無意識で理解するのが難しいことが挙げられます。結果、場にそぐわない行動をしたり、相手の意図とは見当違いな受け答えをしたりして、周囲とトラブルになってしまうことも多いです。
また、仕事では顧客や業者、上司、先輩などさまざまな上下関係がありますが、ASDの方はこうした人間関係や上下関係を意識することも苦手としています。そのため、関係性を意識した発言が必要になる場面でも、不適切な言葉遣いなどをしてしまい、怒られてしまうこともあるでしょう。
特に、電話対応は急にかかってくることに加えさまざまなマナーがあり、相手との関係性によって適切な言葉遣いを瞬時に求められるため、苦手とするASDの方が多いです。
手元の仕事にのめり込んでしまう
ASDの方は行動や気持ちの切り替えが苦手な傾向が強く、集中力を過剰に働かせてしまう「過集中」という状態になりがちです。そのため、手元の仕事にのめり込んでしまい、他にもやらなければいけない仕事が手につかないこともあります。
1つの仕事に集中しすぎるあまり、周りがサポートを必要としている状況にも気づけないケースもあります。このようなことが重なり続けると、周囲と足並みを揃えた仕事ができず、関係性が悪化したり、仕事に影響が出たりします。
マルチタスクが苦手
ASDの方は指示された仕事はしっかりこなそうとしますが、一度に複数の仕事を任されるとパニックに陥ることがあります。ASDには、複数の仕事に優先順位をつけることが難しい特性があるからです。
そのため、複数ある仕事を進めようとしてもどの仕事から始めればいいのかわからず、混乱してしまう経験をした方も多いのではないでしょうか。作業に集中しているときに別の作業が入り、どれを優先していいのかわからず、どの作業にも集中できなくなってしまう方もいるでしょう。
このようにマルチタスクを強いられる職場では、業務を思ったように進めることができず、強いストレスを感じてしまう可能性が高くなってしまいます。
急な予定変更や人事異動に適応できない
ASDの方は、柔軟な対応が難しい特性があるため、急な予定変更や環境ががらりと変わる人事異動などを苦手とする方が多いです。別の仕事が突然入ってしまい、予定や作業の手順が狂ってしまうことでパニックに陥ってしまった方も多いのではないでしょうか。
常に臨機応変な対応が求められる職場では、そもそも決められた手順から外れることが当たり前であり、ASDの方とは非常に相性が悪いです。また、人事異動で直属の上司や業務内容ががらりと変わってしまうと、大きな不安を抱えてしまい、こちらも強いストレスを感じてしまうことになるでしょう。
二次障がいを発症してしまう
ここまで解説したような困りごとで強いストレスを感じ続け、うつ病やパニック障がいなどの二次障がいを発症して仕事を続けられなくなった方も多くいます。
二次障がいは一度発症すると治療にも時間がかかり、場合によっては引きこもり状態に移行してしまうケースもあります。ある程度症状が落ち着いてから復職しても、それを引き金に体調がまた悪化してしまうことも少なくありません。
仕事を続けているうちに、心身に不調が出てきた場合は早めに医療機関へ相談しに行きましょう。後ほど紹介する支援制度でも心身の不調について相談できますので、参考にしてください。
ASDでも無理なく仕事を長続きさせるための仕事術8選

ASDを持つ方が直面する困りごとには、さまざまな種類があることが分かりました。では、このような困りごとが多いASDの方が無理なく仕事を続けていくためには、どのような工夫をしていけば良いのでしょうか。
ここからは、ASDがあっても仕事を無理なく長く続けていくための仕事術として、下記の8つを紹介していきます。
- 自分の特性に対し理解を深める
- 自身の特性を職場に理解してもらう
- 上司とコミュニケーションを取る際のルールを作る
- 指示の方法を変えてもらう
- 具体的な言葉を使った指示や説明を求める
- やるべき仕事やその優先順位を目に見える形にする
- 自身の感覚過敏に合わせた対策を行う
- 自分の特性と相性が悪い職場は避けるようにする
これから紹介する仕事術はあくまで一例ですが、あなたの特性を補うことができるものがあれば、積極的に活用していくことをオススメします。
➀ 自分の特性に対し理解を深める
まずは、自分の特性を深く理解することが大切です。
ASDの特性は個人差が大きく、人によって表れ方も変わってきます。一般的にASDの方には向いていないと言われる仕事でも、あなたには向いていた、ということも珍しくありません。仕事を無理なく長く続けるためにも、あなた自身の特性を理解することはとても重要です。
できることやできないこと、得意・不得意、興味の有無などに注目して、自身の障がい特性への理解を深めていきましょう。注目すべき点に加えて、職場の中でのあなたの困りごとを紙に書き出していくと、特性をより整理しやすくなります。
特性の理解をする際、「こうありたい」という願望や自己評価の低さによって、上手く進められない場合もあります。その時は、家族・友人の意見や後で紹介する支援機関、医師などの客観的な視点を取り入れるようにすると、偏った理解を防ぐことができます。
こうして自身の特性を深めることができれば、どのような対策や配慮が必要か考えられるようになるでしょう。言葉で具体的に説明ができるようにしておくと、職場の方も必要な配慮をイメージしやすくなります。
➁ 自分の特性を職場に理解してもらう
職場にあなたのASDの特性について説明し、理解してもらうことも仕事を長く続けるうえで非常に大切です。
あなたの特性を周囲に伝えずにいた場合、下記のような事態が考えられます。
- 特性によって業務に支障が出たり、周囲とうまくコミュニケーションが取れなかったりすることが重なると、「トラブルメーカー」「面倒くさい人」という認識をされてしまう
- 急な体調不良が起こってしまっても「体調管理ができていない」と思われてしまう
- 通院や服薬が必要であっても理解が得られず、有給休暇や休日の利用を避けられない
ASDの特性による苦手なことや努力・工夫だけではどうにもならないこと、自身の不調のパターンなどについては、周囲に伝え障がいへの理解を求めるようにしましょう。理解を得られれば、あなたに合った配慮を受けることができます。
障がい者雇用枠を検討する
特性を理解してもらい、合理的な配慮を受けるための手段として障がい者雇用枠を検討する方法も挙げられます。
障がい者雇用枠では、障がいがあることを前提に採用しているので、仕事内容や勤務形態に必要な配慮を受けられます。二次障がいが出てしまっていても、仕事と治療を両立しやすくなります。
ただし、就職先の選択肢が一般雇用枠よりも少なく、給与水準も比較的低いことに注意が必要です。
➂ 上司とコミュニケーションを取る際のルールを作る
先ほども解説したように、ASDの方は上司との報告・連絡・相談といったコミュニケーションを苦手とする方が多いです。コミュニケーションを円滑にするためにも、ルールを作ることをオススメします。
例えば、報告や相談をする際は、事前にわかりやすく内容を整理することで、上司にもしっかりと伝えられるようになります。はじめのうちは、自分の意識している以上に内容を細かく上司に報告するといったルールを作れば、予期せぬトラブルも回避しやすくなるでしょう。
上司に話しかけて良いタイミングはどんな時かを確認しておけば、怒らせることも少なくなりますし、スムーズにコミュニケーションを取ることができるようになります。他にも、上司と一緒にコミュニケーションを取る際のルールを考えたり、定期的に相談や確認できる機会を設けたりすれば、コミュニケーションに関する悩みも少なくなるでしょう。
また、ASDの方は明記されていないルールや暗黙の了解などを読み取るのが苦手なことが多いため、職場内にはどういうルールがあるのか説明を受けておくことをオススメします。
➃ 指示の方法を変えてもらう
ASDの方の中には、口頭など指示の方法によっては情報を把握しづらい方もいます。そういう方は、自分の理解しやすい指示の方法に変えてもらうことをお願いしましょう。
例えば、文章や画像など目で見る情報の方が理解・記憶しやすい方は、チャットツールを用いたコミュニケーションをお願いすると良いでしょう。こうした工夫をすることで、今まで理解しづらかった指示内容が頭の中にすんなり入ってくるようになるはずです。説明においても、文字や図を用いてもらうと、より内容を把握しやすくなります。
どうしても口頭で指示を受ける必要がある場合は、内容を細かいところまでメモに取っておくと、理解しやすくなります。メモに取った内容に間違いがないか確認してもらうと、より確実です。許可をもらうことができれば、指示の内容を携帯などを使い画像や録音で記録しておくのも良いでしょう。
このように、指示の仕方を自分の特性に合わせた方法に変えるだけで、指示内容の行き違いを防ぐことができます。
➄ 具体的な言葉を使った指示や説明を求める
指示をもらう際、具体的な言葉を使うようにお願いすることも大切です。
ASDの方は、曖昧な表現や「時間があるときに」「状況に合わせて」など自分の判断が求められる言葉で指示されると、混乱することが多いです。きちんと数字や時間を具体的に用いた指示をもらうことができれば、安心して業務を進められるでしょう。先ほども解説したように、文書や図などでの補助があればより効果的です。
日ごろから「指示をするときは具体的にお願いします」とコミュニケーションを取っておけば、スムーズに仕事ができるようになるでしょう。
➅ やるべき仕事や優先順位を目に見える形にする
手元の仕事に夢中になりがちだったり、複数の仕事を振られてどこから手を付けていいかわからなかったりする方は、やるべき仕事や仕事の優先順位を目に見える形にしておくことをオススメします。
例えば、やるべき仕事を紙に書き出したTODOリストを作り、仕事の順番を振り分けるという方法があります。優先順位をつけることが苦手であれば、TODOリストを上司や同僚に見せて順位を割り振ってもらうと良いでしょう。作ったTODOリストを目に見えるところへ貼ることで、仕事を忘れる可能性を減らせます。
加えて、スケジュールも一緒に目に見える形にしておきましょう。予定の見通しが視覚的にわかるので、安心して仕事を行えるようになります。
色分けやイラスト、図などでより視覚的に分かりやすくしておくと、仕事における混乱も少なくなるでしょう。
➆ 自身の感覚過敏に合わせた対策を行う
感覚過敏が強い方は、職場の些細な音に敏感に反応してしまったり、既定の服装だと肌に合わなかったりして、仕事に集中できないことがあります。そういう方は、自身の感覚過敏に合わせた対策を行いましょう。
周りの音が気になる方は、ノイズキャンセル機能があるイヤホンを使用すれば仕事に集中できるようになるでしょう。肌の感覚が過敏な方は、業種にもよりますが、ネクタイ着用の免除や私服での勤務の許可をもらう、服装の関係ない在宅勤務で働く、などの対策が考えられます。
ただし、周りがあなたのASDの特性を理解していない場合、誤解を受けてしまうかもしれません。こういった対策をするときは、上司や周囲の方に可能な範囲で自分の特性を説明し、理解を得ておきましょう。
➇ 自分の特性と相性の悪い職場は避けるようにする
仕事を長く続けるためには、あなたの特性と相性が悪い職場を避けることも大切な仕事術の1つです。転職を繰り返しても仕事が長続きしない場合、あなたの特性と職場との相性が悪いことが原因かもしれません。
例えば、臨機応変な対応やマルチタスクを求められる職場は、ASDの特性と非常に相性が悪いです。配置転換や人事異動が多い職場も、変化に適応することが難しいため強いストレスを感じてしまいます。
ASDの特性の中には、努力や工夫だけでは補え切れないものもあります。そのため、特性と合わない職場や業務を避けるように心がければ、仕事を長く続けやすくなるでしょう。
新たに仕事を探す際は、しっかりと自分の特性を理解したうえで、特性と相性が良い職場かしっかりと調べておきましょう。
仕事が続かないASDの方にオススメの支援機関

「仕事術を色々試してみても仕事が長続きしない」とお悩みの方もいるでしょう。自分の特性に向き合って努力しているはずなのに、上手くいかないのはとても苦しいことです。
そんな方は、ここで紹介する支援機関を利用してみてください。
支援制度を利用することで、就労や発達障がいに関して専門的な知識を持った方からのサポートが受けられるようになります。定期面談があれば改めて自身の特性と向き合えますし、支援制度の中にはあなたと職場との間に立って、さまざまな業務の調整や職場に定着するためのサポートを行っていることもあります。
この項目では、仕事を長く続けたいASDの方にオススメの支援機関を紹介していきます。無料で利用できるものも多いので、気になったものがあれば気軽に問い合わせてみましょう。
- ハローワーク
- 発達障がい者支援センター
- 地域障がい者職業センター
- 障がい者就業・生活支援センター
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所
では、一緒に見ていきましょう。
ハローワーク
ハローワークには、障がいのある方専用の窓口が設置されています。
窓口には、障がいに関する専門的な知識を持つ職員・職業相談員がおり、あなたの障がい特性や希望職種に応じた職業相談や職業紹介、職場適応指導、職場定着支援を行っています。発達障がい者雇用トータルサポーターが在籍している場合は、専用のカウンセリングを受けることもできます。
障がい者窓口を利用するのに障がい者手帳は必要ありませんが、受ける支援によっては主治医の診断書が必要です。
ハローワークで受けられる支援について、下記の記事でも解説しています。
また、ハローワークでは「トライアル雇用」という就労支援制度も実施しています。トライアル雇用では、一定の期間あなたと企業が雇用契約を結び、職場とあなたの適性が合っているかどうか、給与をもらって働きながら見極めることができます。長く仕事を続けることが難しいASDの方にとって、事前に職場の雰囲気や業務内容を体験できることは大きな魅力と言えます。
トライアル雇用については、下記の記事で解説しています。
発達障がい者支援センター
発達障がい者支援センターとは、都道府県や政令指定都市が設置している発達障害に関する相談・支援を行っている機関です。専門の職員のほか、社会福祉士や臨床心理士などの発達障害に関する専門的な知識を持つ方が在籍しており、さまざまな相談を受け付けています。
例えば、ASDの特性によって起きている困りごとについての相談や、就労で必要な対策・アドバイスをもらうことができます。必要に応じて、センターのスタッフが就労先に訪問して障害特性や就業適性に関してアドバイスを行ったり、作業工程や環境の調整をしたりするなど、利用者が職場に定着するためのサポートも行っています。
発達障がい者支援センターの利用に障害者手帳は必要ありません。何か困りごとがあれば、気軽に利用してみると良いでしょう。
全国の発達障がい者支援センター窓口は下記から調べることができます。
発達障害者支援センター・一覧|国立障害者リハビリテーションセンター 発達障害情報・支援センター
発達障がい者支援センターについては、下記の記事で解説しています。
地域障がい者職業センター
地域障がい者職業センターとは、障がいのある方に対しハローワークと連携しながら、専門的な職業リハビリテーションを提供する公的機関です。
職業リハビリテーションでは、仕事に必要なスキルやコミュニケーション能力の向上のために、一人ひとりの特性に応じて作成した支援計画を元にした、就職に向けた作業体験や職業準備講習、職業紹介などを行っています。
支援計画を作る際は、あなたにどのような特性があるのか検査も行われるため、自分の特性に改めて向き合うことができます。訓練や作業体験も自身の特性に応じて設定されているので、仕事に向けた対策を受けられます。
就職後も職場に定着できるように、職場適応援助者(ジョブコーチ)を派遣し、本人や職場に対して障がい特性を踏まえた支援を行っています。
全国の地域障がい者職業センターは下記から調べることができます。
地域障害者職業センター|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
地域障がい者職業センターについては、下記の記事で解説しています。
障がい者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターでは、ASDを含むすべての障がいがある方に向けて、就業・生活に関する包括的な相談・支援や適切な専門機関の紹介、職場適応支援などを行っています。
転職を繰り返してどのような仕事が合うのかわからないASDの方の相談も受け付けており、具体的なアドバイスや必要なサポートを受けることができます。
例えば、就労前であれば面談を通して障害特性が原因の仕事上での困りごとや不安、得意・不得意なことを聞き、あなたが長く仕事を続けるための方法を一緒に考えてもらえます。就労後も困りごとがあればセンターのスタッフが職場訪問したり、地域障害者センターと連携してジョブコーチを派遣したりするなど、職場に定着するための支援を行ってもらえます。
就職後もしっかりと職場に定着して働きたいという方にオススメです。
下記から全国の障がい者就業・生活支援センターの一覧を見ることができます。
令和6年度障害者就業・生活支援センター 一覧|厚生労働省 pdf
障がい者就業・生活支援センターについては、下記の記事でも解説しています。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、一般企業での就職を目指す障がいがある方に向けて、就職活動のサポートを行う支援機関です。障がい者手帳を持っていなくても、障害福祉サービス受給者証があれば利用できます。
各地に設立されている事業所にて、一般企業で働くために必要な知識やビジネスマナーなどの基本を身に付ける訓練や、プログラミングなどの専門的スキルの講習、自己分析のサポート、履歴書添削・面接指導などを行っています。特に、学ぶことができるスキルは幅広く、事業所によっても異なります。興味がある内容を行っている事業所があれば、見学に行ってみると良いでしょう。
ASDの特性により転職を繰り返している方にとっては、働き方や希望する業界、障害特性との付き合い方など、さまざまなことを相談できるのが大きなメリットでしょう。定期面談も行っているため精神的なケアも手厚いです。
なお、就労移行支援事業所でも職場定着支援が行われています。例えば、職場に向けた必要な配慮の説明や関係機関を交えた面談などが行われています。定期面談を受けていれば、何か困りごとがあってもすぐに相談できますよね。その後もサポートが必要であれば、就労定着支援の移行手続きをすることで月に1度の頻度で相談支援を受けることができます。
利用期間は原則24か月と定められています。また、大半の方は無料で利用できますが世帯の収入状況によっては利用料が発生する点に注意しましょう。
以下に例として、オススメの就労移行支援事業所をご紹介します。気になる方はチェックしてみてください。
ミラトレ
ミラトレは、企業が求めるスキルを効率的に習得できる実践的なプログラムが魅力の就労移行支援事業所です。就労経験に乏しい方も、模擬オフィスでの業務体験や企業実習を通じて、働くことのイメージを具体化できます。
就職活動では、履歴書の書き方から面接対策まで徹底指導してくれます。高い就職率と定着率を誇っており、「しっかりと就職までサポートしてほしい」という方にオススメです。
NeuroDive
NeuroDiveは、IT・Web分野の専門スキルを身につけ、その道のプロを目指せる就労移行支援事業所です。あなたの集中力や探求心を、プログラミングやデザインといった分野で活かせます。
個々の特性に合わせた学習環境と、業界経験豊富な講師陣が魅力です。「せっかく就職を目指すなら自分の好きなことで頑張りたい」という方にオススメできます。
atGpジョブトレ 発達障害コース
atGpジョブトレ 発達障害コースは、発達障がいのある方に特化した就労移行支援事業所です。
発達障がい者に対するサポート実績が豊富なので、ASD特有のお悩みにも、具体的なアドバイスやサポートをしてもらえます。
「自分の障がい特性を徹底的に見直したい」という方にオススメです。
就労継続支援事業所
就労継続支援事業所は、障がいや難病により一般就労が難しいけれど、雇用契約を結んで働くことは可能な方が利用できる障害福祉サービス施設です。目的に「障がいのある方に働く機会を提供する」ことがあり、職場では障がい者の方が働きやすいように一定の支援やサポートを行っています。
このため、「一般就労で働くことに不安がある」「支援がないと長く働くことが難しいかもしれない」と考えている方にオススメです。雇用契約を結んでいるため、利用者は最低賃金以上の給与が得られます。経済的にもメリットがあると言えるでしょう。
業務内容としては、パンやお菓子の製造、レストランのホールスタッフから、軽作業のほか、近年ではWebサイト制作などのIT業務に力を入れている事業所も増えています。
こうした業務を通して、仕事に必要なコミュニケーション能力や専門的なスキルを身につけ、一般就労に進む方も珍しくありません。一般就労で長く働き続けることを目標として、まずは就労継続支援事業所を利用して仕事に慣れながらスキルを磨く方法もオススメです。
利用期間の制限はありません。しかし、就労移行支援事業所と同じく利用料がかかる場合がある点に注意しておきましょう。
就労継続支援事業所については、先述した就労移行支援事業所と併せて下記の記事で解説しています。
まとめ|ASDの仕事が続かない理由と対策
- ASDのある方が仕事を長く続けることができない要因として、「コミュニケーションの難しさ」「柔軟な対応が苦手」「感覚過敏、あるいは鈍麻」などの特性があることが挙げられる。
- ASDの方が仕事で直面してしまう困りごととして、「職場内で上手くコミュニケーションが取れない」「暗黙の了解などがわからない」「手元の仕事にのめり込みがち」「マルチタスクができない」「急な予定変更や人事異動に適応できない」などが挙げられる。こうした困りごとが重なり続け、ストレスを抱えてしまうと、うつ病などの二次障がいを発症してしまう場合もある。
- ASDの方が仕事を長続きさせるための仕事術には、「自分の特性を理解する」「職場に自身の特性を理解してもらう」「上司とコミュニケーションを取る際のルールを作る」「具体的な言葉を使った指示や説明を求める」「やるべき仕事や優先順位を目に見える形にする」「自身の感覚過敏に合わせた対策」「自身の特性と相性が悪い職場は避ける」ことが挙げられる。
- 仕事術などを試してもうまくいかないときは、支援制度を利用も考える。「ハローワーク」のほか、「発達障がい者支援センター」「地域障がい者職業センター」「障がい者就業・生活支援センター」などで相談や支援を受けられる。また「就労移行支援事業所」「就労継続支援A型」で一般就労に向けた準備もできる。
今回紹介した仕事術のほかにも、あなたの特性に合った方法がまだあるかもしれません。あなた自身の特性と深く向き合い、色々な仕事術を考えて試してみると良いでしょう。どうしても仕事が長く続かない方や、自分の特性と1人で向き合うことが難しい方は、記事で解説した就労支援制度を利用してみましょう。
就労支援機関では、あなたのような仕事が長続きせず悩んでいる方とたくさん向き合ってきています。きっと、あなたの悩みにも寄り添い、具体的な対策やアドバイスを受けられるでしょう。
この記事が仕事を長く続けたい方の一助となれば幸いです。